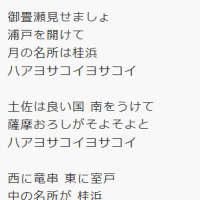2011年3月2日(水) 日本の伝統色―歌舞伎の引き幕
当ブログでは、これまで、色の世界の話題として
色材の三原色 (2011/1/13)
光の三原色 (2011/1/21)
茜色 (2011/1/28)
交差点の信号機の色は?(2011/2/1)
日の丸の旗 (2011/2/7)
ユニフォームとCI (2011/2/15)
について触れてきたが、今回は、日本の伝統色の一つである、歌舞伎の引き幕の色、について述べてみたい。
日本の伝統芸能である歌舞伎の舞台を、直接見たのは、これまでで、数回である。 取り立てて、歌舞伎のフアンと言うことではないが、以前、仕事の取引先から招待されたこともある。 最近では、新聞販売店のサービスの一環で、観劇券の抽選に運よく当たり、見通しの良い、3階の大衆席で観賞したのが多い。 無線による解説が大いに、役に立った。
観賞した演目については、云う程の知識は無いし、又、目下、世間を騒がせている、団十郎事件についても、ここでは、取り上げる積りはない。
東銀座にある歌舞伎座は、目下、建て替え中だ。 上方や江戸など、座のある場所によって、幕の色は異なるようだが、歌舞伎座で使われている、引き幕(定式幕)は、江戸の森田座の流れを受ける、という。
以下は、あるサイトから借用した定式幕の図である。 左から、黒、柿、萌黄の順に並ぶ、立縞模様である。

 歌舞伎座
歌舞伎座
国立劇場の定式幕の配色は、左から、黒、萌黄、柿の順で、こちらは、市村座の流れという。
 国立劇場
国立劇場
この歌舞伎の引き幕の色を、座として、どのように規定しているかは、情報不足で、不明であるが、日本の伝統的習慣からして、単に、色名と順序だけを決めているのであろう。
あの配色を見れば、歌舞伎だな、と直ぐ連想される。この配色は、柿と萌黄は、補色関係に近いため、艶やかな色合いなのだが、黒があるせいか、全体として、どこか、ほっとするような印象がある。
○この引き幕の三つの色の中で、先ず黒色だ。 黒とは、色の基本である光の世界では、一切の光が無いため、物が見えない状態が、黒ということで、一義的に決まっている。でも、真っ暗では、生活も何もできないので、光がある所で黒く見え、出来る限り、光の反射が少ないのが、黒という事である。
長い歴史と伝統のある、色材や染色の世界では、黒色については、色んな工夫がなされてきたようだ。 逆に、反射があるようにした黒もある。
又、最近の、テレビやプリンタの世界では、どのように黒を扱うかは、大きなポイントにもなっている。
自分にとって、日常的にかかわりのある、黒い衣装としては、尺八の演奏会で身に付ける紋付や、喪服などになるが、生地の種類や、光沢や、つや加減などで、色々な黒があるようだ。でも、ここでは、これ以上は、触れない。
○次の二つ目の柿色は、言うまでも無く、日本の秋には欠かせない、柿の実の色だ。 以前に、下記のブログに載せたものだが、
柿の季節 (2010/11/23)
先ず、写真での柿の実の色を、以下に示す。


富有柿 次郎柿 平種柿 富士柿
歌舞伎の引き幕の柿色は、富士柿の色合いに、やや近いだろうか。
次に、パソコンでの柿色だが、規定されているシステムにより、カラーコードなどが、以下のようになっている。


JIS慣用色 #bb5c35 和色大辞典 #ed6d3d
マンセル表示 10R 5.5/12
カラーコードは、異なるものの、両者の色合いは、殆ど同じといえる。
渋柿から採った柿渋を塗った渋紙も、以前はよく使われたが、この渋紙の色は、柿渋色として、以下のように規定されている。

和色大辞典 #ed6d3d
柿色系の色では、他に
水柿、薄柿、照柿
等も規定されている。
○三つ目の、萌黄(もえぎ)色だが、以前から、気になっていた名前の色で、どんな色か、はっきりとは知らなかったのだが、今回、漸く、明確になった。 古来、衣装など、色んなものに使われてきた、伝統色であり、「moegi」という音の響きも良い。 厳密に言うと、この呼 び方の色には、二通りがあるようだ。
一つは、黄緑系の萌黄(もえぎ)色で 春に萌えでる草の芽の色といわれ、歌舞伎の引き幕の色の一つである。JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #97a61e 和色大辞典 #a9d159
一方、葱の芽の色と言われる青緑系で、字が異なる、萌葱(もえぎ)色があり、これも、日本の伝統色の一つで、JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。この両者も、カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #00533e 和色大辞典 #006c4f
ここで、紛らわしいのだが、「asagi」色、と言うのがあり、この語感も大好きである。 字では、浅葱色(浅黄色とも)と書くが、葱の葉の色と言われ、述の、萌葱色にやや近い、薄い青緑系の色だ。これも、日本の伝統色の一つで、新撰組の羽織の色だった、と言う。JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。これも、カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #00533e 和色大辞典 #006c4f
これら、萌黄色、萌葱色、浅葱色、とも、春の若草や新芽などの、若々しい生命力を讃える、日本人の感性を表した色であり、ネーミングである、と言えようか。
余談になるが、永谷園の、御茶漬け袋の色模様は、歌舞伎の引き幕と、可なり似ている(萌黄色が萌葱色に、柿色が黄色に、なっているがーー)。大相撲の懸賞でも、よく目にする光景だが、オーナーが、伝統的な、歌舞伎や大相撲等の大ファン、なのだそうな。

当ブログでは、これまで、色の世界の話題として
色材の三原色 (2011/1/13)
光の三原色 (2011/1/21)
茜色 (2011/1/28)
交差点の信号機の色は?(2011/2/1)
日の丸の旗 (2011/2/7)
ユニフォームとCI (2011/2/15)
について触れてきたが、今回は、日本の伝統色の一つである、歌舞伎の引き幕の色、について述べてみたい。
日本の伝統芸能である歌舞伎の舞台を、直接見たのは、これまでで、数回である。 取り立てて、歌舞伎のフアンと言うことではないが、以前、仕事の取引先から招待されたこともある。 最近では、新聞販売店のサービスの一環で、観劇券の抽選に運よく当たり、見通しの良い、3階の大衆席で観賞したのが多い。 無線による解説が大いに、役に立った。
観賞した演目については、云う程の知識は無いし、又、目下、世間を騒がせている、団十郎事件についても、ここでは、取り上げる積りはない。
東銀座にある歌舞伎座は、目下、建て替え中だ。 上方や江戸など、座のある場所によって、幕の色は異なるようだが、歌舞伎座で使われている、引き幕(定式幕)は、江戸の森田座の流れを受ける、という。
以下は、あるサイトから借用した定式幕の図である。 左から、黒、柿、萌黄の順に並ぶ、立縞模様である。

 歌舞伎座
歌舞伎座国立劇場の定式幕の配色は、左から、黒、萌黄、柿の順で、こちらは、市村座の流れという。
 国立劇場
国立劇場この歌舞伎の引き幕の色を、座として、どのように規定しているかは、情報不足で、不明であるが、日本の伝統的習慣からして、単に、色名と順序だけを決めているのであろう。
あの配色を見れば、歌舞伎だな、と直ぐ連想される。この配色は、柿と萌黄は、補色関係に近いため、艶やかな色合いなのだが、黒があるせいか、全体として、どこか、ほっとするような印象がある。
○この引き幕の三つの色の中で、先ず黒色だ。 黒とは、色の基本である光の世界では、一切の光が無いため、物が見えない状態が、黒ということで、一義的に決まっている。でも、真っ暗では、生活も何もできないので、光がある所で黒く見え、出来る限り、光の反射が少ないのが、黒という事である。
長い歴史と伝統のある、色材や染色の世界では、黒色については、色んな工夫がなされてきたようだ。 逆に、反射があるようにした黒もある。
又、最近の、テレビやプリンタの世界では、どのように黒を扱うかは、大きなポイントにもなっている。
自分にとって、日常的にかかわりのある、黒い衣装としては、尺八の演奏会で身に付ける紋付や、喪服などになるが、生地の種類や、光沢や、つや加減などで、色々な黒があるようだ。でも、ここでは、これ以上は、触れない。
○次の二つ目の柿色は、言うまでも無く、日本の秋には欠かせない、柿の実の色だ。 以前に、下記のブログに載せたものだが、
柿の季節 (2010/11/23)
先ず、写真での柿の実の色を、以下に示す。


富有柿 次郎柿 平種柿 富士柿
歌舞伎の引き幕の柿色は、富士柿の色合いに、やや近いだろうか。
次に、パソコンでの柿色だが、規定されているシステムにより、カラーコードなどが、以下のようになっている。


JIS慣用色 #bb5c35 和色大辞典 #ed6d3d
マンセル表示 10R 5.5/12
カラーコードは、異なるものの、両者の色合いは、殆ど同じといえる。
渋柿から採った柿渋を塗った渋紙も、以前はよく使われたが、この渋紙の色は、柿渋色として、以下のように規定されている。

和色大辞典 #ed6d3d
柿色系の色では、他に
水柿、薄柿、照柿
等も規定されている。
○三つ目の、萌黄(もえぎ)色だが、以前から、気になっていた名前の色で、どんな色か、はっきりとは知らなかったのだが、今回、漸く、明確になった。 古来、衣装など、色んなものに使われてきた、伝統色であり、「moegi」という音の響きも良い。 厳密に言うと、この呼 び方の色には、二通りがあるようだ。
一つは、黄緑系の萌黄(もえぎ)色で 春に萌えでる草の芽の色といわれ、歌舞伎の引き幕の色の一つである。JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #97a61e 和色大辞典 #a9d159
一方、葱の芽の色と言われる青緑系で、字が異なる、萌葱(もえぎ)色があり、これも、日本の伝統色の一つで、JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。この両者も、カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #00533e 和色大辞典 #006c4f
ここで、紛らわしいのだが、「asagi」色、と言うのがあり、この語感も大好きである。 字では、浅葱色(浅黄色とも)と書くが、葱の葉の色と言われ、述の、萌葱色にやや近い、薄い青緑系の色だ。これも、日本の伝統色の一つで、新撰組の羽織の色だった、と言う。JIS慣用色と和色大辞典では、カラーコードと色見本は、以下のように、規定されている。これも、カラーコードは異なるが、色合いは同じ、と言ってよい。


JIS慣用色 #00533e 和色大辞典 #006c4f
これら、萌黄色、萌葱色、浅葱色、とも、春の若草や新芽などの、若々しい生命力を讃える、日本人の感性を表した色であり、ネーミングである、と言えようか。
余談になるが、永谷園の、御茶漬け袋の色模様は、歌舞伎の引き幕と、可なり似ている(萌黄色が萌葱色に、柿色が黄色に、なっているがーー)。大相撲の懸賞でも、よく目にする光景だが、オーナーが、伝統的な、歌舞伎や大相撲等の大ファン、なのだそうな。