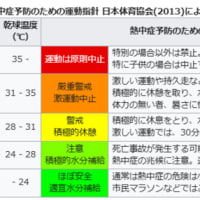2010年9月10日(金) 自然と人間と
先日の8月18日に、TVで見たNHK番組、ちょっと変だぞ日本の自然「大ピンチ? ふるさと激変スペシャル」は、かなりの驚きである。最近は、地球温暖化問題を中心に、色んな報道が行われているが、今回は、少し違った視点からの環境問題として、自然と人間との関わり方が変わることで、自然界に起きた異変を取り上げている。幾つかの話題の中から、興味を魅かれたニュースについて、以下に取り上げてみたい。
○ 宮城県石巻市の海岸で、アサリが、全く獲れなくなっているようだ。海岸に無数に散ら
ばっている、死んだアサリの貝殻には、どれも、丸い小さな穴が開いている。原因は、外来種の、サキグロタマツメタという巻貝が異常繁殖し、覆いかぶさるようにアサリを包みこんで、貝殻に穴をあけ、アサリを食べてしまった結果、全滅してしまったようだ。この巻貝の名前も、ネットで調べて何とか分かったのだが、このサキグロタマツメタによる被害は、石巻だけでなく、全国的に広がっているようだ。以下の写真は、宮城県水産技術総合センターのHPから借用している。
 サキグロタマツメタ 貝
サキグロタマツメタ 貝
 穴をあけられて死んだ貝(上シジミ 下アサリ)
穴をあけられて死んだ貝(上シジミ 下アサリ)
原因究明が行われた。この所、石巻では、アサリの漁が思わしくなくなって来ていたため、中国からアサリの稚貝を、大量に輸入し、海岸に撒いたようだ。この時に、その中に、先述の巻貝が混入していたのでは、との推定である。輸入品にたまたま混入していた外来の生物が、国内で異常繁殖して、とんでもない事態になる例は、良く聞く話ではある。
輸入元の中国沿岸では、この巻貝を、人間が食料として採取して食べるので、バランスが取れているのだという。日本では、この貝は、人間が食べないので、海岸から駆除するには、親貝だけでなく、卵の段階から取り除かねばならず、大変な作業になるようである。
アサリは、何時になったら、元に戻るのだろうか。
○ 日光の中禅寺湖周辺や戦場ヶ原では、サクラソウの仲間である、クリンソウの花の群落
が、最近の人気のようだ。 ネットで調べると、クリンソウの群落は、重要な観光資源として、盛んにPRされている。
 クリンソウの群落
クリンソウの群落
でもこの植物は、元々は、中禅寺湖周辺や戦場ヶ原やには、殆ど自生していなかったようだ。ニホンジカが異常繁殖し、彼らが食べないクリンソウや他の数種類を残して、ほとんど食べつくしてしまったので、クリンソウなどの、特定の野草だけが群落として残り、草原の多様性が失われてしまったという。そのクリンソウの広大な花畑が、最近の日光の人気の一つという、皮肉な結果になっているようだ。
日光や戦場ヶ原には、これまで、何度か訪れたことがあり、湿原が次第に乾燥してきていて、植生が変化しつつある、とは聞いていたが、クリンソウの群落の話は知らなかった。
愛らし気で、温和なニホンジカ君が悪者にされてしまったが、彼らが異常に増えたのは、人間が山林を開発して作った緑地が、大幅に増えたためという。人間の所作が、草原の異変の原因なのである。
 ニホンジカ
ニホンジカ
ネット情報では、宮城県の牡鹿半島の先にある、金華山でも、生息しているニホンジカ
の食性から、クリンソウなどの群落が出来ているという。
○ 佐渡のトキと言えば、人工孵化して育てられた鳥たちの野生復帰が、重要な話題である。この春、トキ保護センターで、放鳥訓練用の広いケージの中に、イタチのような小動物が入り込んで、多くのトキがやられた話は、痛ましい事件だ。
野生復帰での最大の課題は、トキが自力で餌を獲り、繁殖していけるかどうか、ということだ。トキの餌となる、小魚や蛙などが住める沼地や田んぼが、往時よりも、1/3位までに大幅に減っている、という。
 トキ(Nipponia nippon)
トキ(Nipponia nippon)
以前田んぼだった土地が、後継者不足などで、耕作放棄地となり、草地や雑木林に変わりつつあるという。地域の皆さんが、地元の小学生などとともに、草地を、元の田んぼに戻す作業を、必死で行って様子が、報道された。
ここで、知らされたのが、里地・里山の環境の大切さ、についてである。人間が手を加える前の、自然林(原生林)は、一次自然と呼ばれる。そこに人間が定住し、生活を営み、農耕を行うようになって、以下のような、色んな環境が出現した。その様子を、番組では、分かりやすい絵パネルを使って、解説してくれた。
住居 :雨風や寒さを防ぐ家
田んぼ :米作り
畑 :野菜や穀物の栽培
雑木林 :燃料採取
溜池と水路 :灌漑用 生活用水
牧草地 :家畜の飼料
鎮守の森:緑 防風
わが国では、弥生時代以降、狩猟中心の生活から、定住型の米作が始まった、といわれるが、以来、数千年にわたって、農業が営まれ、田んぼや畑を中心とした、上記のような環境が整えられてきた。人間の手が加えられた、このような、里山・里地を中心とした、 環境は、二次自然と呼ぶようだ。
ここで重要なことは、人間の手が入っていない一次自然よりも、二次自然の方が、生物の多様性が豊かになる、ということで、自分も認識を新たにした。この場合、当然のことだが、手を加えてできた二次自然を、人間が、継続的に維持してのことである。
ところが、佐渡の例のように、耕作放棄などで、継続的に手を加えて維持することを、人間が止めてしまうと、多様性も失われて行き、数百年という長い時間がかかるようだが、一次自然に帰っていく、という。このことで、それまで保たれてきた自然界のバランスが崩れていき、結果、トキも共生できる環境が少なくなり、失われて行く。
物心ついた終戦直前から、戦後もしばらくの間は、自分の生まれ育った田舎には、里地・里山が確かにあり、一種の自給自足的な、循環型の営みが行われていた。例えば、田んぼから刈り取った稲の藁(わら)は、捨てることなく、牛小屋に入れて堆肥にしたり、農作業用の縄や筵(むしろ)や俵などに作った。養蚕が盛んで、蚕に食べさせる畑から刈り取った桑の枝は、藁や豆殻などと一緒に、ご飯を炊く竈(かまど)の重要な燃料となった。又、裏山の間伐で刈り取った薪(たきぎ)や小枝は、囲炉裏の燃料となった。田んぼや畑の作業や山林の手入れも、生活と繋がっていて、回っていたのである。その後、農作業の合理化(機械化、紙袋、ビニール製品)や、生活の近代化(電気、ガス、水道)が急速に進み、今や、農村では、以前のような形は、殆ど姿を消してしまっている。
○ トキのためだけでなく、人間の生存のためにも、生物の多様性を維持することは、喫緊の課題なのだが、かと言って、今ある里山・里地を保存し、出来れば再び取り戻すために、農作業の形態や生活様式を、以前の形に戻す、ということは、事実上、不可能である。勿論、佐渡においても、である。
しからば、これからは、どのようにすればいいのだろうか。自然と人間の関係のあり方という、環境問題全体について、答を出していくのは、容易ではない。方法が近代化されるのは避けられないが、ぎりぎりの所で、知恵を絞って、持続可能な社会システムを編み出していかねばならない。
この場合、以下のような事項が、キーワードになるのだろうか。
生物の多様性の保全を大切にする
漁業も狩猟型から養殖型に転換する
経済原則や合理性だけでは行動しない
生き物は汚れた側面も持っている
技術的には可能でも資源保護のために量を我慢する
多少コスト高になっても受け入れる
個々の小さな一歩の積み重ねを大事にする
○ 佐渡と言えば、実は、ほぼ50年前に結婚した時の、新婚旅行先である。生まれて初めてカラー写真を撮ったのもこの時からだ。新潟から乗った佐渡行きの船が、揺れて酔いそうだったことや、両津港の海岸で体感した、オンデコ座一団の太鼓の響きや、尖閣湾の激しい波しぶきなど、いまだに忘れられない思い出である。そして、最後に、新潟から東京に戻るのに、初めて乗った特急電車が、懐かしい「とき」なのである。
 特急 とき
特急 とき
その当時、佐渡では、野生のトキが、見られたのかどうかは定かではないが、わが国の環境問題の、象徴的な存在のトキ君に、絶大なる声援を送りたい。
先日の8月18日に、TVで見たNHK番組、ちょっと変だぞ日本の自然「大ピンチ? ふるさと激変スペシャル」は、かなりの驚きである。最近は、地球温暖化問題を中心に、色んな報道が行われているが、今回は、少し違った視点からの環境問題として、自然と人間との関わり方が変わることで、自然界に起きた異変を取り上げている。幾つかの話題の中から、興味を魅かれたニュースについて、以下に取り上げてみたい。
○ 宮城県石巻市の海岸で、アサリが、全く獲れなくなっているようだ。海岸に無数に散ら
ばっている、死んだアサリの貝殻には、どれも、丸い小さな穴が開いている。原因は、外来種の、サキグロタマツメタという巻貝が異常繁殖し、覆いかぶさるようにアサリを包みこんで、貝殻に穴をあけ、アサリを食べてしまった結果、全滅してしまったようだ。この巻貝の名前も、ネットで調べて何とか分かったのだが、このサキグロタマツメタによる被害は、石巻だけでなく、全国的に広がっているようだ。以下の写真は、宮城県水産技術総合センターのHPから借用している。
 サキグロタマツメタ 貝
サキグロタマツメタ 貝 穴をあけられて死んだ貝(上シジミ 下アサリ)
穴をあけられて死んだ貝(上シジミ 下アサリ)原因究明が行われた。この所、石巻では、アサリの漁が思わしくなくなって来ていたため、中国からアサリの稚貝を、大量に輸入し、海岸に撒いたようだ。この時に、その中に、先述の巻貝が混入していたのでは、との推定である。輸入品にたまたま混入していた外来の生物が、国内で異常繁殖して、とんでもない事態になる例は、良く聞く話ではある。
輸入元の中国沿岸では、この巻貝を、人間が食料として採取して食べるので、バランスが取れているのだという。日本では、この貝は、人間が食べないので、海岸から駆除するには、親貝だけでなく、卵の段階から取り除かねばならず、大変な作業になるようである。
アサリは、何時になったら、元に戻るのだろうか。
○ 日光の中禅寺湖周辺や戦場ヶ原では、サクラソウの仲間である、クリンソウの花の群落
が、最近の人気のようだ。 ネットで調べると、クリンソウの群落は、重要な観光資源として、盛んにPRされている。
 クリンソウの群落
クリンソウの群落でもこの植物は、元々は、中禅寺湖周辺や戦場ヶ原やには、殆ど自生していなかったようだ。ニホンジカが異常繁殖し、彼らが食べないクリンソウや他の数種類を残して、ほとんど食べつくしてしまったので、クリンソウなどの、特定の野草だけが群落として残り、草原の多様性が失われてしまったという。そのクリンソウの広大な花畑が、最近の日光の人気の一つという、皮肉な結果になっているようだ。
日光や戦場ヶ原には、これまで、何度か訪れたことがあり、湿原が次第に乾燥してきていて、植生が変化しつつある、とは聞いていたが、クリンソウの群落の話は知らなかった。
愛らし気で、温和なニホンジカ君が悪者にされてしまったが、彼らが異常に増えたのは、人間が山林を開発して作った緑地が、大幅に増えたためという。人間の所作が、草原の異変の原因なのである。
 ニホンジカ
ニホンジカネット情報では、宮城県の牡鹿半島の先にある、金華山でも、生息しているニホンジカ
の食性から、クリンソウなどの群落が出来ているという。
○ 佐渡のトキと言えば、人工孵化して育てられた鳥たちの野生復帰が、重要な話題である。この春、トキ保護センターで、放鳥訓練用の広いケージの中に、イタチのような小動物が入り込んで、多くのトキがやられた話は、痛ましい事件だ。
野生復帰での最大の課題は、トキが自力で餌を獲り、繁殖していけるかどうか、ということだ。トキの餌となる、小魚や蛙などが住める沼地や田んぼが、往時よりも、1/3位までに大幅に減っている、という。
 トキ(Nipponia nippon)
トキ(Nipponia nippon)以前田んぼだった土地が、後継者不足などで、耕作放棄地となり、草地や雑木林に変わりつつあるという。地域の皆さんが、地元の小学生などとともに、草地を、元の田んぼに戻す作業を、必死で行って様子が、報道された。
ここで、知らされたのが、里地・里山の環境の大切さ、についてである。人間が手を加える前の、自然林(原生林)は、一次自然と呼ばれる。そこに人間が定住し、生活を営み、農耕を行うようになって、以下のような、色んな環境が出現した。その様子を、番組では、分かりやすい絵パネルを使って、解説してくれた。
住居 :雨風や寒さを防ぐ家
田んぼ :米作り
畑 :野菜や穀物の栽培
雑木林 :燃料採取
溜池と水路 :灌漑用 生活用水
牧草地 :家畜の飼料
鎮守の森:緑 防風
わが国では、弥生時代以降、狩猟中心の生活から、定住型の米作が始まった、といわれるが、以来、数千年にわたって、農業が営まれ、田んぼや畑を中心とした、上記のような環境が整えられてきた。人間の手が加えられた、このような、里山・里地を中心とした、 環境は、二次自然と呼ぶようだ。
ここで重要なことは、人間の手が入っていない一次自然よりも、二次自然の方が、生物の多様性が豊かになる、ということで、自分も認識を新たにした。この場合、当然のことだが、手を加えてできた二次自然を、人間が、継続的に維持してのことである。
ところが、佐渡の例のように、耕作放棄などで、継続的に手を加えて維持することを、人間が止めてしまうと、多様性も失われて行き、数百年という長い時間がかかるようだが、一次自然に帰っていく、という。このことで、それまで保たれてきた自然界のバランスが崩れていき、結果、トキも共生できる環境が少なくなり、失われて行く。
物心ついた終戦直前から、戦後もしばらくの間は、自分の生まれ育った田舎には、里地・里山が確かにあり、一種の自給自足的な、循環型の営みが行われていた。例えば、田んぼから刈り取った稲の藁(わら)は、捨てることなく、牛小屋に入れて堆肥にしたり、農作業用の縄や筵(むしろ)や俵などに作った。養蚕が盛んで、蚕に食べさせる畑から刈り取った桑の枝は、藁や豆殻などと一緒に、ご飯を炊く竈(かまど)の重要な燃料となった。又、裏山の間伐で刈り取った薪(たきぎ)や小枝は、囲炉裏の燃料となった。田んぼや畑の作業や山林の手入れも、生活と繋がっていて、回っていたのである。その後、農作業の合理化(機械化、紙袋、ビニール製品)や、生活の近代化(電気、ガス、水道)が急速に進み、今や、農村では、以前のような形は、殆ど姿を消してしまっている。
○ トキのためだけでなく、人間の生存のためにも、生物の多様性を維持することは、喫緊の課題なのだが、かと言って、今ある里山・里地を保存し、出来れば再び取り戻すために、農作業の形態や生活様式を、以前の形に戻す、ということは、事実上、不可能である。勿論、佐渡においても、である。
しからば、これからは、どのようにすればいいのだろうか。自然と人間の関係のあり方という、環境問題全体について、答を出していくのは、容易ではない。方法が近代化されるのは避けられないが、ぎりぎりの所で、知恵を絞って、持続可能な社会システムを編み出していかねばならない。
この場合、以下のような事項が、キーワードになるのだろうか。
生物の多様性の保全を大切にする
漁業も狩猟型から養殖型に転換する
経済原則や合理性だけでは行動しない
生き物は汚れた側面も持っている
技術的には可能でも資源保護のために量を我慢する
多少コスト高になっても受け入れる
個々の小さな一歩の積み重ねを大事にする
○ 佐渡と言えば、実は、ほぼ50年前に結婚した時の、新婚旅行先である。生まれて初めてカラー写真を撮ったのもこの時からだ。新潟から乗った佐渡行きの船が、揺れて酔いそうだったことや、両津港の海岸で体感した、オンデコ座一団の太鼓の響きや、尖閣湾の激しい波しぶきなど、いまだに忘れられない思い出である。そして、最後に、新潟から東京に戻るのに、初めて乗った特急電車が、懐かしい「とき」なのである。
 特急 とき
特急 ときその当時、佐渡では、野生のトキが、見られたのかどうかは定かではないが、わが国の環境問題の、象徴的な存在のトキ君に、絶大なる声援を送りたい。