
花陵会は旧制第五高等学校のキリスト教信者7名による相互協力や聖書に基づく真理の探究、社会への貢献などを固く誓って明治29(1896)年に結ばれた団体。 翌年には貸家を借りての共同生活を始め、自炊寮を苦心しながらも経営しました。 この建物は北米YMCA同盟、花陵会OBや熊本の有志の寄付を得て昭和6(1931)年に建てられた2代目の会館で、設計はOBの大倉三郎(1900~1983)によるものだそうです。 終戦後、第五高等学校は熊本大学へと引き継がれ花陵会も熊本大学YMCAへと継承、現在も聖書を中心とした共同生活を行って活動を展開しています。 熊本県熊本市黒髪2-27-21 12年01月上旬

建物はRC造2階建て、南東の隅に八角塔屋を載せたモダンな造り。

テラスの屋根を支える5連のアーチが自由な気風を感じさせます。

大倉三郎は京都帝国大学建築学科で武田五一に薫陶を受け、卒業後直ぐに大阪の宗建築事務所に入所。 昭和3(1928)年から同・15(1940)年までは京都帝国大学の営繕課に勤めていました。 彼の作風はセセッション・表現派的なものからドイツ・クラシシズム、近代主義的なものなど幅広く完成度も高かったという。

窓から内部を拝見。 今も聖書研究会などの活動が週に1回行われているそう。

北東面。 写真の撮影日は一緒ですが時間に1時間ほどのズレがあるので天気が違っています。

ポーチの開口部は尖頭アーチ。

花陵会の沿革は銀色のプレートに書かれている内容を参考にさせてもらいました。

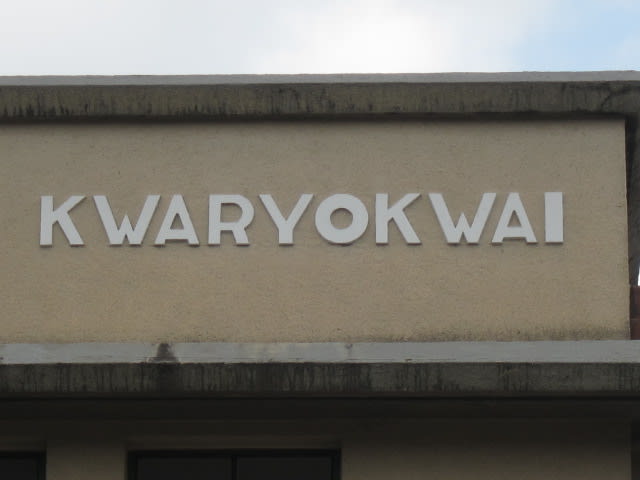

建物の性質上、皇紀ではなく西紀となっているのがポイントですね。

この窓枠のグリーンが好き。

こちらが寮の建物で、花陵会のHPを見ると築79年となっているので会館とほぼ同じ時代に竣工したものと思われます。 ちなみに寮生は熊本大学の男子学生に限られています。

帰り際に再び立ち寄ったら晴れてきた。




















カクカクしてて面白い建物ですな~。
縁取りもカクカク。
「武田五一に薫陶を受け」っていうのが
なんとなくわかる気が…。
(素人がおこがましいですな。汗)
まぁ、言われたらなのですが、
武田五一の京都の1928ビルに
ちょっと雰囲気が似てるな~とか思いました。
本当グリーン枠素敵ですね~。
設計者を調べたところで大倉三郎という名前を知りました。
現存している作品で関西のものは各種建築ブログで紹介されていたのですが、
この建物はほとんど取り上げられていなかったのでラッキーかと思い載せてみました。
アール・デコというかカクカクした直線が特徴的ですが、
窓越しに覗いた内部空間は教会建築のような雰囲気がしてとても落ち着きます。
不思議な魅力を合わせ持った建築という印象が強かったですね。
武田五一の1928ビル、私も見た事がありますよ!
内部は階段部分しか見られなかったのですが、星形の窓や独特な形状のバルコニーなど外観も面白いですね。
しばらく見てないからまた京都に行きたいな~。