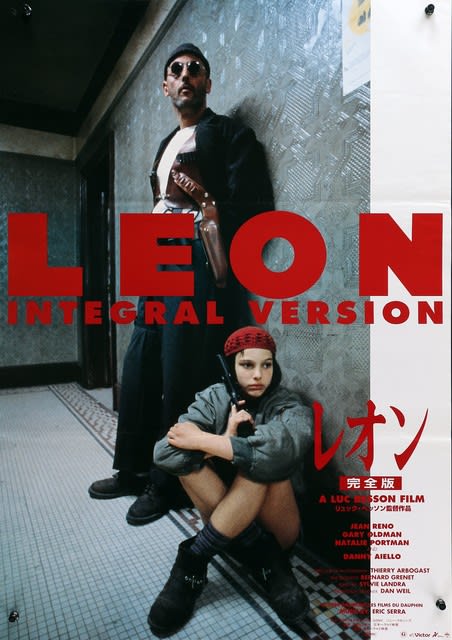初出 2013/09/29(のち一部を改稿)
「ある特定の時代に書かれた小説/作られた映画」を調べ上げるのは容易いけれど、「ある特定の時代を舞台にした小説や映画」について調べるのは厄介だ。ためしに『1930年代を舞台にした(あるいは、「背景にした」)映画』というワードで検索を掛けてみたけども、思わしい結果は得られなかった。腰を据えてやったわけじゃないので不備があるかも知れないが、ネット文化の盲点といえる気もする。こんなときにはやはり書物のほうが役に立つ。
手元にある映画関連の本を見ると、子供の頃に「日曜洋画劇場」や「金曜ロードショー」なんかで観た有名な映画がけっこう意外な時代を舞台にしていて面白かった。ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード主演のニュー・スタイル西部劇『明日に向かって撃て!』は1969年の作品だが、舞台は1900年つまり明治33年なのだ。「西部劇」といったらせいぜい19世紀の半ばくらいじゃないかと思ってしまうが、じっさいにはアメリカの一角では20世紀の初頭まで無法者たちがパンパン撃ち合いをやってたわけだ。今もなお社会に暗い影を落とす「銃への信仰」のルーツの一端が垣間見えるようだ。しかしこの時代にはもう「映画」というジャンルは誕生しており、ゆえに「最初の西部劇」といわれる1903年の「大列車強盗」なんてのはじつは「同時代映画」であったということになる。
作品としてはたんなる大げさなメロドラマだが、記録的な興行収入を上げて賞も貰った『タイタニック』は1912年つまり大正元年が舞台。これは史実に即しているから分かりやすい。しかしあの映画を観たひとのうち何人くらいが「これは大正元年のことなんだ……」と認識していたか怪しいように思うので、いちおうここに書いとこう。なお、「タイタニックの悲劇」を描いた映画で、あれほどカネは掛かっていないが優れたものは他にもっとたくさんありますよ。
『風立ちぬ』のコメント欄で話に出たウォーレン・ベイティーの『レッズ』は、1917年つまり大正6年のロシア革命に衝撃を受けて母国アメリカに共産主義運動を根付かせようとした実在のジャーナリスト/社会活動家ジョン・リードを描いた作品。「レッズ」とはまさに日本語でいう「アカ」である。長く重厚な作品だが、これが封切られたのが1981年つまり昭和56年というのが興味ぶかいところ。時あたかもタカ派のR・レーガン(思えばこの人も元俳優)が大統領の座に就き、「新自由主義」の原点のひとつ「レーガノミクス」を推し進めていた時期であった。ハリウッドの映画人たちが気骨を示したということか。1917年はまた第一次大戦のさなかでもあって、ピーター・オトゥール主演の『アラビアのロレンス』もこの時代が舞台ということになる。製作は1962年。高校の世界史の若い女性の先生がこの映画の(そしてたぶんピーター・オトゥールの)大ファンだったのをいま思い出した。
映画そのものを観たことがない若い人でも主題歌だけは必ずどこかで耳にしているジーン・ケリーの『雨に唄えば』は1928年つまり昭和3年が舞台。無声映画からトーキーに移り変わる映画界のウラ事情が背景となっている。作られたのは1952年。1950年代には1920年代を描いた佳作がいろいろ作られており、マリリン・モンローの代表作のひとつ『お熱いのがお好き』もその中の一本だ。「聖バレンタインデーの虐殺」を目撃してしまったばかりにマフィアから狙われ、女装して逃げ回るトニー・カーチスとジャック・レモンの珍道中を描いた喜劇。製作は1959年だけど、舞台は1929年つまり昭和4年。1920年代はジャズエイジと呼ばれるが、アル・カポネを筆頭にギャングの跳梁した物騒な時代でもあった。もちろん1929年は、NY市場の大暴落に端を発した世界恐慌勃発の年でもある。海の向こう、ニュルンベルクではナチスが60万人を集めて党大会を開催した。第二次世界大戦の胎動は少しずつ高まり始めていたのである。
続いて1930年代を舞台にした映画をリストアップ。「忙中自ずから閑あり」ってやつで、暇を見つけて気分転換に書いてるので、とうてい網羅的なものではない。まあ茶飲み話と思ってお読みください。まず1930年つまり昭和5年といえば、前年の世界恐慌の余波が隅々まで行きわたり、失業者が街にあふれた年。この年のニューヨークのありさまを描いたハリウッド映画がないはずはないと思うんだけど、ぼくにはちょっと思いつかない。心当たりのある向きはコメント欄でご教示を賜れば幸いだけど、とりあえずここでは名匠ジョン・フォードが1930年の中西部の惨状を描いた『怒りの葡萄』を挙げておきましょう。原作は言わずと知れたスタインベックの同題の名作。作られたのは1940年とかなり早くて、ほぼ同時代と言える。スポットが当てられているのは都市生活者ではなくオクラホマに住む農民だけど、アメリカ流のプロレタリア文学というべき一大叙事詩で、今も新潮文庫で手に入る。
そんな中でもエンパイア・ステート・ビルなんてものをぶっ建ててしまうのがアメリカって国の凄いところ。摩天楼という言葉はここから生まれた。1931年つまり昭和6年に完成したこのエンパイア・ステート・ビルをさっそく舞台にしたのが2年後の1933年に作られた『キング・コング』。追い詰められたコングは愛する美女を守ってこの天辺から墜落する。まあ地上最大のストーカーというべきか。特撮怪獣映画の原点でもあり、この作品自体が一つの「記念碑」と呼べるかもしれない。キング・コングはアメリカ人の琴線にふれるのか、このあとも繰り返しリメイクされる。
ライアン・オニールと実娘のテイタム・オニールが共演し、テイタムが史上最年少(この記録はまだ破られていない)でアカデミーを取った『ペーパー・ムーン』は1973年つまり昭和48年の作品だが、1932年つまり昭和7年を舞台にしている。このあいだ続編が公開されたフルCGアニメ『怪盗グルーの月泥棒』や、コンゲームものの要素を加味した『マッチスティック・メン』など、「要領よく世の中を渡ってきた無責任な男が、ある日とつぜん《子ども》を得ることによって生活が激変し、人間として成長していく」という物語類型のおそらくこれが原点かと思う。日本のドラマでも手を変え品を変えこのパターンは作られており、脚本家と演出家と主演男優と子役の力量がキビしく問われる次第となっている。
1934年つまり昭和9年ごろの、「行き場のない若者たちの焦燥と暴走」を描いた作品といえば何といっても『俺たちに明日はない』。主演はウォーレン・ベイティーとフェイ・ダナウェイ。ふたりの演じた「ボニーとクライド」は固有名ではなくもはやほとんど普遍名詞であり(宇多田ヒカルの歌にもある)、この作品もまたひとつの物語類型の原点といえよう。公開は1967年つまり昭和42年で、ベトナム戦争の真っ只中だった。そういった時代背景へのメッセージが込められてるのは言うまでもない。
1936年つまり昭和11年はベルリン五輪、226事件、スペイン内乱と内外で大きな出来事があった。ベルリン・オリンピックを神々しく撮った記録映画が女性監督レニ・リーフェンシュタールの『民族の祭典』。むろん国策映画なのだが圧倒的な完成度を誇る名作であり、その芸術性は認めざるをえない。7年後の東京五輪でもひょっとしたら類似の企画が立てられるかもしれないが、だれが監督に選ばれたとしてもこれを超えるのは至難であろう。スペイン内戦を扱った作品としては、じっさいに従軍したヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』が1943年にゲイリー・クーパー、イングリッド・バーグマン主演で映画化されている。戦時下において『風と共に去りぬ』や『誰がために鐘は鳴る』なんかを作っちゃう国と戦争しちゃあいけません。
1938年つまり昭和13年になると、欧州全域にヒトラーのナチス・ドイツの恐怖が行きわたる。これを痛烈に風刺したのがご存知チャップリンの『独裁者』。子供のころに観たときはただ笑い転げただけだったが、20代半ばで再見した際はご多分に漏れずあの演説シーンで涙が出た。「チャップリンのああいうところが好きになれない。」と言ってバスター・キートンのほうを支持する喜劇通の方も少なくないようにお見受けするが、やっぱりチャップリンの偉大さは否定できないと思う。彼がこれを作ったのは1940年で、だからさあ、戦時下において『独裁者』なんかを作っちゃう国と戦争したら駄目だっての。
1938年を舞台にした映画で、もう一つ忘れてはならないのが『サウンド・オブ・ミュージック』。製作は1965年つまり昭和40年だけど、超大作『クレオパトラ』のせいで会社が傾いた20世紀フォックスは、この作品の思いもよらぬ大ヒットのおかげで持ち直したといわれる。ジュリー・アンドリュース演じる修道院出身のマリアが、トラップ一家の7人の子供と共にアルプスを越えてスイスに亡命するのは、オーストリアがナチス・ドイツに併合されたためだった。彼女と子供たちとの関係性もまた、ひとつの「物語類型」として、その後のいろいろなドラマに影響を与えているに違いない。
このあとはいよいよ戦争の影が世界を覆い、「この時代を舞台にした映画」といえばたいていが戦争ものということになる。そろそろ時間もなくなってきたし、1942年つまり昭和17年を舞台にした名作中の名作を最後に挙げておきますか。そう。もちろん『カサブランカ』。しかもこの映画、その1942年に製作されているわけで、じつは同時代映画なのである。だから戦時下において『カサブランカ』なんかを……もういいか。
モロッコのカサブランカが舞台となっているのは、戦火のヨーロッパを逃れてアメリカに渡ろうとする人たちが、この地でリスボン経由アメリカ行きの切符を手に入れたいがためである。数々の名シーン、名せりふに彩られた作品ながら、なにぶん戦時下ゆえに現場はかなり混乱しており、ラストシーンでイルザが夫と逃げるかハンフリー・ボガートのもとに留まるか、ぎりぎりまでシナリオが決まらなかったという話もある。イングリッド・バーグマンが困っていたそうだ。それであれだけのものに仕上がっちゃうんだからなあ……。この名作もまた、その後に続くたくさんのドラマに決定的な影響を与えているのはいうまでもない。「乾杯だ。こうやって、ここで君を見ていられることにね。」を「君の瞳に乾杯。」と訳したのは、当時の字幕屋さんの大手柄であった。