
11期だけでなく、栄光の卒業生全体でも神輿を担いだことがある人はほとんどいないと思います。私は30年くらい前に神輿保存会(南貮会:地元の神輿保存会)に入会し、余裕時間が出来たいまでは年間7~8回あちこちへ担ぎに出かけています。きっかけは「地元神輿の担ぎ手募集」の記事が町の広報誌に掲載され、神輿担ぎとはどんなものかと興味を示したところいつのまにか会員になり、現在に至っています。

2012年9月
1.誰がかつぐの?
東京や神奈川付近では、神社があるところでは祭りがあり神輿渡御が行われます。各神輿は、それぞれ地区にある神輿会と地元の人で担ぐことが基本です。しかしながら人が足りず担ぎきれないため神輿会相互で応援し合います。「南貮」は10か所程度他の会と連携していますので、私は年間7~8回担ぐことになります。
2.神輿は重いの?重さはどのくらいあるの?
はっきり言って重いです。ただ「南貮」の神輿でさえどのくらいの重さがあるのか分かりません。会の仲間から「神輿は神様なので重さを知らせてはいけない。」という話を聞いたことがあります。私の経験では、古くて彫りが深い神輿は重く、新しい金ぴかの神輿は軽く感じます。なかには千貫神輿と呼ばれる小さな神社くらいのものがあります。台に乗せ地上に置いてあるときは感じませんが、担ぎ上げた時には、その大きさと迫力で見ている人達から思わず「ウオー」という歓声が上がります。小さな神輿より、大きな神輿、軽い神輿よりも重い神輿の方が担いでいて気持ちが良く、重い神輿の肩に来る「ずっしり感」は何とも言えません。
3.どうやって担ぐの?
神輿には大別して二つの種類があります。二本の台棒にロープをかけ甚句を歌い「ドッコイ」という掛け声挙げながら担ぐ「どっこい神輿」と、台棒を縦横に通して担ぐ、小さな神社の形をした江戸前神輿に分かれます。私は江戸前神輿の会に入会しています。 掛け声は地区によって異なりますが、一般的に江戸前神輿(普通の小さな神社の形をした神輿)の場合、4隅に下がった房がゆったりと左右に振れる担ぎ方が見た目も綺麗で上手だと言われています。背筋を伸ばし、ゆっくりとしたリズムで担ぎ続ければいいのですが、重いのでどうしても前かがみになり一人でも掛け声が早い人がいるとそちらに合わされてしまいます。よい姿勢でかつ疲れにくい担ぎ方をするには、時間と経験が必要です。初めて神輿を担いだときは、次の日の朝目が覚めて布団から起き上がろうとしましたが、足に力が入らずひっくり返ってしまいました。
4.担ぐ場所はどこがいいの?
肩にピッタリと収まる所が一番担ぎやすい場所で、自分と同じくらいの背の高さ付近が丁度良いところになります。若くて可愛い女の子のそば・・と思いがちですが、背が低い女の子の近くは重くて大変です。一方自分より大きい人の近くでは背伸びをするだけでなく揺らすたびに肩にズシン・ズシンと当ります。先頭は先棒と言って一番目立つところです。先棒を担ぐには前から5番目くらいに入り、徐々に前に行くことが暗黙のルールになっています。先棒になったときは、背筋を伸ばし観客の目を意識しながら重いのを我慢して担ぎます。神輿は前が低く後を高くして渡御するのが通常で、前は特に重く感じます。私は、すぐに後の人と交代して逃げ出すことにしてします。人によって左肩・右肩の得意・不得意あり、また担ぐ場所も前・真ん中・神輿の下・後と好みが異なります。中にはどこへ行っても必ず同じ場所を担ぐ有名な人がいて、その人が来るとわざわざその指定席を空けたりします。
5.何人くらいでかつぐの?
小さな神輿ですと20人~30人くらいですが大きなものになると60~80人、時には100人近くなることもあります。頻繁に交代するので実際には2倍から3倍のくらいの人数になります。それでも担ぎきれないときは台車に乗せ押しながら歩き、時にはトラックに載せて移動します。
6.向いている職業は?
何と言っても鳶職、大工さん建築関係の人が向いています。祭り準備で行う神輿の組み立て、掲示板建て等の作業は本当に上手で素早く処理します。入会して30年位経つ私ですがいつも横で感心しながら見ています。普段、背広にネクタイ姿で仕事をしている人が袢纏を着ても、どこかすっきりしません。地元の祭りの時は帯を締めますが、鳶の人は帯を結びません。体に帯を巻き付け数回折りかえしながら端を中にしまい込みます。これだけで動いたり汗をかいたりしているうちに帯がどんどん締まっていき袢纏がゆるみません。以前、巻き方を教わったのですが未だに覚えることができません。
7.袢纏
袢纏にも流行があるようで丈が長くなった短くなったりします。「南貮」には3種類の袢纏があり、応援先に合わせた袢纏を会長が決め出かけます。ちなみに古くて色があせた袢纏を着ている人は周囲から格好良くみられます。汗かきな私の袢纏は色が剝げ落ちているため仲間から羨ましがられています。確かに新しくバリバリで色が鮮明な袢纏を着た人の立ち姿はちぐはぐな人が多いように感じます。
8.担いだあとは?
場所によってやり方は異なりますが、神事ですので宮入の儀式を行い直会(なおらい)といってワイワイガヤガヤと語り合いながら全員で酒食いたします。直会が済むとそれぞれの会ごとに一列に並んで掛け声とともに挨拶をして別れます。普通の生活では経験しない挨拶でなかなかいいものです。
9.担がないときは?練習は?
「南貮」には練習がありません。ただ新年会、忘年会だけでなく理由の無い反省会(飲み会)が時々あります。また毎年大晦日から元旦にかけて地元の神社で初詣客にお神酒と甘酒配り、お焚き上げをします。真夜中の12時なると横浜港から「ボー」という汽笛と神社の大きな太鼓の音を聞きながら「あけましておめでとう」の挨拶が恒例になっています。地元のお祭では子供会のお母さんたちと一緒に屋台を出します。私は、主にヨーヨー釣り、かき氷を担当しますが過去には綿飴作りや焼き鳥屋をしたこともあります。
10.最後に
神輿担ぎは、仲間と一緒に重いものをかつぐだけですが、呼び出しがかかると何故か出かけたくなります。気がむしゃくしゃしたとき、落ち込んだとき、考えに行き詰まっているときなど、汗をびっしょりかきながら担いでいると嫌なことは全て忘れてしまい気持ちがすっきりします。神輿担ぎは、本を読んで覚えるものではなく、何の知識もいりません。一度担ぐと病み付きになり、栄光出身者とは、少し違う仲間を知り交流が出来るようになります。

















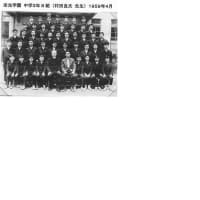



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます