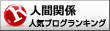礼拝宣教 創世記1章26節~2章4節前半
先週に続き今日は神による「人の創造」と創造が完成をした後に、「神が安息なさった」記事から御言葉に聞いていきます。
創造主であられる神は、第1の日の光の創造をはじめ、第2、第3,第4、第5、第6の日にご自身が創造されたそれぞれのものを「見て、良しとされた」とあります。さらにそれらのお造りになったすべてをご覧になって「見よ、それは極めて良かった」と絶賛なさるのです。神が創造された世界はなんと美しく「極めて良いものであるかを、見よ」と呼びかけているのです。ちなみに、ギリシャ語訳;70人訳の2章1節、さらに2節の「完成された」の前には、「共に」という前置詞があります。それらは「共に完成された」、つまり、すべての被造物のいのちは個別にあるのではなく、共につながり、共に補い合うことによって天地創造は「極めて良い」、その完成に至るのです。
創造主であられる神は、第1の日の光の創造をはじめ、第2、第3,第4、第5、第6の日にご自身が創造されたそれぞれのものを「見て、良しとされた」とあります。さらにそれらのお造りになったすべてをご覧になって「見よ、それは極めて良かった」と絶賛なさるのです。神が創造された世界はなんと美しく「極めて良いものであるかを、見よ」と呼びかけているのです。ちなみに、ギリシャ語訳;70人訳の2章1節、さらに2節の「完成された」の前には、「共に」という前置詞があります。それらは「共に完成された」、つまり、すべての被造物のいのちは個別にあるのではなく、共につながり、共に補い合うことによって天地創造は「極めて良い」、その完成に至るのです。
その神のお造りになった大自然と様々な生き物のいのちの営みを私たちも目にする時、それは時に感動を与えるほど美しく壮大で、神の御手の業への賛美が溢れてくるでしょう。
そのような中で殊に27節において、「神が御自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された」と、3度に亘って「人の創造」について語られています。
人は何と畏れ多いことか、神の似姿として創造されたというのです。
人は何と畏れ多いことか、神の似姿として創造されたというのです。
この神にかたどった神の似姿とは、外形が神に似ているという意味ではなく、その霊性においてであるのです。人は神との霊的交わり、交流をもつ存在であるということが、その本質として備えられているということです。
神は又、人を男と女に創造されたとあります。古今東西、社会における男性優位の権威主義が存在してきたわけですが。聖書は女性も男性と同じように神にかたどって創造されたのだと語ります。人はみな神にかたどって造られた尊厳があり、性差の違いによる特性はあっても決して優劣をつけられるものではないということです。男であれ、女であれ、その一人ひとりをかけがえのない存在、オンリーワンの存在として創造されているのです。どんなに似ていたとしても、どんなに近い血縁関係であっても「私」と同じ人はどこにもいません。世界中どこを探しても私という存在は唯一人なのです。だれも、一人ひとりが神の似姿として造られているという事を思う時、私たちは自分の、そして他者の存在と尊さ覚えることができるでしょう。
さらに、神はご自身の似姿に創造された人間を祝福してこう言われます。
さらに、神はご自身の似姿に創造された人間を祝福してこう言われます。
28節「産めよ、増えよ、地に満ちて地に従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべて支配せよ。」
神は人のほかにはこのようにお語りになりませんでした。唯、人の創造に際し初めて、28節でその男も女も祝福して語りかけておられるのです。
神は人のほかにはこのようにお語りになりませんでした。唯、人の創造に際し初めて、28節でその男も女も祝福して語りかけておられるのです。
神はそのお造りになった自然界の生き物、動物を、「すべて支配せよ」とお命じになられます。しかし、この「支配せよ」という意味は、権力を自分たちに都合のよいように使い、思い通りにしてよいという意味ではありません。創造主のご意思に沿った統治であり、管理者として務めでありましょう。
ところが、如何に人間はその神の言葉を取り違えて乱用し、むさぼりと無責任によって神の祝福をないがしろにし、損なってきたことでしょう。
神が「極めて良かった」とされたこの世界に不正と搾取と暴力が起こり、自然環境に至っては壊滅的ともいえる現況を頻繁に目にするようになりました。戦争や核の問題もそうです。
神は極めて良い、とお造りになったこの世界を人が正しく守り治めていくようにと、その働きを託しておられる。そのことが今日、私たちはじめ、すべての人に思い起こされていくように祈り続けてまいりましょう。
さらに、神は人に向けて次のように呼びかけます。
29節「『見よ、全地に生える、種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物になる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべていのちあるものはあらゆる青草を食べさせよう。』そのようになった。」
29節「『見よ、全地に生える、種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物になる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべていのちあるものはあらゆる青草を食べさせよう。』そのようになった。」
全世界で食糧危機は深刻な問題です。いろんな要因はありますが、日本国内でも食材が日増しに高くなっていますが。今や長い網や虫籠をもって追っかけていたセミやコオロギなどの昆虫も加工し、一般的食料になろうとしています。
それらも戦争やグローバル化などから食材に係わる生産者に負担を強いるような事が起き続けてきた結果といえるかも知れません。又、動物のいのちも脅かされ、これまで地球上に生息してきた鳥、魚、動物、昆虫がだんだん減り、絶滅危惧種も増え、神の作品が次第に地球から消えています。
先にも触れましたが、神の似姿として創造された人間は、同じく神によって造られ、生かされている自然界の植物、動物、あらゆる生きものと共に生き、そのいのちとつながりながら存在している、そのところに、神の祝福が与えられます。あらゆるいのちと共生していくために私たちそれぞれに身近なところから何ができるか、祈り求めてまいりましょう。
今日のもう一つのメッセージは、「主の安息」についてです。
2章2節で、「第7日に、神は御自分の仕事を完成され、第七の日に、神は御自分の仕事を離れ、安息なさった」とあります。
2章2節で、「第7日に、神は御自分の仕事を完成され、第七の日に、神は御自分の仕事を離れ、安息なさった」とあります。
神が「御自分の仕事を離れ安息なさった。」そのように「安息日」とは、読んで字のごとく「安心して一息つく日」のことでありますが。ところで、お休みの日はどのように過ごされますか?なかには日頃できない選択や片付け、その他諸々で休んだ気がしないという人もおられるかと思います。が、ただ休むといっても、体を休めるだけで真の休息を得ることができるでしょうか。レジャーやショッピングを楽しむだけで真の安らぎは得られるでしょうか。そういう自由な選び取りの中で、この場にお出でになった皆さまは時を聖別し、神を礼拝できる期待と喜びをもって集っておられるでしょう。
それは、私どもにとりましてこの日が、イエス・キリストの死と復活を記念する日曜日としてずっと礼拝が守られてきたわけであります。そしてその根底には、あの出エジプトによって救われ神の民に与えられた十戒の1つであった「安息日」に関する戒めがあるのです。
エジプトの地で奴隷とされ、苦役の労働を強いられたイスラエルの民の姿です。不当に働かされ、どれだけ仕事をしても終わりなく、肉体も精神もぼろぼろになって苦痛を経験したイスラエルの民。
出エジプト3章で、神はモーセに言われます。「わたしは、エジプトにいるわたしの民の苦しみをつぶさに見、追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知った。」そうして神はモーセを指導者として立て、出エジプトという奴隷からの解放を遂行なさるのです。
そうして神はイスラエルと契約を交わし、シナイ山で十戒をお授けになられます。その序文には「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である」と述べられ、その十戒の中に、「安息日に関する」戒めが収められます。
「安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、7日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。」
申命記5章12節以降には、「そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのために、あなたの神、主は安息日を守り行うように命じられたのである」と、記されています。
このように安息日は、まず仕事の手を止めて、神の民として導きたもう「「主を礼拝する」日であるということです。それは同時に、あなたが仕事を止めることによって身近な隣人や家畜までも休ませ、安息させることになる、ということです。
以前ニュースで、残業を無くしオーバーワークを防ぐため終業時間が近づくとパソコンが警報音を鳴らし、3回警告しても切らない場合、強制的にシャットダウンされてしまうという方策をとるようになったある役所の様子が映っていましたけども。まあそんなことまでしなければならないほど、意識して、体も心も休まなければつい働いてしまい、又、働かせてしまうものなのだなぁと思います。人が人らしく生きていくための休息はやはり必要であります。けれど先にも申しましたが、それが一時的には気分転換や一休みになっても、本来の生きる力を取り戻すものになるかはわかりません。実に多くの現代人が日曜夕方から月曜にかけて憂鬱な気分と不調を訴えるのはよく知られていることですが。
単なる休日ではなく本物の安息に与るためには、「すべての創造主、いのちの源であられるお方に立ち返る」。そこに人間本来の安らぎ、憩いが得られるのです。
まさにそのために、救いの主、イエス・キリストが来てくださったのです。主イエスは言われました。「疲れた者、重荷を負う者はわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。」(マタイ11章28節)この方こそ「安息の主」であります。それが始めに申しましたように、7日目の安息日があって完成ということの中に込められている重要なメッセージなのかという思いがいたします。
主イエスは罪の世の奴隷であった私たちに救いと解放をもたらすため、自ら十字架にかかり死なれました。しかし、いのちをお与えになることのできる天地創造の神が死より復活させられたのです。、それは又、キリストによって神との和解、平和を与えられた私たちが、キリストによって死の滅びから復活のいのち、新生の喜びと希望につながっています。このような救いに与っている感謝をもって神に礼拝を捧げているこの時、そして日々の礼拝なのです。
出エジプトの時代、さらにバビロン捕囚時代とその解放を経験したイスラエルの民がそうであったように、天地創造の神が遣わして下さったイエス・キリストの十字架と復活のみ業によって神の御前における安息、天地創造の初めにあった安息に与らせて頂いているのです。
今日は、人の創造について御言葉を読んできましたが。この「創造」は新約聖書に照らして読めば、「人が新しく生まれ変る」ということでありましょう。神の御前に日々新しくされる。安息の礼拝を通して新たにされる。そこが聖書の中心のメッセージであり、その原点こそ、創世記の2章3節の「第7の日を神は祝福し、聖別された」といういのちの御言葉にございます。この御言葉に促されて魂の真の安息、新生の創造が完成されたこの主の日からの祝福の歩みを感謝をもって、始めていきたいと思います。