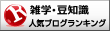礼拝宣教 ルカ15章11~32節
今日は受難節(レント)の最初の主日礼拝となります。主イエスの十字架の受難と死を心に留めつつ、4月5日の復活祭・イースター礼拝に備えてあゆんでいきたいと思います。
先週は礼拝後ここで連合壮年会講演と総会があり、月曜には連合牧師研修会で、白浜の三段壁で自殺を水際で防ぎ、保護して受入れるまでの活動をされている藤藪庸一牧師の貴重な講演をお聞きしました。又、水曜祈祷会をはさんで木曜には関西地方連合の役員会、そして古賀教会の金子敬牧師の講演による連合教育信徒研修会と、大阪教会を会場にした諸集会が目白押しに開催されました。会場教会としてこのように用いて頂けるというのは、本当に会堂を建て替えた意義があったとつくづく思いますね。これかたも益々主に用いて頂き、連合や連盟との信徒の絆をつなげる一助になる事を願うものです。
季節は春に向かっての三寒四温とはいえまだ寒さの厳しい日々が続いております。1月から始りました路上生活をされている方々への越冬夜回活動もいよいよ今週金曜日のあと1回を残すことになりました。この日は静岡県にあるルーテル教会の施設「デンマーク牧場」の少年少女十数人が参加合流しての夜回りになると伺っています。どうか苦境に立たされている方々をおぼえ、お祈りください。
さて、先々週は「善きサマリア人」のたとえ、先週は「愚かな金持ち」のたとえと、主イエスのたとえ話を読んできましたが。本日もまたルカ15章のいわゆる「放蕩息子」のたとえから御言葉を聞いていきたいと思います。
「ある人に息子が二人いた」。彼は二人の息子の父親であり、多くの財産を所有する人でありました。ところがその弟の方が、父親が生きているというのに、将来自分がもらえると予想される財産を、今欲しいと言い出すのです。父親がまだまだ元気でいるのに財産を分けてもらいたいとはとんでもないと思いますけれども。まあ、なぜこの息子がそう言いだしたのか分かりませんが、自分一人で立派に生きていけると息がっていたのか。あるいは、誰からも拘束されない気ままな人生を送りたかったのかも知れません。けれども、その弟息子が自分一人でいきるための資金は、自分自身で稼いだものではなく、不当に要求した父親の財産であったのですね。まあそのようなどら息子を持つこの父親でありますが、何とこの父親はその弟息子の不当な要求に対して、「財産を二人に分けてやった」というのですね。何という親ばかでしょうか。この父親は弟息子だけに財産を分け与えたのではなく、兄息子にも同様に分けてやったのですね。もはや気前がよいというレベルを超えて非常識なくらいです。
しかしそこには、このたとえ話の中心を貫いているメッセージ(大前提)が示されているのです。
それは、この父親がこれほど惜しみなく与え尽くすほど、2人の息子をそれぞれに愛してやまないということです。弟息子がかわいいから、心配だから彼だけにというのではなく、財産を要求していない兄息子にもそれを与えたように、この父親にとってはどちらも惜しみなく愛してやまないかけがえのない息子たちなのですね。
さて、父親から財産を分けてもらった弟息子のその後についてですが。彼は何と父から譲りうけた財産の全部をお金にかえてしまい、遠い父の目の届かない国へ旅立ち、そこで放蕩の限りをつくして、そのお金を無駄使いしてしまうのです。そして何もかも使い果たしてしまったそのような時に、追い打ちをかけるように飢饉が起こり、彼は食べる物にも困り始め、結局、彼は異邦人のある豚を飼う主人のもとに身を寄せることになります。ユダヤ人にとって豚は汚れた動物とされていたので、飼ったりその肉を食べることはありません。が、彼はそういうユダヤの人々が忌み嫌うところのその家に身をおく以外ないような状況に追い込まれるのです。しかも彼は極度の飢えから、豚の餌さえも食べたいほどであったのですが、何とそれさえ分けてくれる人がいないという、どん底のような惨めな目に遭うのです。
17節、「そこで、彼は我に返って言った」。彼はそのような状況になって初めて「はっ」と我に返るのですね。彼は肉体的に飢え死にしそうな状態でしたが、それは単に肉体の飢え死にだけでなく、魂の飢え渇きを自覚するのです。「いったい自分はこうなるまで何をしていたんだ」「何と愚かなことをしたんだろう」。そうして父の家を思い出すのであります。「父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどのパンがあるに、わたしはここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください』と。」
そして、彼はそこをたち、父親のもとに向かいます。そこにはきっと意気揚々と出て行った時の面影もなく、弱り、やせ細り、身なりもボロボロだったのではないでしょうか。ところが、「まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した」とあります。
父親は息子のやせ細り変りはてた姿を見て、これは単に可哀そうに思ったとか、哀れんだというのではありません。ここで、息子を見て「憐れに」思ったというのは、腸がちぎれんばかりの思いという原語の意味です。父親はまさに「断腸の思いに駆られ」走り寄って息子の首を抱き、接吻するのです。この父親はどれ程息子を愛しているか、と思うのでありますが。イエスさまはまさしく、ここに父なる神ご自身のお姿をお示しになっているのであります。父なる神さまは、これ程までにさまよい出た一人の人のその魂を愛しく思い、その魂が立ち返ることを待ち望んでおられる、ということなのですね。
そこで、息子は父に対して心に決めていた言葉を口にします。「お父さん、もう息子と呼ばれる資格はありません」。実はここに「雇い人の一人にして下さい」という言葉が入るはずでした。しかし息子がそれを口にする前に父親は僕たちに、「急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう」と言うのです。
(岩波訳聖書)24節「なぜなら、私のこの息子は死んでいたのにまた生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」と言うのですね。
もう息子と呼ばれる資格はない。雇い人(奴隷)の一人にしてくださいと息子は思うのでありますが、この父親にとってはたとえどんな状況にあったとしても、変わることのない息子なのです。息子が奴隷のような者になることを決して望まれないのです。
棄てるように家を出て行き財産を食いつぶされ、周囲には恥をかかされたあげくボロボロになって帰って来た息子を、世間一般の考えであれば、そんなもん関係ない。まあ奴隷となっていたのなら理解できますが。しかし、その彼を奴隷としてではなく息子として無条件に受け入れ、その喜びを最大限に表すこの親の姿。それはまさに父なる神さまの愛を表しています。この罪を犯した息子を赦し、受け入れたという背後には、父なる神さまの大きく尊い自己犠牲があります。
私たちはどうでしょうか。かつては父なる神さまの愛を知らず、思うままに生きる者ではなかったでしょうか。しかし神はそんな私を愛し、無条件で受け入れて最大の愛、犠牲を払われたのです。そうです、御独り子のイエス・キリストの十字架の痛みと苦しみ、そして悲惨な死という大きな代価を払って私の罪を贖い、ゆるし、子として受入れて下さったのですね。「この息子は死んでいたのにまた生き返った。失われていたのに見つかった」。今こうして主によって「新しい命」と「神の国の幸い」とに与らせて戴いていることを心から感謝するものです。
たとえの後半に移りますが、そこは兄息子と父親に焦点が向けられています。
兄は畑で変ることなく労働に勤しんでおりました。弟は父から財産をもらうと出て行きましたが、兄は父から財産をもらった後も、忠実に父の家に仕えて来たのです。そこにはユダヤの民が様々な歴史的な困難な中でも信仰を守り、神の律法を守るよう努めてきた背景が読み取れます。そしてそれは又、その民を指導してきた祭司や律法学者たちの姿にも重ねられています。
兄息子は放蕩のあげくに帰ってきた弟のために催されているお祭り騒ぎを知った時、怒って父の家に入ろうとはしませんでした。彼はこの父に対して、「このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、わたしが友達と宴会するために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる」と怒りをぶちまけます。
世間の常識で言えば、この兄の抗議というのはもっともな気もいたします。この兄は父の家でひたすら仕え、従ってきたのです。それだからこそ、「何であんな放蕩の息子のために。不公平だ」と激しい怒りが込み上げてきたのですね。
すると、父親は兄息子を優しく諭すように言われます。「子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」。
父親は兄息子に、三つのこと言います。
一つは、「あなたはいつもわたしと一緒にいる」。
確かにそうですね。兄はいつも父親と一緒でした。けれども彼はその父親の愛情の深さになかなか気づくことができません。実際にはそいうものかも知れません。身近にいる時の方がなかなか気づくことができないのが親の愛情なのかも知れません。
二つ目は「わたしのものは全部あなたのものだ」。
兄は「わたしのためには子山羊一匹すらくれなかった」と言うのですが。父親はちゃんとこの兄にも財産を分け与えているんですね。彼はその大きく尊い恵みに気づいていない。心が鈍くなっていたのです。
そして父親が言った三つ目は、「あなたのあの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」。
父親が「あなたのあの弟」と言ったのは、兄が弟のことを「自分の弟」とはいわず、「あなたのあの息子」と他人のように呼んだからです。そんな兄息子に父は「あなたの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに見つかったのだ」と諭すのであります。
そもそもイエスさまがこのたとえ話をなさったのは、15章の冒頭にありますように、で「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、『この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている』と不平を言いだした」という事態に対して、イエスさまは「見失った羊」のたとえ、続く「失くした銀貨」のたとえ、そして今日のたとえ話をなさったのですね。
イエスさまはこれらのたとえ話を通して、ファリサイ派の人々や律法学者たち常に主なる神のみもとにある存在と描きます。迷っていない九十九匹の羊、又、失われていない九枚の銀貨、また父の家にいる兄息子として描きます。その一方で、イエスさまは罪人といわれていた人たちや徴税人を、迷い出た一匹の羊、失われた一枚の銀貨、父の家から遠く離れていた弟息子というかけがえのない存在として描きだされるのです。
そのメッセ―ジの中心は、ファリサイ人や律法学者然り、また徴税人や罪人と呼ばれていた人々然り、この両者に「父なる神さまが注ぎ込まれる愛」なのです。
そしてこのたとえ話のクライマックスは、羊飼いが100匹の中の迷い出た1匹を見つけ出すまで探し回り100匹の群れとして取り戻されたように。又10枚の銀貨の中の失われていた1枚を家じゅうで探し回って見つけ宝の10枚として取り戻されたように、父にとってかけがえのない2人の息子が、兄弟として共に父の家にある、ということを父なる神さまは切に願っておられるということであります。そこに言い尽せない大きな天の喜びと祝福が、この弟の帰りを祝う父の家に満ち溢れるというメッセージであります。
この父なる神の愛によって受け入れられている私たちも又、御子イエスさまの十字架をとおして示しお与えくださった神さまの愛を分ち合うべく集うお互いを喜び合い、祝福に溢れる主イエスの救いの証しの教会とされてまいりましょう。
今日は受難節(レント)の最初の主日礼拝となります。主イエスの十字架の受難と死を心に留めつつ、4月5日の復活祭・イースター礼拝に備えてあゆんでいきたいと思います。
先週は礼拝後ここで連合壮年会講演と総会があり、月曜には連合牧師研修会で、白浜の三段壁で自殺を水際で防ぎ、保護して受入れるまでの活動をされている藤藪庸一牧師の貴重な講演をお聞きしました。又、水曜祈祷会をはさんで木曜には関西地方連合の役員会、そして古賀教会の金子敬牧師の講演による連合教育信徒研修会と、大阪教会を会場にした諸集会が目白押しに開催されました。会場教会としてこのように用いて頂けるというのは、本当に会堂を建て替えた意義があったとつくづく思いますね。これかたも益々主に用いて頂き、連合や連盟との信徒の絆をつなげる一助になる事を願うものです。
季節は春に向かっての三寒四温とはいえまだ寒さの厳しい日々が続いております。1月から始りました路上生活をされている方々への越冬夜回活動もいよいよ今週金曜日のあと1回を残すことになりました。この日は静岡県にあるルーテル教会の施設「デンマーク牧場」の少年少女十数人が参加合流しての夜回りになると伺っています。どうか苦境に立たされている方々をおぼえ、お祈りください。
さて、先々週は「善きサマリア人」のたとえ、先週は「愚かな金持ち」のたとえと、主イエスのたとえ話を読んできましたが。本日もまたルカ15章のいわゆる「放蕩息子」のたとえから御言葉を聞いていきたいと思います。
「ある人に息子が二人いた」。彼は二人の息子の父親であり、多くの財産を所有する人でありました。ところがその弟の方が、父親が生きているというのに、将来自分がもらえると予想される財産を、今欲しいと言い出すのです。父親がまだまだ元気でいるのに財産を分けてもらいたいとはとんでもないと思いますけれども。まあ、なぜこの息子がそう言いだしたのか分かりませんが、自分一人で立派に生きていけると息がっていたのか。あるいは、誰からも拘束されない気ままな人生を送りたかったのかも知れません。けれども、その弟息子が自分一人でいきるための資金は、自分自身で稼いだものではなく、不当に要求した父親の財産であったのですね。まあそのようなどら息子を持つこの父親でありますが、何とこの父親はその弟息子の不当な要求に対して、「財産を二人に分けてやった」というのですね。何という親ばかでしょうか。この父親は弟息子だけに財産を分け与えたのではなく、兄息子にも同様に分けてやったのですね。もはや気前がよいというレベルを超えて非常識なくらいです。
しかしそこには、このたとえ話の中心を貫いているメッセージ(大前提)が示されているのです。
それは、この父親がこれほど惜しみなく与え尽くすほど、2人の息子をそれぞれに愛してやまないということです。弟息子がかわいいから、心配だから彼だけにというのではなく、財産を要求していない兄息子にもそれを与えたように、この父親にとってはどちらも惜しみなく愛してやまないかけがえのない息子たちなのですね。
さて、父親から財産を分けてもらった弟息子のその後についてですが。彼は何と父から譲りうけた財産の全部をお金にかえてしまい、遠い父の目の届かない国へ旅立ち、そこで放蕩の限りをつくして、そのお金を無駄使いしてしまうのです。そして何もかも使い果たしてしまったそのような時に、追い打ちをかけるように飢饉が起こり、彼は食べる物にも困り始め、結局、彼は異邦人のある豚を飼う主人のもとに身を寄せることになります。ユダヤ人にとって豚は汚れた動物とされていたので、飼ったりその肉を食べることはありません。が、彼はそういうユダヤの人々が忌み嫌うところのその家に身をおく以外ないような状況に追い込まれるのです。しかも彼は極度の飢えから、豚の餌さえも食べたいほどであったのですが、何とそれさえ分けてくれる人がいないという、どん底のような惨めな目に遭うのです。
17節、「そこで、彼は我に返って言った」。彼はそのような状況になって初めて「はっ」と我に返るのですね。彼は肉体的に飢え死にしそうな状態でしたが、それは単に肉体の飢え死にだけでなく、魂の飢え渇きを自覚するのです。「いったい自分はこうなるまで何をしていたんだ」「何と愚かなことをしたんだろう」。そうして父の家を思い出すのであります。「父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどのパンがあるに、わたしはここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください』と。」
そして、彼はそこをたち、父親のもとに向かいます。そこにはきっと意気揚々と出て行った時の面影もなく、弱り、やせ細り、身なりもボロボロだったのではないでしょうか。ところが、「まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した」とあります。
父親は息子のやせ細り変りはてた姿を見て、これは単に可哀そうに思ったとか、哀れんだというのではありません。ここで、息子を見て「憐れに」思ったというのは、腸がちぎれんばかりの思いという原語の意味です。父親はまさに「断腸の思いに駆られ」走り寄って息子の首を抱き、接吻するのです。この父親はどれ程息子を愛しているか、と思うのでありますが。イエスさまはまさしく、ここに父なる神ご自身のお姿をお示しになっているのであります。父なる神さまは、これ程までにさまよい出た一人の人のその魂を愛しく思い、その魂が立ち返ることを待ち望んでおられる、ということなのですね。
そこで、息子は父に対して心に決めていた言葉を口にします。「お父さん、もう息子と呼ばれる資格はありません」。実はここに「雇い人の一人にして下さい」という言葉が入るはずでした。しかし息子がそれを口にする前に父親は僕たちに、「急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう」と言うのです。
(岩波訳聖書)24節「なぜなら、私のこの息子は死んでいたのにまた生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」と言うのですね。
もう息子と呼ばれる資格はない。雇い人(奴隷)の一人にしてくださいと息子は思うのでありますが、この父親にとってはたとえどんな状況にあったとしても、変わることのない息子なのです。息子が奴隷のような者になることを決して望まれないのです。
棄てるように家を出て行き財産を食いつぶされ、周囲には恥をかかされたあげくボロボロになって帰って来た息子を、世間一般の考えであれば、そんなもん関係ない。まあ奴隷となっていたのなら理解できますが。しかし、その彼を奴隷としてではなく息子として無条件に受け入れ、その喜びを最大限に表すこの親の姿。それはまさに父なる神さまの愛を表しています。この罪を犯した息子を赦し、受け入れたという背後には、父なる神さまの大きく尊い自己犠牲があります。
私たちはどうでしょうか。かつては父なる神さまの愛を知らず、思うままに生きる者ではなかったでしょうか。しかし神はそんな私を愛し、無条件で受け入れて最大の愛、犠牲を払われたのです。そうです、御独り子のイエス・キリストの十字架の痛みと苦しみ、そして悲惨な死という大きな代価を払って私の罪を贖い、ゆるし、子として受入れて下さったのですね。「この息子は死んでいたのにまた生き返った。失われていたのに見つかった」。今こうして主によって「新しい命」と「神の国の幸い」とに与らせて戴いていることを心から感謝するものです。
たとえの後半に移りますが、そこは兄息子と父親に焦点が向けられています。
兄は畑で変ることなく労働に勤しんでおりました。弟は父から財産をもらうと出て行きましたが、兄は父から財産をもらった後も、忠実に父の家に仕えて来たのです。そこにはユダヤの民が様々な歴史的な困難な中でも信仰を守り、神の律法を守るよう努めてきた背景が読み取れます。そしてそれは又、その民を指導してきた祭司や律法学者たちの姿にも重ねられています。
兄息子は放蕩のあげくに帰ってきた弟のために催されているお祭り騒ぎを知った時、怒って父の家に入ろうとはしませんでした。彼はこの父に対して、「このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、わたしが友達と宴会するために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる」と怒りをぶちまけます。
世間の常識で言えば、この兄の抗議というのはもっともな気もいたします。この兄は父の家でひたすら仕え、従ってきたのです。それだからこそ、「何であんな放蕩の息子のために。不公平だ」と激しい怒りが込み上げてきたのですね。
すると、父親は兄息子を優しく諭すように言われます。「子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」。
父親は兄息子に、三つのこと言います。
一つは、「あなたはいつもわたしと一緒にいる」。
確かにそうですね。兄はいつも父親と一緒でした。けれども彼はその父親の愛情の深さになかなか気づくことができません。実際にはそいうものかも知れません。身近にいる時の方がなかなか気づくことができないのが親の愛情なのかも知れません。
二つ目は「わたしのものは全部あなたのものだ」。
兄は「わたしのためには子山羊一匹すらくれなかった」と言うのですが。父親はちゃんとこの兄にも財産を分け与えているんですね。彼はその大きく尊い恵みに気づいていない。心が鈍くなっていたのです。
そして父親が言った三つ目は、「あなたのあの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに、見つかったのだ」。
父親が「あなたのあの弟」と言ったのは、兄が弟のことを「自分の弟」とはいわず、「あなたのあの息子」と他人のように呼んだからです。そんな兄息子に父は「あなたの弟は死んでいたのに生き返った。失われていたのに見つかったのだ」と諭すのであります。
そもそもイエスさまがこのたとえ話をなさったのは、15章の冒頭にありますように、で「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、『この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている』と不平を言いだした」という事態に対して、イエスさまは「見失った羊」のたとえ、続く「失くした銀貨」のたとえ、そして今日のたとえ話をなさったのですね。
イエスさまはこれらのたとえ話を通して、ファリサイ派の人々や律法学者たち常に主なる神のみもとにある存在と描きます。迷っていない九十九匹の羊、又、失われていない九枚の銀貨、また父の家にいる兄息子として描きます。その一方で、イエスさまは罪人といわれていた人たちや徴税人を、迷い出た一匹の羊、失われた一枚の銀貨、父の家から遠く離れていた弟息子というかけがえのない存在として描きだされるのです。
そのメッセ―ジの中心は、ファリサイ人や律法学者然り、また徴税人や罪人と呼ばれていた人々然り、この両者に「父なる神さまが注ぎ込まれる愛」なのです。
そしてこのたとえ話のクライマックスは、羊飼いが100匹の中の迷い出た1匹を見つけ出すまで探し回り100匹の群れとして取り戻されたように。又10枚の銀貨の中の失われていた1枚を家じゅうで探し回って見つけ宝の10枚として取り戻されたように、父にとってかけがえのない2人の息子が、兄弟として共に父の家にある、ということを父なる神さまは切に願っておられるということであります。そこに言い尽せない大きな天の喜びと祝福が、この弟の帰りを祝う父の家に満ち溢れるというメッセージであります。
この父なる神の愛によって受け入れられている私たちも又、御子イエスさまの十字架をとおして示しお与えくださった神さまの愛を分ち合うべく集うお互いを喜び合い、祝福に溢れる主イエスの救いの証しの教会とされてまいりましょう。