講演会聴講のため、久方ぶりに母校を訪れました。
実に10年ぶり。
10年の間に母校は学部が増え、生徒数も増え、
大学の建物も倍以上に増え、と取り巻く環境が大きく様変わりしており。
その一方で、大学周辺の地域は個人商店が次々と姿を消し
更地が増え、在学時より一層空の広い地域となっていました。
10年て本当に大きいんだな、ということを肌で実感できた一日。
そんな中、お世話になっていたパンやさんはまだ営業していて
私のこともすぐに分かってくださいました。
いろんなお店がなくなっていた商店街の中で
今も変わらず営業していたことも大きな喜びでしたが
お店の奥さんが私を「思い出してくれた」のではなく
「分かってくれた」っていうのが本当に本当にうれしかったなー。
以下、講演会を聞いて。
自分の頭を整理するためのメモです。
講演タイトル:今、ソーシャルワーカーに求められる使命
講演者:ルーテル学院大 西原教授
・ある児童養護施設のスーパーバイザをしていた際、
施設内の雰囲気に問題があること、施設を「家庭」ではなく
「軍隊」のような雰囲気にしている職員がいること、
その職員は児童と適切に関われていないことを意見書にまとめて提出した。
・施設長は、意見書を確認後、自分でもそれらの事実を認めて
職員の配置転換を実行した。
・配置転換をされた職員は「不当な配置転換」だとして裁判に。
・第一審は敗訴。
敗訴理由は「児童養護施設の職員に対して、高度な理念や技能、役割を
求めるような制度はどこにもない。現時点では、役割として求められている
ことがきちんと明文化されていない。それなのに、求められている役割が
果たせていない、という理由で配置転換を行うことは不当である。」
・上告。
最高裁では逆転勝訴。
勝訴理由は「書類や制度で定められていはいないが、世界の流れから
見ても、児童に関わる者は専門的な役割を求められてしかるべきである。
よって今回の配置転換は不当としない。」
・もし、上告していなかったらどうなっていたのか。
何をするにしても、理念を持って、思いをもって行動する必要がある。
自分たちが大切にするもの、「求めるもの」を明確にして行動するべき。
・グループケアホームや児童養護施設の職員は、仕事内容は「お母さん」
とほぼ同じであり、現時点では専門性が認められないため、給料も非常に低い。
・しかし、児童や入所者を支配しようと思えばできる仕事である。
・だからこそ、専門性が求められる。はず。
・しかし、今はまだ専門性のないまま、仕事をしている人が多い。
・きちんとした制度が必要な分野である。
特に人の配置に関しては根本的な制度が必要。
・ソーシャルワーカーに求められること
⇒1を聞いて10を知ることではない。
⇒当事者に10を話してもらうことである。
⇒当事者の話す量がワーカーより多くなくてはならない。
・利用者の一番身近にいる人(職員)がレベルアップしなければ、
利用者に質の良い暮らしは提供できない。
⇒つまり、利用者の一番身近にいる人は、利用者の権利侵害を
行う可能性は大きい。
・福祉は感情労働である。
・感情労働とは「人格的な関わりを持ちながら人を支援する労働。」
・勿論、人と関わるからこそ、失敗はつきものである。
・プロとは「失敗を失敗と認識できる人。失敗を認識した上で
なぜ失敗が起きたのか、組織としてどう対応するのか」を
データとしてストックできる人である。
・今、社会福祉の現場は転換期ゆえに混沌としている。
・福祉施設の経営も非常に難しく、求人をしても人が集まらない。
「モノからヒトへ」という政治家の言葉は今こそ、実行されるべき。
・現在、生活保護は「削減対象」として話題に上ることが多い。
しかし、生活保護は最も内需拡大に貢献している。
「必ず地域経済に貢献されている」側面もあることを見てほしい。
実に10年ぶり。
10年の間に母校は学部が増え、生徒数も増え、
大学の建物も倍以上に増え、と取り巻く環境が大きく様変わりしており。
その一方で、大学周辺の地域は個人商店が次々と姿を消し
更地が増え、在学時より一層空の広い地域となっていました。
10年て本当に大きいんだな、ということを肌で実感できた一日。
そんな中、お世話になっていたパンやさんはまだ営業していて
私のこともすぐに分かってくださいました。
いろんなお店がなくなっていた商店街の中で
今も変わらず営業していたことも大きな喜びでしたが
お店の奥さんが私を「思い出してくれた」のではなく
「分かってくれた」っていうのが本当に本当にうれしかったなー。
以下、講演会を聞いて。
自分の頭を整理するためのメモです。
講演タイトル:今、ソーシャルワーカーに求められる使命
講演者:ルーテル学院大 西原教授
・ある児童養護施設のスーパーバイザをしていた際、
施設内の雰囲気に問題があること、施設を「家庭」ではなく
「軍隊」のような雰囲気にしている職員がいること、
その職員は児童と適切に関われていないことを意見書にまとめて提出した。
・施設長は、意見書を確認後、自分でもそれらの事実を認めて
職員の配置転換を実行した。
・配置転換をされた職員は「不当な配置転換」だとして裁判に。
・第一審は敗訴。
敗訴理由は「児童養護施設の職員に対して、高度な理念や技能、役割を
求めるような制度はどこにもない。現時点では、役割として求められている
ことがきちんと明文化されていない。それなのに、求められている役割が
果たせていない、という理由で配置転換を行うことは不当である。」
・上告。
最高裁では逆転勝訴。
勝訴理由は「書類や制度で定められていはいないが、世界の流れから
見ても、児童に関わる者は専門的な役割を求められてしかるべきである。
よって今回の配置転換は不当としない。」
・もし、上告していなかったらどうなっていたのか。
何をするにしても、理念を持って、思いをもって行動する必要がある。
自分たちが大切にするもの、「求めるもの」を明確にして行動するべき。
・グループケアホームや児童養護施設の職員は、仕事内容は「お母さん」
とほぼ同じであり、現時点では専門性が認められないため、給料も非常に低い。
・しかし、児童や入所者を支配しようと思えばできる仕事である。
・だからこそ、専門性が求められる。はず。
・しかし、今はまだ専門性のないまま、仕事をしている人が多い。
・きちんとした制度が必要な分野である。
特に人の配置に関しては根本的な制度が必要。
・ソーシャルワーカーに求められること
⇒1を聞いて10を知ることではない。
⇒当事者に10を話してもらうことである。
⇒当事者の話す量がワーカーより多くなくてはならない。
・利用者の一番身近にいる人(職員)がレベルアップしなければ、
利用者に質の良い暮らしは提供できない。
⇒つまり、利用者の一番身近にいる人は、利用者の権利侵害を
行う可能性は大きい。
・福祉は感情労働である。
・感情労働とは「人格的な関わりを持ちながら人を支援する労働。」
・勿論、人と関わるからこそ、失敗はつきものである。
・プロとは「失敗を失敗と認識できる人。失敗を認識した上で
なぜ失敗が起きたのか、組織としてどう対応するのか」を
データとしてストックできる人である。
・今、社会福祉の現場は転換期ゆえに混沌としている。
・福祉施設の経営も非常に難しく、求人をしても人が集まらない。
「モノからヒトへ」という政治家の言葉は今こそ、実行されるべき。
・現在、生活保護は「削減対象」として話題に上ることが多い。
しかし、生活保護は最も内需拡大に貢献している。
「必ず地域経済に貢献されている」側面もあることを見てほしい。















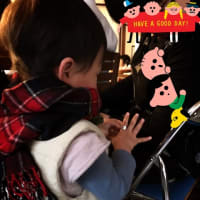




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます