一昨日、デュッセルドルフのロバート・シューマンホールで開かれた雅楽と舞楽の夕べに行ってきました。
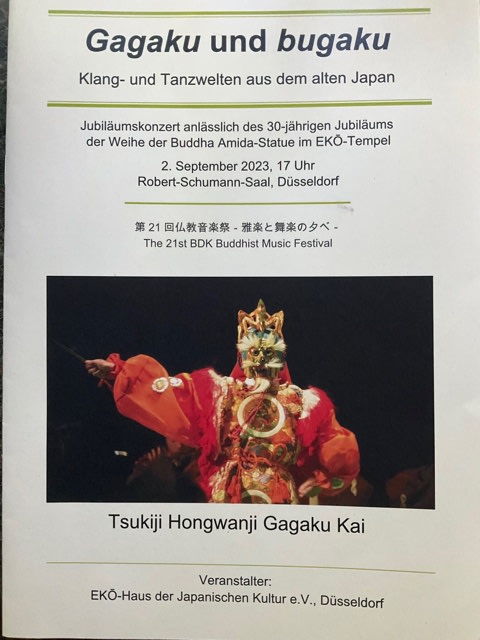

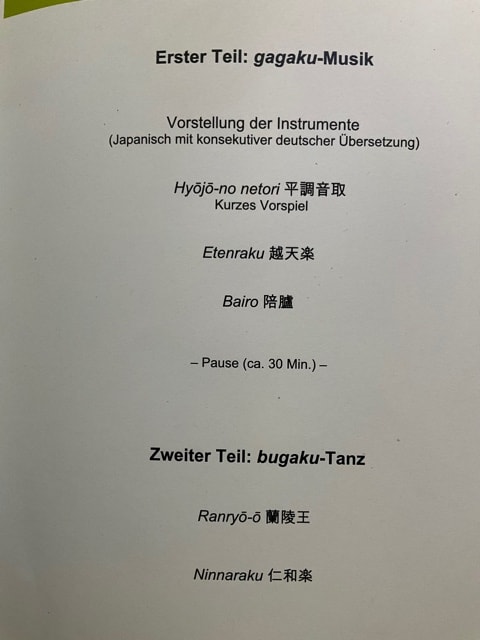



デュッセルドルフにある浄土真宗のお寺、恵光寺本堂に設置された阿弥陀仏の入仏式30周年を記念する演奏会です。
築地本願寺雅楽会の優雅な音色と幽玄の舞を堪能しました。
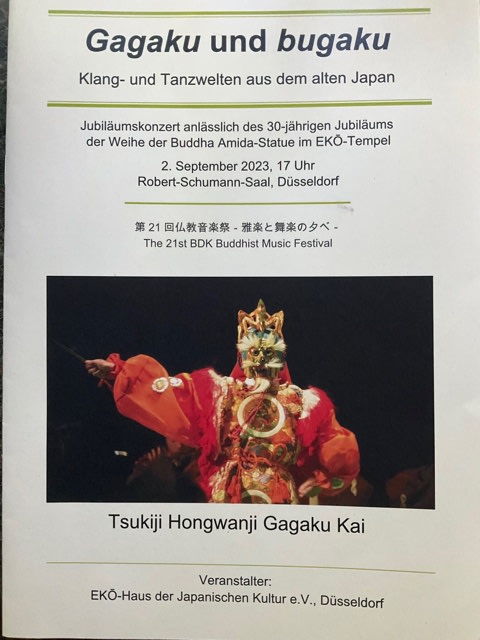
演奏前の楽器の説明も興味深かったです。
篳篥は地上の音、笙は天上の音、そして龍笛はその間を動く龍の声ということで、
雅楽は宇宙空間の響きなのだそうです。

雅楽は以前ケルンでも聴いたことがあり、その時も平調音取と越天楽が演奏されました。
舞楽の蘭陵王と仁和楽は初めてでした。
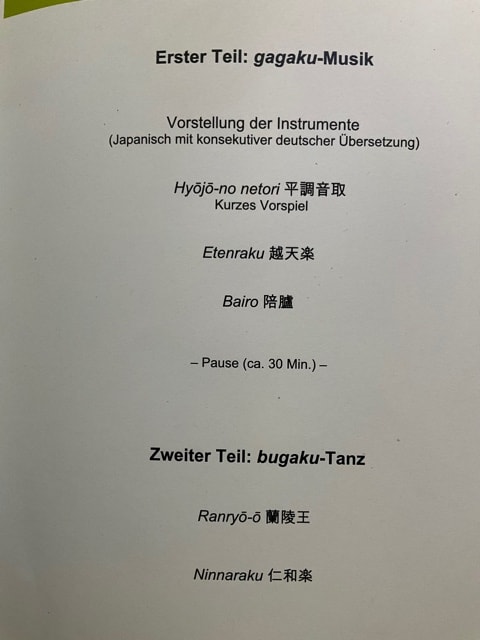























海外にいると、日本の伝統文化をたやすく(?)見ることができますよね。
望んでいなくても、やってくる…というか(^^;
雅楽は、姪の大学の文化祭(?)で見たことがあり、その豪華絢爛な舞台に驚いたことが思い出されます。
いつも思うのですが、義務教育の音楽の時間とかに見た記憶がないのです(^^;
いや、その衣装とか楽器とかは教科書とかで見たことがあっても、記憶に残るような映像が思い出せないのです。
でも、ドイツのバッハやモーツァルトetc.の顔も音楽も、きっちりと思い出せるのは、西洋主義の教育の問題かなぁ…と。。
ベルリンで駐在員夫人のドイツ語の曲のコーラスをやっていたことがあり、その先生(音楽大学生)が、「野バラ」や「シューベルトの子守唄」「鱒」などを皆知ってるのに驚いてましたよ。
「ローレライ」(ドイツ人でも知らない人が多い)を何故知ってるのか?としつこく聞かれました。
「私は日本の歌は1つも知らない」とも。。(^^;
このことは、いつかブログの記事にしようと思いつつ、チャンスがないのですけどね。
いつか雅楽や舞楽を見てみたいです♪
長くなってしまって、申し訳ありませんでしたm(_ _)m
コメントをありがとうございます。
日本の伝統芸能は国際交流基金がスポンサーとなり、ケルンの日本文化会館で時折演じられます。
雅楽は句会のお仲間が雅楽奏者で、雅楽愛好会のメンバーであることから比較的触れる機会が多いのです。
この方が教えてくださったのですが、枕草子の207段に篳篥の音をけなす記述があります。
「篳篥の音色はとてもうるさくて、秋の虫だとクツワムシのようで嫌いなので近くでは聞きたくない。
まして下手に吹いたのは憎たらしくなる......」
→雅楽奏者の間ではなく「篳篥弄りの段」と呼ばれているそうです(^O^)。