世界が、日本がおかしくなっている。ことに日本の農業の衰退は著しく、中山間地の過疎化から限界集落の問題がが問われるようになってしまった。景気の回復だとか、地方創生とか言われているが、農業の国際競争力を求めることは農業の選択的規模拡大を目標として農業を衰退させたのと同じ道だ。農業の現場を知らず、現場に責任を持たない「バカの壁」は、農業をおかしくしても自分たちは贅沢に生きていけると思っているのだろう。
アメリカやオーストラリアから安い牛肉輸入にどう対抗してゆくか? 日本には「霜降り肉」の和牛がいるので、これで世界に打って出る。これが国際競争力の強化のシンボルとして語られる。しかし、彼らの大規模な肉牛産業は砂漠化を防止する放牧の副産物だということをご存知だろうか。「初めに資源管理ありき」なので生産コストが安いのである。日本の和牛は農耕牛としての役割を終えて、「霜降り肉」という「高いから成立」する神話の世界に生き残った。しかし、資源に恵まれた里山は放置されているので、田畑は荒れて山に戻り、猪などの野生動物の棲家になっている。日本は資源の豊富な里山を家畜の放牧管理で守ることから始めなければならない。それが、牛やヤギ、ヒツジの役割だ。ここでは「牛の放牧による里山管理」を実践する会の立ち上げについて、その原案を提案したい。
以前、「自然とデザイン研究所」を設立しようと呼びかけたことがある。また、「和牛の伝統と牛のハイブリッド生産」では、和牛の伝統を守りつつ、人工授精の普及している日本では種雄牛の交配まで指定できる世界の最先端のハイブリッド生産のシステム化が可能なことを提案した。これらは少し専門過ぎて多くの方の興味を引かなかったかもしれない。和牛を尊重しているつもりだが、和牛関係者の警戒と反発を招いたかもしれない。
システムというのはいろいろな要素を繋いでできあがる。ここではもっとシンプルに、牛の放牧で里山管理していくことを、全国のネットワークにして実践していくことを提案したい。
牛の放牧には里山の公園化を含む様々な要素が含まれるが、里山を美しくするために次の活動から始めたらいかがであろうか。
1.共有林、旧牧場跡等の里山の牛の放牧管理の指導
2.放牧管理における地域自治体との所有権、管理方法等の交渉
3.放牧牛から生産される牛肉や乳製品等の販売に関する指導
4.放牧する牛の供給に関する指導
5.放牧する牛の飼養管理、繁殖管理、衛生管理等に関する指導
この会の事務局には北海道旭川市の斉藤晶牧場との交流があり、その価値をよく理解し、牛の管理技術も優れている方を必要とする。また、草刈り隊から放牧管理で里山を美しくした「大谷山里山牧場」の方々の経験も貴重だ。その方たちとの連絡を取り、その人件費や交通費をどうやって捻出するかの見通しを立てる作業から始める必要があるが、ここではこれらの検討を含めて、皆さん方の知恵を頂きたいので、まずは原案を提案することから始めさせていただいた。
若い世代は未知の世界に胸ふるわせ、古稀を過ぎると無知のまま死に至ることを恥とする。必ず来る死への道が見えてきた私にできることは、歩行が困難で十分な仕事ができないかも知れないが、「次の世代」に幸福を残す仕事を始めめることだと思っている。
初稿 2016.5.12










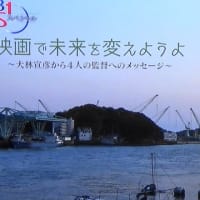



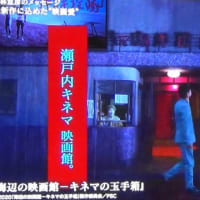
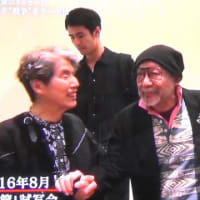

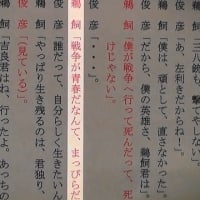



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます