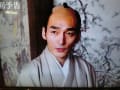「尊王攘夷」思想が日本に吹き荒れた1850年代後半から1860年代の前半の10年間。1842年に阿片(あへん)戦争で英国に敗れた中国や東南・東アジアには、ヨーロッパやアメリカ、ロシアなどの列強諸国の植民地侵略支配が本格化しようとしていた。1853年に米国艦隊(黒船)が日本に来航した。そんなアジアの世界情勢の中なので、この尊王攘夷という思想が日本にわき起こるのは当然と言えば当然なのかもしれない。「天皇を中心として国民がまとまり、徳川幕府もこの最有力勢力として政治に参画し、外国勢力(外夷)を近づけない」というこの尊王攘夷思想。豪農の家に生まれ育った渋沢栄一やいとこたちも、この思想に染まるのも自然ではあったのかもしれない。
まして、この時代の尊王攘夷思想の中心的な地だった水戸藩に、栄一たちの故郷・武蔵国血洗島村(現在の群馬県深谷市)はそう遠くはない。渋沢栄一たちは仲間たちとともに、高崎城乗っ取りや横浜異人街襲撃を計画もしていた。
そんな渋沢栄一といとこの渋沢喜作は、村を出て江戸に出て遊学することを父から許される。そしてひょんなことから、かって一ツ橋慶喜の小姓をしていた平岡円四郎の知己をえることなった。平岡の住まいを訪ねた二人は、平岡が一ツ橋慶喜とともに上洛していることを知り、平岡を追って京都に向かった。ここから、二人の京都との縁が生まれることとなる。慶喜の右腕側近となっていた平岡の推挙で、迷いながらも、二人は一ツ橋家の幕臣に連なることとなり、武士の身分となった。
将軍後見役となっていた一ツ橋慶喜は、第14代将軍の徳川家茂とともに上洛したのは1863年1月だった。一旦は江戸に戻るが、再び同年11月には上洛している。おそらく、栄一と喜作が上洛したのも、その後ではないかと思われる。
栄一や喜作の恩人とも言える、一ツ橋慶喜の側近・平岡円四郎は、尊王攘夷派の浪士たちによって1864年6月に暗殺されてしまった。その翌月の7月、京都御所に突入しようとした長州藩軍と会津・薩摩・桑名藩軍との間で、「蛤御門の変(禁門の変)」戦いが起こり、京都の町の多くが炎上することともなった。
この同年3月には、藤田小四郎らが水戸の筑波山で挙兵、11月には京都にいる一ツ橋慶喜に会い「尊王攘夷」を訴え、朝廷にもこのことを働きかけるため、武田耕雲斎を首領として1000人超の軍勢で上洛行動をとり始めた。(水戸天狗党騒乱)
水戸天狗党が関ヶ原近くまで到達している事態に、一ツ橋慶喜は水戸天狗党鎮圧のため出兵する。美濃国を経由して越前国に入った水戸天狗党に対し、慶喜の軍勢は琵琶湖北岸まで進出。この舞台に栄一や喜作も従軍している。水戸天狗党の副首領であった藤田小四郎など、天狗党内には栄一や喜作の知古も多くいたので、心中複雑な気持ちであっただろう。喜作は天狗党の降伏を勧めるための使者として、敦賀の新保(水戸天狗党本陣があった)の近くまで来てもいるようだ。雪が積もっていた1864年12月のことだった。
上記写真は『幕末・維新 彩色の京都』(白幡洋三郎著)より、左から②③枚目は東本願寺、④⑤枚目は二条城
将軍後見職として1863年1月に上洛した一ツ橋慶喜の宿舎(本営)は、東本願寺だった。再度の上洛となった同年11月の本営もこことしている。
東本願寺は1602年にこの地に建立された浄土真宗(開祖・親鸞)の大伽藍だ。一ツ橋慶喜はしばらくここを京都の本営としていた。新選組(京都守護職会津藩傘下)は、はじめの屯所(本陣)は壬生にあったが、隊士が増えたために、西本願寺を1985年より本陣としていた。
二条城は1603年に徳川家康により築城された。以後、徳川幕府の京都の拠点となる。1863年に上洛した第14代将軍の徳川家茂はこの二条城に入った。
今は天守閣はないが、当時は堂々たる天守閣があった。外堀と内堀の二重防御の近世城郭が今も残る。将軍・家茂死去のため、1866年に一ッ橋慶喜は第15代将軍となった。そして、歴史上有名な「大政奉還」(1867年10月)は、ここで宣布された。
この二条城の南に神泉苑という場所がある。京都盆地の地下水が湧き出る広い池がある。その近くに、若洲「小浜藩藩邸」跡がある。小浜藩は若狭の小浜城を本拠地とする10万石の大名だった。幕末期の小浜藩主は京都所司代となっていた。京都所司代屋敷は二条城の北側にあり、広大な敷地や建物で構成されていた。
このような事情もあり、この広い京都の小浜藩邸を一ツ橋慶喜が借り受けて住み、一ツ橋家の郎党とともにここに本営をおいた。慶喜がここに拠点をおいた時期は1863年12月から1867年の9月までの約4年間だ。その後、二条城に移る。この小浜藩邸での4年間は、幕末の政局が大きく揺れ動いた期間でもあった。渋沢栄一や渋沢喜作たちも、この小浜藩邸に4年間あまりを過ごすこととなった。
今は骨董品店となっている家の前に、当時の小浜藩邸内にあった石灯篭が一つ置かれている。その前に「小浜藩藩邸跡」と書かれた石碑がある。この文字は、幕末期の小浜藩主酒井家の末裔が書いたもののようだ。
小浜藩邸跡から二条城は目の前に見える。このあたりを、渋沢栄一・喜作たちは当時、歩いてもいたのだろう。時には、鴨川を越えて祇園町にも出かけたりもしたのだろう。