筆者を含め、戦後、高校までの日本史を左翼的な進歩主義の歴史観で習ってきた方がきわめて多いと思われる。
そして、「奈良仏教は鎮護国家=天皇の権力を護るための呪術的宗教であって、鎌倉仏教のような民衆の宗教、民衆の救いではなかった」といった否定的な評価を先入見的に教え込まれたのではないだろうか。
(「古代日本仏教への否定的見解:家永三郎氏の場合」「古代日本の天皇と仏教:従来の左翼進歩派的評価への反論」、参照)
しかし、筆者は幸いにしていろいろな経過があって左と右の先入見とは別に、自らの視点で『日本書紀』や『続日本紀』『日本後紀』といったその時代の文献を読むようになった。
すると、とりわけ聖武天皇における「鎮護国家」とは、単に迷信的な呪術によって自分たちの権力の維持を図るというだけのことではなく、むしろ「人民すべて、さらには生きとし生けるものすべてが幸せに暮らせる国になるように」と祈り願うことだった、と読めてきた。
すなわち、この時代の仏教は、まだ「民衆が信じて救われる仏教」にはなっていなかったとしても、「リーダーが民衆の幸せを祈る仏教」ではあったのだ。
国のリーダーが心を込めて民衆の幸せを祈るというのは、それはやはりすばらしいことなのではないだろうか。
しかも、それは単に観念的あるいは心情的なことだけではなく、これまで十分に語られてこなかったと思われるが、文献そのものをよく読んでいくと、天武天皇から聖武天皇に到る歴代の天皇たちは、時代の制約の中では精いっぱいといっていいほど、民たちの幸せのためにいわば福祉政策を実践しているのである。
さらに最近の日本仏教史の研究の進展によって、かつての奈良の国家仏教と鎌倉の民衆仏教という図式的な捉え方は、史料に基づいて批判され、奈良時代すでに仏教は呪術的面ではかなりの程度民衆のものになっていたことも明らかになってきているが(例えば吉田一彦『古代仏教をよみなおす』(吉川弘文館、二〇〇六年)など)、本書ではそうした面については触れない。
繰り返すと、筆者は、直に歴史資料を読むことによって、当時の日本のリーダーたちは、本気で日本を人々すべてが幸せないい国にしたいと思っており、古代という限界のなかで可能な限りの努力・実行をしていたのだ、と解釈するようになった。
(このあたりのことについては、筆者の研究所の機関紙『サングラハ』九一号以降に「日本の心と仏教」という記事を三度にわたって書き、また何度もそれに関わる講義も行なってきたし、現在も進行中であり、やがて本稿に続いて書籍のかたちにまとめたいと思っている)。
そうした学びを通じて筆者は、日本に『大般若経』ほかの般若経典が奈良時代から伝わって千年以上しっかりと保存されてきたことはとても幸いなことであり、さらに今、現代の私たちがこれを読み解くことができたら、さらに幸いなことになるだろうと考えている。










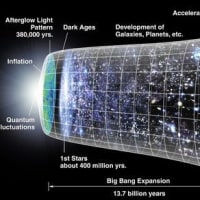



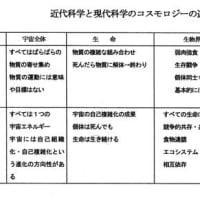
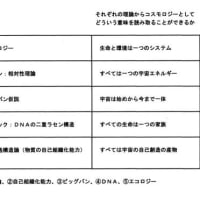

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます