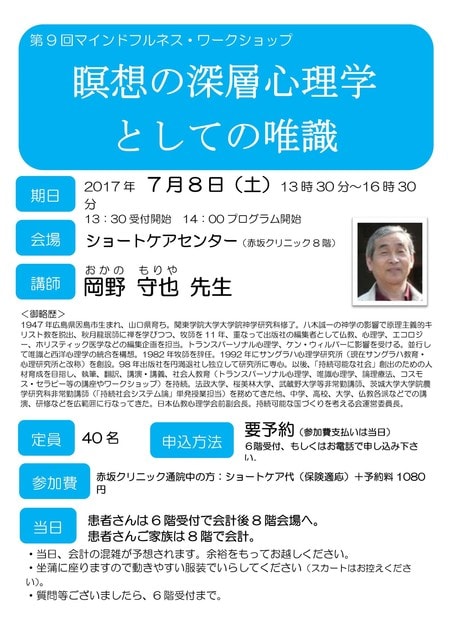もう十年以上前に書いた「足の痛み・しびれは心配ありません:禅定の話2」という記事が今でも毎日かなりの数読まれています。
それどころか、特に9月9日には8千人以上の方が読んでくださいました。
それは、坐禅・瞑想をやってみたいが、足の痛み・しびれが心配でなかなか踏み出せないという方、思い切ってやってみたがやっぱり辛くて続けられなかったという方が、驚くほど多いということなのかと思われます。
そこで、そういう方々のために、過去の記事を増補改訂して再録しておくことにしました。参考にしていただければ幸いです。
坐禅・瞑想は、覚りというレベルまで目指さなくても、ストレスを緩和する効果がとても高いことからしても、それはもったいないことだと思い、筆者は、なるべく痛い思いをしないですむよう、柔軟体操付の坐禅の指導をしてきました。
さらに、最近では、マインドフルネス瞑想の効果の科学的研究により、ストレス緩和という目的には、両足を組むいわゆる結跏趺坐は必ずしも不可欠でなく、呼吸法がポイントであることが明らかになったようなので、
イスでできるやさしい呼吸法・瞑想法=イス坐禅もお伝えすることにしています。
足の痛みやしびれがやっぱり心配だという方は、ここからスタートしていただけると、楽に入門できると思います。
もちろん、本格的になってきたら結跏趺坐の坐禅を身に付けていただくのが望ましいと思いますが。
私は、四十五年以上前に、臨済宗系の秋月龍珉(あきづきりょうみん)先生の道場で坐禅を教わりました。
他にいろいろな瞑想法があることは、いろいろな文献で学んできましたし、試しにやってみたこともありますが、自分にはこれがいちばん合っていると感じてきました。
ただ最近は、先にも書いたとおり、試してみてマインドフルネス瞑想法も悪くないと感じていますが。
ともかく、私がこれまでお伝えしてきたのは、臨済禅系の「坐禅」というかたちの禅定・瞑想です。
まず「調身」といって体の姿勢を調えるのですが、ご存知のように、坐禅では、左右の足を組む「結跏趺坐(けっかふざ)」というかたちを取ります。
これはもともと、足をしびれさせて我慢会をさせ、根性を養うためにするのではありません。
両ひざとお尻の下にしいた座蒲(ざふ)で長さを足した尾てい骨の3点で、ちょうどカメラの三脚のような安定した状態を作るためにするのです。
これは、脚が長くて痩せている人の多いインド人にとって、静かに長く坐っているためにはいちばん楽な姿勢だと言われています。
確かに比較的脚の短めの日本人が、足首、膝、股関節やその周辺の筋肉がこちこちに硬いままで、最初から無理にこんな姿勢をすると痛い目にあいます。
最近は、脚が長い若い世代も多くなりましたが、筋肉・関節が硬いままだと、やはりかなり痛みはあるでしょう。
かつては、社員研修などで無理やりに坐禅をさせられて、足のしびれと痛みですっかり懲りて、坐禅なんか二度としたくないと思ってしまう人が多かったようで、残念なことでした。
しかし、ちゃんと準備の柔軟体操をして筋肉・関節を柔らかくしてからすると、それほどひどいことにはなりませんし、慣れてくると体を安定した姿勢にして心を安定させるという目的のためにはやはり結跏趺坐がいちばんふさわしいと感じるようになります。
最近は、柔軟体操から指導する禅道場もあるようですし、イス坐禅を指導している若い僧侶の方もおられるようですし、私の講座では、必ず柔軟体操をしてから坐っています。
これまで、このブログの唯識‐仏教の記事を読んできて、人間の根本問題を解決するには、やはりアーラヤ識、マナ識という無意識の領域まで含めた心全体の浄化が必要だと感じた方、少なくとも私のところでは、「足がしびれて痛くてひどい目にあうのではないか」という心配はありません。
それに、人間の体はとても柔軟に適応できるように出来ていて、坐禅の結跏趺坐や茶道の正座のようなふだんしない坐り方もしばらく続けていると、脚の血管にバイパスが作られてちゃんと血液が流れるようになり、しびれは問題なくなると言われています。
慣れるまで、つまりバイパスが出来るまで、ほんのしばらくの辛抱です。
思い切ってがんばって、坐禅に取り組んでみませんか。あるいは、やさしいイスでできる瞑想・イス坐禅からでも始めてみませんか。
どんなに効果の高いトレーニング・メニューがあっても、それを読んでいるだけでは、レベル・アップはしません。
どんな特効薬の効能書きがあっても、読んでいるだけでは治りません。
まちがえないでいただけるとうれしいのですが、仏教の話・知識は薬の効能書きのようなものだと筆者は考えています。
読んだだけでも、ほっとするという安心効果があるのですから、それではダメだとは思いませんが、それだけではもったいないと思うのです。
薬やリハビリ・メニューにあたる実際の効果をもたらすのは、六波羅蜜です。
私は、まわりの若い人によく「飲まない薬は効きません」と言ったものです。
「飲まない薬が効かなくて、病気がよくならないのは、ぼくの責任じゃないよね?」と。
これは別に意地悪を言っているわけではないと思いますが、どう思われますか?
因みに、過去記事のコメントで、お釈迦さまも『遺教経』で「服すと服せざるとは医の咎(とが)に非ず」(飲むか飲まないかは医者の責任ではない)と言っておられることを教えていただきました。
もっとも最近は、よりポジティブかつやさしく、「飲んだら、よくなりますよ」と言うようにしています。