前回(→こちら)の続き。
先日から、
「ダラダラしながら初段になる」
という、人生をナメ……効率よく上達するため、そこはクリアできた私自身の将棋歴を語っているところ。
高校時代、よくやっと同世代で、将棋の楽しさを分かち合える友人を見つけたと思ったら、まさかの
「詰将棋マニア」
だったりしたわけだが、今回も『詰将棋パラダイス』(略称『詰パラ』)を解くだけでなく、創作にも手を染める「アーティスト」の友人コウノイケ君のお話。
彼とは高校3年間で、実戦を指したのは、20局行くか行かないかだった。
結構ガチ目の将棋ファン同士が、同じクラスにいて、その局数は少なすぎるというか、ふつうなら「1日20局」くらい遊びそうなものだが、なんとも不思議な関係であった。
たまに指しても、これがまた変な将棋。
私は序盤で、仕掛けられたあたりの対処が雑だから、棒銀とか右四間飛車のようなシンプルな攻めでこられると、たいがい突破される。
今でいえば、評価値でマイナス800から、1000くらいの不利におちいるのだが、実はここからが腕の見せ所。
私は定跡のこまかい知識や、実戦経験こそ少ないが、将棋雑誌の自戦記や観戦記を山盛り読み、そこで、
「棋譜並べ」
これだけは、人並み以上にやったという自負がある。
といっても、別に勉強したかったわけではなく、ネット中継もない時代、強い人の将棋を鑑賞するには、そうするしかなかっただけだが(だから今はやらなくなった)、これによって私は
「教科書には載ってない(載せても解説しにくい)実戦的な手」
というのを、多く指におぼえさせることができた。
なので、中盤から終盤の入口にかけて、あれやこれやとアヤシイねばりを駆使。
そうして闇試合に持ちこみ、どさくさ紛れに追い上げていくのは、得意中の得意なのだ。
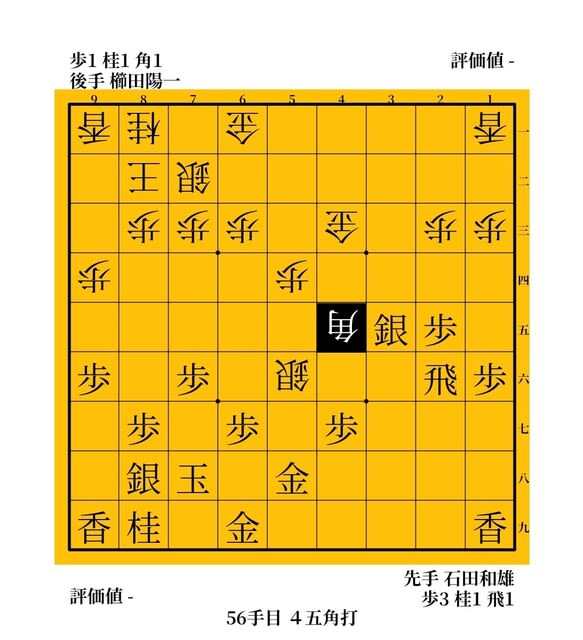
1993年のNHK杯。石田和雄九段と、櫛田陽一五段の一戦。
本格派の石田が、筋の良い仕掛けで攻めこんだところ、△45角が「教科書に載ってない」類のアヤシイ反撃。
不安定な角で、良い手かどうかは不明だが、対処をあやまった石田が敗れる。
よほど悔しかったのだろう、感想戦で駒をバシバシとカラ打ちしながら、櫛田に「まだやるんですか? 先生サマ?」と、からんでいた石田の姿が印象的だった。
さらには、若さゆえの、自陣に駒を打ちまくり、ねばりまくってひっくり返す、昭和の「根性エンジン」も搭載。
この棋風(?)だと、多少の不利など、モノともしないわけである。
そんな、相手の撃ち疲れを待つ、米長泥沼流ならぬ
「スターリングラード流」
と恐れられた私の粘着だが、一方のコウノイケ君の棋風もまた、かなりかたよっていた。
序盤がテキトーなのは、おたがいさま。
中盤での手練手管はこっちが上として、おそろしいのが終盤である。
なんといっても、相手は詰将棋の名手。
泣く子も黙る『詰パラ』定期購読者なのだ。
こういう人の寄せの力は、筋に入れば、一種トンデモなかったりする。
かくいう私も「勝ったな」と温泉気分だったところから、すごいトン死を何度かいただいた。
とにかく、こっちはしっかり受けているはずなのに、とんでもないところからバンバン弾が飛んできて、あっと言う間に仕留められしまう。
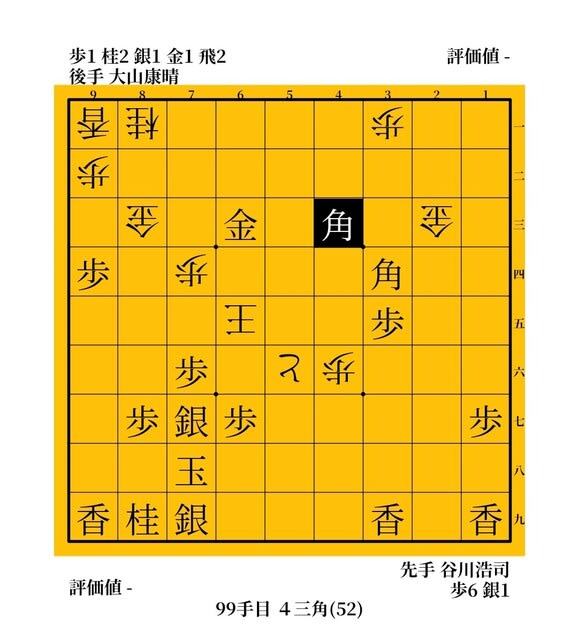
1983年の王位リーグ。谷川浩司名人と大山康晴十五世名人の一戦。
▲52にいる角で、▲43角不成(!)としたのが、盤上この1手の神業的な絶妙手。
ここで▲43角成は△54歩、▲66銀打、△同と、▲同歩、△55玉となって、▲56歩までの「打ち歩詰」になってしまう。
そこで▲43角不成とすれば、▲56歩に△44玉と逃げられるため反則にならず、以下▲45歩から押していけば詰む。
つまりは、こういう筋をねらってくるわけです。網にかかったら、おしまい。
その様はヴァシリ・ザイツェフのごとしで、まさに一撃必殺。
あまりにあざやかに詰まされると、感心が先に立って、案外くやしくなかったりするのが不思議なもの。
長手順のトン死を食らって、
「よう、こんな詰み筋読んでるなあ」
あきれると、友はこれ以上なく得意そうに、
「ボクはトン死勝ちしか、ねらってないからね」
変な将棋や!
つまり彼にとって、序盤の駒組や、中盤のねじり合いなど、たいして興味がなく、終盤戦だけを、
「ランダムに発生する実戦型詰将棋」
と、とらえているわけ。
うーん、まるで若手時代、序中盤で不利になると、
「早く終盤戦になればいい」
そう、うそぶいていたという、「光速の寄せ」谷川浩司九段のようではないか。
こうして「読む将」と「詰め将」のわれわれが戦うと、クソねばりとトン死筋という、あまりにも相反するというか、
「山岳パルチザン対スナイパー」
という実にマニアックな戦いとなってしまい、これがまた、ギャラリー受けも、すこぶる悪かった。
中盤は、駒がゴチャゴチャと入り組んで、セオリーもへったくれもないジャングル戦。
なのに終盤だけは、コウノイケ君の目がキラリと光れば、わけのわからない難解な詰み筋が光の速さで披露され、「え?」という間もなく、おしまい。
つまりは、
「メチャクチャ、カンどころがわかりにくい戦い」
だったわけで、見ているほうも、やっているほうも、頭がおかしくなるのだ。
もしかしたら、それもまた、あまり指さなかった理由のひとつかもしれないが、われわれはどちらかといえば、指してる最中よりも、終局後の、
「感想戦」
こっちが長かったタイプで、要するに、
「将棋をネタに、ワチャワチャとおしゃべりする」
ことの方が、楽しかったのだろう。
なんで、盤を前にしても「一局、指そうぜ」とはならない(その間しゃべれないから)、なんともおかしな、将棋青春時代であった。
(ネット将棋で大爆発編に続く→こちら)















