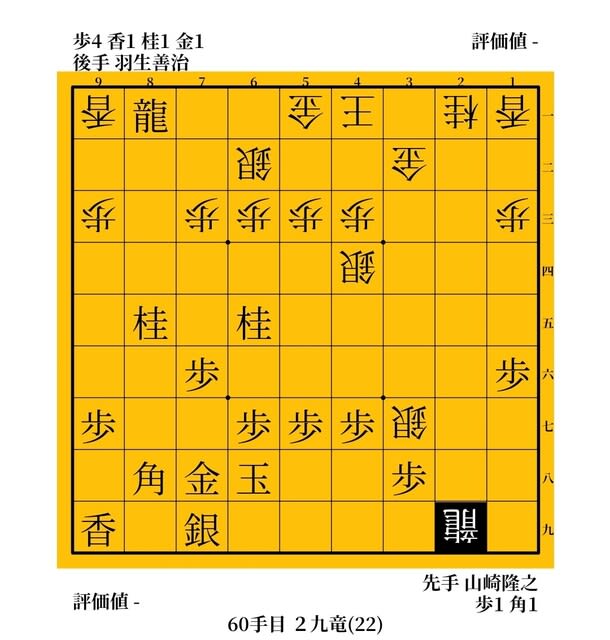トルコ語に苦戦している。
2年程前から私は、いろんな語学のさわりの部分だけを学ぶということをやっている。
日本人と言えば「外国語=英語」というイメージだけど、実際はに旅行したときなどハイレベルな英語よりも、
「中1レベルの現地語」
こっちのほうが、よほど使えることを何度も経験したからだ。
なので、そこでは「th」の「ス」や、「明るいL」と「暗いL」を発音しわけるよりも、
「台湾華語の【ありがとう】」
「タイ語の【パクチー抜きで】」
とかの方が、よほど実用的なのだ。
そこでここに発動された「シュリーマン作戦」により、私は世界のいろんな国の「基礎的な部分」だけにしぼって学習。
ここまで、
フランス語
スペイン語
ドイツ語(これは学生時代の復習)
ポルトガル語
をクリアしマルチリンガル(ちょっとだけ)として名をはせている。
と言っても、1日に15分くらいアプリで遊んだり、YouTube講座をダラダラ見たりするくらいだが、そんなものでも続けていると、
Comme on peut s'y attendre de Gog, il n'a pas subi de dégâts.
(さすがゴッグだ、なんともないぜ!)
Im Weltraum dieses Films scheint es Sauerstoff zu geben.
(その映画の宇宙空間には酸素が存在するようです)
El que corre es vietcong. El que no corre es un vietcong bien entrenado.
(逃げる人はベトコンです。逃げない人は、よく訓練されたベトコンなのです)
くらいなら理解できるのだから、なかなかなものではないか。
根をつめることなく「飽きたら次へ」がルールだから、そろそろ別のやるかなーと、選んだのがトルコ語であった。
トルコ語は「テュルク系」の言語で、アゼルバイジャン、ウイグル、キルギスあたりの言葉に似ていると言われる。
トルコは高橋由佳利さんの『トルコで私も考えた』の大ファンだし、実際に旅行したらオールタイムベスト級のいいところ。
ヨーロッパ系以外の言語にも興味があったし、なによりトルコ語はかつて、
「日本語とトルコ語は起源が同じ」
という説が長くささやかれたほど、似ている言語なのだ。
残念ながらこの、
「日本語=アルタイ語族」
という説は現在では否定されてしまったが、同じ膠着語に所属し、語順が同じとかいろいろと共通点はある。
単語にしても、
iyi(イイ)=いい(良い)
yamaç(ヤマチュ)=山地
yakmak(ヤクマク)=焼く
などなど、発音と意味が似ていたり、
「クスクス」(日本語と同じく「クスクス」笑うという使い方)
「ガルガラ」(やはり同じく、うがいなどの「ガラガラ」という音)
といった共通のオノマトペがあったりと、たとえ血縁(?)はなくとも、かなり親しみやすいのは確かなのだ。
そんなトルコ語となれば、きっと学習はサクサク進むはず。
フランス語の多すぎる母音や、ドイツ語の格変化ように、つっかえることもないだろうと思いきや、あにはからんや。
トルコ語、スタートからつまずきっぱなしであった。
理由は単純で、まず単語がおぼえられない。
というと、それはフランス語やドイツ語でも同じではないかと言われそうだが、これがそうでもない。
それこそフランス語やドイツ語は、日本人になじみのある言語ではないが、これらはわれわれが一応は勉強した英語の仲間。
ドイツ語は同じ「ゲルマン語派」に属して兄弟みたいなものだし、フランス語はノルマン・コンクエストなどの影響で、英語の語彙に多大な影響をあたえている。
なので、初見でも結構、語彙や文法の類推がきくし、それがフックになって暗記の助けにもなる。
たとえば、ドイツ語で「息子」は「Sohn」で「娘」は「Tochter」。
それぞれ英語の「son」「daughter」と似ている。
「お父さん」は「Vater」「お母さん」は「Mutter」で、それぞれ「father」「mother」っぽい。
というか元は同じ言葉で、距離が離れるごとに「伝言ゲーム」みたいな形でくずれていくようなもんだけど、これだと結構おぼえやすいと思いませんか?
発音すると「ファーター」と「ファーザー」。「ドーター」と「トホター」とか、ますます近しく感じる。
フランス語に至っては、英語の語彙の6割近くがフランス語(とその元ネタのラテン語)から借用したもので、
dinner(仏・dîner)
mountain(仏・Montagne)
flower(仏・fleur)
blue(仏・bleu)
などなど、フランス語の単語なくして英語が成り立たないほど、いただいており、やはりつながりは深い。
さらにいえば、そのフランス語と共通の「親」(ラテン語)を持つスペイン語やイタリア語では、
「仏・facile」
「西・fácil」
「伊・facile」
(英語のeasy)
「仏・difficile」
「西・difícil」
「伊・difficile」
(英語のdifficult)
などなど「まんまやん!」という単語が山盛りで、どんどん楽になる。
もっとも、あまりに似すぎると
「あれ? difficileって綴りやと、フランス語とスペイン語とどっちやったっけ?」
なんて混乱しがちですが。
ところがどっこい、それとくらべると、ヨーロッパ系言語とつながりのないトルコ語は、そういうリンクがない状態。
それを続けざまに投げられても、ちっとも頭に入ってこないのだ。
まあ、これはこっちがオジサ……シブい壮年の紳士になって記憶力が落ちたせいもあるかもしれないが、
Merhaba(こんにちは)
Selam(「こんにちは」のカジュアル版)
くらいならまだしも、
İyi akşamlar(こんばんは)
Görüşürüz(またね)
Nasılsınız(お元気ですか?)
Tanıştığıma memnun oldum(はじめまして)
とかとか、とっかかりがなさすぎて、どんどん脳をスルーしていく。
母音が多いというのも、日本人に発音こそしやすいが、単語の字数が増えて目がチカチカするのもあるかもしれない。
ということで、現在の私はトルコ語の「ありがとう」(Teşekkür ederim)がおぼえられなくて大苦戦中。
マジでムズイなー、どないしたもんでしょ?
(トルコ語の語順編に続く)