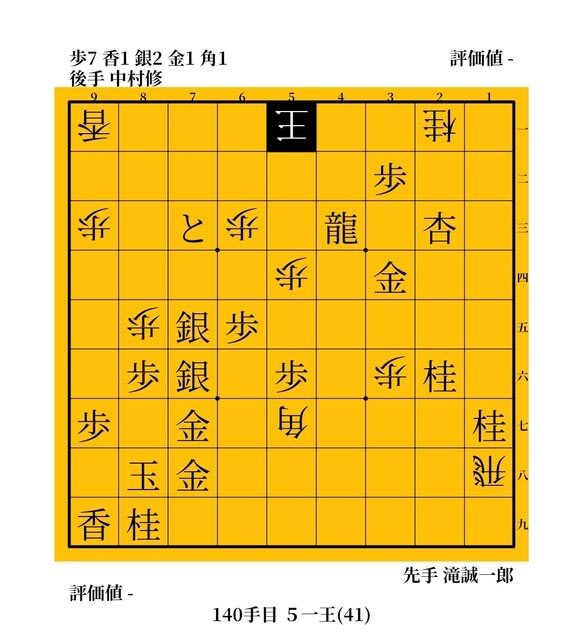
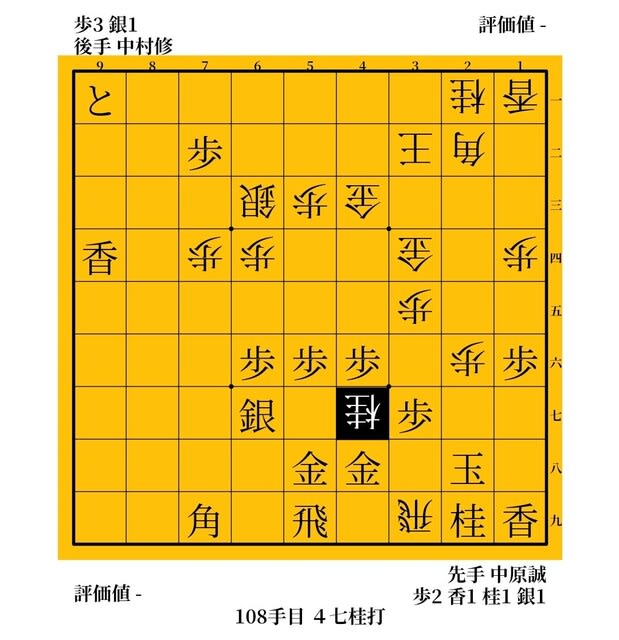
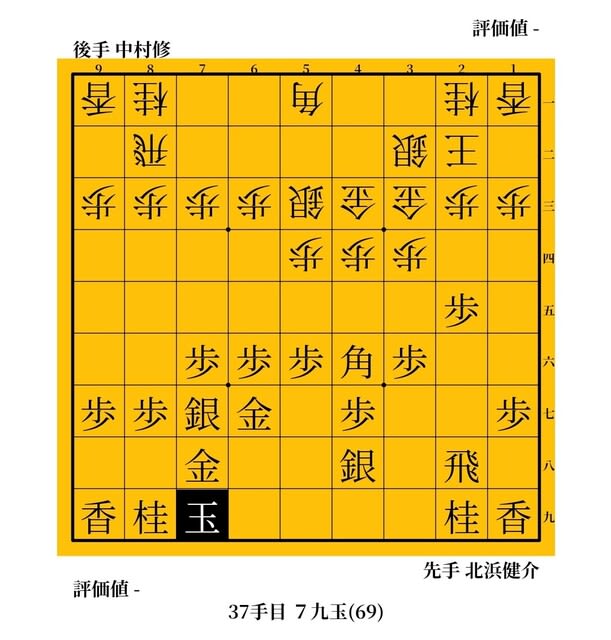
「SFとは筋の通ったホラ話である」
そう喝破したのは、SF作家の山本弘さんである。
そんな出だしから、前回(→こちら)は山田正紀『神狩り』によって、まさに「SFの壮大なるホラとハッタリ」に目覚めさせられた話をした。
私はSFとともにミステリも好きで、基本はそっち系だが、思えばミステリもまた、そのキモは
「ホラとハッタリ」
密室とか名探偵とか、我々は真剣になって読んでいるけど、ミステリに興味がない人からすると、
「なんやのそれ?」
ってなもんである。
だが好きな人には、そこがたまらないのだ。
「潤沢な食料のある部屋で、なぜ男は餓死したのか」
「九マイルもの道を歩くのは容易じゃない、まして雨の中となるとなおさらだ」
という言葉だけで、事件を解決してしまう名探偵とか、密室殺人とかダイイングメッセージとか、まさにハッタリである。ケレン味たっぷりだ。
そんな阿呆なジャンルである(もちろんホメ言葉です)SFとミステリが融合するとどうなるか。
その奇想のエッジが効いていればいるほど、それはそれは楽しい物語ができあがる。
SFミステリの古典的名作である、J・P・ホーガン『星を継ぐもの』の、
「月面で真紅の宇宙服を着た人間の遺骸が発見された。しかも、その身元不明の遺骸は、なんと5万年前に死んだ男のものだった……」
とか、まさに大ハッタリ。
設定だけで、まるでベートーベンの大仰な交響曲を聴いてるみたい。大見得切りまくり。
ものすごい「どや」感。この謎だけで、
「勝ったも同然や!」
という作者の雄叫びが聞こえてきそうではないか。
大好きなフレドリック・ブラウンなんか、ホントに楽しいバカ話が多いものなあ。素敵すぎる。
まあ、「ホラ」というと、なんだか軽いので、みな頭をひねって
「センス・オブ・ワンダー」
「奇想コレクション」
なんてネーミングするんだろうけど、私から言わせれば、その正体は落語の『あたま山』だ。
主人公は、いたってケチな男。
ある日この男が、道で落ちているさくらんぼを拾って食べる。
あまりにおいしいので、つい種まで食べてしまったら、なんと次の日起きたら、頭のてっぺんから桜の木が生えている。
あまりにもきれいな花が咲くので、そのまま放っておいたら、花見の客がひきもきらず、頭の上で毎日どんちゃん酒盛りをするのでうるさくてしかたがない。
頭にきて木を引っこ抜くが、今度はそこに雨水がたまって池になる。
そこに魚が住みだして、やってくるのは釣り人。
投げ釣りはするわ、投網はするわで、これまたやかましゅうて仕方がない。
ついにはノイローゼになってしまった男は、頭の池にどぼんと身投げをしてしまったとさ、ナンマンダブ……。
なんという、へんちくりんな話か。
これこそが、SFの骨子だと思うのですが、いかがなものでしょうか。
もしそんな素敵なホラ話が好きな方は、山本会長の熱いSFガイド『トンデモ本?違う、SFだ!』をオススメします。
「SFとは筋の通ったホラ話である」
そう喝破したのは、SF作家の山本弘さんである。
読書好きという人種は、大きく2つに分けられる。
それはミステリを読む者と、SFを読む者。
というのは、ものすごい、ざっくりした分け方であるが、イメージとしてはわかってもらえるのではあるまいか。
私の場合は、ミステリ派であった。
元の読書の入口が江戸川乱歩ということもあって、自然に路線は推理小説に決まることとなったのだ。
少年探偵団から、ホームズ、クリスティーときて、クレイグ・ライスやウールリッチ、ロアルド・ダールなどに広がっていくという、典型的な王道ミステリ野郎である。
とはいえSFも、まったく読まないわけでもなかった。
根が早川に創元っ子なので、SFというジャンルは身近なもの。
高校時代には、早川の『ミステリハンドブック』と『SFハンドブック』を購入し、ボロボロになるまで読みこんで、せっせと青い背表紙の本を買い集めた。
なんといっても、はじめて女の子にプレゼントした品というのが、プレゼント包装をした
『夏への扉』
『火星人ゴーホーム』
だったというのだから、今思い返すと冷や汗もの。
『夏への扉』はまだしも、なぜ『火星人ゴーホーム』なのか。
火星なら、せめてブラッドベリの『火星年代記』にしろよ!
いや、『夏への扉』も、一見さわやかに見えて実は問題だらけの小説だしなあ。
受けとたっときの、彼女の困ったような笑顔が忘れられません。
そんなこともあったので、この読書男子の分かれ道としては、ここでSFにシフトしてもおかしくなかったのだが、やはり乱歩チルドレンとして、
「いや、オレはミスヲタ道をつらぬくのだ」
という、よくわからない求道的な哲学と、あとハードSFが苦手だったことも、とどめをさした。
今でも、科学考証がどうとか、延々とSF的設定を語られる作品はつらい。
山本会長も、フェブラリーから最新の『MM9』までだいたい全部読んでるけど、『地球移動作戦』は、最初の100ページがしんどくて挫折してしまったくらいだ(のちに読了、超おもしろかった)。
なもんで、比率で言えばミステリ8に、SFが2程度の割合で読み分けていた。
いわば、ミステリが本妻で、SFは二号さんのような存在であったわけだ。
そんな私だが、ある時期からこの比率が5・5。
ときにはSFの方が上回ることにもなるほど、SFに傾倒することとなったのである。
そのきっかけは、『神狩り』であった。
『神狩り』。いうまでもなかろう、山田正紀の書いた、日本SFの古典であり、名作中の名作。
「人間は、関係代名詞が7重以上入り組んだ文章を理解することができない」にもかかわらず、冒頭で出てくる古墳に書かれた古代文字は、なんと論理記号が2つしかなく(人間の言語では5つらしい)、しかも関係代名詞が13重以上に入り組んでいるという」。
このつかみで、「おお!」とばかりにグッと引きこまれる。
そこからのストーリーもものすごく、神学論的展開から、最後には全知全能の神に人間の知恵を集結させて立ち向かうという、とんでもないスケールのものに。
もうページを繰りながら「なんやこれ!」「すげえ!」と、ブレイクなしの一気読み。
当時の私はミステリもSFも海外物一辺倒であったが、日本のSFがこんなにもおもしろいとは思いもしなくてショックであった。吃驚しました。
ちなみに、これがなんと山田正紀のデビュー作。
おいおい待てい。はじめて世に出た小説が、このクオリティー。
いかついな。あんたこそ神やないか! と、本気で文庫本に向かって、つっこんでしまったものである。
でもって、読み終えての感想というのが、
「なんちゅうハッタリや……」
すごい。こんな壮大なハッタリは、私の読書生活の中でもはじめてであった。
つかみの関係代名詞うんぬんとか、果ては神と戦うとか、ようこんなとんでもないこと考えつくなあ。あんたは、どんなホラ吹きや!
そう、私はここで、はじめてSFの本質を理解したのである。
SFとは科学がどうとか、タイムパラドックスがどうとか、シュレディンガーの猫がどうとか、なんだか理屈がややこしくて、そこが敷居の高さになるという人もいるだろうけど、なんのことはない。
そういうのは、すべて「ホラとハッタリ」なのである。
そのことがわかった瞬間から、私のSF感は変わった。
「いやーん、こんなアホな(超ほめ言葉)物語書いてもええんやー」
目がハートになってしまったのだ。
それ以降は、ミステリとSFは半分ずつくらいで共存共栄して、楽しい読書ライフを送っている。
最近おもしろかったのは、松岡圭祐『人造人間キカイダー The Novel』。
売れっ子作家が書いたノベライズなんて、どうせスッカスカでつまらんのやろ。
なんて、あなどりながら読んでたら、あにはからんや、無茶苦茶におもしろくて腰を抜かしてしまった。
物語の進行やアクションシーンのテンポが良く、なによりも「SFしてる」感がすばらしい。
完全になめてました。「ごめーん」と心で土下座しながら一気に読了。超オススメ。
(続く→こちら)
サービスが「超S」、パワー「A」。あとは、スピード、ストローク、ボレー、技術その軒並みが「E」という、あまりにも偏ったパラメータをもつオランダの女子テニス選手ブレンダ・シュルツ=マッカーシー。
時速200キロ近いスーパーサービスだけを武器に、トップ10プレーヤーの仲間入りをした彼女だったが、そんなサーブだけという選手が本当に勝てるのかといえば、これが案外勝てるもので、そのことをものの見事に証明して見せたのが、1995年のUSオープン、対伊達公子戦であった。
ブレンダと伊達がぶつかったのは4回戦。試合前の予想では、伊達が若干有利。この時期の伊達はテニスも充実しており、またUSオープンは何度も上位進出している相性のいい大会だったからだ。
ところが、この試合のブレンダは調子がよかった。
はっきりって、勝敗の行方に伊達の出来は関係ない。決め手となるのは「サービスが入るかどうか」だけであったが、この日は「当たり」の日だったようだ。
女子の選手というのは、男子ほどサービスに頼れないぶん、逆にリターンの技術が高い。中でも伊達は「サービスゲームよりも、リターンゲームをキープするイメージ」というほどに自信を持っているが、その伊達をしてもラケットにさわれない高速サーブがバンバン飛んでくる。
試合展開を実況すると、
「パーン!」「15-0」
「パーン!」「30-0」
「パーン!」「40-0」
「パーン!」「フォールト!」
「パーン!」「フォールト!40-15」
「パーン!」「ゲーム、シュルツ=マッカーシー」
終始、こんな感じ。この間、伊達はレディポジションで棒立ち。あまりの速さに、他にすることがないのだ。
エースかダブルフォルトだけ。ラリーなんてありようもない。なんて大味な。なんだか、三振かホームランかで鳴らした、元カープのランスみたいである。
ビッグサーバーは、サービスの調子がよいと他のショットも気持ちよく打てるらしく、この日のブレンダはサーブ以外も冴えていた。
もちろん、まともな打ち合いになったら伊達にはまるでかなわないのはわかっているから、リターンゲームでは後ろで待たず、どんどんネットに出てくる。
ときには、なかば強引な体勢からもチップ&チャージをかけてくる。かなり荒っぽいやり方で、普通なら伊達レベルの選手には通じないところだが、とにかくサービスゲームに不安がないものだから、ゲームのひとつふたつは捨てるつもりで戦えるのが強みだ。
パスやロブで抜かれようがとにかく、目をつぶってダッシュ。組み立ての苦手なブレンダには、こういう愚直なやり方があっていたのであろうか、試合は終始彼女のペースで進んだ。なんといっても、身長188センチのリーチの長さは、少々のボレーの稚拙さをおぎなうアドバンテージでもある。
だがそこは伊達もさるもので、要所でブレンダのサービスゲームを破り、試合の方はフルセットにまでもつれこむ熱戦となったが、最後はサーブ力がものを言って、ブレンダが勝利。
試合前、「とにかく、ファーストサーブが入らないでくれと祈ります」と、苦笑いしながら言っていた伊達の言葉が、冗談でもなんでもなかったことが理解できるような内容だった。
サーブだけで勝っちゃった。いや、なんたること。女子でそんなことができるんですねえ。もう感心するやらあきれるやら。こりゃ脱帽するしかありません。
のちに、「絶対にリターンできないスーパーサーブ」だけが武器の杉本宇宙という選手がウィンブルドンで大活躍する川上健一『宇宙のウィンブルドン』という小説を読んだが、まさに
「これってブレンダのこと?」
とページを繰りながら笑ってしまったものだ。
男子ならともかく、女子ではこんな選手はまず現れるものではない。サーブだけの女子選手ブレンダ・シュルツ=マッカーシー。彼女を個性派といわずして、誰を個性派というのか。まさに空前にして絶後の選手といえよう。
※おまけ 1994年最終戦。対シュテフィ・グラフ戦は→こちら
スポーツの世界には、「個性派」と呼ばれる選手がいる。それは才能ゆえか、それとも自己流ゆえか、いわゆる「基本」とか「常識」にとらわれず、独自のスタイルできびしい競争の世界を勝ち上がっていく者のこと。
野茂のトルネード投法や相撲なら舞の海などなど、そういった例は数あるが、これが女子テニスとなると、私がまっさきに思い浮かべるのがオランダのブレンダ・シュルツ=マッカーシー。
一昔前、まだシュテフィ・グラフが女王の座を張っていた時代、女子テニスでトッププレーヤーになるには、ひとつ抜きんでたショットを武器にすることが不可欠であった。
グラフならあの鋭いフォアハンド、モニカ・セレスなら両サイド両手打ちからの強打、アランチャ・サンチェス・ビカリオのフットワーク、マリー・ピアースのフォアの豪打、伊達公子のライジングショット。
ブレンダの場合は、これがサービスであった。
それも、なまなかのやさしいものではない。188センチの長身を生かしたそれは時速200キロに近い。並の男子選手以上のスピードとパワーを誇る、まさにスーパーショットの持ち主だった。
時速200キロといえば今でこそウィリアムズ姉妹などによって、それなりにおなじみにもなったが、当時の女子テニス界では破格の一撃。現実離れした冗談みたいなショットであった。ブレンダはこのビッグサーブを武器に世界ランキング最高9位に入り、トッププレーヤの仲間入りをする。
ここでおもしろいのが、ブレンダのサービスは抜きんでた一芸というか、これが本当に「一芸」だったこと。
普通、男子でも女子でも上位でしのぎを削る選手は、それぞれプレーに得意と苦手があるのは当然として、苦手なショットでもまったく打てないというわけではない。フェデラーにとってのバックハンドのように、あくまでも「あえていえば苦手」といったケースが多いものだ。
ところがブレンダとなると、これが本当に「サーブだけ」の選手なのだ。他のショットは、はっきりいって下手。
いや、下手なんてもんじゃない。そのフットワークも、フォアもバックもボレーも、果ては試合運びからなにから、すべてにおいて、こういってはなんだが
「これでよくトップ10に入れたなあ」
と、あきれるような、できなさぶり。もう、すべてがあぶなっかしくて見ていられない超ド下手なのだ。
ゲームでたとえるならパラメーターが「サービス」のところのみ「超S」で、あとは「パワー」が「A」と、「メンタル」がなんとか「B」くらいで、あとの「スピード」「ストローク」「ボレー」「テクニック」といった基本的技術がのきなみ「E」判定なのである。これを個性派といわずして、だれを個性派と呼ぼうか。
ブレンダのテニスはまさに一発ねらいの砲台。ファーストサービスでドカンとエース。ポイントが取れるのは、それ「のみ」。
いや、これは全然大げさな話でもなんでもなく、それ以外のショットがてんでダメなんだからしょうがない。
その証拠に一度古い映像を探してブレンダの試合を見てみてほしい。そのドタドタとしたプレーぶりは、まるで古い喜劇映画でも見ているようなふらつきぶりで、プロとは思えない頼りなさ。
マリア・シャラポワは苦手のクレーコートでプレーする自分のことを「氷の上の牛」と表現したが、身長190センチ近いブレンダの場合、目隠ししてローラースケートをはいた大熊にラケットを持たせたようなありさまになるのだ。とにかく、あぶなっかしくてしょうがない。
ところがこれがサービスゲームになると、次々に目にもとまらぬサーブでエースを量産していくだのから、相手からしたらやりにくくてしょうがなかろう。
なんといっても、テニスという競技は、サービスポイントをひとつも落とさなければ、理論上では絶対に負けがないというゲームなのである。
そんな動きは重いが直撃を食らうとひとたまりもないという、ティーガー戦車のようなブレンダがもっとも輝いたのが、1995年のUSオープンであった。
結婚を機に「シュルツ」から「シュルツ=マッカーシー」と名乗るようになった彼女は、この年絶好調で、ウィンブルドンに続いてUSオープンでもベスト8に進出する。このとき「一撃」を食らってしまったのが、なにを隠そう日本の伊達公子だったのである。
(次回【→こちら】に続く)
外国の名前は難しい。
前回(→こちら)、外国人には日本人の名前は発音しにくく、さんざん舌をもつれさせた異人さんに、
「発音できないから、お前のことは『ロッキー』と呼ぶ」
などと、実にアバウトな命名をされてしまう話をした。
そういった「異人さん仕様のホーリーネーム」をつけられるというのは、日本人には時折ある悲劇だが、中にはさらなる変わり種の名前をいただく人もいるものである。
エジプトはカイロの安宿でナンザン君という青年と出会った。
彼は大学院でイスラム史を勉強しているらしく、エジプトの歴史にもくわしかった。
土地のエキスパート。旅先で仲良くなるには、もってこいの人材である。
そんな彼は、笑いながらこんな言ったのである。
「ボクね、実はムスリムになったんですよ」
イスラム教徒になる。
宗教にうとい日本人からすると、そんな簡単になれるものなのかと疑問であるが、なんでもエジプトのあるモスク(イスラムの寺院)に入りたくて、近くにいたイスラム教徒に
「これ、日本人でも入っていいのか」
と訊くと、
「いや、ムスリムじゃないとダメだ」
無理かとガッカリしていると、そのイスラムの人は、
「じゃあ、イスラム教徒になって入ればいいじゃないか」
イスラム教徒になれ。いきなりの勧誘である。
異教徒がダメなら、改宗すればいい。
なにやら、パンがなければケーキを食べればいいのよ、と言い放ったアントワネットみたいである。
そんな簡単になれるのかといえば、くわしいことはわからないが、「アラーは偉大なり」みたいなことを何度か唱えると、一応なれるそうである。ホンマかいな。
そこで、「アラーさん、マジすげえッス」と言う通りにしてみると、
「よし、これでお前も立派なムスリムだ。よかったな」
あっさり審査に通ったくさい。そこで、
「せっかくだから、お前にイスラム・ネームをやろう。今日からムスタファだ」
なんかメチャクチャにアバウトなノリだが、イスラムの国で
「オレはムスタファだ」
というと「おお、そうなのか」と、ずいぶんとウケるらしく、「いいものもらいました」とビールを飲みながらニコニコしていた。
酒飲んどるがな。ずいぶんとゆるいムスリムである。
笑って話を聞いていた私だが、かくいう自分も実はイスラム・ネームをもらったことがある。
モロッコを旅行中、知り合った学生に気に入られ、
「ムスリムにならないか」
熱心にオルグされそうになったのだ。
なにが気に入られたのかわからないが、どうやら一緒にアメリカのブッシュ大統領について悪口を言い合ったことが、彼の心のヒットしたらしい。
出会って開口一番、
「お前はブッシュとビンラディンのどっちを支持する?」
などと質問され、どういうこっちゃと首をひねっていると、
「日本はアメリカに原子爆弾を2発も落とされたのに、どうして同盟なんか結んでいるんだ」
まったくもって、知り合って5秒でたずねることじゃないけど、政治経済にうといが調子乗りではある私が、
「まあ、ブッシュは一回しばいたらなあかん。町山智浩にケーキパイ持たして、ホワイトハウスに突入させたったらええねん」
なんてテキトーに話を合わせていたら、
「その通りだ」
「心の友よ!」
大感激されてしまったのだ。
まるで涙を流さんばかりの勢いで、
「ノーアメリカ! ノーブッシュ! ビバ、ビンラディン」
なんて握手してくるモロッコ愛国者に、今さら
「いや、実はボク、ノンポリやねん」
とはとても言えないが、
「おまえもムスリムになって、一緒にアメリカと戦おう!」
などと勧誘されて、ますますまいっちんぐである。
私みたいなスカタンを味方にして、どう使おうというのか。やっぱり、人間魚雷なんだろうなあ。
争いは好まず、酒もカツ丼も婚前交渉も大好きな私にはストイックな宗教は向かないと固辞したが、名残惜しいのか、
「せめて名前だけでももらってくれ」
と粘られ、まあそれくらいならと「アリー」という名前をいただいたのである。
それ以来、履歴書なんかに名前を書くとき、やはり「佐藤=アリー=太郎」みたいに書くべきなのか、いつも悩んでしまうのだ。















