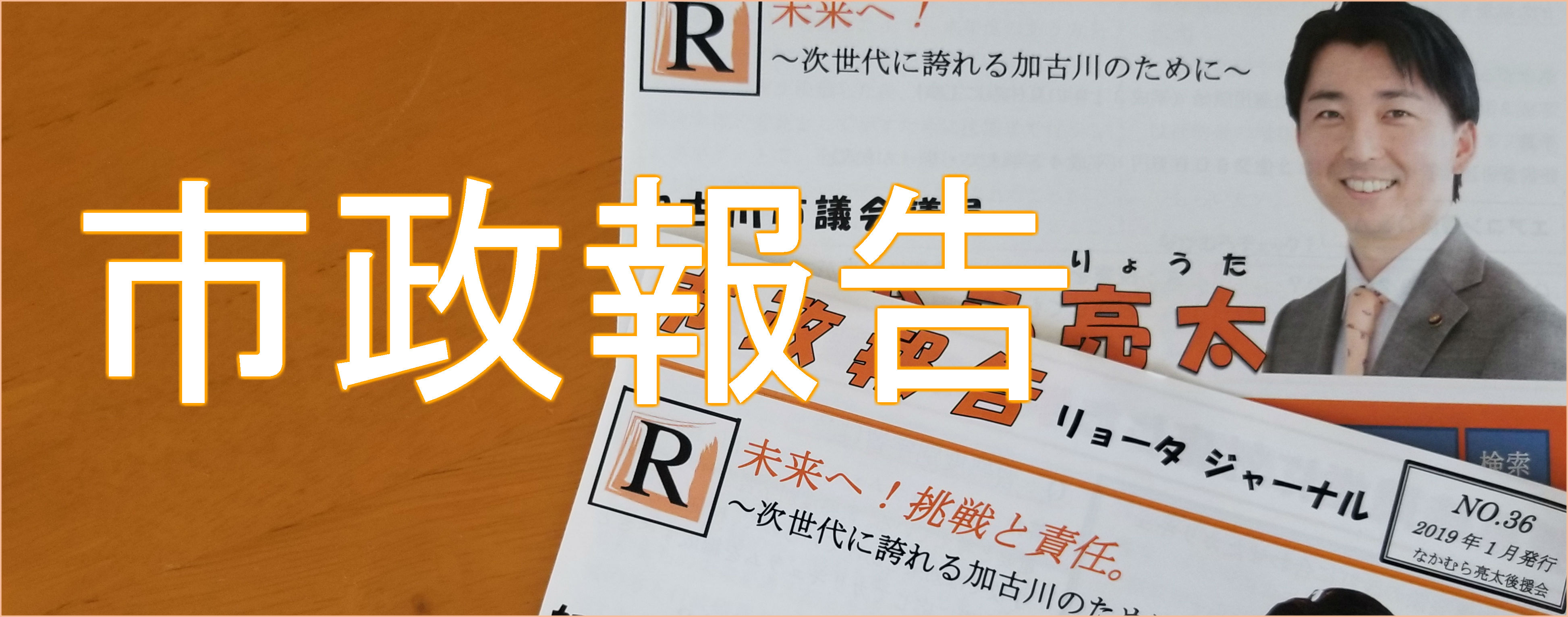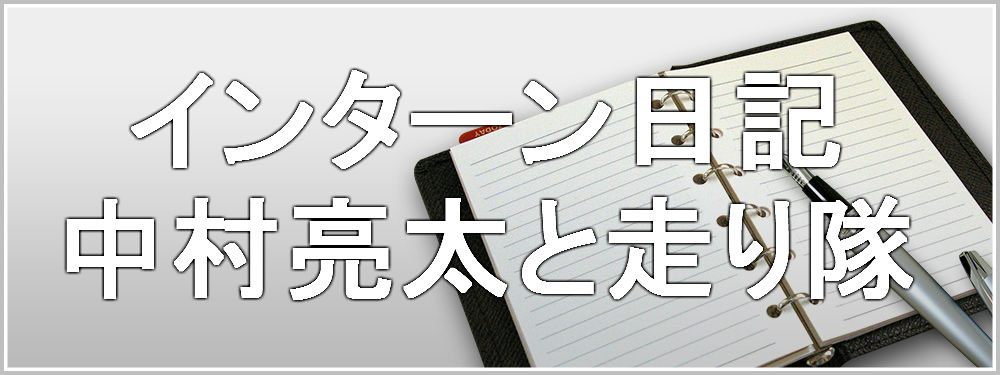今日は明石市にお邪魔をしてきました。
議会活性化特別委員会の傍聴をするためです。
他市のことなので、どこまで詳しく書いていいかわかりませんが。。
明石市では、昨年度に議会基本条例検討委員会が開かれていたようです。
その検討会から、来年の9月を目途に条例制定を検討すべきという答申がなされ、
それに向けて特別委員会が設置された流れのようです。
今回は2回目ということで、今後の進め方・体制・スケジュールについてや、定数・報酬
についてなどが議題となっていました。
1回目は議会報告会とそのあり方だったようで、初めにそれについて会派の考えを述べる
時間もありました。
体制については、特別委員会の委員が2つの部会に分かれるようです。
そして、特別委員会と各部会に、それぞれ論点を振り分けます。
部会は月に2・3回開催し、委員会は直近部会の報告と論点の議論を行い、これは月1・2回とのこと。
トータルでみると週に1~2回必ず会があり、それが来年まで続いていくということで、なかなか
ハードなスケジュールです。
この体制のありかたについては、参考になりますね。
加古川においても議会活性化をしていかねばなりませんので、今後の参考にしたいと思います。
議会活性化特別委員会の傍聴をするためです。
他市のことなので、どこまで詳しく書いていいかわかりませんが。。
明石市では、昨年度に議会基本条例検討委員会が開かれていたようです。
その検討会から、来年の9月を目途に条例制定を検討すべきという答申がなされ、
それに向けて特別委員会が設置された流れのようです。
今回は2回目ということで、今後の進め方・体制・スケジュールについてや、定数・報酬
についてなどが議題となっていました。
1回目は議会報告会とそのあり方だったようで、初めにそれについて会派の考えを述べる
時間もありました。
体制については、特別委員会の委員が2つの部会に分かれるようです。
そして、特別委員会と各部会に、それぞれ論点を振り分けます。
部会は月に2・3回開催し、委員会は直近部会の報告と論点の議論を行い、これは月1・2回とのこと。
トータルでみると週に1~2回必ず会があり、それが来年まで続いていくということで、なかなか
ハードなスケジュールです。
この体制のありかたについては、参考になりますね。
加古川においても議会活性化をしていかねばなりませんので、今後の参考にしたいと思います。