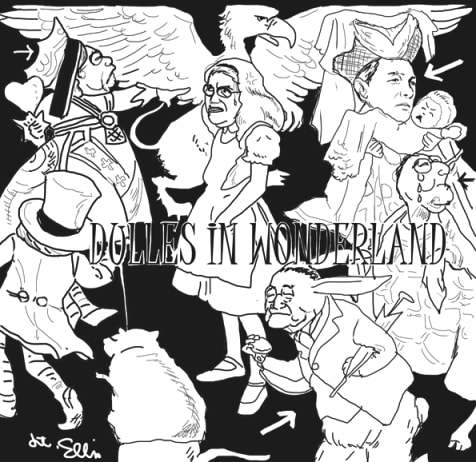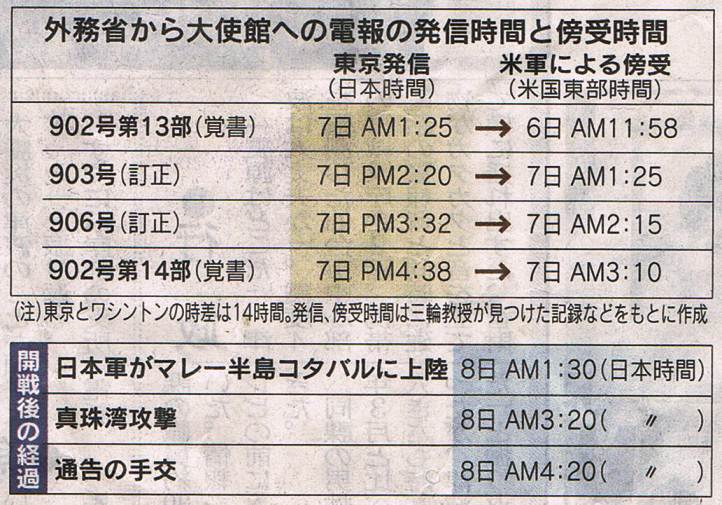基本的に
「世界はあまりに広くそして人生は短い。
できるだけ死ぬまでにいろんなところを見たいので、
旅行で訪れる場所はどんな素晴らしいところでも一度だけ」
と決めていた我が家が二年連続で台湾を訪れた理由が、金美齢さんです。
昨年、金さんとはある講演会で初めてお会いし、その後「遊びにいらっしゃい」と
お声をかけていただいていたのですが、ご縁はそれだけではありませんでした。
うちのTOが、その後ある地方の仕事先で金さんとばったり再会したのです。
「この運命的な出会いで、独身の男女同士なら恋に落ちるのでしょうが、
残念ながら彼(TO)には素敵な奥様(わたし)がおられまして・・・」
金さんが人に語ったという再会の様子です。
そのとき、台湾旅行から帰ったばかりだったTOがその話を彼女にすると、
「来年のお正月台湾に来るならご馳走してあげるわよ」
この言葉を聞いて、誰が再び台湾に行くことをためらうでありましょうか。
しかも、台湾という国についてその歴史も深く知らず、
「地震でたくさん寄付してくれたお礼の意味を込めついでに美味しい台湾料理」
程度の目的であった前回とは違い、金さんの講演から知りえた日本と台湾の関係、
日本が統治時代を通じて台湾に残したものをできるだけ感じる旅にしよう!と、
向学心と探究心を掲げ、満を持しての再訪です。
え?
その割には台湾に着いてから「どこに行こう」なんていってなかったか、って?
エリス中尉、自分が自分に対して認められる数少ない強みがあるとしたら、それは
「実行力とそれを遂行するための企画力」ではないかと僭越ながら思っています。
よく言えば。
悪く言えば「思い付きを熟考せず行動に移す考えの浅さ」ともいう果断即決は、
ときとして後々のトラブルを生む結果となり、「やめりゃよかった」
と思うことも過去にないわけでもなかったのですが、まあその話はさておき(-_-)
今回の台湾旅行は、この会合だけが最重要にして重要目的であったわけで、
そのほかのことは全く「おまけ」。
つまり後のことはすべてこのわたしの実行力と企画力に委ねられていたというわけ。
この会合が旅行の前半にあったことが後半の行動に大きく影響を与えることになったのですが。
この会合には、その影響のもととなった「サプライズ」が待ち受けていました。

指定されたレストランは、都心の一角にある普通の中華料理店。
名前からもお分かりと思いますが、ここは「鶏専門店」。
台湾っ子にも有名な美味しい鶏料理が食べられる家だそうです。
ここは金さんのお気に入りのお店だそうで、
しかも、この日私たちのために珍しい烏骨鶏を予約してくださっていました。
金さんは時間通りに店の前に現れました。
皆で店の奥の個室に入り、二つのテーブルに分かれて座ります。
勿論、メンバーは皆初対面。
個人参加であるわたしたちにはよくわからなかったのですが、
金さんの「私塾」や、あるいは「李登輝友の会」の人々であるように思われました。
テレビによく出演しておられるので皆さまのほうがご存知かもしれませんが、
実際に見る金さんは、小柄ながら実にオーラのある人物で、
お肌もつやつやして実にお美しい。
これで御年79になんなんとするとは、知らなければ誰も思わないでしょう。
おまけにこのお洒落なこと。
白髪と色白の肌ににエルメスオレンジのストールが映えて粋です。
金さん、どうやらエリス中尉と同じくエルメスファンと見た。
バッグもストールと同色のエルメス、右の紙袋は、金さんの定宿で、
台湾の家のように支配人以下全従業員に迎えられるというシャーウッドホテルの紙袋。
ちなみに被っておられるお帽子もエルメス製でございました。
型通りのあいさつの後、金さんが紙袋から出してくれたのは、
エビアンのボトルに詰めたホテルのオレンジジュース。
「ここのは美味しいので、お酒の飲めない人のために持ってきたの」
ということで、それはわたしたち家族のためってことですか?
台湾は果物が美味しいので、フルーツジュースも美味ですが、
それをわざわざ持ってきてくださるという金さんのお心遣い。
こんなところにもこの女性が多くの人を惹きつける秘密が垣間見えました。
皆が席に着いた頃、金さんが
「今日はサプライズゲストを呼んでるのよ」とおっしゃったので、
一同ワクワクして待つことほんの少し、そのゲストとは、
タイトルでもお分かりのようにそれが蔡燦坤さんでした。
蔡燦坤(さい・こんさん)。
もしあなたが司馬遼太郎の「街道を行く―台湾紀行」を読んだことがあるなら、
その文中、「老台湾」と司馬が称した「元日本人」、蔡さんのことが書かれているのを
ご存知かもしれません。
あるいは、小林よしのりの「台湾論」で、金美齢さんとともにその漫画に登場、
この漫画の中で語られている日本統治から戦後国民党の支配に変わった台湾が、
いかに蒋介石の元で大陸からの支配により荒廃し、白色テロによる戒厳令で
圧政に耐え、日本時代と日本精神の素晴らしさを懐かしんだかと言ったストーリーは、
全てこの蔡さんの著書
「台湾人と日本精神(リップンチュンシン)―日本人よ胸を張りなさい」
からそのほとんどが取られていることをご存知かもしれません。
わたしは実はこの本をそのとき読んでいませんでした。
度々その題名を目に止め、読みたいと思いながら機を逸していたのを
このときほど後悔したことはありません。
その後帰国と同時にこの本を注文し、第一空挺団の降下始めに持参し、
降下および訓練の始まるまでの待ち時間を利用して、立ったまま読破しました(笑)
そして、この本によって、今回台湾で見学した歴史的な痕跡、建築物や記念館や、
あるいは現在残る国民党政府の「聖地」など―と史実が見事につじつまが合ったというか、
絡んだ糸がほどけたような、「そうだったのか」と合点がいったような気がしました。
それについてはまた写真を挙げながらお話ししていくつもりです。
とにかく、その伝説の「元日本人」「老台湾」そして「愛日家」、蔡焜燦氏が、
今まさに目の前に、しかもすぐ近くに座っているのです。
「みんな僕の本読んだの?」
わたしは勿論、テーブルの誰一人として読んだものは無かったらしく、
皆きまり悪そうに俯きました。
今まで何度も読もうと思っていただけに、ここで「読みました」
と言って差し上げられなかったのが今でも悔やまれます。
ところで、参加者は二つの卓に別れ、こちらには蔡さんが、向こうには金さんが、
と、その後もずっと動かずに食事が進行しました。
こちらでは蔡さんがいかに普通の日本人より知日であるかに驚かされっぱなしです。
しかも、かつて体育の教師でもあった(体育だと戦後公用語となった北京語を使わなくて済む)
という蔡さん、いきなり、
「西郷隆盛が自害した時に介錯したのは誰だったか?」
というような「日本人なら誰でも知っているべき」小ネタを先生口調で問いかけ、
「知らんのか。しょうがないなあ」と講釈が始まります。
ちなみにこの話がどういう流れであったかというと、金さんが開口一番
「わたし、今はなんといっても安倍さんとラブラブだから」
と言って一座を笑わせたことから始まった話。
つまり別府晋介の晋と、安倍晋三の晋が一緒の字である、ということが
おっしゃりたかったのではないかと思います。
「西郷隆盛は最後に『晋どん、ここらでもうよか』と言ったんだよ」
わたしは蔡さんのなさった質問に『ハイ!』とこれもつい生徒のように手を挙げました。
そのうち蔡さんは
「そこの別嬪さん(強調)、あんたは何をしているの」
「ハ、ピアノを弾いています」
それからというもの、何かというと円卓の中の紅一点だったわたしに
「皇太子殿下のお誕生日はいつか?」
「知りません」
「美智子さまのお生まれになった日はいつか?」
「知りません」
「肉弾三勇士の名前を知っているか?」
「(全く)知りません」
と、日本人でもほとんどが知らないような質問を・・・・。orz
時折このようにメモを出しては字を書きつつお話は続きます。
この写真を拡大したのは、蔡さんの使っている万年筆を見ていただきたく。
いかにも昔の文人が愛用したような、ただものではない万年筆。
金さんの持ち物に目を奪われるように、蔡さんのこの筆記具にも、
「昔の日本人」を見るようで、わたしは手許を凝視してしまいました。
「みんなだめだなあ、本当に日本人なの?」
「ここにいるだれも俳句はしないのか?」
蔡さんはしょっちゅうこのように皆に問いかけ、その都度一同下を向くのですが、
それはわたしたちに呆れているというより、いかに自分が日本人であったか、
そして日本をよく知っているかを日本人、ここに集まった若者に伝えたくて仕方がない、
そんな蔡さんの無邪気な自慢の発露であるように思われました。
つまり、この人はたいていの日本人の知らないことを知っているだけでなく、
元日本人として日本を評価し、熱烈に日本を愛してているのです。
ちなみに「建国記念日」は紀元節、「文化の日」は「明治節」に戻すべきだ、
とおっしゃってもいましたよ。
蔡さんは18歳まで、日本人でした。
台湾に志願兵制度ができたとき、志願して陸軍整備兵となり、奈良教育隊で終戦を迎えました。
日本が負けたとき、蔡さんはじめ台湾出身の兵隊は、皆泣いたそうです。
戦後、日本の統治政府が去った台湾に戻った蔡さんは、他の台湾人と同じく、
大陸からやってきた国民党の無教養で野蛮で、略奪や汚職を何とも思わない民度に愕然とします。
そしてそのあと、2,28事件などを経て、李登輝総統によって民主化がもたらされるまで、
台湾の暗黒時代、いわゆる「白色テロ」の時代を通じて、自分が日本の教育によって
その骨肉を作られている「元皇民」であるということをいつも実感し続けてきたのでした。
この日、その蔡さんの口から聞く「歴史的証言」について、
思い出す限り何かの折に触れて書き残したいと思いますが、
とにかく、蔡さんは「日本人の心を持つ、台湾人」、
まさに司馬遼太郎のの言う「老台湾」そのものでありました。
蔡さんの独演会の合間に、向こうのテーブルでは金さんが、
「娘が言うのよ。
わたしがもう七十八歳で無かったら、安倍さん安倍さんなんて言っているのを
ヘンな風に勘違いされてしまうからよかったわねって」
「安倍さん、三回も電話くれたのよ。
総裁選のとき、解散のとき、選挙の後。
『総裁選立候補しました』『総裁になりました』『選挙勝ちました』って。
いちいち報告してこなくても、こっちは知ってるのにねえ」
などと皆を笑わせています。
ご存知かもしれませんが、金さんは第二次安倍内閣の成立を念じ、
東奔西走してその力になっていた一人です。
このときには安倍氏が新内閣の総裁として選挙に勝ち、金さん言うところの
「日本人のための政治をする内閣」が成立したことに対する一方ならぬ感激が
まだ尾を引いているのではないか、と思われました。
さて、そんな和気藹々とした?会話の中、テーブルには

黒っぽい肉が金さんが特にレストランに頼んで出してくださった烏骨鶏。
じつに滋味あふれるお味の肉でした。
蔡さんは、テーブルでひとしきり話をしたと思ったらつと立って、
そこにいる全員に前置き無く、話をひとくさり始めます。
詳細を忘れてしまったのが残念ですが、ある文書か書籍について
「これをあんたの事務所で皆に送ってもらってだね」
と蔡さんが金さんに言うと、金さん、言下に
「やーだよー!」
皆大笑い。
というようなやりとりに二人の厚い友情?も垣間見ることができました。
ちなみに、蔡さんはその著書で金さんのことを
「台湾のジャンヌ・ダルク」だと絶賛しています。
同じテーブルに(詳しくは自己紹介しなかったので会話から想像するだけでしたが)
わかっただけで新聞記者、中学校の先生などの方がおられました。
台湾からの義捐金に対する感謝イベントを企画したと思しき人もいました。
李登輝友の会から来ている人もおられたようです。
興味深かったのは、北海道から来た中学の先生たち。
エリス中尉、例の「コスタリカ事件」で家庭教師をクビにしたばかりで、
その話をごくごくかいつまんでさせていただきました。
ところで、北海道と言うと別名「赤い大地」。
日教組活動が盛んで、北教組による民主議員への裏金工作事件もありました。
「北海道というと・・・・・」
それを思い出し、ついこれだけ言ったところ、そのうちの一人の方が、
「そういった教育を何とか変えようとしているんです」
とおっしゃいました。
金美齢さんを囲む会に出ている方であるからには、当然そうなのでしょう。
具体的にどのような活動をしているかとかいうことまでは聴きませんでしたが、
帰りに金さんがその先生たちに向かって、
「わたしはさ、ほら、何を言ってもある意味大丈夫だけど、
急にいろいろとやると、反動(だったかな)がどうしてもくるから、
気持ちはわかるけど、その辺は焦らずにね」
というようなことを言っているのを聞いて、
その冷静沈着かつ賢明なことにあらためて感銘を受けました。
この言葉により、わが身の果断即決に流れ易きを反省した次第です。
さて、何回目かに皆の前に立った蔡さん、なぜかいきなりわたしの名を呼んで
「こっちに来なさい」
言われるがままに隣に立つと、
「あんたピアニストなんだから歌いなさい。『十五夜お月さん』。
♪じゅ~う~ご~や~お~つきさ~ん」
いきなり歌いだす蔡さん。
「せ、先生、キイが高いです」
以降、蔡さんが三番まで歌詞を朗読し、それについてわたしが
全曲この歌をみんなの前で歌うはめになったのでございます。
十五夜お月さんという歌を台湾人の蔡さんがが一言の間違いもなく覚えている、
というのも不思議な話ですが、エリス中尉がが小さいとき、もちろん覚えていませんが、
聴くといかなる時も涙を流した、というのがまさにこの曲なのです。
父がうまくもない自分の歌で赤子が泣くのを面白がって繰り返すため、
母が怒って「いい加減にして」と文句を言ったこともあるという思い出の曲でした。
不思議、というほどではないにせよ、縁というものを感じた一瞬でした。
TOはあとで「君があんなに蔡さんにいろいろと話しかけられていたのに、
僕は存在すら気づいてもらえなかったらしいのが印象的だった」
と拗ねていたのですが、まあそれはほかの男性陣も似たようなもので^_^;
「老台湾」と「台湾のジャンヌダルク」を囲む、若い世代の日本人たち。
この二人の台湾人より日本の文化に詳しく、この二人の元日本人より
日本を本当の意味で評価している日本人はいないのではないか、と
最初から最後まで圧倒されるがままと言った感のある一夜でした。
お開きのあいさつをする金さん。
「向こうのテーブルばかりでこちらにお構いもできずにごめんなさいね」
この日の食事はお二人にごちそうしていただきました。
金さんによると「何日にもわたる酒池肉林」のうちの一日だったとか。
皆でお見送り。
最後のあいさつのとき、金さんが
「台湾は人が暖かいでしょう」
と誇らしげにおっしゃいました。
実はこんなことがあったのです。
皆が到着してしばらくした時、タクシーの運転手が店に来て、
「さっきここで降ろした人が座席に携帯を忘れていった」と持ってきました。
すぐさま蔡さんが出て行き、どうやらお礼のいくばくかを握らせたようです。
帰ってきた蔡さん、携帯を忘れた人に「手を出しなさい!」
その手を軽くぱしっとたたいて、
「あんたが忘れ物などするから、わたしが御礼をした」
その人は頭をかいて恐縮し、皆、台湾のタクシーの運転手が、
まるで日本並みに誠実で親切であることに感心しました。
ところがこの話はここで終わらなかったのです。
そのお金を受け取った運転手は、自分がそれを取らずに、
車の中に待たせている客にそれを渡そうとしたらしいのです。
というのは、もともと携帯を見つけたのは次に乗った客でした。
その人は車をレストランの前まで戻ってこさせ、さらに
運転手に携帯をレストランに届けるように頼んだのだそうで、
さらに蔡さんから預かってきた運転手の出すお金を
「そんな御礼などいらない」
とわざわざ返しにこさせたというのです。
よく「忘れ物が必ず帰ってくる国」日本が、訪れる海外の人々に驚きとともに
絶賛されているようですが、台湾もまたこうなのです。
蔡さんに言わせればこれも「いまだ残る台湾人に根付いた日本精神の証拠」。
運転手と乗客、二人の台湾人の行為に一同が感心して嘆声を漏らすのを、
二人の日本精神を体現する台湾人は実に誇らしげに眺めていました。