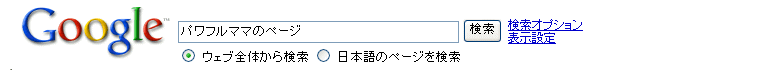
ヒト以外の動物にももちろん、ウイルス感染症はあります(他の生物の細胞を利用して、自己を複製する構造体がウイルスであるので、植物にもウイルス感染症はある。例えば、タバコなどの葉にモザイク状の斑点を作り、葉の成長を悪くする「タバコモザイクウイルス(tobacco mosaic virus、TMV)」)。「ウイルス感染症(viral infectious disease)」とは、「病原体(pathogen、パソジェン)」であるウイルスに感染することで、その生物に生じる「不都合な症状(=病気)」を言います。
「人獣共通感染症(zoonosis、ズーノーシス)」という言葉があります。「動物由来感染症」と言い換えられるように、「ヒト」とヒト以外の脊椎動物の両方に感染、寄生する病原体によって生じる感染症のことを言います。例えば、「狂犬病(rabies)」は、「狂犬病ウイルス(rabies virus、レイビーズウイルス)」を病原体とする人獣共通感染症で、ヒトを含めて、すべての哺乳類が感染します(アメリカでは哺乳類であるコウモリから感染したヒトの狂犬病の症例が多いという)。
全身に、体表だけなく内臓にも、膿疱が生じ、呼吸器に生じた膿疱により肺が損傷を受け、重篤な呼吸不全によって、死に至る(致死率は40%前後といわれた)こともある「天然痘(疱瘡、痘瘡、smallpox、variola)」は、「天然痘ウイルス(variola virus、バリオラウイルス、痘瘡ウイルス)」によるウイルス感染症で、ヒトのみに感染し発病させます。20世紀だけでも2~3億人が死亡したとされる天然痘は、1980年5月に世界保健機関(World Health Organization、WHO)が「天然痘根絶宣言」を出しています。
ヒトのみに感染するウイルスを根絶することは、可能であるといわれます(実際、1958年に世界保健機関が始めた「世界天然痘根絶計画」で、天然痘では達成できた)が、人獣共通感染症であるウイルスを根絶することは不可能でしょう。草むらに潜んで不意に攻撃を仕掛けてくるゲリラのように、ヒト以外の宿主に潜み、ヒトに散発的に流行をもたらすウイルスを根絶する手段を人間は持ちえていないのです。
インフルエンザウイルスは、ヒト、豚、鳥などの間で複雑に行動するウイルスです。長距離を移動する渡り鳥などの体内に潜み、国境を容易に越えていきます。家禽であるニワトリやアヒルに乗り換え、姿を徐々に変えながら(「変異」)、家畜である豚に乗り換えます。その間にチャンスがあれば、ヒトにも乗り換えます。
ヒトに38~40度の高熱を出させる気道感染症である「インフルエンザ」は、「インフルエンザウイルス(influenza virus、flu virus)」による、ウイルス感染症です。インフルエンザは、「宿主(host)」の種類によって、ヒトインフルエンザ以外に、トリインフルエンザ(鳥インフルエンザ、avian influenza、avian flu、bird flu)、ブタインフルエンザ(豚インフルエンザ、swine influenza, swine flu, hog flu, pig flu)、ウマインフルエンザ(馬インフルエンザ、equine influenza、horse flu)などがあります。
鳥インフルエンザは、「トリインフルエンザウイルス」が「鳥類」に感染して起きる鳥類のウイルス感染症です。ウイルスなどの病原体が、宿主となる生物に「感染(infection)」して、宿主に感染症を「発症(onset)」させる性質を「病原性(pathogenicity)」と言います。「病原性」は本来、「ある」か「ない」かですが、「ウイルス感染症」では病原性のあるウイルスしか問題にならないわけですから、宿主に与えるダメージの強度に応じて、「高病原性(highly pathogenic)」、「中病原性(mild pathogenic)」、「低病原性(low pathogenic)」というような表現が行われています。
「高病原性鳥インフルエンザウイルス」は、次のいずれかの条件に合うものを言います。
(1)ニワトリの静脈内に接種すると、ニワトリを高い確率で死亡させる。
(2)ウイルスのHAというタンパク質の一部が、強毒タイプのウイルスのHAに似ている。
(3)全てのH5またはH7亜型(家禽に対する病原性の強さに関係ない判断基準。この判断基準に疑問が呈されることがある)
上記の定義(1)では、「病原性」は致死率の高さを意味するように思われます。しかし、H5型、H7型のすべての鳥インフルエンザウイルスを「高病原性」と定義((3))する(日本の「家畜伝染病予防法」)と(この型の鳥インフルエンザの中には低病原性のものもある)混乱することになり、致死率の差(「トリ」の致死率)に応じて、「強毒性」、「弱毒性」という呼び分けも行われています。
H5型、H7型の鳥インフルエンザウイルスでは、「高病原性」だが「低毒性」である、という表現が現れる可能性もあります。「ヒト」にとっては、「強毒性」、「弱毒性」という区別のみが分かりやすいようにも思われます。いま中国で、ヒトへの感染拡大が懸念されているH7N9という型の鳥インフルエンザウイルスは、複雑です。このウイルス、トリにとって「弱毒性」であるにもかかわらず、ヒトにとっては「強毒性」である疑いがあるのです。
鳥インフルエンザウイルスは、濃厚接触(鶏の糞や剥がれ落ちた皮膚、羽毛などが飛沫として舞う鶏舎などに長時間留まるなど)の場合を除いて、「ヒト」には本来感染しないと言われています(変異をすると「ヒト」に感染するようになる)。「ヒトインフルエンザウイルス」と「鳥インフルエンザウイルス」は、別のウイルスなのです。
A型インフルエンザウイルスは、その粒子の表面にある「赤血球凝集素(この働きによって細胞に感染する。ヘマグルチニン、haemagglutinin、HA)」と「ノイラミニダーゼ(ウイルスの自己複製プロセスに必要。neuraminidase、NA)」という酵素の種類によって、分類されています。赤血球凝集素には16種類、ノイラミニダーゼという酵素には9種類が見つかっています。
ヒトにインフルエンザを発症させるインフルエンザウイルスには、次のようなものがあります。2009年4月にメキシコでの流行が始まり、やがて世界的に流行したいわゆる「新型インフルエンザ」は、H1N1という型であり、「A香港型」は、主にH3N2という型です。また、南アジアの多くのトリの間で局地的流行(エピデミック)を起こしている「高病原性トリインフルエンザ(Hyper Pathogenic Avian Influenza、HPAI)」は、H5N1という型です。
2013年4月9日の「共同」の記事には、「ベトナム保健省当局者は4月9日、南部ドンタップ省の4歳の男児が鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に感染し、4月4日に死亡したことを明らかにした。ベトナムで同ウイルスによる死者が出たのは、昨年2012年1月28日以来となる。男児は3月23日に高熱やせきなどを発症。死亡後の4月5日に感染が確認された。世界保健機関(WHO)などによると、ベトナムでの同ウイルス感染者は、今回の男児を含めこれまでに124人、うち死者は62人となった。」とあります。発症者をすべて把握できていたとすると、致死率は50%という高率になります。
国境を越えて感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐために、「検疫(quarantine)」が行われています。検疫とは、出入国する人、輸出入される動植物や食品などを一定期間隔離して(quarantineという語は、1347年の黒死病(ペスト)大流行の際に、潜伏期間に等しい40日の間、船を入港させず港外に留め置いたことに由来するという)、伝染病の病原体などへの汚染の有無を確認することです。人は厚生労働省健康局所管の検疫所、食品は医薬食品局食品安全部所管の検疫所、動植物は農林水産省消費・安全局所管の動物防疫所と植物検疫所がそれぞれ管轄しています。
厚生労働省検疫所が海外感染症情報を提供している「FORTH(For Traveler's Health、フォース)」というサイトがあります。2013年4月2日の「新着情報」は次のように述べます。
4月1日付けで公表された世界保健機関(WHO)の情報によりますと、中国の国家衛生・計画出産委員会は3月31日、インフルエンザA(H7N9)に感染した患者が3人発生したとWHOに報告しました。患者は3月29日に中国の疾病予防管理センターで実施された検査で確定されました。インフルエンザA(H3N2)、インフルエンザA(H1N1)pdm09、インフルエンザA(H5N1)、新種のコロナウイルスの検査も実施されましたが、いずれも陰性でした。
患者は上海市で2名、安徽省で1名発生しました。患者は3人とも重症の肺炎と呼吸困難を合併した呼吸器感染症を発症しました。発症日は2月19日から3月15日までの間でした。患者のうち2人は死亡し、1人は現在重篤な状態にあります。
これまでのところ、患者の間に疫学的な関連は確認されていません。接触者の経過観察を含む調査が行われています。現時点では、経過観察中の88人の接触者から新たな患者は発生していません。
「呉亮亮」は、妻「呉曉雅」と子「軒々」とともに、2013年1月に江蘇省塩城市から上海にやって来て、上海市閔行区にある景川菜市場で、よりよい生活を望んで、1日12時間労働という仕事に就きます。しかし、鳥インフルエンザウイルス(「禽流感病毒」)H7N9に感染し、発症し、転院した「復旦大学附属上海市第五人民医院」で、2013年3月10日に27歳という若さでこの世を去ってしまうのです。2月27日に発症して「風邪を引いて具合が悪い」と訴え、12日間病魔と闘い、力尽きて、呼吸不全で亡くなりました(2月27日,他自覚“感冒不適”,3月10日便因呼吸衰竭去世。)。鳥インフルエンザウイルスH7N9による2人目の被害者でした(1人目は、3月27日に発症し、4月3日に「復旦大学医学院附属崋山医院」で、「急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome、ARDS) 」で亡くなった52歳女性(52-year-old retired female resident in Shanghai))。
27歳的呉亮亮死了。殺死他的是H7N9禽流感病毒。
私たちは、中国での鳥インフルエンザの流行の記事を目にするとき、「4月23日の時点で、中国全土の感染者数は108人になり、死者も22人に上った。」というように数字でしか人の死が表現されていません。そこで、若くして突然に亡くなった人やその家族に気持ちを寄り添わせて悼むために、「中国青年網」(2013年4月8日)の記事を引用して、実名で臨床症状の経過を記述してみたいと思います。

関東の「横浜中華街」、関西の「神戸南京町」、九州の「長崎新地中華街」を「日本三大中華街」と呼び、その南京町に台湾料理の「攤販街(タンファンチェ)」があります。手偏に「難」と書く「攤(タン、tan、1声)」には「平らに広げる、並べる」という意味があり、「屋台、露店」を意味することもあります。一方、「販(ファン、fan、4声)」には「仕入れる」という意味があり、「物売り、行商人、小商人」を意味することもあります。そこで「攤販(タンファン)」とは「露店商」を指すことになります。
「呉亮亮」の奥さんは「呉曉雅」です。中国では、女性は結婚しても「姓」が変わることがありません。制度的に「夫婦別姓」なのです。中華人民共和国第7代国家主席「習近平」氏の奥さんは「彭麗媛」で、姓は異なります。しかし、日本でも結婚しても姓が変わらないときがあります。たとえば、「佐藤」(日本で一番多い姓)さんが「佐藤」さんと結婚をするときです。中国で、「呉」姓の人が「呉」姓の人と結婚すると姓は同一になります。「呉亮亮」は「呉曉雅」と2010年12月に結婚して、露天商である奥さんの父親の仕事を手伝って、屋台で「豚肉(中国語では「猪肉」と表現される)」を販売していました。
中国語では、ニックネームのことを「小名(xiao ming、シャオミン)」、本来の名前は「大名(da ming、ダーミン)」と言いますが、呉亮亮は奥さんのことを「小名」で「婷婷(ティンティン、Ting ting)」と呼んでいました。「婷婷」は「女性の様子がしとやかであったり、しなやかであること」を意味します。
2月27日、呉亮亮は熱があるのか顔を火照らせて、奥さんに「婷々、俺、身体の具合が悪い(我 難受)」と訴えます。家に帰り、体温を計ると、39℃ありました。この頃には、すでに高熱のせいで意識がはっきりせず(已経焼得有点迷糊了)、家の近くの診療所で点滴を受けることになります。このときは、徐々に熱が下がったといいます。
上海の52歳の女性も「悪寒(rigor)」を感じ、40.6℃に達する高熱で発症しています(インフルエンザの「全身症状」はあったことになります)。このときは、「気道症状」(インフルエンザの「局部症状」の1つ)の咳(cough)、咽喉痛( pharyngalgia)、鼻詰まり(stuffiness)も「胃腸症状」(これも「局部症状」の1つ)の吐き気(nausea)、嘔吐(vomiting)、腹痛(abdominal pain)、下痢(diarrhea)も明らかな症状がなかったことから、医師に診てもらうこともなく、服薬もしなかったようです。
(参考) 「風邪かな?それともインフルエンザ?-インフルエンザの症状について」
インフルエンザは、急な発熱で発症することが多いと言えます。このインフルエンザ発症の初期段階で、ウイルスが持つ「ノイラミニダーゼ」という酵素の働きを阻害する「ノイラミニダーゼ阻害薬(Neuraminidase inhibitors)」を投与できれば、ヒトの感染細胞からインフルエンザウイルスが外部に放出されることを阻害でき、ヒトの体内でインフルエンザウイルスが増殖することを妨げることができるといいます。
「ノイラミニダーゼ阻害薬」には、経口薬のオセルタミビル(商品名「タミフル(Tamiflu)」、吸入薬のザナミビル(商品名「リレンザ(Relenza)」とラニナミビル(商品名「イナビル(Inavir)」、点滴注射薬のペラミビル(商品名「ラピアクタ(Rapiacta)」)の4種類があります。WHOは、中国で行われた臨床検査の結果、この鳥インフルエンザ(H7N9)ウイルスに対しては、タミフル(「達菲」)とリレンザに感受性がある(ウイルスの増殖を防ぐ)ことが示されたと発表しています。また、日本の国立感染症研究所が、中国から4月10日に届いたウイルス株を用いて行った実験でも、タミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタのいずれでもウイルスの増殖を抑えることができたといいます。
日本の厚生労働省によると、この鳥インフルエンザウイルスを検出できる検査キットが開発され、日本全国の検疫所や地方衛生研究所、計90か所に配備され、鳥インフルエンザウイルス(H7N9)への感染が疑われる人が出た場合、鼻やのどから粘膜を採取し、この検査キットで感染の有無を調べる(早ければ6時間程度で結果がわかる)ことになっているといいます。
流行の初期では、インフルエンザであることは認識されていなかったため、抗インフルエンザ薬を投与するなどの適切な治療が施されなかった可能性はあるのですが、最初の鳥インフルエンザウイルス(H7N9)感染例の報告があってから、すでに3週間以上が経とうとしているのに、このウイルスに感染し発症して亡くなる人の数は着実に累積していっています。公表日でみると、4月1日に2人、4日3人、5日1人、9日1人、10日2人、11日1人、12日1人、15日2人、16日1人、17日3人、21日3人、22日1人、23日1人となっています。
これはどういうことでしょう。次のような場合などが考えられます。
(1)抗インフルエンザ薬が投与されていない。
(2)投与はされているが、抗インフルエンザ薬に効果はない。
(3)抗インフルエンザ薬に効果はあるが、発症から数日経ってからの投与で手遅れである。
(4)すみやかに投与され効果をあげているが、発症者が公表されている数よりもはるかに多く、基礎疾患があったため快復しなかったなどの不幸な例が報告されている。
2月28日、この日の朝、呉亮亮は再び高熱を出し、診療所を再診し、また点滴を受けることになります。しかし、熱は下がりませんでした。
3月 1日、この日も点滴を受けますが、熱が引くことはありません。この場合の点滴にはどのような意味があったのでしょうか。水分などの補給だったのでしょうか、抗生物質などの投与に点滴を利用したのでしょうか。
3月 2日、治療の効果が上がらなかったためでしょうか、呉亮亮は上海市第五人民医院に転院します。X線がとられます。肺にいくつか異常陰影が発見されます(拍了X光。結果顕示呉亮亮肺部上有几个白点。)医師は肺炎の可能性を示唆します。インフルエンザウイルスによってウイルス性肺炎を起こしていたものと思われます。
インフルエンザウイルスに感染して重症化する場合、たいていはウイルス性肺炎を起こし、「急性呼吸窮迫症候群」という重症の肺の障害を起こします。ウイルス性肺炎は、高度な医療でも、治療が非常に難しく、このような状態になってから抗インフルエンザ薬で治療しても、容易には救命は望めません。肺に空気が入っていかなくなり、呼吸不全で亡くなっていきます。
インフルエンザウイルスが気管、気管支、細気管支といった「下気道」にも達し、肺が重度の炎症を起こすとインタ-フェロンなどのサイトカイン類はウイルスを攻撃して死滅させようとしますが、正常な細胞まで攻撃してしまいます。その結果、正常の肺の機能である酸素を取り入れて二酸化炭素を排出する働きができなくなり、呼吸困難が生じることになります。症状としては、肺機能の低下により、1回の換気量が少なくなり、頻呼吸が現れます。これを急性呼吸窮迫症候群と言います。
3月4日、呉亮亮には咳が出始めます。それとともに、呼吸も苦しげになります。妻婷々は傍にいて看病を続けます。朝には薄い粥を茶碗に半分ほど口にしたのですが、昼には元気なときには大好きだった肉であっても一口も口にはできなかったといいます。
3月5日、咳がひどくなり、食欲は完全に落ちます。熱が一向に下がらず、治療の効果が上がらないことに、妻婷々は不満を口にします。このような状態になっていても、医師は「肺炎では咳が出ることもあり、数日経てば良くなりますよ(説肺炎就是会咳嗽,過几天就好)」という暢気な返事をしていたといいます。
3月6日、呉亮亮の病状は急激に悪化し始め、集中治療室 (Intensive Care Unit、ICU)に移されます。同済大学附属上海市肺科医院
の専門家や上海CDC(疾病予防コントロールセンター)の専門家もやってきますが、病状の進行をとめることはできません(上海市肺科医院的専家,上海市疾控中心的専家曾先后為呉亮亮会診,併提出了一系列的救治方案,但都無法制止他的病情継続悪化。)。
3月10日、この日の昼12時10分に、呉亮亮は「重症肺炎」、「呼吸不全」で死亡します(呉亮亮扼救無効后死亡,当時的死亡原因是重症肺炎,呼吸衰竭。)。
4月24日、厚生労働省は鳥インフルエンザH7N9型の感染が中国で広がっているのを受け、H7N9型を感染症法に基づく「指定感染症」に指定することを決めました。指定感染症は、生命や健康に深刻な被害を与える恐れのある事態が発生したときに迅速な対応をするため指定します。指定感染症への指定は、新型肺炎(SARS)、H5N1型の鳥インフルエンザに続き、3例目になります。
指定感染症に指定されれば、感染の疑いのある人に強制的に健康診断を受けさせたり、患者を入院させたりできるほか、接客業や食品加工業など感染を広げる可能性が高い仕事については、休業の指示も可能となります。
また、海外からのウイルス持ち込みを防ぐため、検疫法の政令も改正し、H7N9型に感染した疑いがある海外からの入国者に対して、検疫所での診察や検査を実施できる「検疫感染症」にH7N9型の鳥インフルエンザを指定することも決めました。
(追記)
毎日新聞の2013年05月11日配信の記事からです。
中国・上海市政府は5月10日、鳥インフルエンザ(H7N9型)の新たな感染者が20日間連続で確認されていないとして、同型ウイルスに対する警戒態勢を解除した。ヒトからヒトへの感染を示す証拠も現時点では無いとしている。ただし、感染源の可能性がある家禽類を扱う市場の閉鎖や取引停止措置は続ける。上海市では3月31日に世界で初めての感染が報告されて以降、33人が感染し、このうち13人が死亡した。市政府は4月6日から市内の家禽類を扱う市場をすべて閉鎖。同20日に75歳女性の感染が報告されたのを最後に新たな感染例はなく、「拡大を防止し、制御できる状態にある」と判断した。感染者のうち5人は治療中で、15人は退院した。密接な接触があった458人の医学的な観察も解除された。中国本土では2市8省で計131人の感染が確認され、このうち32人が死亡している。
毎日新聞の2013年05月31日配信の記事からです。
中国の鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)は、3月31日に感染が明らかになってから2か月が過ぎた。新たな感染者は激減し、一定の封じ込めに成功した形だ。ただ、世界保健機関(WHO)は秋以降に再び拡大する可能性も指摘。中国本土の感染者は2市8省で132人(うち37人死亡)。4月は120人以上確認されたが、5月は福建省などで5人だけ。感染者が突出して多かった上海市や江蘇省、浙江省で新たな感染者は出ておらず、警戒態勢は順次解除された。上海市などは4月上旬から市場での家禽類の取引を停止し、その後、新たな感染者は激減した。浙江省は衛生管理の徹底などを条件に5月31日からの取引再開を認めた。
時事通信の2013年07月10日配信の記事からです。
中国国家衛生計画出産委員会は7月10日、H7N9型鳥インフルエンザの感染状況に関する月例データを発表した。6月30日時点の死者は5月末から4人増え43人、感染者は江蘇省で1人増え133人となった。
毎日新聞の2013年07月11日配信の記事からです。
今春から中国で感染者が相次いだ鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)の特徴を、さまざまな哺乳類を使った実験で解明したと、東京大などのチームが7月10日付の英科学誌ネイチャー(電子版)に発表する(“Characterization of H7N9 influenza A viruses isolated from humans”)。日本人は感染や悪化を防ぐための抗体を持っていないことも判明した。チームの河岡義裕・東京大教授は「パンデミック(大流行)を起こした場合、肺炎患者が増える可能性がある」と指摘する。H7N9型ウイルスは、遺伝子解析から、ヒトの細胞に感染・増殖しやすい特徴があると予想されていた。チームは、上海市と安徽省で見つかった最初の2人の患者から採取したウイルス( A/安徽/1/2013 (H7N9)、A/上海i/1/2013 (H7N9))で、哺乳類のフェレットやマウス、サルなどに感染させた。その結果、両方のウイルスは、フェレットの鼻やのどなどの上気道で増殖しやすかったほか、サルでは上気道に加え肺でも増殖した。また、安徽省のウイルスでは、飛沫感染を起こすことをフェレットで確認。マウスの実験では、既存の抗ウイルス薬が、2009年に大流行したH1N1型に比べ、症状を抑える効果が低いことも分かった。さらに、日本人500人を調べたところ、全員がH7N9型のウイルスに対する抗体を持っていなかった。
産経新聞の2014年1月18日配信の記事からです。
インフルエンザやノロウイルスなどが流行する「感染症シーズン」が到来し、中国では昨春流行した鳥インフルエンザ(H7N9型)の人への感染が相次いで報告されている。再流行が懸念される中、2009年のH1N1型のようにウイルスが人から人に持続的に感染する「新型」に変異し、世界的流行(パンでミック)となる恐れも指摘される。国内では季節性のインフルエンザが流行期に入っており、厚生労働省は国内外の警戒を続ける。
国立感染症研究所によると、昨年3月に初めて中国で人への感染が確認されたH7N9型は、5月以降は小康状態が続いていたが、10月に新たに4人の患者が発生。その後も中国国内で相次いで感染が報告されている。世界保健機関(WHO)によると、中国と香港、台湾の感染者は約200人、致死率は3割に近い。今月に入ってからは毎日のように新たな患者の報告があり、再流行が指摘されている。
国立感染症研究所の大石和徳センター長は「H7N9型の発生を受け、中国では生きた鳥を扱う市場は一時閉鎖されていたが、それが再開されたことで感染拡大した恐れがある」とみる。患者の多くは鳥との接触があった。
「冬になれば増えると思っていたが、予想通りだ。昨年、患者が一気に増えたときと同じような形で増えている」と指摘するのは、東北大大学院医学系研究科の押谷仁教授(ウイルス学)だ。押谷教授が注目するのは、中国の旧正月である春節(今年は1月31日)。春節の時期、中国国内は人や鳥の往来が増える。押谷教授は「これまでの鳥インフルエンザも春節の時期に増えている。人々の移動が多く、鳥を食べる機会が増えるからだろう」と分析する。
(この項 健人のパパ)
| Trackback ( 0 )
|
|