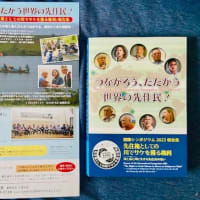とてもあわただしくも、充実した週末でした。
11日(土)に登別に向かい、まずは幌別へ。J.バチェラーがつくった「愛隣学校跡」の碑を、今回はしっかりと見つけ、確認しました。この場にわたしの母が住んでいたということを思い浮かべながら、愛隣学校がたてられていた時代や、その後のこの辺りはどんな風景だったのかと、ひととき、思いにふけました。

その後、一週間後に開館が迫っている、知里幸恵さんの記念館「銀のしずく館」の場所の確認と、外観だけでも写真を撮ろうと思い、そちらに向かいました。すぐに見つけて写真を撮りながら、中はどんなかなぁ~と窓をのぞいていると・・・、お隣から、「何を見ているのですか。こちらにいらっしゃい」とご婦人の声。説明すると、今、むつみさんも来られているから、ちょっとだけお入りなさいと中にいれてくだすった!! 展示の最終打ち合わせ中にも関わらず、少し入れて頂いて、10月にフィールドワークにお訪ねすることをお願いして来ました。こじんまりしていますが、とてもきれいな展示室でした。
以下の通り、今週の17日(金)、18日(土)と知里幸恵フォーラム‘10in登別 知里幸恵 銀のしずく記念館オープン記念が開催されます。わたしも行きたいところですが・・・
17日(金) チセノミ(知里幸恵銀のしずく記念館完成アイヌ式儀式) 記念館にて
11:00~チセノミ 13:00~古式舞踊、アイヌ料理試食
18日(土) 講演 ホテル平安にて(登別市中央町5-1-1)
13:00~佐々木利和「アイヌ文化の中での知里幸恵の役割」
14:40~公演 マレウレウ 15:15~交流
主催:NPO法人知里森舎(問い合わせ 0143-83-3677)

夜は、お待ちかねの一人芝居「神々の謡~知里幸恵の自ら歌った謡~」を鑑賞。150分もの大作で、しかも20人の役を見事に演じられました。
アイヌ神謡集の序言が最初に朗読され、4歳の幸恵さんが森の中でふくろうの赤ちゃんと出会うところから物語が始まりました。その後、旭川に移っての学校生活や伝道所でのお話、金田一が来てカムイユカラのすばらしさを知ってノートに書き始めたところまでが第一部。
途中で、アイヌ神謡集の中の「シマフクロウの神が自らをうたった謡=銀の滴降る降るまはりに」と、「小狼の神が自ら歌った謡=ホテナオ」も、劇の中で取り込んで演じてくれ、そのユカラに示されている
メッセージも伝えてくれました。
第2部は、上京して金田一宅にお世話になって神謡集を書き上げて天に召されるまでのお話。
最後の「ぶった切り」はインパクトが強かった(観ていないとわからない表現でごめんなさい)。他者を否定し切る剣が最終的に己に向かう。そこから一部で扱われた「ホテナオ」のメッセージが活きてくる。なかなかの見ごたえでした。
お話の中で知らなかったことも多く出てきました。それが着色なのか、どこかに書かれているものなのかを確認して行きたいと思います。特に関心を持ったのは幸恵さんのキリスト教徒としての罪感でした。
アイヌ民族の皆さんの感想も、聞かせて頂きたいと思いました。
もうひとつだけ、演出でなければ、きっとわたしだけが気づいたことがあったので書いておきます。
わたしは舞台前方の2ブロック目の最初の列で舞台に向かっていちばん左に座って鑑賞していました。第1部の「銀の滴降る降るまわりに」が演じられている時のことです。ちょうど彼女がシマフクロウのカムイになりきっている時、舞台に向かって左奥から中央の彼女を緑の光が照らしていたのですが、そのシルエットが舞台に向かって右側前の客席の壁に大きく写っていたのですが、ちょうどわたしのところからそのシルエットを見ると、なんと、巨大なふくろうが優雅に舞っているように見えたではありませんか。彼女の右肩からふくろうの羽をイメージしているようなストールがついていたのですが、それがシルエットでは本物の羽ばたく羽に写ったのです。
壁は微妙な角度がひとつついていたので、それを計算の上であの演出するほど凝ったとは思いませんから、偶然なのでしょう。会場の写真係がうろついていたので、教えようとも思いましたができず。
第2部の最後のほうに、最初に出てきたふくろうのこどもが成長して出てくるときも同じようなシルエットが出来たのです。わたしにとっては劇のはじめからおわりまでシマフクロウに見守られている幸恵さんが見えました。
11日(土)に登別に向かい、まずは幌別へ。J.バチェラーがつくった「愛隣学校跡」の碑を、今回はしっかりと見つけ、確認しました。この場にわたしの母が住んでいたということを思い浮かべながら、愛隣学校がたてられていた時代や、その後のこの辺りはどんな風景だったのかと、ひととき、思いにふけました。

その後、一週間後に開館が迫っている、知里幸恵さんの記念館「銀のしずく館」の場所の確認と、外観だけでも写真を撮ろうと思い、そちらに向かいました。すぐに見つけて写真を撮りながら、中はどんなかなぁ~と窓をのぞいていると・・・、お隣から、「何を見ているのですか。こちらにいらっしゃい」とご婦人の声。説明すると、今、むつみさんも来られているから、ちょっとだけお入りなさいと中にいれてくだすった!! 展示の最終打ち合わせ中にも関わらず、少し入れて頂いて、10月にフィールドワークにお訪ねすることをお願いして来ました。こじんまりしていますが、とてもきれいな展示室でした。
以下の通り、今週の17日(金)、18日(土)と知里幸恵フォーラム‘10in登別 知里幸恵 銀のしずく記念館オープン記念が開催されます。わたしも行きたいところですが・・・
17日(金) チセノミ(知里幸恵銀のしずく記念館完成アイヌ式儀式) 記念館にて
11:00~チセノミ 13:00~古式舞踊、アイヌ料理試食
18日(土) 講演 ホテル平安にて(登別市中央町5-1-1)
13:00~佐々木利和「アイヌ文化の中での知里幸恵の役割」
14:40~公演 マレウレウ 15:15~交流
主催:NPO法人知里森舎(問い合わせ 0143-83-3677)

夜は、お待ちかねの一人芝居「神々の謡~知里幸恵の自ら歌った謡~」を鑑賞。150分もの大作で、しかも20人の役を見事に演じられました。
アイヌ神謡集の序言が最初に朗読され、4歳の幸恵さんが森の中でふくろうの赤ちゃんと出会うところから物語が始まりました。その後、旭川に移っての学校生活や伝道所でのお話、金田一が来てカムイユカラのすばらしさを知ってノートに書き始めたところまでが第一部。
途中で、アイヌ神謡集の中の「シマフクロウの神が自らをうたった謡=銀の滴降る降るまはりに」と、「小狼の神が自ら歌った謡=ホテナオ」も、劇の中で取り込んで演じてくれ、そのユカラに示されている
メッセージも伝えてくれました。
第2部は、上京して金田一宅にお世話になって神謡集を書き上げて天に召されるまでのお話。
最後の「ぶった切り」はインパクトが強かった(観ていないとわからない表現でごめんなさい)。他者を否定し切る剣が最終的に己に向かう。そこから一部で扱われた「ホテナオ」のメッセージが活きてくる。なかなかの見ごたえでした。
お話の中で知らなかったことも多く出てきました。それが着色なのか、どこかに書かれているものなのかを確認して行きたいと思います。特に関心を持ったのは幸恵さんのキリスト教徒としての罪感でした。
アイヌ民族の皆さんの感想も、聞かせて頂きたいと思いました。
もうひとつだけ、演出でなければ、きっとわたしだけが気づいたことがあったので書いておきます。
わたしは舞台前方の2ブロック目の最初の列で舞台に向かっていちばん左に座って鑑賞していました。第1部の「銀の滴降る降るまわりに」が演じられている時のことです。ちょうど彼女がシマフクロウのカムイになりきっている時、舞台に向かって左奥から中央の彼女を緑の光が照らしていたのですが、そのシルエットが舞台に向かって右側前の客席の壁に大きく写っていたのですが、ちょうどわたしのところからそのシルエットを見ると、なんと、巨大なふくろうが優雅に舞っているように見えたではありませんか。彼女の右肩からふくろうの羽をイメージしているようなストールがついていたのですが、それがシルエットでは本物の羽ばたく羽に写ったのです。
壁は微妙な角度がひとつついていたので、それを計算の上であの演出するほど凝ったとは思いませんから、偶然なのでしょう。会場の写真係がうろついていたので、教えようとも思いましたができず。
第2部の最後のほうに、最初に出てきたふくろうのこどもが成長して出てくるときも同じようなシルエットが出来たのです。わたしにとっては劇のはじめからおわりまでシマフクロウに見守られている幸恵さんが見えました。