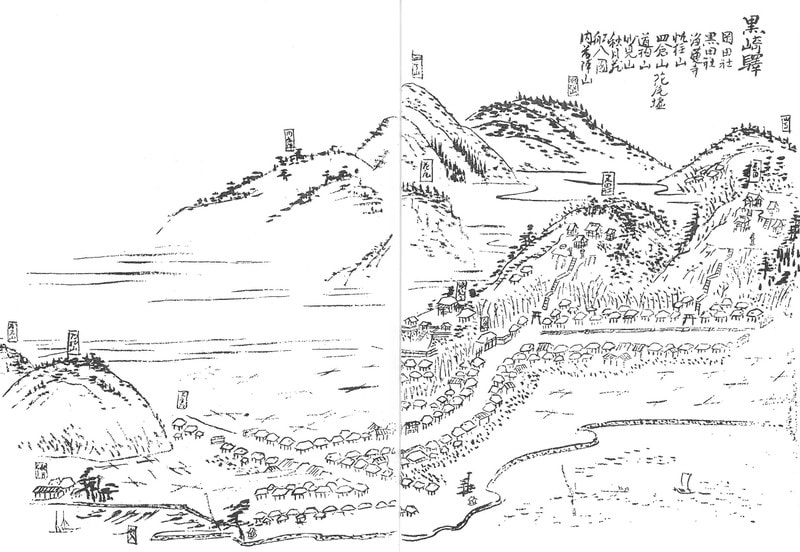本日も秋晴れ。
朝夕は肌寒いとはいえ、日中は過ごし易い日々が続きますね。
こんにちは。禰宜です。
さて。
突然ですが、当社には何人の神職・巫女が奉仕しているでしょう?

日々更新するブログで「宮司」やら「禰宜」やら「K権禰宜」やら「T権禰宜」やら「さくら」に「ぶぅ」に「ぬこ」などなど・・・色んな人物が出てきますが把握するのは難しいですよね?
・・・というわけで。
本日は岡田宮の神職・巫女のご紹介です。
先ずは神職から。

『宮司』
「宮の司」の職名の通り当社の責任者。郷土史講演などでも活躍中。
ブログは『名所・パワースポット』系。今何ヵ所目でしょう?

『禰宜』
かつての「I権禰宜」。机をすぐ散らかして巫女長に怒られる日々。
力を入れる時と入れない時の差が激しいブログが特徴。

『K権禰宜』
かつての「K出仕」。書道は師範の腕前。マイブームは篳篥(らしい)。
最近、堅かったブログの文章が面白くなってきたと評判(笑)

『T権禰宜』
田川の神社の禰宜さんですが、当社の神職も兼任されています。
お宮の風景ブログといったらこの方。「ほっ」とするブログを更新中。

『H助勤』
先日ご紹介した助っ人。旧官社の元宮司さん。
宮司職を定年退職された為、当社でお手伝い頂いています。

『O研修生』
こちらも先日ご紹介したO研修生。
いつか彼にもブログを書いてもらえるかも。
・・・ここまでがいわゆる「神主」さん。
-----------------------------------------------------------
お次は巫女さんのご紹介。

『さくら巫女長』
いつも明るく爽やかな人気者。甘い物大好きで「ぬり絵」渡しの達人。
可愛らしい絵文字と顔文字を使ってブログを更新中。

『ぶぅ巫女』
副巫女長格。年は若いですがしっかりしています。
ぱぱっと短時間で読みやすいブログを書き上げる才能アリ。

『すーたん巫女』
受験生のすーたん巫女。今年の七五三は勉学専念で不参加。
お正月からまたブログを更新してくれる事でしょう!

『ぬこ巫女』
「にゃー」と始まるぬこ巫女ブログ。
当社最年少の一人ですが、ご奉仕の場数は踏んでいます。

『すず巫女』
先日ご紹介した新人巫女の一人。巫女長の妹。
噂では姉よりしっかりしているとかなんとか(笑)

『ゆり巫女』
先日ご紹介した新人巫女で、当社最年少の一人でもあります。
これから色々と学んできっと素敵なブログを書いてくれる事でしょう。
・・・と、以上が平時御奉仕に来ていただける巫女さん達。
-----------------------------------------------------
ここからは繁忙時に臨時で駆けつけてくれる頼もしい巫女さん達です。

『Z巫女』
一番の古株ベテラン巫女。もはやレジェンドの域に達しています。
因みに「Z」はずら(ヅラ)の意。ただし本人はカツラではないですよ。

『D巫女』
Z巫女の相棒。どちらかというと「つっこみ」担当。
Z巫女とD巫女の息の合った掛け合いは見ていて飽きません(笑)

『le巫女』
「レ」・・・いや「エルイー」だったかな?(笑)
英語が得意な才媛です。ディス・イズ・ア・ペン!!

『F巫女』
県外の大学に通う看護師のタマゴ。
これで病気になったらいつでも看護してもらえますね!(笑)

『たもさん巫女』
県外の大学に通うお医者さんのタマゴ。
これで病気になったらいつでも手術・・・(以下略)

『きなこ巫女』
なんとも甘そうな名前の巫女さん(笑)彼女も県外へ進学。
来年のお正月は土産話を聞かせてくれる事でしょう。
さてさて。
いかがだったでしょうか。
岡田宮の人々が少しだけ垣間見れたのではないでしょうか?
誰がどんなブログを書いているか・・・把握できました?
これら一人一人の力が合わさることによって岡田宮の社務は成り立っています。
神様が静かに鎮まります様に、また参拝者の方々が気持ちよく参拝できるように。
岡田宮奉仕者一同、これからも頑張ってまいります!
禰宜