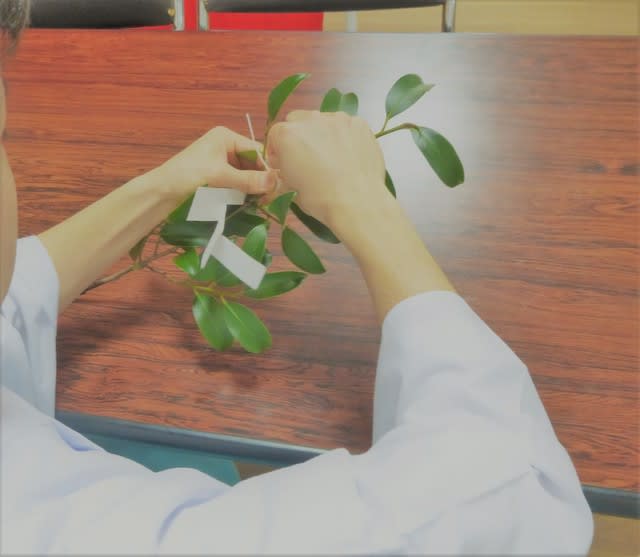こんにちは、めんたい出仕です。
時々雪がちらほらしています。
12月も半ばになり、新年が目前に迫ってきました。
平成30年も気分新たに過ごせますよう、
ブログをご覧の方々も神社に参拝されることかと思います。
参拝には2礼2拍手1礼などの作法があり、
様々なウェブサイトで紹介されています。
しかしそれらのサイトではあまり紹介されませんが、
拍手(はくしゅ、かしわで)の作法にはコツがあります。
拍手を打つ前には1度両手を合わせ、
右手を斜め下手前にずらして打ちますが、

この際、良い音が鳴るように手を打ちます。
手同士を強く打ち付けて音を鳴らすのではなく、
左手の平の僅かな窪みに、

右手の平の上部を軽く打ち付け、

両手の間に空気を含むように打つと、「パンパン」と高く乾いた音がします。

手が乾燥していると音が出辛いので、
冬は手を保湿して労わってください。

時々雪がちらほらしています。
12月も半ばになり、新年が目前に迫ってきました。
平成30年も気分新たに過ごせますよう、
ブログをご覧の方々も神社に参拝されることかと思います。
参拝には2礼2拍手1礼などの作法があり、
様々なウェブサイトで紹介されています。
しかしそれらのサイトではあまり紹介されませんが、
拍手(はくしゅ、かしわで)の作法にはコツがあります。
拍手を打つ前には1度両手を合わせ、
右手を斜め下手前にずらして打ちますが、

この際、良い音が鳴るように手を打ちます。
手同士を強く打ち付けて音を鳴らすのではなく、
左手の平の僅かな窪みに、

右手の平の上部を軽く打ち付け、

両手の間に空気を含むように打つと、「パンパン」と高く乾いた音がします。

手が乾燥していると音が出辛いので、
冬は手を保湿して労わってください。