隠岐さや香『文系と理系はなぜ別れたのか』(星海社新書、2018年)
 フランスの科学史を専門に研究している人の学問論みたいなものである。古くは中世における大学の成立から解きはじめて、現代における文理融合とか学際的研究などの話にまで進んでいる。
フランスの科学史を専門に研究している人の学問論みたいなものである。古くは中世における大学の成立から解きはじめて、現代における文理融合とか学際的研究などの話にまで進んでいる。
この本の内容とはまったく無関係な話だが、私は小学生の頃から理科が好きだった。これは黒田くんという知り合いの影響なのだが、といってももともと理科が好きだったから、担任の教師が私と黒田くんを「理科リーダーズ養成プログラム」みたいな集まりに参加させたことで彼と仲良くなり、彼の影響を受けたのだろう。
私のほうはあまり本を読まない子どもであったので、せいぜい「偉い人シリーズ」のニュートンなんかを読む程度だったのだが、彼は両親とも教師の息子で、鍵っ子だから、好きなように本を買ってもらっていたみたいで、沢山の本を読んでいた。(ちなみに、土曜日の昼ごはん時によしもと新喜劇を見るという、私にとって衝撃的な文化を教えてくれたのも彼である。)残念ながら、彼は20才台に病気で早逝した。
彼の影響で天文に関することが好きになり、そういった関係の科学読み物のようなものを乱読するようになった。中学校では成績もよく(まぁ田舎の中学校だが、全県で行われる実力テストでも上位5位に入っていたのだから、まぁ自慢してもいいだろう)、将来は天文学を研究したいと思い、当然のことながら、高校で3年に上がる時に理系を選択した。
しかし理系の科目の成績がまったくふるわず、学年の途中で担任に文系に変更することを伝えた。それで大学は文学部に入ったのだが、基本的に理系が好きなのだ。
それで思うのだが、文系と理系という区分けにどれほどの意義があるのだろうかと疑問に思う。扱う概念のありようが違う、それと数学で定式化できない(近代経済学のように数式化可能な分野もあるようだが)などの相違があるにせよ、基本的なものはどちらでも変わらない。
研究にしても、よくテレビでやっているような、自然科学の研究者たちが研究ラボで地道に試験管にいろんな試薬を入れ替えとっかえして無数のケースを実験している姿は、人文系の研究者が自分の仮説の有効性を引き出すために、いろんな文献を読んでいくのと似ている。
 フランスの科学史を専門に研究している人の学問論みたいなものである。古くは中世における大学の成立から解きはじめて、現代における文理融合とか学際的研究などの話にまで進んでいる。
フランスの科学史を専門に研究している人の学問論みたいなものである。古くは中世における大学の成立から解きはじめて、現代における文理融合とか学際的研究などの話にまで進んでいる。この本の内容とはまったく無関係な話だが、私は小学生の頃から理科が好きだった。これは黒田くんという知り合いの影響なのだが、といってももともと理科が好きだったから、担任の教師が私と黒田くんを「理科リーダーズ養成プログラム」みたいな集まりに参加させたことで彼と仲良くなり、彼の影響を受けたのだろう。
私のほうはあまり本を読まない子どもであったので、せいぜい「偉い人シリーズ」のニュートンなんかを読む程度だったのだが、彼は両親とも教師の息子で、鍵っ子だから、好きなように本を買ってもらっていたみたいで、沢山の本を読んでいた。(ちなみに、土曜日の昼ごはん時によしもと新喜劇を見るという、私にとって衝撃的な文化を教えてくれたのも彼である。)残念ながら、彼は20才台に病気で早逝した。
彼の影響で天文に関することが好きになり、そういった関係の科学読み物のようなものを乱読するようになった。中学校では成績もよく(まぁ田舎の中学校だが、全県で行われる実力テストでも上位5位に入っていたのだから、まぁ自慢してもいいだろう)、将来は天文学を研究したいと思い、当然のことながら、高校で3年に上がる時に理系を選択した。
しかし理系の科目の成績がまったくふるわず、学年の途中で担任に文系に変更することを伝えた。それで大学は文学部に入ったのだが、基本的に理系が好きなのだ。
それで思うのだが、文系と理系という区分けにどれほどの意義があるのだろうかと疑問に思う。扱う概念のありようが違う、それと数学で定式化できない(近代経済学のように数式化可能な分野もあるようだが)などの相違があるにせよ、基本的なものはどちらでも変わらない。
研究にしても、よくテレビでやっているような、自然科学の研究者たちが研究ラボで地道に試験管にいろんな試薬を入れ替えとっかえして無数のケースを実験している姿は、人文系の研究者が自分の仮説の有効性を引き出すために、いろんな文献を読んでいくのと似ている。










 編集者の良し悪しが本の出来具合を左右するという好例のような本であった。
編集者の良し悪しが本の出来具合を左右するという好例のような本であった。 こんなものがあるというのをどこで知ったのだっけ。たぶん新聞の書評欄だと思うのだけど、思い出せない。いずれにしても、ずいぶん待たされて、やっと私の手元に届いた。
こんなものがあるというのをどこで知ったのだっけ。たぶん新聞の書評欄だと思うのだけど、思い出せない。いずれにしても、ずいぶん待たされて、やっと私の手元に届いた。 小林惠子の日本古代史シリーズ第二巻である。今回は四世紀が取り上げられている。崇神、垂仁、景行、成務、仲哀、応神がこの時期の天皇になる。
小林惠子の日本古代史シリーズ第二巻である。今回は四世紀が取り上げられている。崇神、垂仁、景行、成務、仲哀、応神がこの時期の天皇になる。 ヘンデルの音楽が政治と密接に関係している「機会音楽」であったことを提示した著作である。
ヘンデルの音楽が政治と密接に関係している「機会音楽」であったことを提示した著作である。 「オペラ・歌曲がもっと楽しくなる教養講座」という副題が付いているように、とくにオペラの題材になるギリシャ神話の神々について解説したもの。
「オペラ・歌曲がもっと楽しくなる教養講座」という副題が付いているように、とくにオペラの題材になるギリシャ神話の神々について解説したもの。 後期高齢者、というか、副題にもあるように、「口から食べられなくなった」寝たきりの高齢者の医療のあり方、それは取りも直さず人間の最後の看取りのあり方を問題にした本である。
後期高齢者、というか、副題にもあるように、「口から食べられなくなった」寝たきりの高齢者の医療のあり方、それは取りも直さず人間の最後の看取りのあり方を問題にした本である。 女子群像などの壁画で有名な高松塚古墳の発掘調査をこの人が行ったのが1972年。私が大学に入ったのが1974年。
女子群像などの壁画で有名な高松塚古墳の発掘調査をこの人が行ったのが1972年。私が大学に入ったのが1974年。 優れた論文でなくてよい、論文としてきちんとした体裁の整った論文を書いて、ギリギリ合格すればいいという趣旨で書かれた論文指南書である。
優れた論文でなくてよい、論文としてきちんとした体裁の整った論文を書いて、ギリギリ合格すればいいという趣旨で書かれた論文指南書である。 作家として、父親として、昆虫好きとして、医師として、躁うつ病、マンボウ・マブゼ共和国などなど、多面的な北杜夫の人生を紹介するというような本である。
作家として、父親として、昆虫好きとして、医師として、躁うつ病、マンボウ・マブゼ共和国などなど、多面的な北杜夫の人生を紹介するというような本である。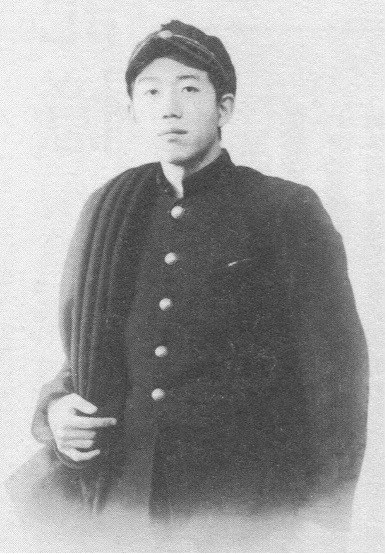 年譜を見ると、すでに東北大学の学生時代から頻繁に小説を懸賞などに応募したり、同人誌に参加して切磋琢磨していたことが分かる。本気で作家になるつもりなら、そこまでしなければならないのだろうが、私にはそんな根性はなかったようだ。
年譜を見ると、すでに東北大学の学生時代から頻繁に小説を懸賞などに応募したり、同人誌に参加して切磋琢磨していたことが分かる。本気で作家になるつもりなら、そこまでしなければならないのだろうが、私にはそんな根性はなかったようだ。