 1995年歴史上稀に見る事件であった地下鉄サリン事件の直後に起きた警察庁長官狙撃事件の真犯人を追って、その目的、方法、真犯人の人物を追求した本である。
1995年歴史上稀に見る事件であった地下鉄サリン事件の直後に起きた警察庁長官狙撃事件の真犯人を追って、その目的、方法、真犯人の人物を追求した本である。この本を読んで感じるのは、たしかに真犯人による供述や告白があってのことだが、その供述の裏を取るということが、いかに重要かということが分かる。
ほぼ不可能と思われたアメリカでの拳銃や銃弾の売買や射撃練習などの裏取りが現地に行ってみれば(もちろん優秀な通訳やアドバイザーあってのことだが)可能だということ。なんでもその気になれば調べられるということだ。
そして最も衝撃的なことは、犯人の中村泰のこともそうだが、それ以上にはっきりと中村泰が真犯人だという裏が取れているのに、オウム真理教が犯人だということを前提にした公安出身の米村警視総監の妨害によって真犯人を立件できないで迷宮入りにしてしまい、時効になったことである。
警察庁長官が瀕死の重傷を負わされた事件だぜ、警察のトップが死にそうになった事件だぜ、その真犯人が誰の目にも明らかになっているのに、警視庁のトップのエゴのために立件できないって。殺されそうになった国松長官も何も言わないって、どういうこと!!日本の警察組織、腐ってる。
前にグリコ事件の件で、大阪府警のトップがバカだったので、真犯人を取り逃がしたという話のことを書いた時にも触れたが、テレビドラマ『踊る大捜査線』での警視庁幹部の責任のなすりつけあいはドラマの上の話ではなくて現実のことだと書いたが、それを裏付ける出来事がこの事件だろう。










 強制不妊問題についての5月28日の仙台地裁の判決は「旧法は個人の尊厳を踏みにじるもので、誠に悲惨だ」として、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとの判断を示した。
強制不妊問題についての5月28日の仙台地裁の判決は「旧法は個人の尊厳を踏みにじるもので、誠に悲惨だ」として、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとの判断を示した。 佐々木友次さんという北海道出身の特攻兵が9回特攻命令を受けながらも、死んでこいという上官の命令に反抗して、生きて帰ってきたという話を書いたもの。
佐々木友次さんという北海道出身の特攻兵が9回特攻命令を受けながらも、死んでこいという上官の命令に反抗して、生きて帰ってきたという話を書いたもの。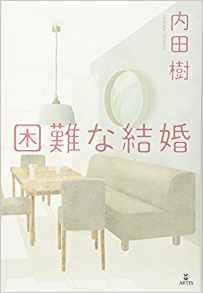 内田樹が結婚の話って、なんか軽い読み物だなと思いつつ、手にしてパラ読みをしたところ、なんか面白そうなことが書いてあることが分かり、借りてきてしっかり読むことにした。
内田樹が結婚の話って、なんか軽い読み物だなと思いつつ、手にしてパラ読みをしたところ、なんか面白そうなことが書いてあることが分かり、借りてきてしっかり読むことにした。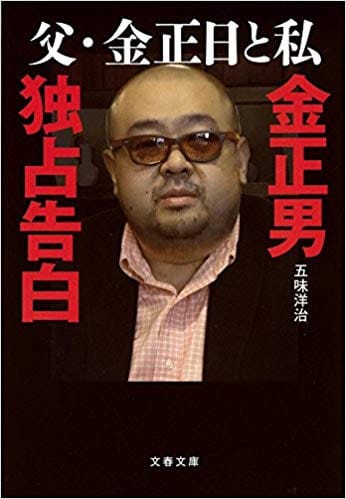 金正男は2017年2月に暗殺されるまで、おそらく半島ウォッチャーにとっての最大のターゲットだったと言っても過言ではないだろう。
金正男は2017年2月に暗殺されるまで、おそらく半島ウォッチャーにとっての最大のターゲットだったと言っても過言ではないだろう。 いわゆるフランス人レスペクト物の一冊である。これらの多くはアメリカ人が書いたものというのが味噌である。つまりアメリカという伝統を持たない大量消費社会から見ると、フランスという伝統をもち、(アメリカ人から見たら)コンサバティブな国民の生活の仕方がすごく新鮮に見えてくるのだろう。
いわゆるフランス人レスペクト物の一冊である。これらの多くはアメリカ人が書いたものというのが味噌である。つまりアメリカという伝統を持たない大量消費社会から見ると、フランスという伝統をもち、(アメリカ人から見たら)コンサバティブな国民の生活の仕方がすごく新鮮に見えてくるのだろう。 加藤陽子が『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』で紹介していたので、読んでみた。未曽有の戦死者・負傷者を出した太平洋戦争へいたる日本政府や日本軍の情報活動について詳述した本である。
加藤陽子が『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』で紹介していたので、読んでみた。未曽有の戦死者・負傷者を出した太平洋戦争へいたる日本政府や日本軍の情報活動について詳述した本である。 家の中では歩けるようになったが、また外歩きをするほどではなく、読書の時間が有り余るほどあるので、よく読める。
家の中では歩けるようになったが、また外歩きをするほどではなく、読書の時間が有り余るほどあるので、よく読める。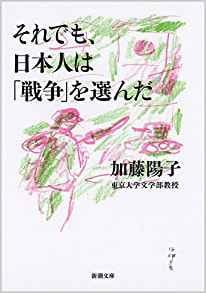 先週の金曜日(15日)に孫たちが遊びに来て、こんどサッカークラブに入るという孫がサッカーをしようというので、じいちゃん・ばあちゃんと孫二人でやり始めたところ、普段使わない筋肉を使ったせいか、肉離れを起こしてしまった。痛いけど歩けるという軽症ではなくて、痛くて歩けない中程度の症状のようだ。肉離れにはRICEが大事という。安静、アイシング、圧迫、高くする。安静とアイシングなら自分でもできるので、それから家から出ずに、ずっと安静状態にしていた。本を読むことぐらいしかできない。
先週の金曜日(15日)に孫たちが遊びに来て、こんどサッカークラブに入るという孫がサッカーをしようというので、じいちゃん・ばあちゃんと孫二人でやり始めたところ、普段使わない筋肉を使ったせいか、肉離れを起こしてしまった。痛いけど歩けるという軽症ではなくて、痛くて歩けない中程度の症状のようだ。肉離れにはRICEが大事という。安静、アイシング、圧迫、高くする。安静とアイシングなら自分でもできるので、それから家から出ずに、ずっと安静状態にしていた。本を読むことぐらいしかできない。 朝日新聞の3月7日号に「平成の30冊」というのが載っていた。
朝日新聞の3月7日号に「平成の30冊」というのが載っていた。