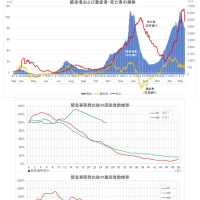(二週間以上寝かせてしまった原稿で、もはや旧聞に属するが)全仏オープンで最も話題をさらったのは、加藤未唯選手の失格問題だったのではなかろうか。活躍した多くの選手にも、主催者にも、全く不本意な状況だったであろう。加藤選手の提訴が大会側に却下されたことを受けて、獲得するはずだった賞金額の寄付を募る活動が海外でスタートしたという。
女子ダブルス3回戦第2セットの途中、加藤選手が相手コートに返したボールがボールガールに当たってしまい、いったん警告と判断されながら、対戦相手からの猛抗議を受けて裁定が覆り、危険行為と見做されて失格処分となった、あれである。どこが危険行為か? と訝しく思うが、他の種目にも出場出来ない可能性があったところ、主催者側の配慮で、混合ダブルスには出場でき、失意の思いをバネに優勝を勝ち取った。見事と言うほかない。さらに翌日、手土産を持ってボールガールを見舞うという、WBCの佐々木朗希投手を思わせる美談で盛り上がった。
敢えて相手選手のスポーツマンシップ欠如は問うまい。危険行為と言っても、故意か故意でないかは判断のポイントではないらしいので、ルール上は問題ないようだ。しかし、かつて憎らしいほど強かった(大相撲で言えばかつての北の湖のような、と言ってしまうのは言い過ぎか・・・一応、最大の敬意である 微笑)マルチナ・ナブラチロワさんは「ルール変更が必要。映像で検証も出来たはず」と私見を述べ、プロ選手協会も「不当な判定」と加藤選手を擁護する声明を出すなど、大きな波紋を呼んだ。当の選手だけでなく、せっかく試合を見に来た人をもガッカリさせるようなルールは、やはり見直しを期待したい。
話は変わるが、かつて「ルール・ベースのリベラルな国際秩序」などと言って、今では「自由で開かれたインド太平洋」にすっかり取って代わられた印象だが、言わば中国を牽制する(包囲するとまでは言わない)外交上の標語があった。ジョン・アイケンベリー氏によれば、戦後に成立したアメリカを中心とした開放的で制度化された協調的な国際秩序のことだという。それを意識したのかどうか、その後、中国はやたら「法治」を言い出すようになった。
中国が、特に国の安全や利益擁護を目的とした法律を整備し始めたのは、習近平氏が国家主席になった2013年以降のことである。香港の民主化運動弾圧で有名になった「国家安全法」の本国版は2015年7月の制定だが、実は1993年制定のもともとの「国家安全法」を今話題の「反スパイ法」として改定(2014年11月)したことに伴い、新たに制定したものだ。2015年12月には「反テロリズム法」を、2016年4月には「国外NGO 国内活動管理法」なる法律を制定した。後者はロシアが2012年に「NGO法」改正により取締り強化したことに倣ったものと思われる。ここで言うNGOは、東欧のカラー革命やアラブの春で暗躍したと噂される、アメリカ政府の財政資金が投入されて民主主義を推進する特定NGOを意識したのだろう。体制転覆に繋がりかねないものとして警戒したものだ。そして、2016年11月に「サイバーセキュリティ法」が、2017年6月には、学生だろうが勤労者だろうが、海外留学していようが海外駐在していようが、中国人や中国企業である限り、政府の情報活動に協力させることで悪名高い「国家情報法」が制定された。いずれも概ね国家の安全を目的としている。
もとより中国で法治と言っても、欧米で法が支配する法治(Rule of Law)ではなく、憲法の上に中国共産党が君臨し、中国共産党が法を使って支配するという意味での法治(Rule by Law)である。日本のように、憲法をはじめとして民主主義的な手続きによって法をアップデートして手段として安全を維持するのではなく、憲法そのものを守ることが第一義のような、手段と目的が倒錯するのもどうかと思うが、独裁政権のもとで法を操りながら、法治というグローバルスタンダードにさも従っているかのように装い、つまるところ独裁と同義なのだから、堪ったものではない。
かつて、息子の命名にあたって、使えない漢字を使って届け出て、後に却下され、当時、届け出たボストン総領事館の担当官に、漢字という文化を縛るとは酷い法だと思わずボヤいたら、悪法も法だと開き直られてしまった。Law Maker側の人間に言われたくないものだ(まあ、徒らに読めない漢字が人名として横行するとすれば、名付けられた本人にとっても気の毒ではあるのだが)。法治(Rule of Law)なのだから、法なるもの(あるいは全仏オープンのルールにしても)、多少、時代に後れるにしても、余程、心してアップ・トゥ・デイトを保って人心が離れることがないようにして貰いたいものだと思う。