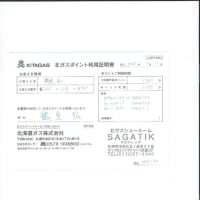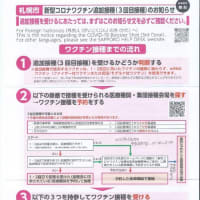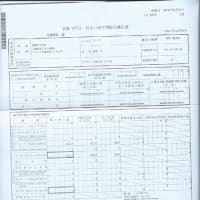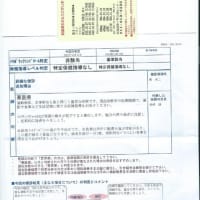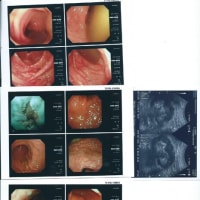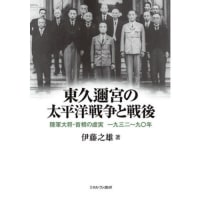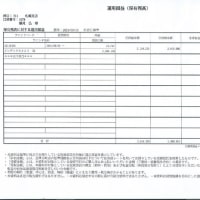今日の続編日記は、今読んでいる田中小実昌著『コミマサシネノート』(1978年晶文社刊)に登場した映画『愛の嵐』(1973年製作 リリアーナ・カヴァーニ監督 ダーク・ボガード シャーロット・ランプリング主演)のことです。
この著書に映画『愛の嵐』に関する記述がありました。私はこの記述を読んでいて、とても懐かしい思い出が蘇り、この映画をとても観たくなり、今お茶の間鑑賞しています。
この映画は、1957年のウィーンが舞台です。元ナチス親衛隊員で今はホテル夜間フロント係に身を隠している男(ダーク・ボガード)が、第二次大戦中のユダヤ人強制収容所で彼の倒錯した愛玩物にしたユダヤ人少女(シャーロット・ランプリング)に、勤めているホテルで偶然に再会し、お互いに禁断の愛に堕ちていく男女の愛情ドラマです。添付した写真は、そのホテルのフロントに来た時のシャーロット・ランプリングです。
田中小実昌氏は、自著でこの映画の興味深い評論を書かれています。以下に、その著書から引用・掲載します。
『ヘラルド映画「愛の嵐」。この映画もあれこれ評判になることだろう。ナチスのユダヤ人収容所でのナチ親衛隊員とユダヤ人の美しい少女との男女の遊び(ユダヤ人の少女にとっては拒めないことだっただろうが)。収容所での親衛隊員たちのだらけたパーティで、少女は上半身裸でナチスの軍服を着て歌をうたう(この姿が、たぶん、この映画の広告の写真になるだろう)そのご褒美に、主人公の親衛隊員が、箱に入れて兵隊に持ってこさせたものは、男の生首だった。自分をいじめる、と少女が訴えていた、収容所の同じ部屋の男の首だ。この映画は英語なので、そのユダヤ人の男の名前はジョンとなっていたが、洗礼者のヨハネと同じ名前で、だから、主人公のナチ親衛隊にとって、このユダヤ人の少女はサロメってことになる。余計なことだけど、洗礼者のヨハネの首が盆に載せて運ばれ、サロメに渡されることは(サロメという名前はない)聖書のマタイ伝十四章に出ているが、サロメのことを少女という訳語になってるのに、今、気がついた。この男女が十なん年か経った1957年、男が夜勤のポーターをしている、ウィーンのホテルで会い(ザ・ナイト・ポーターというのが原題名)、ナチのユダヤ人収容所で始まった関係だからというわけか、それとそっくりのような状態になっていく。しかし、1957年のウィーンで、戦争中のユダヤ人収容所と同じような状態というのは、たいへんに無理なことで、その大無理が、実は、この映画の狙いだろう。監督は女性だそうだが、まったく、女というのは、男と女の愛の遊びが好きだ。愛の遊びのバリエーションとして、とうとう、ナチのユダヤ人収容所まで出てきた。この映画の製作にあたっては、ある実話がヒントになったそうだが、実話というようなものは、ほんとにいろんな実話がある。それを聞いて、こいつは映画になるぞと思い、映画を作るのは、また別のことだ。』
映画を鑑賞して、この田中小実昌氏が言及した「男の生首」シーンを補足すると、元ナチス親衛隊員(ダーク・ボガード)はナチのユダヤ人収容所で一緒だった没落貴族の伯爵夫人に、過去の収容所での出来事を語る回想の場面で出てきます。その際、夫人には「聖書」の物語だと親衛隊員は説明しています。だから、親衛隊員自身はユダヤ人少女(シャーロット・ランプリング)がサロメ(何も映画ではこの名が出てこない)との自覚なく、聖書のマタイ伝十四章のヘロデ王の誕生日に踊ったヘロディアの娘としか思っていません。でも、何度観てもこの問題シーンは、とても衝撃的です。
この著書に映画『愛の嵐』に関する記述がありました。私はこの記述を読んでいて、とても懐かしい思い出が蘇り、この映画をとても観たくなり、今お茶の間鑑賞しています。
この映画は、1957年のウィーンが舞台です。元ナチス親衛隊員で今はホテル夜間フロント係に身を隠している男(ダーク・ボガード)が、第二次大戦中のユダヤ人強制収容所で彼の倒錯した愛玩物にしたユダヤ人少女(シャーロット・ランプリング)に、勤めているホテルで偶然に再会し、お互いに禁断の愛に堕ちていく男女の愛情ドラマです。添付した写真は、そのホテルのフロントに来た時のシャーロット・ランプリングです。
田中小実昌氏は、自著でこの映画の興味深い評論を書かれています。以下に、その著書から引用・掲載します。
『ヘラルド映画「愛の嵐」。この映画もあれこれ評判になることだろう。ナチスのユダヤ人収容所でのナチ親衛隊員とユダヤ人の美しい少女との男女の遊び(ユダヤ人の少女にとっては拒めないことだっただろうが)。収容所での親衛隊員たちのだらけたパーティで、少女は上半身裸でナチスの軍服を着て歌をうたう(この姿が、たぶん、この映画の広告の写真になるだろう)そのご褒美に、主人公の親衛隊員が、箱に入れて兵隊に持ってこさせたものは、男の生首だった。自分をいじめる、と少女が訴えていた、収容所の同じ部屋の男の首だ。この映画は英語なので、そのユダヤ人の男の名前はジョンとなっていたが、洗礼者のヨハネと同じ名前で、だから、主人公のナチ親衛隊にとって、このユダヤ人の少女はサロメってことになる。余計なことだけど、洗礼者のヨハネの首が盆に載せて運ばれ、サロメに渡されることは(サロメという名前はない)聖書のマタイ伝十四章に出ているが、サロメのことを少女という訳語になってるのに、今、気がついた。この男女が十なん年か経った1957年、男が夜勤のポーターをしている、ウィーンのホテルで会い(ザ・ナイト・ポーターというのが原題名)、ナチのユダヤ人収容所で始まった関係だからというわけか、それとそっくりのような状態になっていく。しかし、1957年のウィーンで、戦争中のユダヤ人収容所と同じような状態というのは、たいへんに無理なことで、その大無理が、実は、この映画の狙いだろう。監督は女性だそうだが、まったく、女というのは、男と女の愛の遊びが好きだ。愛の遊びのバリエーションとして、とうとう、ナチのユダヤ人収容所まで出てきた。この映画の製作にあたっては、ある実話がヒントになったそうだが、実話というようなものは、ほんとにいろんな実話がある。それを聞いて、こいつは映画になるぞと思い、映画を作るのは、また別のことだ。』
映画を鑑賞して、この田中小実昌氏が言及した「男の生首」シーンを補足すると、元ナチス親衛隊員(ダーク・ボガード)はナチのユダヤ人収容所で一緒だった没落貴族の伯爵夫人に、過去の収容所での出来事を語る回想の場面で出てきます。その際、夫人には「聖書」の物語だと親衛隊員は説明しています。だから、親衛隊員自身はユダヤ人少女(シャーロット・ランプリング)がサロメ(何も映画ではこの名が出てこない)との自覚なく、聖書のマタイ伝十四章のヘロデ王の誕生日に踊ったヘロディアの娘としか思っていません。でも、何度観てもこの問題シーンは、とても衝撃的です。