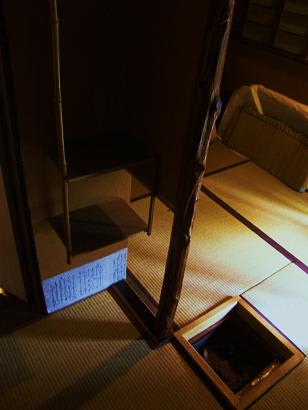|
思考の整理学 (ちくま文庫) 外山 滋比古 筑摩書房 このアイテムの詳細を見る |
なんでも、東大・京大生に2008年にもっとも読まれた本、とのこと。
(昨日 南北線の中でこの本を読んでる学生とおぼしき人も見かけました。結構、さらっと読めてしまいます。)
この本、勝間和代さんや、勝間さんが影響を受けた神田昌典さんの本に登場するような、
"セレンディティピティ"、といった言葉とか、頭の使い方、に通じる話がいたるところに出てきます。
セレンディテイピティ、
(潜水艦の機関音をキャッチしようとして、偶然イルカの交信音をとらえたように、偶然に別の発見が導かれるような事象のこと。)
言いにくい独特の語感もあって、ちょっとオカルト的印象を抱きやすい言葉ですが、語源はセイロン性といったほどの意味らしい。
(セイロン国にいた、物を失くす名人が、失くしては探し、予期しないものを見つける名人でもあったという童話に由来するとのこと。)
例によって、いくつか抜き書き。
のちのちシンプルなスッキリ頭を確立するためにもこれは大切な修行。( ..)φ
○ 夜考えることと、朝考えることは、同じ人間でもかなり違っているのではないかということに何年か前に気づいた。
考えてみると面白い問題である。
(↑)物事によっては、考える時間を選んで、それまであせらず寝かせることも必要。
○ 読書をして、感心するところ、違和感をいだくところ、こういうものを抜き書きしておくこと。
これは、ビール作りに例えれば、素材、麦。
○ これに、別の場所(他の読書や雑談、TVなど)から、思いもかけないヒントやアイデアが出てくれば、
ビールを発酵させる酵素になる。
○ そして、しばらく寝かせること。頭の中の醸造所で時間をかける。
" 見つめるナベは煮えない"。熟したテーマは向こうからやってくる。
発酵が始まれば、自然に頭の中で動きだし、見過ごすことはまずない。
(↑)寝かせることは単なる時間のばしではない。あわてない。
○ 「 発想 」というが、新しいことはそうそうない。
すでに存在するものを結びつけることによって、新しいものが生まれる。
発想の母体は触媒である。
発想の面白さは化合物であり、元素をつくり出すことではない。
寝かせる、忘れる時間をつくる、ということも、主観や個性を抑えて、
頭の中で自由な化合が起こる状態を準備することにほかならない。
(↑)以前 取り上げたピカソも、同じようなことを言ってました。
○ 思考の整理とは、重要なものを残し、他を廃棄するような量的処理のことではない。
断片化した発想を、化合させ、立体的・質的な統合を行ない、普遍化されたメタ思考とすることである。
(↑)簡単にいうと、知識の寄せ集めではなく、自らが触媒となって、そこに何らかのバリューを加えるということなのですな。
この本では、アイデアを寝かせるための方法として、スクラップや手帖やノートの活用方法に言及しています。
その中で、様々なアイデアを分類(タグ付け)したり、
前後づけ(コンテクスト、文脈)による縛りから解放させるための、メタノートへの移植(別のノートへの書き移し)
といったテクニックを紹介しています。
しかし、ブログを活用すれば、、ここのところの手間ヒマは、大幅に簡素化されます。
マインドマップの如く、興味あるテーマを枝分かれさせていって、
タグ付けされた分かりやすい情報の引出しをこしらえて、リンクやカテゴリ分けを適宜施すことで、実現できます。
スクラップはスキャニングや画像データに変わり、ビジョンボードとして適宜統合化も可能。
勝間さんの著書にもありましたが、
ブログは、単なる情報発信の手段以上のもの、グーテンベルク以来の大発明、だと思います。
活用しないと損。
○ 歴史家は現代に近づくことを恐れる。なぜ、一番よく分かっているはずの目前のことについて分からないのか?
それは、それまでの考えや、周りが等しくかけている眼鏡が、
一時的な流行や色眼鏡なのかどうか、看破するのが難しいから。
(↑) 同時並行で『騙される脳 ~ ブームはこうして発生する ~/ 米山公啓』を読んでますが、同様の指摘がありました。
○ われわれの現実に起こっているのは、具体的な問題である。
これは、ひとつひとつ特殊な形をしているから、一見解決が困難に見える。
しかし、自分の思考を整理し、一般的で普性の高いものにまとめて、
自分だけの"ことわざ"みたいなものをコシラエテおく。
すると簡単に処理できる問題も多いし、コシラエタものに照応してそれがますます強化される。
(↓)マインドマップ(まだ試したことありませんが。)やフォトリーディングについての対談。
フォトリーディングとは、速読を目的とした読書法ではないのです。
こうやって、気になるフレージングを探しながら読む、とういうこともフォトリーディングになっているのです。
勝間和代&神田昌典セミナー「新時代のスピード情報編集法 その1」
(↓) 両氏に関係する、これまで書いたブログ記事を抜粋してみました。
・ 非常識な成功法則/神田昌典 http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/1149937da1a479b573d926d0e8b59f4a
・読書進化論/勝間和代 http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/8cd91ed10ab8ad9f75142a9580524b19
・ブログを使って仕組みをつくる http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/f6bbcec7d678073e4414d17a68ff7504

























 )
) )
)