少し肌寒い土曜日の午後、新聞広告で見て気になっていたイベントに一人でふらっと出かけてゆく。
「工房からの風」と題したこのイベントは、全国の作家さんたちが作品を販売するマルシェだ。
会場は市川コルトンプラザというショッピングセンター。
車で15分ほどのこの施設のすぐ近くに、結婚してから長男が2才くらいまで住んでいた。
この施設の敷地内になにやら怪しい神社があって、当時はあまり近寄らなかったものだが、今回のマルシェはその回りにまで出店していて、20数年ぶりにそのあたりに足を踏み入れた。
かなりの広さにたくさんの作家さんたちがご自分の作品をアピールして販売している。
陶芸の作品や、木工作品、皮製品、織物やアクセサリー・・・
かなり楽しい
ビミョーにお手入れが行き届いていないが、なんとなくガーデンっぽくなっているところもあり、ちょっとした癒しのスペースになっている。
ここに特設のカフェができていて、お茶とケーキがいただける
カフェのスタッフの方々は、何となく手際が悪くて、スムーズに席に案内できないが、ものすごく一生懸命で誠実な感じがして微笑ましい。
私はリンゴとルバーブのケーキを

この日は、薄曇りだったけれど、風が気持ちいい。
買おうかどうしようか迷っていた作家さんのところにもう一度見に行って、やっぱり買おう、と説明を聞いてみたりする。
この日の戦利品は
漆と阿蘇山の火山灰を混ぜて塗ったという木のプレート。
ひびの入ったご飯茶碗を使っている夫のためにお茶碗を。
こういうところに来るとついつい買ってしまう一輪挿し2品。
家に帰って、早速庭のチェリーセージを切って飾ってみる。
このイベントは、毎年開催されていたが、いつも何かしらの予定が入っていて、行きそびれていた。
千葉近郊の作家さんだけだと勝手に思っていたけれど、全国だったとは・・・。
テントとテントの間はゆったりとしていて、お祭りのようなごちゃごちゃ感もなく、のんびり、穏やかな時間を過ごすことができた。
自分で作品を生みだすことができるってすごいし、それを続けていられるって幸せなことだ。
あ~楽しかった
来年もぜひ行ってみよう、と心に誓ったのでした
ファンクラブに入っている妹に誘われて、斉藤和義25周年のライブに来ちゃった。
さすがファンクラブだけあって、まさかのアリーナ席。
武道館のアリーナ席は初めてだ💕
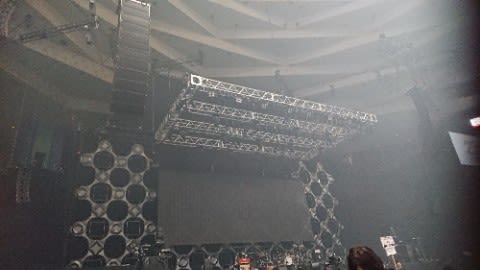
小田和正のときの山頂のような2階席とはちがい、ステージが目の前❗
アリーナ席の人たちは、どのコンサートでもだいたい大ファンなので、開始からずっと立ちっぱなし。
足腰の弱ってる私は、最後までついていけるだろうか💦
一緒に来ている妹の息子(大学生・イケメン)に倒れたら助けてね、とお願いして、初アリーナに挑む。
ものすごくファンってわけでもないので、有名な曲しか知らなかったりする。
それではせっかくのアリーナを楽しめない気がして、3枚組のCDを買って仕事しながら聴いていた。
予習だ

最初はただ聞き流していたけれど、歌詞をじっくりかみしめて聴いているとなんだか元気がでる。
ネットで調べたこの日の曲リストはこちら。
1.FIRE DOG
2.Hello! Everybody!
3.アゲハ
4.男節
5.tokyo blues
6.空に星が綺麗 ~悲しい吉祥寺~
7.真夜中のプール
8.君は僕のなにを好きになったんだろう
9.ウエディング・ソング
10.彼女
11.リズム
12.ぼくらのルール
13.カラー
14.月光
15.Alright Charlie
16.ずっと好きだった
17.Stick to fun! Tonight!
18.ダンシング・ヒーロー
19.Good Luck Baby
20.幸福な朝食 退屈な夕食
21.やさしくなりたい
22.スナフキン・ソング
23.歩いて帰ろう
24.ベリー ベリー ストロング ~アイネクライネ~
25.COME ON!
アンコール
26.僕の見たビートルズはTVの中
27.歌うたいのバラッド
28.月影
案の定、途中バラードの時にちょっとだけ座っただけでほとんど立ちっぱなし。
ふくらはぎがパンパンだ。
それにしても、前の席の3人がとにかく落ち着かない。
始まる前からはしゃぎ方が尋常じゃない上に、後ろの席に誰か芸能人を見つけたらしく、振り返っては指をさして話すのだけれどその指が刺さりそうになる。
そうかと思うと、急に感極まって号泣。
集中できない・・・。
とはいえ、このところ心が折れていたので、なんだか発散できてスッキリした

誘ってくれた妹親子に感謝感謝

へとへとだけれど、スッキリして武道館を出る。
先週と同じく激込みの九段下方面とは反対側の飯田橋に向かって、3人で居酒屋でほっと一息。
私はお酒が飲めないけれど、妹親子はガンガン行ける。
オバサン二人に付き合ってくれた甥っ子にも感謝感謝

楽しかったです。
また誘ってね

朗読会のお誘いをいただいた。
フラワーアレンジメントスクールで長い間ご一緒させていただいいてるお仲間の一人が、「秋桜の会」という朗読グループに所属している。
節分のころに「春呼ぶ朗読会」というイベントにお誘いいただいて、初めて「朗読」というものに触れることができた。
私は演劇が好きでたびたび観に行っているけれど、セリフですべてを表現する演劇とは違い、文章をそのまま忠実に読む朗読は演劇とは違った味わいがあり新鮮だった。
前回は、季節柄 鬼の話がメインだったけれど、今回は全く違っている。
何を基準に朗読をする皆さんがこの文章を選んだのかも興味深いところだ。
その時は私の住む駅のお隣の駅前にある公民館のような施設の一室が会場だった。
今回はなんと銀座。
歌舞伎座のすぐそば「銀座煉瓦画廊」。
主催の豊田紀雄さんという方の作品やコレクションが展示されている中での朗読だ。

このスクリーンに前回と同じく 宇田川民生さんとおっしゃる方の版画が映し出される。
小さな椅子が並べられた会場は満席。
スクリーンの準備をしていた宇田川氏が、ずいぶん前に電車の吊り広告でみた樹木希林さんが池の中に浮かんでいるポスターを映し出し、
すっと立ち上がり、そのポスターに書かれている「死ぬときくらい好きにさせてよ・・・」の文章を朗読する。
とつとつとした語り口がなんとも誠実な感じがして、温かい気持ちになる。
始まりの2作は夏目漱石。
最初は夢十夜の中から「第一夜」
スクリーンには大きく目を見開いた女の人が映る。
日が落ちて、また昇る様子を「のっと落ちる」とか「のそっとあがる」などと表現するのが楽しい。
こういう風な状況の説明は演劇には出てこないので、セリフからそのイメージを想像するしかないのだけれど、
そういう意味では朗読は景色を想像しやすいかもしれない。
続いて「モナリサ」(「永日小品」)
「黄ばんだ顔」の怪しい笑みをたたえるモナリサの絵を何となく気味が悪く感じるさまがリアル。
どこから見てもこっちを見ているようで、確かに不気味。
遠い昔、森永ビスケットの懸賞で「モナリザパズル」というジグソーパズルが当たって、妹たちと必死で作り上げたことを思い出す。
当時、ジグソーパズルみたいな気が遠くなるような細かいピースのパズルに触れたのが初めてだった上に、同じような色の場所が多くて途方に暮れた。
楽しいよりも苦しくなってきて、妹と一緒に宿題のように口も利かずに黙々とピースを合わせていったものだ。
確かに黄ばんだ顔だったなあ。
実は私の脳ミソと夏目漱石の文体は相性がすこぶる悪い。
何度かチャレンジしたけれど、どうもすっと頭に入ってこなくて読むのが苦痛になりリタイアしてしまう。
けれど、人に読んでもらうと、こんなにもすっと頭に入ってくるのが不思議だ。
おかげで文豪の世界を垣間見ることができた。
3番目は「私の風呂戦争」(佐野洋子「ふつうがえらい」)
この作品を朗読したのがこの朗読会に誘ってくださった方。
お風呂ギライの息子の成長がユーモラスに描かれている。
彼女の声や、はきはきとした活舌のよさは、アナウンサーのようでとても心地よい。
人柄の良さもにじみ出て、お母さんのさまざまな思いをすり抜ける息子の様子が目に浮かぶ。
私の二人の息子はもう成人しているが、そのころの大変さを懐かしさとともに思い出す。
仕事をしながらの子育ては、とにかく慌しくて、日々の雑多なことをあれこれをこなしているうちにいつのまにか育ってしまった感があるが、朗読を聞きながら様々なシーンが浮かんできた。
4番目は「まつむし草」(辻邦生「花のレクイエム」)
辻邦生さんの小説は恥ずかしながら読んだことがない。
けれど、なんだか映画のワンシーンが浮かび上がるようだ。
淡い想いみたいなものが、ちょっとせつなく甘酸っぱい。
少し紗のかかった情景が目の前に広がる気がした。
帰宅してから「まつむし草」ってどんな花なんだろう、と思い検索してみる。
するといつもアレンジでよく使うスカビオサだった。
これからレッスンの時にスカビオサが花材として入っていたら、花冠を思い出してしまうかもしれない。
前半の最後は「雪女」(小泉八雲「怪談」)
あまりにも有名なこのお話だけれど、聞いているうちに思いのほかざっくりとしか知らなかったことに気づく。
子供が10人もいたんだ

とか、新鮮な驚きだ。
夫の話を優しく促しながら聞いている妻が、恐ろしい雪女に豹変するときの声色の変化には思わず鳥肌が立つ。
それにしても愛する夫にこの誘導尋問はないだろう、などと思ったりもする。
約束を守るかどうか監視するためだけに一緒にいたのだろうか、でも優しい夫との平穏な日々を愛おしく思っていたはずだ、とか雪女とのハーフの子供って将来どうなるのだろうか、などとくだらないことも考えてしまう。
休憩時間に展示されている絵や陶器を見たかったけれど、とにかく人がいっぱいでなかなか作品に近づけない。
もっと早く会場に入ればよかった。
休憩の後は「無名俳人 鶴巻あやの人生」と付題した口上が宇田川氏から語られる。
なんでも彼の奥様のお母さまだとか。
そのあとは、この朗読の会の主宰である小松久仁枝さんが「鶴巻あやの世界」と題して彼女の人生を語り、彼女の作品を朗読する。
宇田川氏が義母の激動の人生から生まれた詩や俳句に版画を合わせた作品たちが、次々とスクリーンに映し出される。
過酷な生活の中で詩を作ることが生きる力だった、ということがひしひしと伝わってくる。
どこかで同じようなことが・・・と記憶を手繰る。
数年前にみた、金子みすゞが自ら死を選ぶまでの3年間にスポットをあてた「空のハモニカ」という舞台だ。
金子みすゞが、女の子を授かってから、自ら命を絶つまでの日々を描いたお芝居。
女性が社会に進出していくのが、果てしなく難しかった時代、
強く、静かな思いを胸に、詩を書き続けたみすゞが、ついに力尽きるまでが、淡々と、穏やかに描かれていた。
彼女は詩を書くことを取り上げられ、絶望し自ら命を絶ってしまう。
彼女もまた、詩という形で自分を表現することが生きる力だった。
この時のみすゞのセリフに
「心が道を照らす」
というようなものがあり、心に響いた。
あやさんの心も道を照らしていただろうか。
あやさんは詩を書き続けることができて、ホントによかった。
そうでなければ、もしかしたら宇田川氏は奥様と出会うことができなかったかもしれない。
過酷な日々が一段落してからの俳句はなんとも穏やかだ。
その中の一句に心ひかれた。
「一人でも笑うことあり青瓢箪」
描かれている2つの瓢箪がほほえましい。
想像を絶する過酷な日々を経て、たくさんのつらいことを乗り越えて、一人笑える心の余裕というか大きさに、なにか圧倒的なものを感じた。
前回の朗読会は所用で中座したため、小松さんの朗読を聞くことができず残念だったが、今回は最後まで聞くことができた。
なんとも温かい広がりのある声で、深い想いの込められたあやさんの詩や俳句が空中を自由に舞っているようだった。
青瓢箪と糸とんぼの句のときに映し出された版画が心に残り、終演後、宇田川氏に思わず声をかけてしまう。
「作品は絵葉書などにはなってないのでしょうか。」
図々しい・・・。
特に作ってはいないけれど、どの作品かを言ってくれたら作りますよ、などと後片付けの手を止めて、にこやかにおっしゃる。
なんてもったいない

そんなわざわざ作っていただくわけには、と恐縮する私に、宇田川氏は後程送ってくださる、ともったいないお言葉。
お言葉に甘えて名刺を交換させていただく。
本当に図々しくて申し訳ありません。
でも、楽しみにお待ちしています。
前回、今回とも、もう一人フラワーアレンジ仲間が会場に。
彼女は私と同じ観客として、来場していた。
前回は帰るまで彼女が会場に来ていることに気がつかなかったが、今回はお隣に座って、最後まで。
一人で聴くのも楽しいけれど、感動を共有できる仲間がいると、楽しさが倍増する。
というわけで、朗読会を思い切り堪能させていただいた。
秋桜の会のみなさん、宇田川民生さん、楽しい時間をありがとうございました。
益々のご活躍をお祈りしています


我が家から2km弱のところに、宮内庁の新浜鴨場(しんはまかもば)、という施設がある。
周りは木で覆われていて中がどうなっているのかわからない。
その外側に野鳥の楽園っていうのもあって、どこまで何なのかよくわからない謎の場所だ。
皇太子様が雅子さまと結婚前にここでデートした、ってことで、一時期ちょっと有名になった。
普段は一般公開されてないのだが、年に数回、市の広報に見学希望者の募集記事が載り、市内在住の人が往復葉書で申し込んで当選すれば中に入れることとなる。
特に皇室に興味は無いのだけれど、入れない場所ってのに興味津々で応募してみたら当たった
あらかじめ参加者の名前を4人まで書かないといけないので、義母、私の母、夫と私の4人を書いてみた。
当たると思わなかったので事前の了承は得ていなかったから、聞いてみたら全員快諾。
当日は、市役所の支所の前に集合し、そこからバスで鴨場へ。
もう一つの集合場所から乗ってる人たちもいて、全部で30人くらいだろうか。
バスで5分も走ればもう到着。
住宅街の細い道の先に入口が。
こんなところから入るのね。
宮内庁の職員の方のお出迎えを受け、鴨場についての説明VTRを見る。
VTRは画像も音声も相当古い・・・。
記念の写真撮影はOKだけど、SNSへの投稿はNG、という注意を受ける。
残念💦
その後、職員の方の案内で、敷地内を歩き始める。
なんでも池だけで4000坪もあるらしい。
この時期、野生のカモが飛来してきていて、前日まで狩猟が解禁されていたとのこと。
総理大臣とか海外の要人とか議員さんとか、いわゆるおエライさんが招待されて、接待狩猟がおこなわれるらしい。
本溜まりと言われる大きな池から何本かの堀がひかれていて、おとりのアヒルを使って鴨を誘導する。
そこへ、大きな網を持ったおエライさんたちがいきなり顔を出すと、鴨がびっくりして飛び立つのでそこに網をかぶせて捕獲する。
アヒルは飛べないので、鴨だけが網に入る、というわけだ。
捕獲した鴨には足にナンバーが刻印された足環をつけて放すとのこと。
食べるのかと思った・・・
狩猟の後、昼食がふるまわれるらしいが、この時に食する鴨は、合鴨で野生の鴨ではない、と私の心を見透かしたかのような補足説明もあった。
会食のための食堂は、失礼ながらちょっとボロい・・・。
よく言えばレトロ。震災の時よく大丈夫だったな、と感心する。
職員の方によれば、予算がここまで回ってこない、とのこと。
狩猟はしないまでも、堀に鴨を引き寄せるところまでは見せてくださる、という。
条件反射を利用して、餌の係の方が、まず板を木槌でカンカン叩いて音をたてる。
そうすると、餌が貰える、としつけられたアヒルが堀に入ってくる。
そこにカンカンしてた係さんが餌を持ってダッシュして、堀に餌をまく。
このとき、係さんの姿は見えないようになっている。
アヒルについていけば安全に餌が食べられる、と学習した鴨がそれに続いて堀にはいる。
その様子を見るために、私たちは1円玉の大きさもない小さな穴から順番に覗く。
鴨の天敵は鷹と人間、と職員の方はおっしゃる。
人の気配を感じると鴨は逃げてしまうので、通路の両側は背よりも高い笹で覆われている。
笹の葉が風で揺れる音で足音を消すとのこと。
それにしても、板をカンカンする人と、餌を撒く人は同じじゃないといけないんですか?
と聞いてみたところ、なんせ職員が5人しかいないので、とのお答え。
鴨の習性とか、難しい理由があるのかと思ったら、単なる人手不足だったとは。
ちなみに今の係のお兄さんはお陰で痩せました、とおっしゃっていた。
新宿御苑みたいに入場料をとって、一般に公開すればいいのに、なんて思っていたが、これほどデリケートに鴨を守っているのなら、公開なんてできないよなぁ、と納得。
鴨場に関しては、宮内庁のベールに包まれすぎて、地元の人たちも一体何をしている場所なのか、わからないままだ。
鴨場から数百メートルのところにJR京葉線の駅があるのだけれど、鴨場のせいで、駅の周りが発展しない、と昔から住んでる地元の人たちが言うのをよく耳にする。
考えてみれば、隣接する野鳥の楽園も加えれば、都心近くにこれほど広大な自然が存在するってことは貴重なことだと思う。
宮内庁の方たちは、詳しくはホームページで、というのではなく、地元の人たちにもう少し施設の役割をアナウンスして、周囲の理解を深める努力をしてもいいのではないかと思う。
日頃、テレビで記者会見などしている宮内庁の偉い方たちは、なんだか上からの感じがするけれど(個人的な感想です)、鴨場の職員のみなさんは、とてもフレンドリーで、私のどんなくだらない質問にも一つ一つ丁寧に答えてくださり、楽しく気持ちよく見学ができた。
いただいたパンフレットを見ると、宮内庁管轄の色んな施設で見学を受け付けている。
私にとっては謎だらけの宮内庁がほんのちょっとだけ、近づいた気がする
貴重な一日だった。
鴨場の職員のみなさん、ありがとうございました
「続・時をかける少女」を観たその足で、私達は東京ドームに向かう。
テーブルウェア・フェスティバルを見るためだ。
昨年は同時開催の石川県のフェアで、まさかの泥棒扱いをされてしまい、ちょっとトラウマだったが、今回はそちらではなく、メイン会場。
テーブルコーディネートのコンテストをやっていたり、有名人がコーディネートしたコーナーがあったり、ブランドごとの展示もある。
それを取り囲むように、焼き物や、名産品などの販売コーナーもある。
入ってすぐに黒柳徹子さんと、ビーズ作家の田川啓二さんの展示がある。
その近くの特設ステージでたまたまお二人がトークショーをやっていた。

好き嫌いは別として、着物に施されたビーズ刺繍がすばらしい。
食器は黒柳さんの物らしいが、派手な柄だけど品がある。
自分ではきっと選ばないけど、というか選べないけど、素敵だなあ、と思う。
高価な洋食器はもともとあまり興味がないので、なんとなく焼き物や、漆器、硝子のコーナーに足が向いてしまう。
ガーデニングとのコラボみたいなのもあって
食器を買う前に、ポインセチアなんて買ってしまう。
書道家の紫舟さんの展示はこれ
文字がモビールみたいになっていて、動き出しそうだ。
そのほかにも、素敵なコーディネートがいろいろ。








大きなお皿や中くらいの鉢とかどんぶりとか、見てるといろいろほしくなるけど、
現在私はキッチンを片付け中。
ここで食器を増やすわけにはいかない。
でも、小物なら・・・
お値段がお手頃な波佐見焼の箸置きにもなる小皿とドングリの箸置き
公超齋小菅(こうちょうさいこすが)の竹のピックとジャムスプーン
石川県の木のコースター。
ドングリはお花を飾った時にわきに置こう。
さすがに疲れて、会場内に設置されているカフェでちょっと休憩して、6時ごろ会場を後にする。
なんだか、盛りだくさんの一日だった。
私一人なら舞台を観たらどこにも寄らずにまっすぐ帰ってくるけれど、
彼女と一緒だと、どこでどんなイベントをやっているか、ちゃんと調べてきてくれるので、
一日が有効に使える。
しかも彼女は、焼き物や漆器にとても詳しくて、食器の文様の意味など、さまざまなことをしっかり解説してくれるので、普通にみるよりとてもおもしろい。
感謝感謝
このイベントは毎年この時期ドームで開催されている。
今日は、ちょっと遅い時間から行ったので、ちゃんと見られていないところもあったに違いない。
来年はちゃんと午前中から行ってみたい。
もちろん彼女の解説付きでお願いします。



















