

▲ 今週のみけちゃん
▼ 新しい街でもぶどう記録;第459週

■ 今週の武相境斜面



■ 今週の草木花実




■ 今週のキリ番

ブログ開設から7000日
■ 今週の果物



■ 今週の100年、あるいは、可燃物・人間

100年前のこの摂政・ひろひとさんの関東大震災視察の動画があると知る ⇒ 動画:本所深川方面を視察する摂政宮
震災教育で教えられているかわからないのだが、関東大震災での死因(おそらく最大)は焼死であり、その大量焼死は人が避難のため集まったところに火が付くことである。生身であっても人間はものすごい可燃物なのである。
上記本所深川:「今度の大災禍で酸鼻の極を尽したのは何んといっても本所の被服廠跡に避難した三万五千人の焼死である」。
関連愚記事:わざわいでのすめろぎさまのかしらのたかさのうつりゆき; 縮減される庶民の頭の置き場の空間
■ 今週の紅衛兵

東京都内の公共施設にあった迷惑電話の発信元の番号に電話をかけると、中国語で応答があった。声に幼さが残る少女は、江蘇省在住の14歳の女子中学生だという。SNSに投稿された日本に迷惑電話をかける動画を見て、友人と5人で電話をかけた。動機は「刺激が欲しかった」。少女から罪悪感は感じられなかった。(ソース)
でもさ、中国の中学生って、昔、政治的に煽られて、人を殺していたんだよ。
「副校長だった卞仲耘氏を「毛沢東思想に反対した」と決め付け撲殺」

愚記事:詫 び る 老 「老紅衛兵」、あるいは、“要武”の顛末
■ 今週借りた本
「全共闘」小説/大学紛争小説3つ

星野光徳『おれたちの熱い季節』、松原好之『京都よ、わが情念のはるかな飛翔を支えよ』、三田誠広『僕って何』の3冊。1960年代末の大学紛争についての小説。もっとも、『京都よ、わが情念の・・』は大学入学前の浪人生だが。
星野光徳『おれたちの熱い季節』、松原好之『京都よ、わが情念のはるかな飛翔を支えよ』について、初めて最近しった。知った経緯は、笠井潔が全共闘小説2冊としてこの2冊を挙げていたからだ。その挙げた背景は、村上春樹の初期三部作および『ノルウエーの森』との比較、参照としてだ。村上春樹の上記初期作品は<あの時代>を「おれたちの熱い季節」ではなく、醒めて、クールに!描いた作品だからだ。
<復員兵の子どもたち>
星野光徳『おれたちの熱い季節』。著者の星野光徳;昭和26年(1951年)札幌生まれ、昭和44年(1969年)栃木県立宇都宮高校卒、昭和48年(1973年)千葉大学人文学部国文科卒。この作品は、昭和52年/1977年度、文藝賞(河出書房新社)、選考委員は、江藤淳、小島信夫、島尾敏雄、野間宏。知らなかった、こんな小説。何より、江藤淳が選考委員だったのだ。江藤は<あの季節>の頂点&退潮の始まりの190年に、間もなく沖縄・反安保闘争の挫折を主題にした小説が数限りなく書かれるであろう。そしてそれは、いわゆる「経験」が経験の影にすぎなかったという残酷な認識に到達したものでないかぎり、すべて私小説の実質感と抑制を失った”私小説の影”のようなものになり、しかも決して私小説の限界を超えることがあるまいと思われる。と云っている。1977年に現れたこの小説は江藤にとって「間もなく沖縄・反安保闘争の挫折を主題にした小説」のひとつだったのだろう。ただし、この星野光徳『おれたちの熱い季節』への江藤淳評をまだおいらは見つけられていない。なお、この3年後の文藝賞の受賞作が、あの『なんとなく、クリスタル』である。
さて、おいらは、かつて書いた(団塊=復員兵の子供たち、あるいは、few J-children sing, what did you kill ?);
父親が復員兵であり、かつ戦争の後遺症を持っていたと書く団塊世代の人間で、親が戦争で民間の支那人を殺した、と言っているのをみたことがない。もちろん、民間の支那人を殺した復員兵は黙っているのだ。
昨今の従軍慰安婦問題もそうだろう。なぜ、父親が復員兵であり、かつ戦争中戦場で慰安婦に慰めてもらったと書く団塊世代の人間はいない。そもそも、父親が復員兵ですと書く団塊世代の人間はめったにいない。書くのが商売な人なら、父親が復員兵だったら、戦場で何をしていたか聞いて、書けばいいじゃないかと思うのだが。
あったよ。この星野光徳『おれたちの熱い季節』だ。大学紛争にかかわる登場人物・武井和夫の父親について:
親父は酔うと必ず戦争体験を誰彼となく話しかけたがった。そして軍歌だ。俺には、自分の父がまるで過去についてそれ以外の話題を持たず、戦争の時代を殆ど懐かしむようにだらだらと同じ話を繰り返すのが耐え難く苛立たしかった。
「(中略)まったく、日本が勝っていれば、中国は日本のものさ。そうすればなあ。まったく残念だったなあ。そうすれば、父さんも今頃は佐官級で、こんな町役場なんぞにはいなかったぞ。なあ、和男。お前だって今頃は見習兵くらいにとられて、大学なんぞ行って生意気なこと言っている暇はない。もっと鍛えられていたろうさ。なあ。」
「チャンコロの奴ら、岩の影なんかから急に攻撃かけてきやがる。あれは、チェッコ銃でなあ、こう、タンタンタンッという軽い音で撃ってくるんだが、まあ性能はいい機関銃だったなあ。一台ぶんどってやったら、チャンコロの奴ら、捕虜になると顔を地べたに擦りつけてなあ、あいきょーあいきょーって泣きやがる。人間の首をはねるってのはなあ、力と気合いがいるんだ。この首の骨を叩っ切るんだから。」
彼は、箸を両手で軍刀を握るように持って、切り下ろす振りをして見せる。俺はその話をもう何十回聞かされたことか。(星野光徳『おれたちの熱い季節』、第1章 4)
そして、武井和夫は父親と仲違いし仕送りを止められる。そして、活動家仲間とバイトをするのだが、そのバイトは「土方仕事」であり、一緒に働いている中年の男が戦争体験を自慢する。でも、彼は「土方仕事」をする同じ労働者仲間のはずである。
「しかし、実のところ、その殺人者どもに育てられた訳だからなあ。妙な時代に生まれた訳さ、俺たちは。・・・だが、そういう連中と連帯するなんてことができるんだろうか。革命は遠いな。」
と、武井和夫の仲間、山本執一は云う。
というわけで、星野光徳『おれたちの熱い季節』は自分が日帝侵略兵士である男の子供であることを自覚した人物が登場する小説なのだ。
おいらは、以前、こうも書いた;
ところで、これは中二病の頃からうすうす感じていたんだけど、「自分は日帝侵略兵士の子供だから、親をしばいた!」とか、あるいは逆に悩んでいたとか、はたまた、「自分は日帝侵略兵士の子供だから恥ずかして生きていけないから自殺する」とかいう話はきかないよね。おいらが知らないだけなのかもしれないが。 (「反日」思想の源流;津村喬拾い読み)
上記、武井和夫は、戦争自慢をする父親に、自分がどんなに残虐なことをしてきたか自覚しろと迫る。どうすればよかったのか?との父の問いに答える
「・・・赤旗振って牢獄に入るとか、徴兵忌避で銃殺刑になるとか・・・
「この馬鹿野郎・・・」
父の拳が飛んだ。
そして、喧嘩別れ。登場人物は、若いのに、復員兵に負けちゃうのだ。反撃しないのだ。「親をしばいた!」とかいうのは、現実味がなかったらしい。
星野光徳『おれたちの熱い季節』のあらすじ
舞台はC大学のノンセクトグループ(工・文共闘)、時代は1968-9年頃。登場人物は、武井和夫(文学部)、山本執一(文学部)、高沢志津子(文学部)、田崎進(工学部)、篠原次郎(工学部)、加藤守郎(工学部)。自衛官在学問題に端を発し、学内での団交。第1章は武井和夫の主観で物語が進む。グループの中心人物田崎進と山本執一に誘われ(オルグされ)グループに参加。活動を深める。グループメンバーで禁欲的に活動と資金稼ぎのバイトなどを行い、稼いだ金はビラづくりなどに使用。禁欲的求道的修行的学生運動生活。学内闘争から街頭闘争へと田崎進が路線を転換し、推進する。田崎は大衆は豚だと言い始める。メンバー間の意識のずれ。武井、山本は街頭闘争に躊躇。そして、この時点で高沢志津子はグループから脱落気味。結局、田崎に引きずられ街頭闘争、新宿での「10・21」闘争に参加。この裏には田崎の既成セクトへの取り込まれがあった。そして、新宿での「10・21」闘争。脱落気味だった高沢志津子が参加、逮捕される。武井も逮捕。ノンセクトグループ(工・文共闘)の瓦解。田崎進は消える。第2章は山本執一の主観で語られる。その後、学内では共闘組織(全闘委)が制し、バリケード・ストライキを行う。そのバリ・ストの中、封鎖された棟から飛び降り高沢志津子は自殺。田崎はT大全共闘にいると判明。このバリ・ストはのちに機動隊に排除される。
なお、この小説は冒頭があの<季節>の3年後であり、会社員となった武井が、会社の組合に入らない男をあの<季節>を学生として過ごしたはずなのになぜだといぶかしがる場面から始まる。Sは「嫌いなんですよ、組織は。」と断固主張する。第3章は2年後。冒頭の組合に入らない男(S)の話が再び。そして、地方で暮らす山本からの手紙を武井が受け取る。あの<季節>の「総括」を試みる。夢か幻か、必死に説明しようとする状況が書かれている。この小説は終わったあとの回顧の物語である。
▼ あの<季節>での態度・認識
武井和夫の態度・認識
大学の構内は連日、授業を放棄した学生たちで、各派のデモと集会と議論に埋められ、俺たちはいつも勃起したように昂奮し、緊張していた。政治学生たちは、現状分析と称して世界情勢を細ごまと言い争い、日本が帝国主義的に自立したか、とか、街頭ゲバルトの意味とか、闘争の過程で大学に設けるべき完全な自治組織の形態とかについてひどく観念的な口先だけの罵り合うような議論を誰彼となくふっかけ、そのような刺々しく若い観念が学内の到る所に充満し始めたように見えた。しかし、それは俺の目にはまるで、学生がすべて何らかの形で現状という忌々しい世界の破壊を意志し始めた<季節>だった。そうだ、世界は必ず変わらなければならない。そして、C大も。俺は熱に浮かされたように信じ込んだ。
山本執一の態度・認識
そうだった。あの晩、俺は初めて会った田崎の言葉に自分の思いを確かめ、大学の新しい<季節>の兆しの中で、彼こそが俺の求める連隊のオルガナイザーになるだろうと予感したのだった。彼の言葉は、その後俺たちがこの<季節>の象徴としての意味を籠めて用いるようになった<自己否定>と<徹底せる主体性>という二つの核を、俺の心に確実に共鳴させたのだった。徹底せる主体と不断の自己変革!その後の俺がどんなにか自分の心の中に烈しく叫び、刻み付けようとしたそれら。そしてどんなにか遙かで獲得し難いものであるかを幾度となく思い知らされた空しいそれらだ。俺たちは自分を覆い埋めているすべての不自由から解き放されるというなら、それと引き換えに、世界中の一切を犠牲にしてもかまわないと思っていた。俺たちは、ただ自分だけが自分の支配者でありたいと希ったのだ。
「大学に幻想を抱くなよ。ここは真理を追究する所ではない。むしろその逆だ。ここでは真理というものがどれほど限られ隠されなければならないかを実践しているに過ぎないんだ。
いいか。真理がどのように利用されるかということは、真理そのものの価値とは別のものさ。支配する者とされる者がいる限り、支配者には支配者の真理があり、支配される者にはされる者の真理がある。真理、平等、自由といえども、普遍的な形で存在する訳ではないんだ。
大学の自治といい、学問の自由といい、ふざけきった幻想だよ。(中略)
俺たちはそのようなごまかしの構造をこそ、いま打ち破らなけりゃならない。」
山本執一と高沢志津子は同じ高校の出身で、ふたりとも貧しい家庭だった。特に、高沢志津子は私生児で生活保護を受けていた。一方、ふたりとも成績が優秀だった。まわりの経済的に恵まれて、かつ成績が悪い学生は僻んで貧乏なら働けという。そういう状況で山本執一は云う;
(略)ちくしょう、俺たちはお前らなんぞに負けない。俺も必ず大学へ行ってやるぞとひとり呟くことで、辛うじてその口惜しさに耐えたのだった。
そうだ。その頃の俺は、訳も解らず、ただ進学を果たすことが、級友たちに伍して自分を貧しさの卑屈から救い出せる唯一の手段であるかのように哀れにも思い込み、更にその一つの手段を目的であるかのように目指すことによって、あの貧しい受験勉強の日々をしのいだのだ。
大学に入り紛争にのめりこんで疲れた高沢志津子は云う: 「わたしたちは何しに大学に来たの?」
▼ 星野光徳と村上春樹
村上春樹は<あの時代>とその後についてあちこちで手短に、言葉を与えて示している;
僕が学生だったのは、1968年から1969年 という、カウンター・カルチャーと理想主義の時代でした。 既成秩序に対する革命や蜂起を、人々が夢見ていたんです。 そうした日々は過ぎ去り、 僕は大学の卒業証書を手にしました。けれども、 僕はどんなオフィスにも、 どんな会社にも所属したくなかった。ただ自分自身でありたかった。ひとり独立してね。 派閥や集団を基本にする 日本のような国においては、簡単なことではありませんでしたが、それを実行することができました。僕は、 クラブや流派には一切 属していません。 (村上春樹、『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』)
そして、村上春樹の初期三部作および『ノルウエーの森』は<あの時代>とその後についてののちの時代からの回顧だ。この<あの時代>とその後を語るという点で、星野光徳『おれたちの熱い季節』は村上初期作品群と対蹠的であり、ネガとポジといえる。つまり、星野光徳『おれたちの熱い季節』はあの時代を直接的に語り、村上春樹の初期三部作は過去の夢・幻かのごとく語る。ただし、思わせぶりな表現が村上作品には、確実に打ち込んである(鼠が大学を去ったのには幾つかの理由があった。その幾つかの理由が複雑に絡み合ったままある温度に達した時、音をたててヒューズが飛んだ。そしてあるものは残り、あるものははじき飛ばされ、あるものは死んだ。 村上春樹、『1973年のピンボール』)。
星野光徳と村上春樹の<あの時代>とその後を語る作品の大きな相違のひとつが、登場人物の家族関係、特に親との関係を描くか、描かないかである。村上初期作品に与えられた評の典型が、川本三郎による「都市の感受性」を表出する作家=村上春樹、らしい(柴田勝二、村上春樹研究への眼差し、『世界文学としての村上春樹』)。
::「都市とは、おびただしい商品と情報のなかで虚と実が反転していき、人間の情念や感情も生々しさを脱色されて軽さを帯びてしまう空間である。村上作品の主人公たちは「告白や熱い自己主張よりは引用やレトリックを楽しむ」人物たちであり、そうした姿勢によって「気分のよさ」を重んじて生きる「小さな個人」であることを肯定しようとしている。::
星野光徳『おれたちの熱い季節』には、もちろん、「気分のよさ」を重んじて生きる「小さな個人」なぞ出てこない。組織に入る、入らないに始まり、組織の方針を変える、変えない、そして、変わった組織に従う、従わないとう話だ。
さて、興味深いのは、星野光徳『おれたちの熱い季節』では、父親が復員兵である学生運動家が描かれている。彼の父親は復員兵であるばかりか支那兵を斬首したことを自慢する。一方、村上春樹の初期三部作および『ノルウエーの森』が出版されて(商業的に大成功する)しばらくたって、村上春樹の父親は復員兵でどうやら支那兵を斬首にかかわったらしいとわかってきた。わかった経緯はイアン・ブレマーのインタビューだ(愚記事より)。
村上春樹の人生で、最重要なのは、彼が小学生の頃父が息子に自分のチャイナ出征時代にチャイナ兵(以下、支那兵)の処刑に「立ち会い」、支那兵が殺され、死んでいく様子を聞かされた。それが、村上春樹の心障(トラウマ)になっていると告白している(『猫を棄てる』)。この心障(トラウマ)が原因で村上春樹は中華料理を食べられないと伝えられている。さらには、デビュー作以来、チャイナへの、独特の、こだわりが表現に組み込まれている。村上春樹は父親と確執があり、父親の死に際まで没交渉であった。その原因は必ずしも上記の心障(トラウマ)であるとは明言されておらず、別の原因(父が村上春樹に「エリート」街道を進むことを望み、息子が拒否した)が述べられている。しかし、この支那兵の死はのちまで村上春樹の心を占めていたことは、イアン・ブルマーにより伝えられている。そもそも、村上春樹は自分の父親について絶対人にしゃべらなかった(妻の証言)。理由は、上記のように、自分の父親が日帝侵略兵士であり、虐殺に携わっていたからだ。そして、息子は父のチャイナでの所業について詳しくは知らないらしい。知ろうとしなかったのだ。
父親に中国のことをもっと聞かないのか、と私は尋ねた。「聞きたくなかった」と彼は言った。「父にとっても 心の傷であるに違いない。 だから僕にとっても 心の傷なのだ。 父とはうまくいっていない。子供を作らないのはそのせいかもしれない。」
私は黙っていた。彼はなおも続けた。「僕の血の中には彼の経験が入り込んでいると思う。そういう遺伝があり得ると僕は信じている」。村上は父親のことを語るつもりはなかったのだろう。 口にしまってしまって心配になったらしい。 翌日電話をかけてきて、あのことは書きたてないでくれと言った。 私は、あなたにとって大事なことだろう、と言った。彼は、その通りだが、微妙な問題だから、と答えた。
(イアン・ブルマの『日本探訪 村上春樹からヒロシマまで』における春樹への直接インタビューを元にした文章(1996年))
現在となっては、上記のように、村上春樹は『猫を棄てる』で書かれている。つまり、村上春樹の初期三部作および『ノルウエーの森』を書いていた頃は、少年のとき受けた心障(トラウマ)=村上春樹の父親は復員兵でどうやら支那兵の斬首に立ち会った、を持っていたのだ。すなわち、星野光徳『おれたちの熱い季節』では、時代背景として、学生運動家たちは世代的に復員兵の子どもたちであり、復員兵に育てられたこと、さらにそれを認識し解釈すること(上述)が作品に記されているのに対し、村上春樹の初期三部作および『ノルウエーの森』ではそうではないのだ。さらには、星野光徳の父親が現実に復員兵であり、実際に支那兵捕虜を斬首したかは不明である。しかし、村上春樹は父親が支那兵捕虜の斬首に立ち会ったと語ったという事実をノンフィクション作品で報告している。
▼ 村上春樹を読む星野光徳
さて、現在、星野光徳は村上春樹作品を体系的に読んでいるらしい。
■ 松原好之『京都よ、わが情念のはるかな飛翔を支えよ』
1997年、第3回すばる文学賞受賞。松原好之:1952年生まれ、岐阜県出身。金山町立下原小学校、金山町立濃斐中学校、岐阜県立岐阜北高等学校を経て、1978年大阪外国語大学外国語学部英語学科を卒業(wikipedia)。ネットには「1978年3月26日、三里塚空港、管制塔占拠で逮捕された著者が獄中で半分ほど執筆」した作品なのだという(ソース)。
どういう話か:大学紛争の話ではない。大学紛争当事者予備軍の自意識過剰の東大・京大を目指す若者の話。自意識過剰と過剰行動が「痛い」。主人公・空知 [そらち]。静岡で高校時代を過ごし京大を受験するも落第。京都の予備校に通う。下宿で同じ高校出身で活動家だったと吹石と同じとなる。吹石はさらに自意識過剰でカリスマ性を装う。吹石は上から目線で空知と組んでやるという態度で「連隊」する。下宿で「闘争」を行う。大家との闘争。下宿にいた祐天寺は大阪の伝説の高校生活動家。吹石は祐天寺を崇拝。下宿の闘争でのいざこざで吹石と祐天寺は下宿を出る。のち祐天寺は自殺。吹石と祐天寺は同性愛関係。空知は露店商からナイフを買い、痴漢まがいのことをする。改心する。そして、ある女子大生と関係を深める。最後、受験当日、吹石と祐天寺と空知にはみえる活動家の煽動にのり、受験場から去る。
■ 三田誠広『僕って何』
1977年、芥川賞受賞作。三田誠広:1948年生まれ。1968年早大文学部入学というので、村上春樹と一緒である。
おいらは、この本を約40年ぶりに読んだ。そして、当時、三田誠広は嘘をついていたらしい。これは数年前に気づいた。すなわち、あの<季節>の嚆矢とされる「10・8」[じゅっぱち](羽田事件)で死んだ山崎博昭は三田の高校時代の同級生であり、wikipedia には、大阪府立大手前高等学校で岩脇正人、佐々木幹郎、山崎博昭らの学生運動に参加するとある。
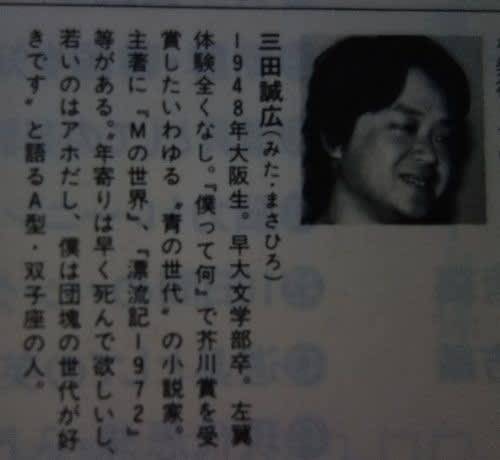
しかしながら、1985年の『保守反動に学ぶ本』(1985年刊)[関連愚記事]では、自分の経歴で、左翼体験全くなしと報告している。
三田誠広『僕って何』 あらすじ:経済的に恵まれた地方出身の学生が母親がかりでアパート借りて一人暮らしを始める。主人公はこの世に対するルサンチマンも情念も思想信条も特になさそうである。誘われて政治セクトB派に入る。そこで組織の中間管理的リーダー、レイコと知り合う。のち、同棲。B派が暴力沙汰を起こしたことをきっかけに、「全共闘」的ノンセクト運動が盛り上がる。海老原登場。本当はE派の工作員なのだが、主人公「僕」をB派から離脱させ、「全共闘」的ノンセクトに引き入れる。しかし、主人公「僕」は海老原の本性を知り、B派に入ったり、辞めたり、うろうろしている自分に「僕って何」?と問う、おXXなお話。
あの<季節>は何であったかという問いに対し、「自分探しであった」という回答が小熊英二からなされ(『1968 若者たちの叛乱とその背景』)、スガ秀実が怒っているらしい。そういう観点からみて、三田誠広『僕って何』とは、自分探し系といえるのではないだろうか?
それにしても、三田誠広は山崎博昭の友人であり、『僕って何』を書いた時点(1977年)で、川口大三郎事件(wiki)が歴史となっていて、『僕って何』の物語というのは、川口大三郎事件への過程であったはずだと、『僕って何』を書いた時点(1977年)でわかっていたことを考慮すると、こんなのんきな作品でよかったのか?と今、おいらには思える。
■










