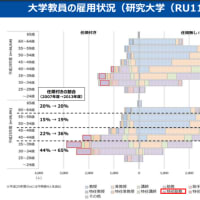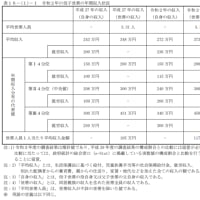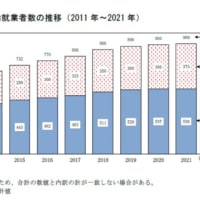先日、Youtubeに登録している美術評論家の山田五郎さんの「オトナの教養講座」を見ていた時、面白いテーマが取り上げられていた。
それが、西洋絵画における男性と女性のファッションの変遷だった。
Youtube: 【絵画で解き明かすファッションの謎】
取り上げられていたのは、「革命旗を持つサンキュロット」。
おそらく、高校の世界史の教科書にも掲載されていた絵画だ。
実際の動画でも、山田さんは高校の世界史の教科書を手に、説明をされている。
懐かしさと共に「あ~、フランス革命後については、あまりやらなかった気がするな~」と思いながらも、高校生の頃に読んだ岩波新書の「パリ・コミューン」(当時は、岩波新書で読んだ記憶があるのだが、現在は上下巻の装丁本になっているようだ)を思い出した。
「思い出した」と言っても、随分前に読んだ本の記憶なので、朧気で「結局のところ、フランス革命は革命を起こした人達の中で、仲間割れをし、権力闘争を起こし、時には粛清をする事態にまで発展した」ことと、その「仲間割れ。権力闘争。粛清」が、後にナポレオンの独裁的政治を産む切っ掛けとなった、という程度のザックリとした覚えがなく、教科書に掲載されている絵画については、記憶が無い。
絵画に描かれた男性の長ズボンが、いわゆる「労働者階級」のファッションであり、当時の貴族はブルマと呼ばれる短いパンツにストッキング、あるいはスカートのようなボトムにストッキングをはいていたようだ。
それが、フランス革命による貴族社会の崩壊により、男性が長ズボンを履くことが当たり前になった、という点に山田さんは注目と解説をされていた。
そこで思い出したのが、18世紀後半英国で起きた「産業革命」だ。
この「産業革命」以降、欧州では「貴族社会」が完全に崩れ、資産家が登場するようになる。
領地を基に財を築くのではなく、自ら産業と関わり財を成す、という社会的変化が現れたのだ。
結果として、「動きやすい服装」が求められ、財を成す中心となっていた男性社会では「長ズボン+単色系」のファッションが中心となっていった、という考察もある。
それに対して、当時の資産家にとってのステータスの一つであった「美しく若い女性を着飾らせ、公の場に出向く」為に、女性のファッションは、きらびやかでアクセサリーも派手なモノへと変化していく。
もちろん、産業革命を支えていたのは資産家ではなく、炭鉱や紡績工場で働く人達であり、中には女性も多く含まれていたはずだ。
残念な事に、このような女性たちの姿を描いた絵画などは、ほとんどなく歴史の記録の中の絵画としては、きらびやかに着飾った娼婦(オペラ「椿姫」のような存在の女性たち)が描かれることになる。
それは画家に絵画を依頼する資産家たちとの関係から、おのずとその理由は分かるはずだ。
それに対して、日本では衣装による男女差はほとんどない。
着物そのものもしたて方は同じで、違いがあるとすれば、その素材や動くために袖や裾のたくし上げ方くらいだろう。
日本で、ファッションにおける男女差が明確になるのは、明治政府による「洋装化」だからだ。
そのような視点で、1枚の絵画を観て時代背景を探り、社会の変化やファッションにより精神的に抑圧された人達、という姿を知ることの面白さのようなモノを感じつづ、数年前に話題になった「アート思考」とは、そのようなことなのでは?という気がしたのだ。
せっかくのGW後半戦、このような時間を過ごすのも悪くない気がした。