
「筆日記」の「筆」とは、夏目金之助・鏡子夫妻のあいだに生まれた第一子「筆子」さんのこと。結婚3年目にできた子どもということもあり、金之助(漱石)もずいぶんかわいがった。
〔長女が生まれましたのは、五月の末のことでありました。私が字がへただから、せめてこの子は少し字をじょうずにしてやりたいというので、夏目の意見に従いまして「筆」と命名いたしました。ところが皮肉なことに私以上の悪筆になってしまったはお笑い草です。で、いまではそんな欲張った名はつけるものではい、そんな名をつけるからこんなに字がへたになったのだなどと、当人の筆子はこの話が出るたびにかえって私たちを恨んでいるのです。親の心子知らずか、子の心親知らずか、ともかくお笑い草には違いありません。〕
(夏目鏡子述・松岡譲筆録 『漱石の思い出』)
鏡子と筆子を日本に残し、漱石はロンドンへ。鏡子さんは妊娠していて、やがて次女恒子が生まれた。
鏡子さんはもともと筆不精で、それに子育てに忙しく、あまり手紙を書かなかった。すると漱石から「なぜ手紙を書かないか」と文句を言ってきた。「どうしたのか、いくら忙しいといったって、たまさか手紙の一本くらい書く時間のないはずはない。」と漱石。それで鏡子さんは「そんなことをいったって、これでもあれやこれやでなかなか手紙が書けない、そういう貴方だってあんまりこのごろは書いてくださらないじゃありませんか」と返した。そしたら漱石、「おれは勉強に来て忙しいのだから、そうそう手紙も書けないと、ちゃんと最初から断ってあるじゃないか。おまえのは断りなしに手紙をよこさない。断って書かないのと、断らずに書かないのとではたいへんな違いだ。それに“あれやこれや”とはいったい何のことだ。」
それで鏡子さんは考えた。毎晩床につく前に、長女の筆子のその日の行動を書き記して、それを『筆日記』とした。他人が見てもたいしておもしろくもない記録だけれど、それを送ると漱石はたいへんよろこんだという。
そんなある日、「夏目発狂す」という電報がロンドンから日本の文部省に打たれたという。ある人が漱石に会いに行った時、部屋に閉じこもりっきりで、真っ暗な中で泣いているというのだ。
それで文部省の役人が妻鏡子さんのところに心配して(探りに)やって来た。鏡子さんはこのような手紙のやりとりをしている、と話したが、すると役人は「手紙が自分で書けるくらいなら大丈夫ですな」と言いつつ、根堀り葉掘り質問する。「発狂した」などという話をまだ聞かされていない鏡子さんは、なんのことだかわからなかったという。
「発狂した」という表現は強烈だが、まちがいでもなかった。漱石の神経症の症状は、かなり激しいものだったようで、日本に帰ってからも、発作が起こると、家族も手がつけられないほどだった。女中や家族が悪だくみをしている…などという妄想が激しく、これは神経発作というより、精神病にちかいのではないだろうか。家族の行動のいちいちが自分へのいじわるに思えてくる。近所に部屋を借りている学生を「あいつは探偵で俺のことを見張っている」などと本気で言い出したり、ボールをうっかり夏目家に投げ込んできた中学生が逃げるのを追いかけたり…という具合である。
長女の筆子さんはその思い出が強く残っていて、漱石のことを、「お父様ったら、それはもう怖かったのよ」と自分の子ども達に話していたという。
今は半藤一利(小説家)の妻である半藤未利子さんは、筆子さんの娘だが、エッセイ集『夏目家の糠みそ』の中にこう書いている。
〔筆子自身もよく殴られたが、おおかた髪でも掴まれて引き擦り廻されたのか、髪をふり乱して目を真赤に泣き腫らして書斎から走り出てくる鏡子を、筆子はよく見かけたものだった。〕
未利子さん自身は、漱石が死んだ後に生まれた孫なので、生前の漱石の思い出はもっていない。
鏡子さんにすれば、それは「あたまがわるい」ときだけで、普段の夏目金之助は優しい穏やかな人なのだ。筆子さんもそれはわかっているのだが、漱石の思い出はと聞かれると「怖い父」が強く記憶に刻まれていて、それが真っ先に出てくるのだろう。
ところで、周知の通り、夏目漱石には多くの弟子がいた。その中に、久米正雄、松岡譲がいた。久米正雄は、(漱石の死後だと思われるが)漱石の長女筆子さんと結婚したい、と母親である鏡子さんに申し出た。鏡子は、筆子本人が了解するならいいでしょうと言った。ところが筆子の選んだのは、久米ではなく、松岡譲だった。松岡も驚いた。彼も、筆子さんは久米と結婚するのだろうと思っていたからだ。しかし、筆子の気持ちが自分にあるのならと、松岡譲もその愛に応え、結婚した。そして生まれた娘(四女)が未利子さんというわけ。
勝手に結婚するつもりでいた久米正雄は、このことを恨んだ。後に、小説の中でリベンジする。『破船』という作品の中で、松岡という男を、姦計をめぐらせて筆子を奪ったずるい奴というように描いたのだ。世間ではそれを信じたようであるが、松岡譲は沈黙をまもった。
まあ、人間、いろいろあるってことですナァ。
「とかくこの世は住みにくい…」 (by 『草枕』 夏目漱石)
ロンドンから帰って東大講師となった漱石だが、この頃が最も「発狂」ぐあいが激しかったようだ。
〔 けれども学校は、ねっからおもしろくないらしく、…
これまでの行きがかりもあり、ほかに生活費を得る道もないので、目をつぶって学校に出ていたようです。
…外国からもってきたあたまの病気が少しもなおらないので、なおさらすべてのことがおもしろくない様子でした。 〕 (夏目鏡子)
帰国して、「いやだいやだ」といいながらも、講師の仕事を続け、その年(1903年)の暮れに、漱石は自分で絵の具を買ってきて水彩画を描くようになった。だれがみてもそれは「すこぶるへた」(by鏡子)だったが、やがて「あたまのぐあい」が穏やかになってゆく。
そして1904年、夏のはじめのことだった。
本郷千駄木の夏目家に、一匹の子猫がどこからともなくやってくる…。
〔長女が生まれましたのは、五月の末のことでありました。私が字がへただから、せめてこの子は少し字をじょうずにしてやりたいというので、夏目の意見に従いまして「筆」と命名いたしました。ところが皮肉なことに私以上の悪筆になってしまったはお笑い草です。で、いまではそんな欲張った名はつけるものではい、そんな名をつけるからこんなに字がへたになったのだなどと、当人の筆子はこの話が出るたびにかえって私たちを恨んでいるのです。親の心子知らずか、子の心親知らずか、ともかくお笑い草には違いありません。〕
(夏目鏡子述・松岡譲筆録 『漱石の思い出』)
鏡子と筆子を日本に残し、漱石はロンドンへ。鏡子さんは妊娠していて、やがて次女恒子が生まれた。
鏡子さんはもともと筆不精で、それに子育てに忙しく、あまり手紙を書かなかった。すると漱石から「なぜ手紙を書かないか」と文句を言ってきた。「どうしたのか、いくら忙しいといったって、たまさか手紙の一本くらい書く時間のないはずはない。」と漱石。それで鏡子さんは「そんなことをいったって、これでもあれやこれやでなかなか手紙が書けない、そういう貴方だってあんまりこのごろは書いてくださらないじゃありませんか」と返した。そしたら漱石、「おれは勉強に来て忙しいのだから、そうそう手紙も書けないと、ちゃんと最初から断ってあるじゃないか。おまえのは断りなしに手紙をよこさない。断って書かないのと、断らずに書かないのとではたいへんな違いだ。それに“あれやこれや”とはいったい何のことだ。」
それで鏡子さんは考えた。毎晩床につく前に、長女の筆子のその日の行動を書き記して、それを『筆日記』とした。他人が見てもたいしておもしろくもない記録だけれど、それを送ると漱石はたいへんよろこんだという。
そんなある日、「夏目発狂す」という電報がロンドンから日本の文部省に打たれたという。ある人が漱石に会いに行った時、部屋に閉じこもりっきりで、真っ暗な中で泣いているというのだ。
それで文部省の役人が妻鏡子さんのところに心配して(探りに)やって来た。鏡子さんはこのような手紙のやりとりをしている、と話したが、すると役人は「手紙が自分で書けるくらいなら大丈夫ですな」と言いつつ、根堀り葉掘り質問する。「発狂した」などという話をまだ聞かされていない鏡子さんは、なんのことだかわからなかったという。
「発狂した」という表現は強烈だが、まちがいでもなかった。漱石の神経症の症状は、かなり激しいものだったようで、日本に帰ってからも、発作が起こると、家族も手がつけられないほどだった。女中や家族が悪だくみをしている…などという妄想が激しく、これは神経発作というより、精神病にちかいのではないだろうか。家族の行動のいちいちが自分へのいじわるに思えてくる。近所に部屋を借りている学生を「あいつは探偵で俺のことを見張っている」などと本気で言い出したり、ボールをうっかり夏目家に投げ込んできた中学生が逃げるのを追いかけたり…という具合である。
長女の筆子さんはその思い出が強く残っていて、漱石のことを、「お父様ったら、それはもう怖かったのよ」と自分の子ども達に話していたという。
今は半藤一利(小説家)の妻である半藤未利子さんは、筆子さんの娘だが、エッセイ集『夏目家の糠みそ』の中にこう書いている。
〔筆子自身もよく殴られたが、おおかた髪でも掴まれて引き擦り廻されたのか、髪をふり乱して目を真赤に泣き腫らして書斎から走り出てくる鏡子を、筆子はよく見かけたものだった。〕
未利子さん自身は、漱石が死んだ後に生まれた孫なので、生前の漱石の思い出はもっていない。
鏡子さんにすれば、それは「あたまがわるい」ときだけで、普段の夏目金之助は優しい穏やかな人なのだ。筆子さんもそれはわかっているのだが、漱石の思い出はと聞かれると「怖い父」が強く記憶に刻まれていて、それが真っ先に出てくるのだろう。
ところで、周知の通り、夏目漱石には多くの弟子がいた。その中に、久米正雄、松岡譲がいた。久米正雄は、(漱石の死後だと思われるが)漱石の長女筆子さんと結婚したい、と母親である鏡子さんに申し出た。鏡子は、筆子本人が了解するならいいでしょうと言った。ところが筆子の選んだのは、久米ではなく、松岡譲だった。松岡も驚いた。彼も、筆子さんは久米と結婚するのだろうと思っていたからだ。しかし、筆子の気持ちが自分にあるのならと、松岡譲もその愛に応え、結婚した。そして生まれた娘(四女)が未利子さんというわけ。
勝手に結婚するつもりでいた久米正雄は、このことを恨んだ。後に、小説の中でリベンジする。『破船』という作品の中で、松岡という男を、姦計をめぐらせて筆子を奪ったずるい奴というように描いたのだ。世間ではそれを信じたようであるが、松岡譲は沈黙をまもった。
まあ、人間、いろいろあるってことですナァ。
「とかくこの世は住みにくい…」 (by 『草枕』 夏目漱石)
ロンドンから帰って東大講師となった漱石だが、この頃が最も「発狂」ぐあいが激しかったようだ。
〔 けれども学校は、ねっからおもしろくないらしく、…
これまでの行きがかりもあり、ほかに生活費を得る道もないので、目をつぶって学校に出ていたようです。
…外国からもってきたあたまの病気が少しもなおらないので、なおさらすべてのことがおもしろくない様子でした。 〕 (夏目鏡子)
帰国して、「いやだいやだ」といいながらも、講師の仕事を続け、その年(1903年)の暮れに、漱石は自分で絵の具を買ってきて水彩画を描くようになった。だれがみてもそれは「すこぶるへた」(by鏡子)だったが、やがて「あたまのぐあい」が穏やかになってゆく。
そして1904年、夏のはじめのことだった。
本郷千駄木の夏目家に、一匹の子猫がどこからともなくやってくる…。










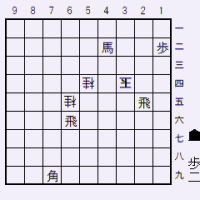
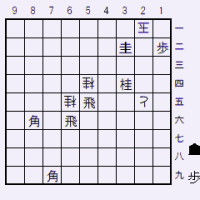
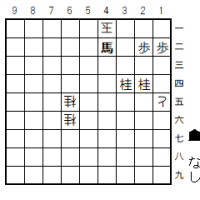
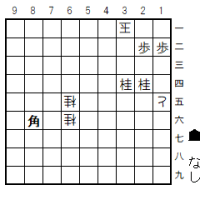
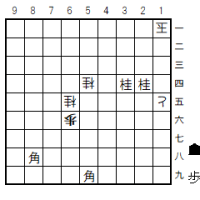
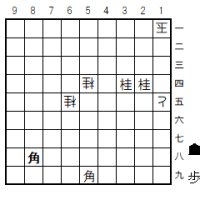
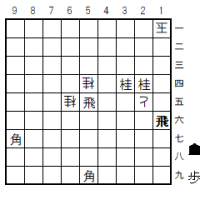
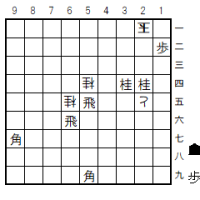
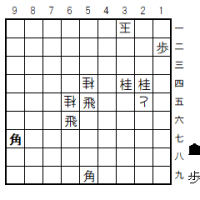
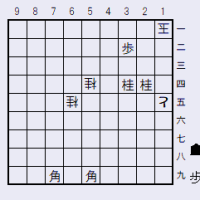






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます