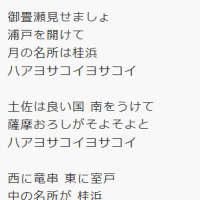2012年1月13日(金) 福神漬とナタマメ 福神漬は、カレーライスの添え物として、根強い人気がある。カレーの辛さと対になって、甘味のある福神漬が好まれるのであろうか。福神漬の色は、以前は、紅色が多かったのだが、この所は、自然志向だろうか、茶色っぽいものに変わってきているという。特に、カレー用はそうで、時々食べに行くカレー屋のテーブル上の壺には、茶色の福神漬が、一杯入っている。 福神漬の中のナタマメ(鉈豆)だが、形が面白いので、自分としては、以前から、気になっていたものだ。先日、カレーライスを作ったので、スーパーで、多少高価だが、袋入りのカレー用の福神漬を買ってみた。袋の裏の表示では、材料として ダイコン、キュウリ、ナス、レンコン、ショウガ、ナタマメ、シソ、ゴマ とある。 が、いざ袋を開けて中を見ると、あの面白い形のナタマメが、なかなか見つからず、辛うじて、2~3個、しかも、形が崩れかかった物に、お目にかかっただけだった。すっかり貴重品になっているようだ。 あのような形のマメとは、一体、どんなマメなのだろうか。どのように加工すると、あのような、不思議な形になるのだろうか。 ネット情報を頼りに、色々、調べて見た。なお以下に引用させてもらっている画像類は、全て、ネットからの借用である。 この豆、立派なマメ科の野菜で、成熟すると、いんげん豆(ささぎ とも)の様な立派な豆になるのだが、若い莢(さや)の時期に、実を採取し、横方向に刻んで、漬け物に入れるようだ。いって見れば、えんどう豆(グリーンピース)を、若いうちに採ると、キヌサヤとして食べるようなものだろうか。 ナタマメの実の莢には、特徴があり、縦方向に、山脈のように盛り上がった構造になっていて、刀剣類の「鎬」(しのぎ)のようになっている、と言う。 この若い莢を、横方向に切った横断面が、福神漬のあの形になる。盛り上がった鎬の部分は、中央からは可成りずれているが、一方、左右はほぼ対称形だ。


ナタマメの若い実(中央が盛り上っている) 若い実の横断面
ナタマメという名称の由来は定かではないが、ナタ(鉈)に似ている、ということだろうが、横断面から来たのか、それとも莢を横から見た形から来たのだろうか。
刃物のナタは、以前は、田舎家や山家では、良く使われた道具の一つだが、最近は余り見かけない。都会暮らしの我が家にも、一丁あるものの、殆ど出番が無く、未だに、ピカピカである。ナタの横断面は、細長~い三角系で、ナタマメのそれとは余り似ていない。
ナタマメのこの形からは、自分の第一感として、古代に、武器や神事に使われたと言う、銅剣を連想してきた。縦方向に中央が盛り上がり、左右対称の形が少し似ているのだ。
 銅剣
銅剣
又、ナタマメは、英名では、horse beans(馬の豆)と言うようだ。馬の顔を正面から見ると、ナタマメの横断面にかなり似ており(下の写真 中央のもの)、うまいネーミングだ。
福神漬では、今や貴重品になっているようなナタマメだが、両者には、どのような関連があるのだろうか。
福神漬と言う名の由来は、一説では、七福神の一人の福禄寿に因むようだ。 細長く巨大な禿頭の福禄寿の、白いあごひげのある顔を正面から見ると、ナタマメの横断面に何処となく似ているようにも見えるのだ。


福禄寿 福神漬のナタマメ(中央が馬に 左右が福禄寿に似ている)
このようなことから、明治初期、上野の某漬け物屋が、七福神にあやかって、七種類の野菜を漬け合わせた漬け物を世に出した所、七福神信仰も篤かった当時の風潮と相俟って、大きな人気を呼んだようだ。
この福神漬の中身は、現代も、名前の由来からして、ナタマメは必須だが、他には、ダイコン、ナス、キュウリはどれにも入るようだ。他の材料については、冒頭に示した材料の他、シロウリ、ニンジン、シイタケ、コンブなどが入ったものもあり、バリエーションがある。福禄寿以外の6人の福神達が、どの野菜とどう対応しているか、或いはしていないかは、良く分からない。
でも、最近は、国内のナタマメの栽培量が少なく、輸入が主のようで、安価な福神漬には、なんと、肝心のナタマメが入っていない物もある、と言うのはどうだろうか。
余談だが、長年やっている尺八の、つい先日の新年吹き初めで、 仲間で、山田流の箏曲 「七福神」を、演奏したところである。
ナタマメは、莢が若いうちは、漬け物だけでなく、モロッコインゲンのように、通常の野菜として、お浸しや、和え物、煮物などにも使えるようだ。でも、種類によっては、毒性をもつものもり、注意が必要のようだが、一方で、このことが、この豆が、健康食品や、薬用としても利用されている、理由なのかも知れない。
季節が暖かくなったら、種を手に入れて、自分でも栽培してみたいものだ。そして、どのような自家製の福神漬ができるのか、試して見るのも面白そうである。