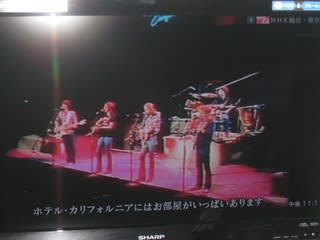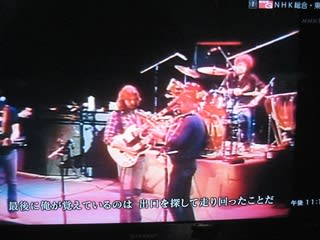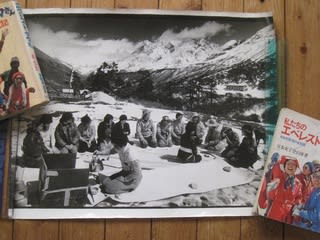*この1987年4月発行の“冒険遊び場がやってきた(羽根木プレーパークの記録);羽根木プレーパークの会編”をどういう意思・目的から買ったのか、よく覚えていません。その頃、発行所“晶文社”の本をよく読んでいたからでもないでしょう。
*この1987年4月発行の“冒険遊び場がやってきた(羽根木プレーパークの記録);羽根木プレーパークの会編”をどういう意思・目的から買ったのか、よく覚えていません。その頃、発行所“晶文社”の本をよく読んでいたからでもないでしょう。
1987年は、23年前です。ウチの子どもらが、5、7、10歳の頃です。
住んでいる地域(旧庄和町・現春日部市)で、お母さんがこどもたちと一緒に遊ぶ、“くれよん・ようちえん”とか、“人形げき・くれよん”あるいは、春日部おやこ劇場といった集まりが、私の家族の周辺で始まっていた頃でしょう。
これらは、 26,7年後の今も、脈々と続いています。
今と違って、行政が“子育て支援”なんて、全く思わなかった時代のことです。
それでも、この地に、家を買って、地縁も何もない中で、新興住民が少しづつ“地域で子育て”の動きを作っていったのです。
ついでに23年前は、今もワタシが所属している町のジャズ・バンド(スウィング・ベアーズ)が始まった年でもあります。
ワタシにも、100%埼玉都民を続けながらも、眠るだけの地域でしたが、暮らしている地域を意識する瞬間が少しはあったのでしょう。
私らの住む埼玉県の郡部ですら、こうであったのですから、東京都、しかも世田谷区の同世代の人たちはもっと、先鋭的、進歩的であったでしょう。
彼らの活動、お手本のひとつが、子どもたちのために、市民が“遊び場(プレーパーク)”作るという活動でした、そのための、人の集まりから、完成に至る記録が、この本です。
この本を読んで、どうかしたか、というほどのこともありません。むしろ10年ぐらい前、家人の“私の蔵書1/3処分指令”に屈した時、処分したと思っていたのですが、本箱の隅に“存命”だったのです。
それでも、“プレーパーク”という響きは、よく覚えていたのです。
ここ1,2年、孫守りのために、越谷に住む娘のアパートにでかけることがあります。 娘のウチの冷蔵庫に、地域のこどもたちの集まりのお知らせなどが貼ってあって、そこにある越谷の“越谷プレーパーク”の文字、場所でなくその活動が、気になっていたのです。
先週末(1月19日)、土曜夕方、越谷の市民活動に詳しい知人Nさんを含んで小さな集まりがあって、話題提供に“この本”を持っていったのです。
Nさんは、すぐに“羽根木プレーパークには、(話に)行っていますよ”と。
再び読み返しているわけではありません。
ただ、家人らの活動を遠目にみていた時代から30年たって、私自身が100%地域だけで暮らす時代に代わっています。
 *この4階に、市民活動センターができます。
*この4階に、市民活動センターができます。
そうして今、春日部市役所が作ろうとしている、春日部市市民活動センターを応援するようになっていて、市民活動センターは、おとなの、若いおとなたちのため“羽根木の冒険遊び場がやってきた”と同じ、“冒険遊び場をつくろう”としている状況と同じだなと思いついたのです。
 *本書10ページ。
*本書10ページ。
羽根木プレーパークには、大きな看板がたっているようです。こう書いてあります。
“・・・子どもが公園で自由に遊ぶためには「事故は自分の責任」という考えが根本です。そうしないと禁止事項ばかりが多くなり楽しい遊び場ができません”
・・・・その通りだと、思います。禁止事項ばかりでは楽しい遊び場になりません。
【おまけ】
 *市民活動センターのことは、1月23日(土)の市民活動フォーラムで話されます。
*市民活動センターのことは、1月23日(土)の市民活動フォーラムで話されます。
 *市役所南側の市立病院移転用地、今は公園として使われています。完成は2015年という。
*市役所南側の市立病院移転用地、今は公園として使われています。完成は2015年という。