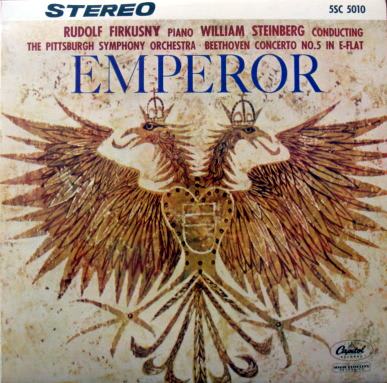これもまた懐かしいLPである。 現在、ベルギー、ブリュッセルを拠点に国際的に活躍中の堀込ゆず子が1980年の「エリーザベト王妃国際音楽コンクール」ヴァイオリン部門で優勝を果たした時のライヴ盤で彼女のデビュー盤でもあった。(写真/DG国内盤、20MG0116/1981年リリース)
シベリウスの「ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47」と第2面の余白にはこの年のコンクール、新曲課題曲となったベルギーの作曲家フレデリック・ヴァン・ロッスムの「ヴァイオリン協奏曲」が収められている。いずれも1980年5月30日ブリュッセルの「パレ・デ・ボーザール」における本選の録音である。この演奏を聴くと彼女のテクニックもさることながらのびのびとした気分で作品に取り組んでいる様子が伝わってくる。管弦楽はベルギー国立管弦楽団、指揮はジョルジュ・オクトール。