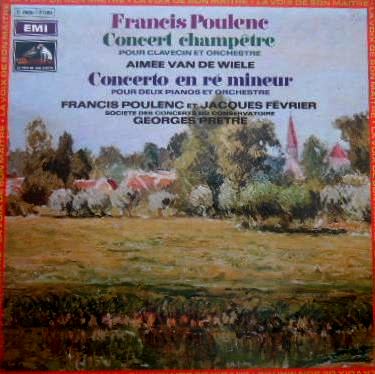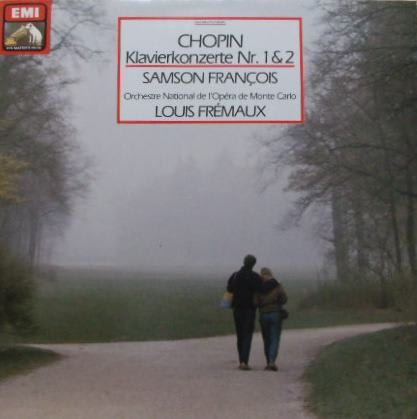今日は「山田一雄の芸術」と題する2枚組みCD(写真/日本光ディスク/JOD116-17)から伊福部 昭の「ラウダコンチェルタータ」にスポットをあててみたい。このCDは戦後の日本の指揮者界を担った山田一雄(1912~1991)の「新星日本交響楽団(現在、東京フィルと合併)」との最晩年(1990年~1991年)のコンサート・ライヴ盤である。
伊福部 昭(1914~2006)は映画「ゴジラ」(1954年)の音楽をはじめ数々の映画音楽を手がけたことでも知られているがこの「ラウダ・コンチェルタータ」という作品は「新星日響」創立10周年に委嘱されたマリンバとオーケストラのための協奏曲である。初演もこのCDと同じく国際的マリンバ奏者安倍圭子とのコンビで行われている。(1979年)解説によれば「ラウダ」とは原始宗教的な頌歌を意味することらしい。作品は3つ部分から構成されオスティナート(反復)のリズムに乗り激しいマリンバ独奏に聴衆は圧倒されてしまう。CDには「新星日響」創立20周年ヨーロッパ公演でのベルリン、「シャウシュピールハウス(現、コンツェルトハウス)」でのライヴ(1990年6月6日)が収録されている。演奏終了後の熱狂した聴衆の拍手が白熱のライヴを物語る。
※「山田一雄の芸術」 収録作品一覧
(CD-1) チャイコフスキー 「弦楽セレナード」 (1991年4月27日、サントリー・ホール)
ヴォルフ=フェラーリ 「マドンナの宝石」から「間奏曲」(1991年4月28日、東京芸術劇場)
ファリャ 「恋は魔術師」から「火祭りの踊り」(1990年4月16日、サントリー・ホール)
ショスタコーヴィッチ 「祝典序曲」 (1991年4月28日、東京芸術劇場)
(CD-2) 伊福部 昭 「ラウダ・コンチェルタータ」 (1990年6月6日、シャウシュピールハウス、 ベルリン)
伊福部 昭 「日本狂詩曲」 (1990年12月7日、サントリー・ホール)