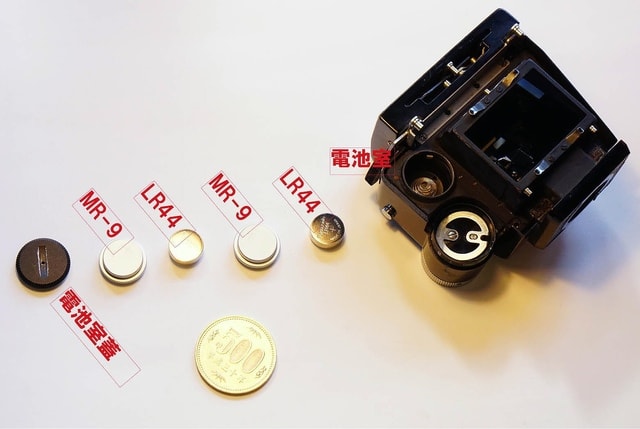過去のこだわりのフィルム撮影機材を全部処分!。頭を刈ったようにスッキリ。
断捨離を実行したおかげで私のフィールド用撮影機材は、以下3タイプに集約。カッコの数値はバッテリー付きボディとレンズの合計重量。
EOSシステム:EOS1Dsmark3+EF28-300mm/F3.5-5.6IS USM(3.1kg)
ニコンシステム:NikonDf+AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR(1.56kg)
SONYシステム:α6000+SEL1018 E10-18mm/F4.0OSS(0.55kg)
エアラインの持込手荷物重量制限に従って、先ずはキャノンかニコンかを選択し、次にサブのSONYを加えるか、加えないかを選択する、それでも重すぎればツァイスの標準ズームレンズを加えてSONYだけ、それでもアカンときはiPhone7だけ(笑)、というシステム。撮影機材の選択は、エアラインの持込手荷物重量制限で決まるから、先ずは持ち出せないことには何も始まらない。
これに旅の必需品などを含めて持ち出す荷物ができあがる。そして旅先では十分に撮影でき、且つ私の手持ち機材を活かすと、こうなるかなぁーというシステム。だから誰にでも推薦できるシステムではない。
そして旅の荷物と合わせて0.7kgの40リットルリュックに入れて出かけるわけである。
もちろん多くの人達が使っているカートを引いていては、ヨーロッパの石畳はつらいし、階段が多い建築遺産の見学時には預けなきゃいけないし、飛行場で接続時間を気にしながら荷物が出てくるのを待つ、というのは面倒だ。それに小さく軽いカートでも2kgを越える重さがある。だったら0.7kgのリュックのほうが荷物が積めるじゃないですか、ということになる。
私は大学で行った講義の旅論の中で「カートを引くな!」と講述してきた。それよりは荷物を軽くすることのほうが旅では大切。そして自分で楽に担げる重さにすることが旅の行動の基本だと考えている。
そんなわけで撮影機材は、自分の体力とエアラインの持込手荷物制限の重さで決まる。
さてニコンDfと調達したての28-300mmレンズで近所を試写した。背景のボケ方は綺麗、歪曲収差は目立たない。だが画像がシャープすぎて切って貼り付けたみたいで、立体感や空間感が希薄なところが私好みではない。これはシャープで発色が良く見栄えが良いとするアマチュア向けのパラメータの設定だろうか。
それにオートブラケットを解除したはずが、実はされていないといった類いの勘違い操作を各所で引き起こしやすい。つまり機能が多すぎる上に操作体系が明確でない。フィールドでは忙しくて機材の設定などを一々確認する時間的ゆとりはないから、操作体系はEOS1Dsのように明快であるべきだろう。
またレンズ鏡胴のロックが不適切なので、レンズの重さで前部が下がってしまうのは心理的にいやだ。ズームレンズは広角で撮ろうか、望遠で撮ろうかと予め自分で焦点距離を設定してから撮影するわけだが、こちらの決めた意志がないがしろにされているようで、いつも初期化され鏡胴が伸びきり300mmで撮る状態ではこちらはやりきれない。
画像は、初見で彩度が高く見応えがあるが、見続けるとすぐに見飽きる、というのもアマチュア・ライクなパラメータ設定の影響か。いずれにしても、これはどうしても手荷物の重量が減らせないときの予備機材だ。
余談だが最後の画像の女性の後ろ姿ぐらいに空気の存在を感じさせてくれて少し空間感がある。いつもこの程度で写ればEOS1Dsに近くて良いのだが。
それにノースリーブから出た二の腕の一寸プニッとした感じは色気と生活感がミックスされた感覚というのは私好み。それは画家ゴーギャンのタヒチのたくましい女達に通じるところがある。というのも小骨が喉に詰まりそうなギャル達の細い体型の女性が多いから私の感性は辟易していて、余計にそう思う。
何でも細きゃいいってものではないだろう!。例えばE.ムンクの「思春期」と題する細い女性は15歳で世を去ったし、B.ビュフェの細い女性の姿も、孤独や虚無や不安のストーリーしか思いつかない。だから女性の体型は、少し横に広がってくれるプロポーションの方が個人的にはデッサンしやすい。
そういえば、しばらく裸婦のクロッキー教室に通っていないから、ブログ・ドローイングのカテゴリーも更新されないままだ。暦の上では秋だけど、まだ暑くて一寸デッサンはねぇー、と遠慮する気分が濃厚。話題がずれた・・・。
iPhone7
トップ9ISO50,焦点距離3,99,露出補正0,f/1.8,1/15
NikonDf+AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
2)ISO1400,焦点距離50mm,露出補正0,f/4.2,1/4000
3)ISO3600,焦点距離100mm,露出補正-0.33,f/5.3,1/100
4)ISO6400,焦点距離70mm,露出補正-1.33,f/5.6,1/125
5)ISO6400,焦点距離28mm,露出補正-0.67,f/5.6,1/15
6)ISO6400,焦点距離28mm,露出補正0,f/5.6,1/25
7)ISO6400,焦点距離70mm,露出補正0,f/5.6,1/50
8)ISO6400,焦点距離300mm,露出補正0,f/5.6,1/250