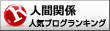礼拝宣教 マタイ23章1-12節 受難節Ⅲ
先週は主イエスの「エルサレム入場」の歓喜、さらに主イエスが義憤に駆られた「宮清め」の記事でした。エルサレム入場の際には、主イエスに従って来た多くの群衆が、「ホサナ、ホサナ、神よ、救い給え。」と主イエスをほめたたえました。
一方、そのような主イエスに反感と妬みをもっていたのが、ユダヤの指導者であったファリサイ派の人々や律法学者たちでした。彼らは、自分たちを救ってくださるメシアとなるお方は、かつてのイスラエル建国の父ともいえるダビデ王の子孫であると主張してきました。王にふさわしい権威と権力、政治的指導力を持っていた人物が救世主であると信じていたのです。
しかし、主イエスはメシアがどのように民の解放と救いを実現なさるかについて、3度に亘って「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活する」(16,17,20章)と告知されていたのです。
彼らはなぜ主イエスを排斥しようと殺意まで持ったのでしょうか。それは彼らの心が頑なになって、自分たちの地位や立場が蔑ろにされることを恐れていたからです。
マタイ22章では一人の律法の専門家が主イエスを試そうとして、「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか」と尋ねますが。それに対して主イエスは、「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」とお答えになります。彼らはその律法の精神を忘れてしまうほどに利得の関係性に依存していたと言えるでしょう。
本日はマタイ23章の主イエスが「律法学者とファリサイ派の人々を非難する」記事から御言に聞いていきますが。このところから主イエスご自身が何を最も大切な教えとして生きられたのかを、私たちは知ることができるでしょう。
主イエスは、弟子たちや従って来た群衆に語られます。
「律法学者たちとファリサイ派の人々は、モーセの座についている。だから彼らの言うことは、すべて行い、また守りなさい。しかし、彼らの行いは、見倣ってはならない。言うだけで、実行しないからである。」
「モーセの座に着く者」と言うのは、モーセが神の教えと戒めをしっかりと聞き、それを行ったように、それを人々に守り行うように指導する人を指しています。
主イエスが弟子たちや群衆に、「彼らの言うことは、すべて行いなさい」と語られたように、律法自体は正しいもので、人を生かすものに違いありません。
しかし、律法学者たちとファリサイ派の人たちは、「言うだけで実行しないから、彼らの行いは、見倣ってはならない。」と主イエスは言われます。
彼らはモーセの律法以外にも、日常においてこのように生活しなさいといった事細かに定めた600以上もの決り事を民衆に押しつけ、守るように教えていました。それを守るのはとても大変なことでした。「彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そうともしない。」と主イエスは指摘されます。彼らは口では律法を語り教えるのですが、肝心の「隣人を自分のように愛する」律法の精神が欠落していたのです。
さらに主イエスは彼らが、「すべて人に見せるため」にそうしていると指摘されます。
額や腕に巻きつける「聖句の入った小箱を大きくしたり」「衣服の房を長くしたり」「宴会では上座(かみざ)、会堂では上席(じょうせき)に好んで座ることを好み」「広場で挨拶されたり」「先生と呼ばれたりすること好んでいた」というのです。彼らはいつも自分を人によく見せ、賞賛されことを求めていたのです。
マタイ6章には、主イエスが「施しをするとき」「祈祷をするとき」「断食をするとき」に大事なことを語られていますので、あとでゆっくりと読んで頂ければと思いますが。
そこには、「見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい」「祈るときも、あなたがたは偽善者のようであってはならない」「断食するときには、あなたがたは偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない」と、主イエスは教えておられます。
ここで共通しているのは、「偽善者のようであってはならない」という点であります。それは本日の箇所の律法学者やファリサイ派の人たちの間に見られることでもありました。
「偽善」という言葉を広辞苑で引くと、「本心からではなく見せかけにする善い事」と解説があります。律法学者たちやファリサイ派の人たちは、本来は神によって招かれ、民の間で立てられた者であったのです。彼らは神を敬い、神の義に聞き従い、律法を説き、教える立場にありました。
しかしそれがいつの間にか、自分たちは特別な者といった特権意識を持つようになっていったのでしょう。賢く立派な人、人に賞賛され、もっと重んじられる者になりたい。いつもそんなことを考え、そのような思いでいっぱいになっていたのかも知れません。
マタイ18章では弟子たちの間で、「天の国でいちばん偉い者は、いったいだれか」といった議論が起こったようですが。そこで、主イエスは一人の子どもを呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われました。「はっきり言っておく。心を入れ替えて子どものようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子どものようになる人が、天の国でいちばん偉いのだ」。
子どものようにというのは様々な解釈があるでしょうが。先の律法学者やファリサイ派の人々の偽善と照らし合わせば、小さな子どもは人からどう見られるかなど重要だとは思わない、ということがあげられるでしょう。見せかけの良いことをして自分が人より立派になりたい、一目おかれたいなどと小さな子どもは思わないでしょう。主イエスが子どもを招かれた時も、子どもはいかに自分が出来る人間かなどとは考えもせず、そのあるがまま主イエスと人々の前に心を開いて出て来たことでしょう。その子どものように何も着飾ることなく、立派に見せようと偽善になることもない。それは真に解放されている人の姿を表わしているように思います。
主イエスは私たちが神の愛といつくしみによって真に解放され、他者と福音の喜びを分かち合うことを願い、招かれます。その招きは私たち自身が、神への愛と隣人愛を生きる者とされるためのものです。
私たちは主に救われた喜びと幸いから、奉仕や働きがなされていきますが。その喜びや幸いが色あせ薄れていきますと、奉仕や働きが重たくなり、しんどくなっていくことが起こることもあります。そういうときにこそ、ヨハネ黙示録2章4節「はじめの愛」に立ち返っていくことが、大事でしょう。奉仕も働きも、また毎週一緒に捧げております主日礼拝も、すべては主の救い、解放された者としての喜びと感謝、それは、ただ、恵みによる外ありません。あの幼子のように主のもとに招かれている喜びを生涯に亘り保っていきたいですね。
最後に8節以降を一気に読ませて頂きます。
「だが、あなたがたは『先生』と呼ばれてはならない。あなたがたの師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また、地上の者を『父』と呼んではならない。あなたがたの父は天の父おひとりだけだ。『教師』と呼ばれてはならない。あなたがたの教師はキリスト一人だけである」。
主イエスは弟子たちの間で、だれがいちばん偉いのか、と論じ合われていること残念に思われていました。倣うべきお方はイエス・キリストお一人なのです。
主イエスは、弟子たちや主イエスに従って来た群衆たちの間で、それは今日的にはキリストの教会において、あるいはキリスト者、クリスチャンの間で、このように指摘されておられるということです。
私たちのバプテスト教会においては、牧師は教職者や聖職者ではなく「教役者」と呼んでいます。役者のようにも読めますが。それは、いわばキリストの教会から託された役割の人ということです。教会が主の導きのもとで宣教や聖礼典、牧会のために立てているのです。役割からしてその責務は重く、その分給与にも与かっているのですが、同じ兄弟であり、信徒なのです。聖霊の導きによって、キリストの信徒である私たちが共にキリストの体なる教会を建て上げていく、そのような共同体なのです。キリストの愛によって互いに仕え合い、助け合いながら、福音の拡がりを祈り求めていく教会、私たち一人ひとりでありたいと願います。
先週お伝えしたように、倒れて救急で病院に搬送されるという初めての経験をしましたが。そこで思いましたのは、私が倒れても教会の働きが不断になされていくだろうか?いや、働きが止まってしまうようなことがあってはならない、ということをつくづく考えさせられました。もちろんそうならないように、どうか私に託されている働きが守られるために続けてお祈りください。同時に皆さまお一人おひとりが主の招きに応え、キリストの弟子として歩まれる幸いを祈りたいと思います。
今日の宣教題を「イエス・キリストに倣って」とつけさせていただきました。
「自分を低くして、子どものようになる人が、天の国でいちばん偉いのだ。」と言われ、自ら柔和なろばの子に乗って来られた主。
「いちばん偉い人は、仕える者になりなさい。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」と語られる主。
今受難節の只中でありますが、そのように語られる主イエス・キリストご自身が家畜小屋に生まれ、生涯神と人に仕え、私たちの罪をあがなうため、十字架の死に至るまでご自身の身を低くされたのです。私たちはその主の救いと解放の恵みに与っている者として、神の愛と隣人愛に生きる実りある人生を歩んでまいりましょう。祈ります。