「薬蜜本舗」というお店をご存知ですか?
最近はご無沙汰しておりますが、
ずっと前から好きで買わせていただいています。
蜂蜜のお店です。
実家の母からの荷物にはちみつが入っていることも多く
はちみつを買う機会が少なくなったので最近は食べていませんが…
薬蜜というだけあって品揃えが面白いのです。
「苜蓿」「枸杞」「龍眼」「茘枝」「茴香」などなど…。
もし商品を見かけたら試してみても面白いかも。
そのホームページの中にある「枸杞」のページより一部を紹介させていただこうと思います。
(日記の最後に載せます)
それというのも、
お土産にと中寧の枸杞(クコ)をいただきました。
そこ出身の先生からのお土産です。
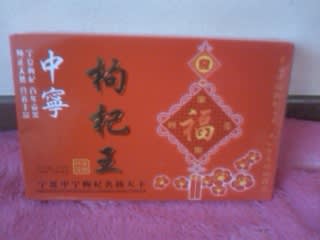
枸杞は最近ではよく知られるようになっていますよね。
先生も地元の特産品「中寧の枸杞」は自慢のようです、とてもうれしそうです!
ありがたくいただこうと思います。
謝謝!
ちなみに効能などは…
中薬名 : 枸杞子
性味 : 甘/平
帰経 : 肝、腎、肺
 おすすめ簡単クコ茶
おすすめ簡単クコ茶 
クコを数粒カップに入れてお湯を注ぐ。
2,3分待てば出来上がり!
これだけでもおいしくいただけると思います!
参考になさってください。
以下はクコの紹介として参考までに薬蜜本舗」さまより
貝原益軒も記した枸杞
『養生訓』をご存知でしょうか。今もなお読み継がれる「健康」についての書物で、作者の貝原益軒の名とともに広く知られています。
貝原益軒は江戸時代の本草学者、儒学者で、「養生訓」「和俗童子訓」などの教訓書を執筆しています。そこには益軒の考える身体と精神の修養法が示されています。
こうした教訓書の『養生訓』と並び、益軒の代表作として知られているのが『大和本草』です。宝永6年(1709)に刊行されており、実に益軒80歳での著作です。「本草学」とは薬用植物についての学問で、日本で最初に書かれた本格的な本草書が『大和本草』といわれています。益軒をはじめ、多くの人がその働きを書物に書き残しているほどです。
貝原益軒は江戸時代の本草学者、儒学者で、「養生訓」「和俗童子訓」などの教訓書を執筆しています。そこには益軒の考える身体と精神の修養法が示されています。
こうした教訓書の『養生訓』と並び、益軒の代表作として知られているのが『大和本草』です。宝永6年(1709)に刊行されており、実に益軒80歳での著作です。「本草学」とは薬用植物についての学問で、日本で最初に書かれた本格的な本草書が『大和本草』といわれています。益軒をはじめ、多くの人がその働きを書物に書き残しているほどです。
薬蜜本舗の枸杞ハチミツの故郷・銀川のある中寧夏は寧夏回族自治区の中心地です。肥沃な田畑が広がる地域もあり、小麦、水稲、トウモロコシ、瓜果実、リンゴ、ナツメなどの農作物、果実の山地としても知られています。
そのひとつが枸杞で、その名は中国語から「『枸(からたち)』のようなトゲがあり、『杞(こりやなぎ)』のようにしなやかに枝がのびる」という意味といわれます。
中寧県は枸杞の産地として古くからの歴史を持っており、1995年には「中国枸杞之郷」として認められています。一説には600年前から栽培されていたといわれ、豊富な水による優良な品質の枸杞は食用だけでなく薬用、美容などにも使われてきたのです。
「中国枸杞之郷」に選ばれたのは、特に安全で高品質な作物生産が可能で、さまざまな厳しい条件をクリアした、模範的な田畑であるからです。ここで薬蜜本舗の枸杞ハチミツは生まれています。
そのひとつが枸杞で、その名は中国語から「『枸(からたち)』のようなトゲがあり、『杞(こりやなぎ)』のようにしなやかに枝がのびる」という意味といわれます。
中寧県は枸杞の産地として古くからの歴史を持っており、1995年には「中国枸杞之郷」として認められています。一説には600年前から栽培されていたといわれ、豊富な水による優良な品質の枸杞は食用だけでなく薬用、美容などにも使われてきたのです。
「中国枸杞之郷」に選ばれたのは、特に安全で高品質な作物生産が可能で、さまざまな厳しい条件をクリアした、模範的な田畑であるからです。ここで薬蜜本舗の枸杞ハチミツは生まれています。
















