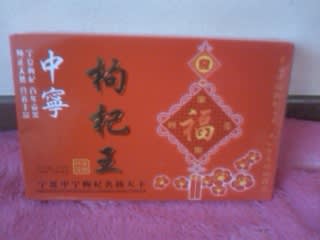宋海君老師
私が心から尊敬する我が師です。
老師の身近で教わっているからこそ感じている魅力ある教えの数々を
「養生気功塾」の生徒さんとも共有し、共に成長したいと思っています!
宋老師をご存じない方のために少しご紹介…



宋老師は、気功師として「本物」「一流」であることはもちろん、
時に「天才」「神」とも呼ばれ、驚くような経歴をお持ちのカリスマ的存在です。
そんなすごい実力と経歴を持つ老師ですが、
今でも誰よりも努力をされ、とても謙虚に日々を過ごされています。
私は宋老師の下で学んでいて、そういう姿からも深い学びをいただいております。
そして
そういう中にこそ“気功本来の魅力”があると思いました。
宋老師は気功の一族?(代々伝統流派を受け継いでいる)のご出身で、
確かに、気功修行の環境に恵まれていたと思います。
さらに、生まれながらの天才で、能力と才能も持ちあわせていたと思います。
でも
そういう“人が真似できない部分”の凄さ以上に
本人の日々の努力には大変なものがあったはずです。
そして、それは現在でも変わることなく続いています。
日々の努力は誰もがかなわないほどだと私は思っています。
この部分は、私が一番尊敬しているところなのです。



私は、宋老師に出会って気功を学ぶようになってから
宋老師の教えが大好きになりました。
「老師のようになりたい」という目標ができたのです。
そんな私がやるべきこと、できること…
「生まれつきの才能」や「環境」は真似できないことであっても
努力することは真似ができるはずだと思い、
生活を気功一色に変えました。
せめて、宋老師と同じ時間は毎日やろうと決意したのです。
(当時毎日4時間くらいと聞いていたのでそれを目安にしました)
それは、私なりに「教わっていることへの感謝の表現」でもありました。
慣れるまでは苦労しましたが、
やがて一日数時間の練功は無くてはならないものとなり
気づけばそれが楽しく、
そして、その結果として心身に大きな変化があらわれました。
適切な気功法の実践は、確実に効果があがることを
自分の体験を通して学んだのです。
私は、この気功の教えを「宝」だと思っています。
そういう体験が出来たのも、そこに至るまで続けることができたのも
宋老師のおかげです。
その経験から、私は『養生気功塾』という場を作り
“人の役に立つ教え”として
宋老師の気功を伝えていく決心をしたのです。
私の気功の原点は「宋海君老師」そのものです。



宋老師がおすすめな理由…
気功の実力はもちろんのこと、その人柄、謙虚な姿勢や誠実さ…
心の底から感謝をしたくなる深いあたたかさ。
一緒の場所にいるだけで、そういうすべてが伝わってきます。
気功世界の「不思議」「神秘的」と言われる部分についても…
自分を大きく見せようとする手段としてではなく、
事実・真実として教えてくれます。
足が地にしっかり着いた教えです。
私はその教えで変われました。
それは、すべての人に役に立つ学びだと思っています。
生徒さん達には、私の原点である宋老師と一緒に練功をしたり、
直に教えを受けることで
気功をより深く学んでほしいと思っています。



ぜひ、この「宝」を!

そんな気功、
体験しませんか?
お問い合わせもお気軽にどうぞ!
皆さまのご参加を心からお待ちしております!
この「縁」に感謝!
養生気功塾
田邉和子
(田辺和子)