21日(金)。東急沿線スタイルマガジン「SALUS」3月号の連載「コンサートの事件簿」に、音楽評論家・飯尾洋一氏が、「いかに楽しむべきものか?」というテーマでエッセイを書いています。超訳すると
「あるオペラ公演で、ひとりの客が手拍子を打ち始めた もちろん非難ごうごうだ。『ニューイヤーコンサート』のアンコールで演奏される『ラデツキ―行進曲』なら分かる。しかし、通常は『演奏中は静かにする』というのがクラシックの原則だ
もちろん非難ごうごうだ。『ニューイヤーコンサート』のアンコールで演奏される『ラデツキ―行進曲』なら分かる。しかし、通常は『演奏中は静かにする』というのがクラシックの原則だ 1778年、モーツアルトは交響曲第31番”パリ”の初演の成功を故郷の父親あての手紙で書いている
1778年、モーツアルトは交響曲第31番”パリ”の初演の成功を故郷の父親あての手紙で書いている それには『いよいよ交響曲が始まりました。第1楽章アレグロの真ん中に、たぶん受けるに違いないとわかっていたパッセージがありました。そこで聴衆はみんな夢中で拍手喝さいでした』。この手紙によれば、当時のパリの聴衆は、感銘を受けたパッセージで演奏中にもかかわらず拍手をしていたのだ
それには『いよいよ交響曲が始まりました。第1楽章アレグロの真ん中に、たぶん受けるに違いないとわかっていたパッセージがありました。そこで聴衆はみんな夢中で拍手喝さいでした』。この手紙によれば、当時のパリの聴衆は、感銘を受けたパッセージで演奏中にもかかわらず拍手をしていたのだ そして、モーツアルト自身は狙い通りに受けたと喜んでいる。彼らと私たちは何と遠い存在だろうか
そして、モーツアルト自身は狙い通りに受けたと喜んでいる。彼らと私たちは何と遠い存在だろうか 」
」
パリの聴衆が感銘を受けたパッセージはどこかについては諸説あるようですが、私なりに「あそこだな 」と思い当たるフシがあります。が、ここではそのことは問題にしません
」と思い当たるフシがあります。が、ここではそのことは問題にしません
当時、コンサート会場で音楽を聴くことのできたのは貴族だったはずですから、曲の途中で拍手喝さいを送ったのは貴族だったことになります ものの本によると、当時はコンサートが始まってもなかなかおしゃべりが止まなかったという話があります。なぜ、オペラには序曲があるかといえば、遅れてきた聴衆が皆そろい静かになるのを待って本番を迎えるためだ、というのをどこかで読みました
ものの本によると、当時はコンサートが始まってもなかなかおしゃべりが止まなかったという話があります。なぜ、オペラには序曲があるかといえば、遅れてきた聴衆が皆そろい静かになるのを待って本番を迎えるためだ、というのをどこかで読みました
要するに当時は、あくまでも貴族である聴衆が主役で、演奏家は彼らの都合や意向に合わせて演奏したのではないか、と思います
振り返って、現在のコンサートはどうでしょうか?同じようなことが言えるのではないかと思います とくにオーケストラの演奏会について言えることですが、大方のプログラムは前半と後半とに分かれ、前半はさらに1曲目の短い曲(オペラの序曲など)と、2曲目の30分程度の曲(協奏曲など)に分かれます
とくにオーケストラの演奏会について言えることですが、大方のプログラムは前半と後半とに分かれ、前半はさらに1曲目の短い曲(オペラの序曲など)と、2曲目の30分程度の曲(協奏曲など)に分かれます そして後半にメインディッシュに相当するやや重い曲が置かれます
そして後半にメインディッシュに相当するやや重い曲が置かれます つまり、現在においても、遅刻者が2曲目以降の曲が聴けるように、1曲目に短い曲を演奏するようになっているのです
つまり、現在においても、遅刻者が2曲目以降の曲が聴けるように、1曲目に短い曲を演奏するようになっているのです ちなみに私の場合は、1曲も聞き逃したくないので、余程のことがない限り30分前には会場に着いて、プログラムに目を通すようにしています
ちなみに私の場合は、1曲も聞き逃したくないので、余程のことがない限り30分前には会場に着いて、プログラムに目を通すようにしています
モーツアルトの時代と現在との違いは、現在においては、原則として曲の途中で拍手をしたり、雄たけびを上げたりしてはいけないということ 同じ聴衆でもわれわれは貴族ではありません
同じ聴衆でもわれわれは貴族ではありません

 閑話休題
閑話休題 

本を5冊買いました 1冊目は誉田哲也著「感染遊戯」(光文社文庫)です。彼の書く本に”外れ”はありません
1冊目は誉田哲也著「感染遊戯」(光文社文庫)です。彼の書く本に”外れ”はありません
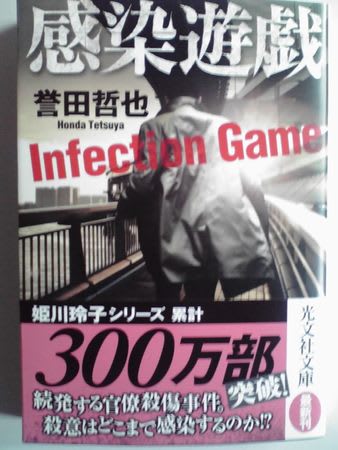
2冊目は東川篤哉著「はやく名探偵になりたい」(光文社文庫)です。ユーモア・ミステリーの代表者の本です
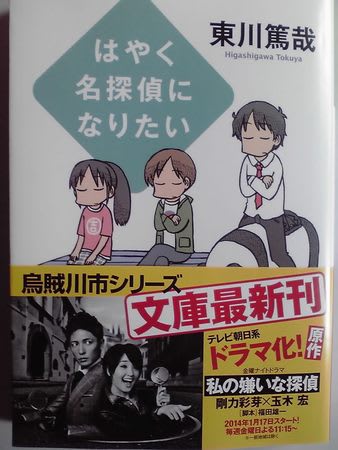
3冊目はカール・ハイアセン著「これ誘拐だよね?」(文春文庫)です。海外ユーモア・ミステリーの第一人者の本です
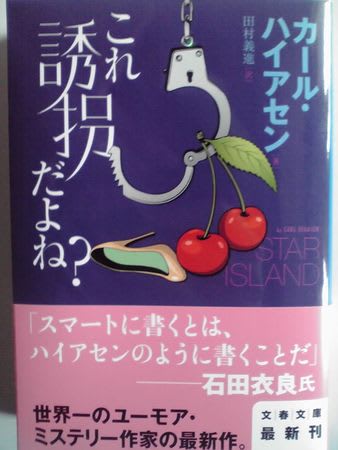
4冊目は鶴我裕子著「バイオリニストに花束を」(中公文庫)です。”クラシック音楽界の向田邦子”と呼ばれる著者の傑作エッセイです
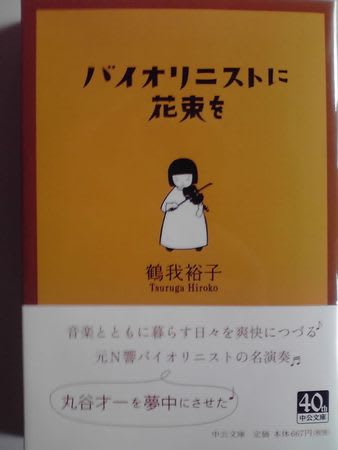
5冊目は青柳いづみこ著「我が偏愛のピアニスト」(中公文庫)です。さて、どんなピアニストがマナ板に乗せられるのか

それにつけても、まだ読んでいない本が山と積まれているのに、なぜ新しい本を買ってしまうのでしょうか?自分で言うのも何ですが、ほとんど病気ですね















