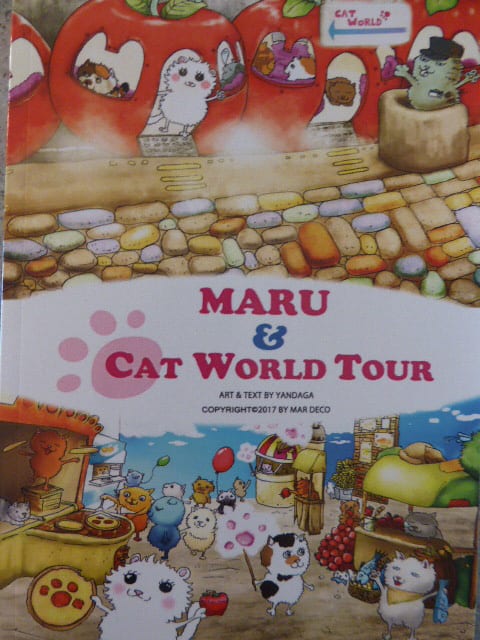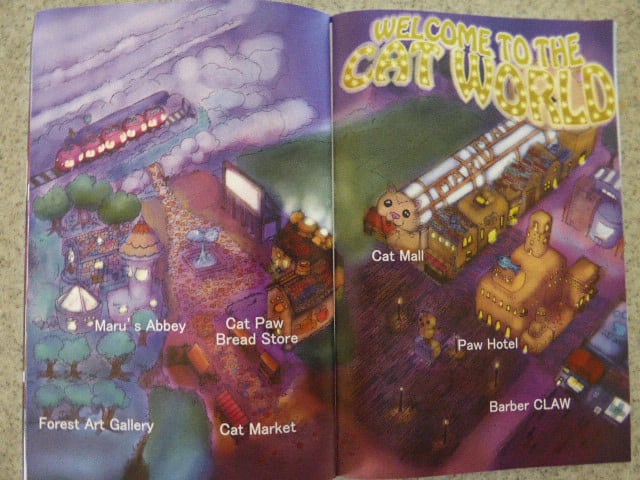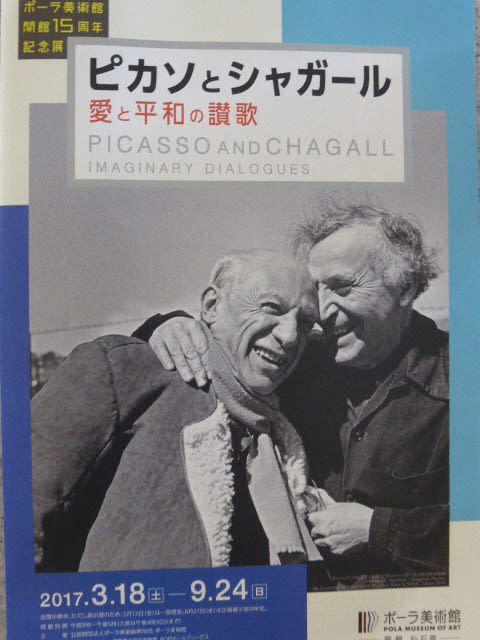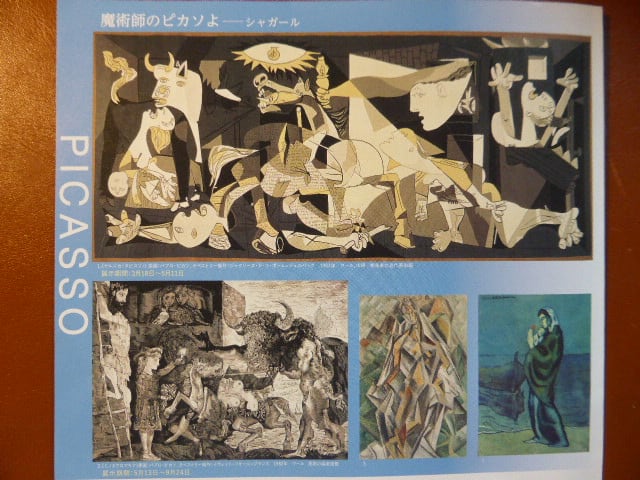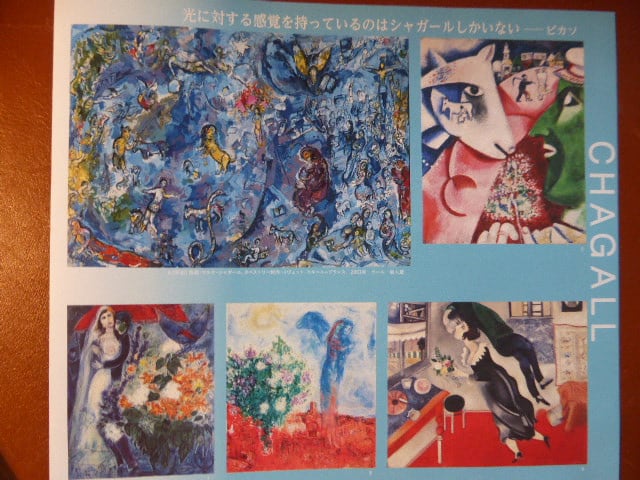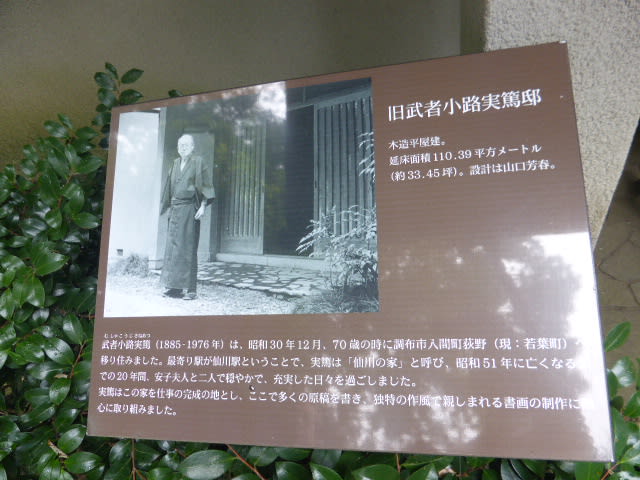なぜに、ドナルド・キーンセンターが柏崎に?と半信半疑で訪れたものだったが、
豊富な資料と年譜によって、思った以上に理解が深まった。



多岐にわたる文学研究を彩る人物関連図は一度には見切れない。


ニューヨークのアパートのハドソン川が見下ろせる書斎が再現されていた☆

<中越沖地震の際の公演ポスター>



この後、近隣のブックオフで、講談社学術文庫;
<果てしなく美しい日本>
<脳・文樂・歌舞伎>
<百代の過客><百代の過客(続)>を買って帰った。
現在は北区の古河庭園近くにお住まいとか、バラの季節を心待ちになさっていることでしょう。
<MEMO>

豊富な資料と年譜によって、思った以上に理解が深まった。



多岐にわたる文学研究を彩る人物関連図は一度には見切れない。


ニューヨークのアパートのハドソン川が見下ろせる書斎が再現されていた☆

<中越沖地震の際の公演ポスター>



この後、近隣のブックオフで、講談社学術文庫;
<果てしなく美しい日本>
<脳・文樂・歌舞伎>
<百代の過客><百代の過客(続)>を買って帰った。
現在は北区の古河庭園近くにお住まいとか、バラの季節を心待ちになさっていることでしょう。
<MEMO>














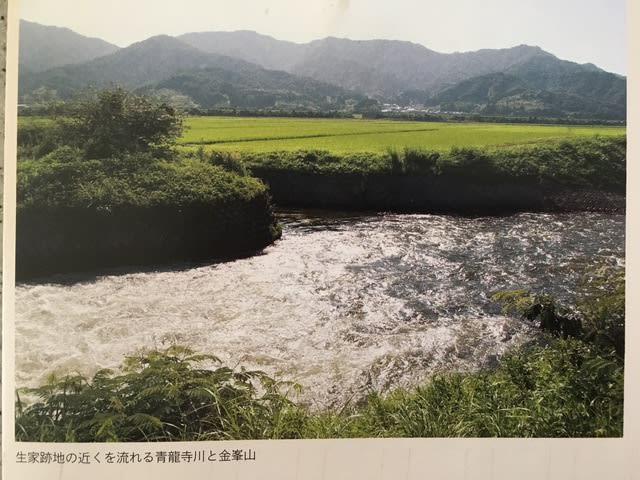




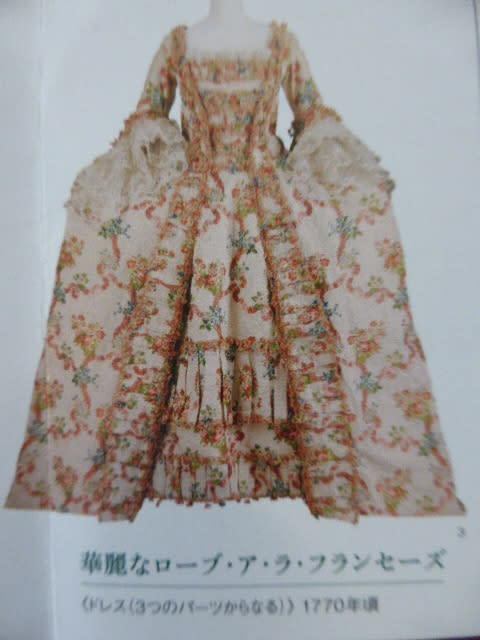
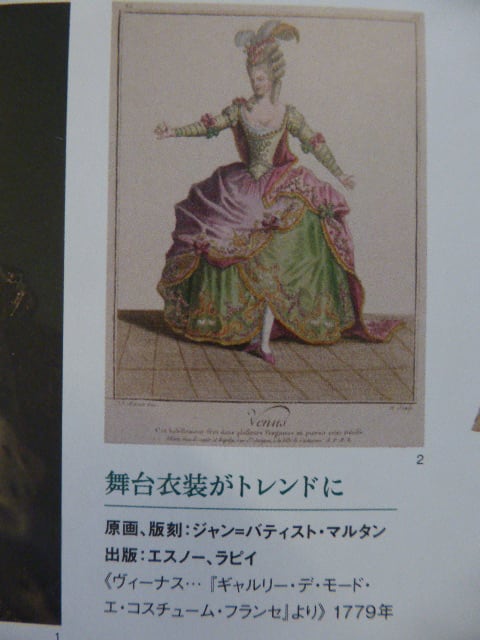

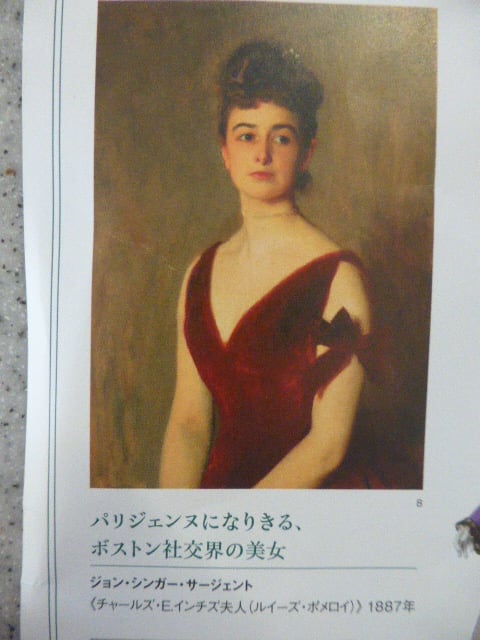


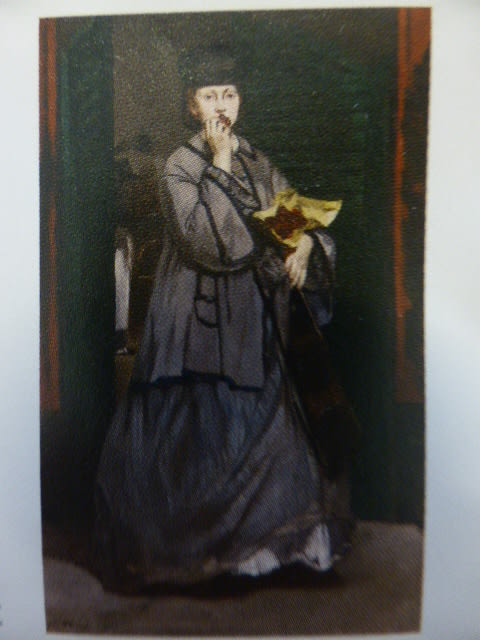
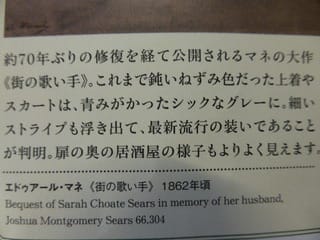
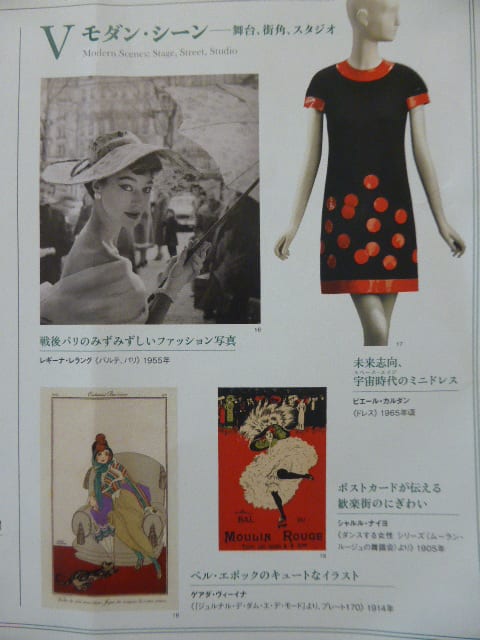











 ふ
ふ
 る
る