新聞広告で見て、馬場の芳林堂の震災コーナーでやっと手に入れました。



佐野眞一、ノンフィクション作家、“『東電OL殺人事件』で東京電力の実相を暴き”~
東京電力のエリート女性社員の夜の顔を追いつつ、東電体質まで言及、
発表当時、その衝撃的内容から、あちこちで紹介され話題になりました。
印象に残る分厚いハードカバー本で、時を隔てて再読、再再読したものです。
自分の視点、取材を第一に、しつこく、執拗に追いかけていくスタイルは、読むほうも途中で降りられなくなる。
団塊の世代(1947年東京生まれ)特有の粘り腰?
その期待は裏切られず…
第一部 日本人と大津波 (「G2]に発表のルポに加筆)
第2部 原発街道を往く
第一章 福島原発の罪と罰 (「週刊現代」発表の同題ルポに大幅加筆)
第2章 原発前夜 原子力の父・正力松太郎
第3章 なぜ「フクシマ」に原発は建設されたか
大病後の万全でない体調で、出かけていく気になったのは、
・著名人のコメントに怒りを覚えた。
・現地を見ずに感想だけ述べるのは、ノンフィクション作家の資格なしと思った。
そして、「取材経験を積んできた私だからこそ~」の自負通り、
「何の構想もあったわけでもない」なか、「出たとこ勝負」で、これだけのルポを書いてくれた。
後半に行くほど、つまり、書き下ろし部分の読ませ方はさすが、
巻末の主要参考文献も親切ていねいで、知的好奇心を刺激されました。
読み終わって、次へ進む道が見えてくる本は、読書冥利につきます。
追~ 今日、月曜日発行の「週刊現代」より


追~ 7月10日の日経新聞書評より




佐野眞一、ノンフィクション作家、“『東電OL殺人事件』で東京電力の実相を暴き”~
東京電力のエリート女性社員の夜の顔を追いつつ、東電体質まで言及、
発表当時、その衝撃的内容から、あちこちで紹介され話題になりました。
印象に残る分厚いハードカバー本で、時を隔てて再読、再再読したものです。
自分の視点、取材を第一に、しつこく、執拗に追いかけていくスタイルは、読むほうも途中で降りられなくなる。
団塊の世代(1947年東京生まれ)特有の粘り腰?
その期待は裏切られず…
第一部 日本人と大津波 (「G2]に発表のルポに加筆)
第2部 原発街道を往く
第一章 福島原発の罪と罰 (「週刊現代」発表の同題ルポに大幅加筆)
第2章 原発前夜 原子力の父・正力松太郎
第3章 なぜ「フクシマ」に原発は建設されたか
大病後の万全でない体調で、出かけていく気になったのは、
・著名人のコメントに怒りを覚えた。
・現地を見ずに感想だけ述べるのは、ノンフィクション作家の資格なしと思った。
そして、「取材経験を積んできた私だからこそ~」の自負通り、
「何の構想もあったわけでもない」なか、「出たとこ勝負」で、これだけのルポを書いてくれた。
後半に行くほど、つまり、書き下ろし部分の読ませ方はさすが、
巻末の主要参考文献も親切ていねいで、知的好奇心を刺激されました。
読み終わって、次へ進む道が見えてくる本は、読書冥利につきます。
追~ 今日、月曜日発行の「週刊現代」より


追~ 7月10日の日経新聞書評より











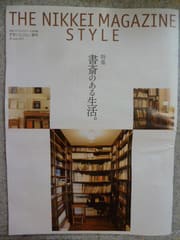



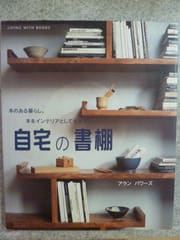



 」
」 」…(笑)(笑えない?)
」…(笑)(笑えない?)








 新潟で購入した3冊のうちの一冊、『晩年の美学を求めて』(朝日文庫2009年)
新潟で購入した3冊のうちの一冊、『晩年の美学を求めて』(朝日文庫2009年)

 を見込んでしまった
を見込んでしまった のか
のか 「日本会議」会員の名詞を下さり、「日本の息吹」をいただきました。。
「日本会議」会員の名詞を下さり、「日本の息吹」をいただきました。。
 野菜の生まれと育ちがわかる、読むサラダ!
野菜の生まれと育ちがわかる、読むサラダ!

 訳書も多いです。
訳書も多いです。 ♢1 ピエール=ジョセフ・ルドゥーテ「バラ」
♢1 ピエール=ジョセフ・ルドゥーテ「バラ」 ♢2 「ネブアメン墳墓絵画」
♢2 「ネブアメン墳墓絵画」 ♢3 ルソー「陽気な道化たち」
♢3 ルソー「陽気な道化たち」 ♢4 河原慶賀「ムサシアブミ」
♢4 河原慶賀「ムサシアブミ」 ♢5 牧野富太郎「ヒガンバナ」
♢5 牧野富太郎「ヒガンバナ」 ♢6 歌川国芳「百種節分菊」
♢6 歌川国芳「百種節分菊」 ♢7 マーガレット・ミー 「カトレア・ウィオラケア」
♢7 マーガレット・ミー 「カトレア・ウィオラケア」 ♢8 エーレット「性分類体系」図解
♢8 エーレット「性分類体系」図解 ♢9 バウアー「ストローブマツ」
♢9 バウアー「ストローブマツ」  ♢10 石上純也「ベネチアビエンナーレ国際建築展 日本館展示」
♢10 石上純也「ベネチアビエンナーレ国際建築展 日本館展示」 “自己を律し生き抜け” “「想定外」は人の愚かさ証明”
“自己を律し生き抜け” “「想定外」は人の愚かさ証明”















 今や貴重な初版本
今や貴重な初版本





 ミステリ・ガイド・ツアーにそってフランス一周~
ミステリ・ガイド・ツアーにそってフランス一周~


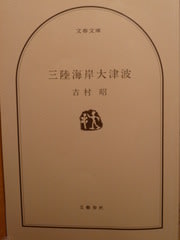



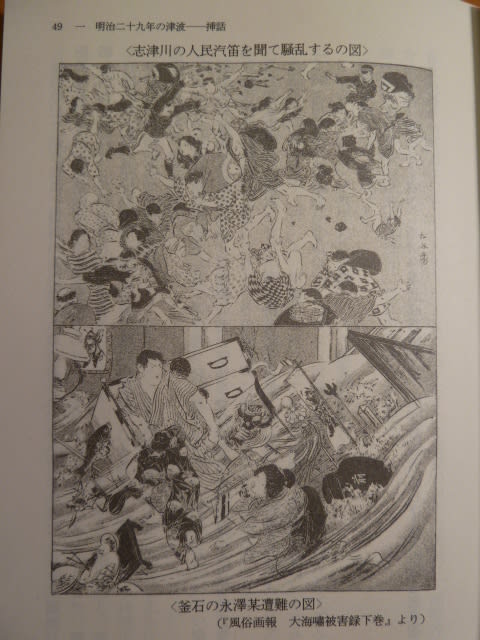
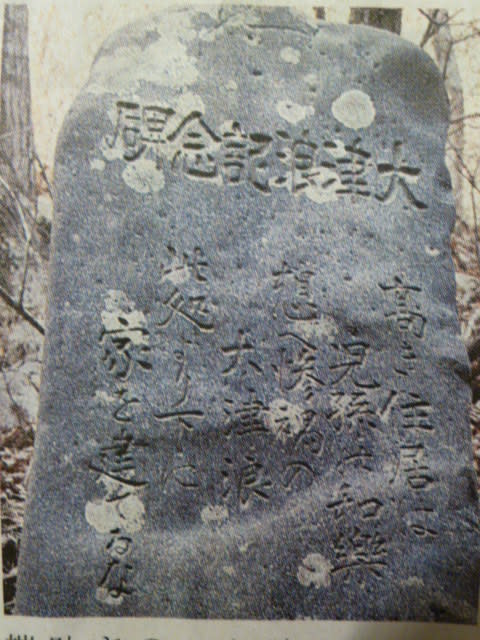
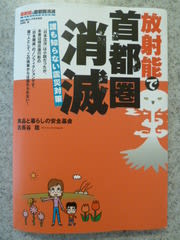


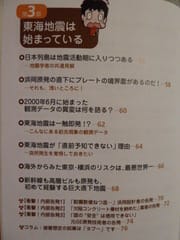

 (本署の出版は2006年4月です!)
(本署の出版は2006年4月です!)


 表扉から
表扉から 


