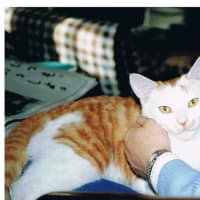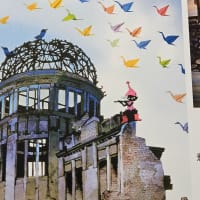今の、日本の家では失われてしまった存在かもしれません。
恩師の納骨の儀に参列してきました。
今では、珍しい、一代づつの墓石が立ち並ぶ、宇塚家の墓地に、新
しく建立された、宝寿院無量医光善照清居士の、永久の住まいの新居の祝いともいうべき、魂入れ、納骨法要です。
40年におよぶつきあいから、されど”名を尊ぶ””義を尊ぶ”ことを第一義とする有り様を、不思議な気持ちで眺めていました。先生の同級生、私の主治医から、先生が名門の出であること、幼少時は、名家の常として、下男、下女月の環境で成長したことから、”家名を汚さない””一族郎党の長”としての判断、身の回りの世話してもらうのに慣れていることが、合点しました。損得勘定抜きには行動しないみみっちさがあるような気がする私の年代とは、違う気品があふれていた。疑い深さを感じさせない、確認する慎重さ、最終判断は、損得抜きで判断し、その後経済観念を入れて結論を下す。対外的には、身内をそしることをしない、見捨てない。
代々受け継いだ土地、家は、個人財産という考えは、まったくなく、しかも、不在地主であるための不利益に対しては、もともと、自分が利するためにあるという考えがないので、鷹揚でした。また、受け渡すのが、自分の責任というので、山林内の自分以外の所有となっていた部分を、臥龍点睛を欠くような、将来に家訓を残してはいけないと、他の理由のために屁理屈をつけ、極めて高額の相場を支払い一山一地主としました。
今回も先例にならっての墓石建立は、平成21年8月15日、深程の地で”家郷会”を開き、冊子作成に続いての一族のためのよりどころとしての意思表示であったかとおもいます。
次世代は、従来通りの維持は困難、何とか対策を立てて後、受け渡したいという思いは、時代の荒波にのまれて果たせませんでした。
木漏れ日あふれる中で、ハンモックに寝そべりながら読書にあけくるれた故地,深程の地に戻り、自由闊達に世界を駆け巡りはじめたのでしょうか。

恩師の納骨の儀に参列してきました。

今では、珍しい、一代づつの墓石が立ち並ぶ、宇塚家の墓地に、新
しく建立された、宝寿院無量医光善照清居士の、永久の住まいの新居の祝いともいうべき、魂入れ、納骨法要です。

40年におよぶつきあいから、されど”名を尊ぶ””義を尊ぶ”ことを第一義とする有り様を、不思議な気持ちで眺めていました。先生の同級生、私の主治医から、先生が名門の出であること、幼少時は、名家の常として、下男、下女月の環境で成長したことから、”家名を汚さない””一族郎党の長”としての判断、身の回りの世話してもらうのに慣れていることが、合点しました。損得勘定抜きには行動しないみみっちさがあるような気がする私の年代とは、違う気品があふれていた。疑い深さを感じさせない、確認する慎重さ、最終判断は、損得抜きで判断し、その後経済観念を入れて結論を下す。対外的には、身内をそしることをしない、見捨てない。
代々受け継いだ土地、家は、個人財産という考えは、まったくなく、しかも、不在地主であるための不利益に対しては、もともと、自分が利するためにあるという考えがないので、鷹揚でした。また、受け渡すのが、自分の責任というので、山林内の自分以外の所有となっていた部分を、臥龍点睛を欠くような、将来に家訓を残してはいけないと、他の理由のために屁理屈をつけ、極めて高額の相場を支払い一山一地主としました。
今回も先例にならっての墓石建立は、平成21年8月15日、深程の地で”家郷会”を開き、冊子作成に続いての一族のためのよりどころとしての意思表示であったかとおもいます。
次世代は、従来通りの維持は困難、何とか対策を立てて後、受け渡したいという思いは、時代の荒波にのまれて果たせませんでした。
木漏れ日あふれる中で、ハンモックに寝そべりながら読書にあけくるれた故地,深程の地に戻り、自由闊達に世界を駆け巡りはじめたのでしょうか。