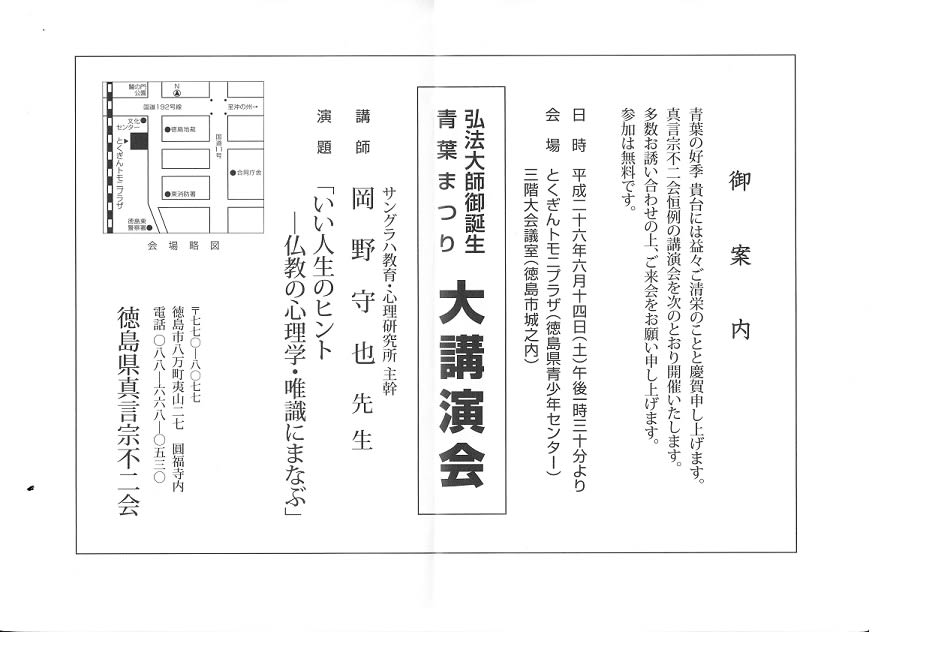長い間宗教や霊性について社会的発言をしてきた者として、読者の心のなかに「イスラム原理主義者によるテロ事件が頻発し、多くの犠牲者が出ている状況に対して、岡野はどう思っているのか、発言をしないのか」という問いが潜在しているのではないか、と感じており、何かお答えしなければならないのではないか、と思っていました。
その前にまず、犠牲者の関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げ、亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思います。
ここのところずっと、何を言うべきかと考えていたのですが、ふと、もう20年も前、1995年に書いた「〈宗教〉に未来はない」という文章(『コスモロジーの創造』2000年、法蔵館、所収)を思い出して読み返し、ほぼこれに尽きると思ったので、以下、抜粋して再掲することにしました。
ただ、そこで使った〈宗教〉という言葉はより正確に〈原理主義的宗教〉〈原理主義〉と言い換えて読んでいただきたいと思います(ところどころ〔 〕で補います)。
〔原理主義的〕〈宗教〉に未来はない
「宗教に未来はない」、しかし「近代主義にも未来はない」、未来は「宗教から霊性へ」という方向にあると、公的な場でものを書き始めて以来、基本的にはずっとおなじことばかり繰り返してきた(たとえば、『トランスパーソナル心理学』1990年、青土社、吉福伸逸氏との対談『テーマは〈意識の変容〉』1992年、春秋社、など)。……
なぜ「〈宗教〉に未来はない」か
〈宗教〉の定義
まず明確にしておくと、未来がないという〈宗教〉とは、みずからの派の教祖―教師、教義、教団、儀式、修行法などの絶対視、つまり言葉の悪い意味での「信仰」と「服従」を不可欠の条件として、人を富や癒しや調和、生きがい、安心、あるいは救い、死後の幸福な生命、悟り……といった肯定的な状態へ導く(と自称する)システムとグループを指す。……これには、一見非宗教的であっても、自己絶対視の体質を抜けられない〈イデオロギー〉をも含めるべきだろう。
自己絶対視と敵意
何を根拠にしようと、自己絶対視は、かならず人を敵と味方に分断する。敵を生みだす思想は、かならず敵意を生み出す。
自己を絶対とみなしている宗教やイデオロギーにとって、自己の味方でない他者は、せいぜい布教し、改心させる(時には洗脳する)対象ではあっても、そのままで認めうる存在ではない。そして、いくら布教しても信じない他者は、哀れむべき存在であり、それにとどまらず、布教に反対する者は憎むべき呪われた存在とみなされることになる。
事と次第では、神(人類、人民、民族、国家、正義、真理……などに置き換えてもおなじことだが)に反する者は、神に呪われたものであり、したがって神に代わって我々が殺してもよい、という結論にまで到る。
建て前上、「布教・説得はしても強制はしない」などと寛容な構えを見せても、自己絶対視は心情としていやおうなしに敵意、すなわち憎悪・殺意を含んでしまう。だから、寛容でありうるのは、集団がまだきわめて小さいか、あるいは逆にかなり大きくなって余裕がある時のことであって、余裕がなくなると、とたんに敵意を剥き出しにする。
しかも行き詰まると、「敵」は、外だけでなく内にもいるように見えてくる(「うまくいかないのはあいつのせいだ」などと)。したがって、憎悪・殺意は、ほとんど必然的に、外だけでなく内にも向かう。
それが「宗教」だけではなくすべてのイデオロギーに秘められた心情の問題である……「絶対に正しい我々が、絶対にまちがったあいつらを改宗させるか、さもなければ全滅させることによって、正しい、すばらしいユートピアがやってくる」(かつて埴谷雄高がいった言葉を借りれば「あいつは敵だあいつを殺せ」)というタイプの思考システムと、それが生み出す心情は、程度の差はあれ必ずといっていいほど、憎悪―闘争―虐殺をもたらすがゆえに、もはや、人類の未来にとって、それこそ絶対に無効―有害である。
その点について、『キリスト教の本質』(上下、船山信一訳、岩波文庫)などにおけるフォイエルバッハの宗教批判の言葉は、古典的でいまさらのようだが、依然として日本の市民……の大多数の常識にはなっていない、どころかほとんど知られてもいないらしいから、改めて引用しておきたい。
宗教は自分の教説にのろいと祝福・罰と浄福を結びつける。信ずる人は浄福であり、信じない人は不幸であり見捨てられており罰せられている。したがって、宗教は理性に訴えないで心情に訴え、また幸福に訴え、恐怖と希望との激情に訴える。宗教は理論的立場に立っていない。(邦訳下、7頁)
……信仰そのものの本性はいたるところで同一である。信仰はあらゆる祝福とあらゆる善とを自分と自分の神へと集める。……信仰はまたあらゆるのろいとあらゆる不都合とあらゆる害悪とを不信仰へ投げつける。信仰をもった人は祝福され神の気に入り永遠の浄福に参与する。信仰をもたない人はのろわれ神に放逐され人間に非難されている。なぜかといえば神が非難するものを人間は認めたりゆるしたりしてはならないからである。そんなことをしたら神の判断を非難することになろう。(同、122頁)
……信仰は本質的に党派的である。……賛成しないものは……反対するものである。信仰はただ敵または友を知っているだけであってなんら非党派性を知らない。信仰はもっぱら自己自身に心をうばわれている。信仰は本質的に不寛容である。(同、126~127頁)
右であれ左であれ、人間に平和と幸福をもたらすと自称した思想が、なぜ憎悪と悲劇を生み出してきたのか。それは、絶対視された物差しによって、天国・ユートピアに入る資格のある者とない者の心情的な絶対的分離=敵意をもたらすからである。自己を絶対視する思想としての〔原理主義的〕〈宗教〉には、原理的にいって、人類規模の平和をもたらす力はない。そういう意味で、未来はないのである。
もちろん、悲しいことながら、ここ当分人類は争い続けるだろうし、争い続けながらも生き延びている間は、建て前として平和を叫びながら実際には平和をもたらせない〈宗教〉も生き延びるだろうし、そういう意味でなら、まだしばらく宗教に未来はある(それどころか、現象的には、一時、宗教紛争、宗教戦争の元になるような〔原理主義的〕宗教の勢力はかえって増大するかもしれない)。
しかし、繰り返すが、人類規模の平和な未来の実現ということからいえば、もはや〔原理主義的〕宗教に有効・妥当性はない、と思う。
なぜ「近代主義に未来はない」か
近代主義とは何か
……人間主義+理性・科学主義+進歩主義=〈近代主義〉は、基本的に無神論的・反宗教的であり、宗教を批判し超えようとする試みであり、いわば「宗教の代案」であった。
近代の進歩的な思想家たちは、宗教は、人間が自分自身の理性の力によって解決すべき・できる問題を、神話・観念・空想によって、心理的に慰めるだけで、かえって現実的な解決を妨げる、そういう意味では、人類の進歩にとって害のあるものだ、と批判した(典型的にはマルクスの「宗教は民衆のアヘンである」)。そして、近代の進歩的思想家たちの宗教批判には、たしかに当たっているところも少なくなかった。
近代主義の立場からいえば、人間が、理性―科学―技術によって社会を進歩させれば、人生の問題はすべて解決できるようになるはずであり、そうなれば宗教は必要なくなる、はずだったのである。そして、それがある程度までは有効であるように見えてきたので、近代のいわゆる先進諸国の大勢を占める思想になってきたのだ。
それについては、右であれ左であれ、欧米であれ日本であれ、進歩的な指導者や知識人たちは、いまだにそう考えているのではないだろうか。そして日本でも、明治以後のいわゆる近代化の流れの中で、近代主義は主流の思想となり、特に戦後は、ほとんど無意識的な常識にまでなっている。
近代主義とニヒリズム―エゴイズム
しかし私の考えでは、人類の現段階の問題としていえば、宗教だけでなく、近代主義にも未来はない。それはまず第一に、近代主義は原理的に人間の〈ニヒリズム〉―〈エゴイズム〉を克服する根拠を見失っているからである。……
しかし、近代主義は、スタートの時点での、ヒューマニズム=人間尊重という建て前にもかかわらず、論理的な必然として、ニヒリズムーエゴイズムに到り、モラルの低下-崩壊をもたらすものであった。
すなわち、自分を超えたもの――神とその創造した自然――に服従する存在ではなく、神を否定し、自然を操作することのできる、能力ある主体という面に視線が集中していた間はよかった。しかし、やがて自然を物質として見る視線が人間自身に向けられた時、人間も客体・対象、生物、有機体の一種、物質の組み合わせにすぎないと見られることになった。人間の心もまた、脳という物質の働きに還元して捉えられる。
だが、もし物質の働きにすぎないとしたら、いのちや心にどんな意味がありうるというのだろうか。物質科学主義の視線によっては、人間の生の意味を見出すことはできない。そういう意味で、近代主義は、論理的必然として、ニヒリズムに到るのである。
しかし生きている個々人にとっては、自分が、結局は物質の組み合わせにすぎないとしても、今、心をもち生きていることは事実、というか実感である。ニヒリズムという帰結を漠然と予感しながらも、なお生きているという実感をもち続けている個人は、もはや客観的な物質的自然に生きる意味の根拠を求めることはできない。
意味がないにしても、なお生きるのは、自分の中に生きたいという心情・欲望がなぜか与えられているからで、それ以外の理由はない、ということになる。
ところが、個人・自分の主観―心情―欲望だけが最後の物差しだとすれば、「ひとに迷惑さえかけなければ」、さらには「迷惑をかけたとしても、自分が報復を受けることがなければ」「自分のやりたいことはなんでもやっていい」ということになりかねない。近代主義には、それ以上のモラルが生まれる根拠はほとんど見出しがたいのではないだろうか。あるいは、近代主義はモラルの根拠を見失ったといったほうがいいだろう。つまり、近代主義のもたらすニヒリズムは、さらにほとんど必然的にエゴイズムに到り着くほかない。
……ニヒリズムとエゴイズムの悪循環を克服する原理を見出しえていないところに、人間の心の面に関する近代主義の決定的限界がある。
近代主義と環境破壊
さらに第二に、先に述べた環境の崩壊も、近代主義がもたらしたものだ、ともいえる。……環境破壊は、個人レベルでのエゴイズム―ニヒリズムとおなじく、近代主義的な態度の必然的な帰結であるともいえる(近代に進歩の面がないというわけではないが)。……
加えていえば、近代は、なぜ、声高く平和を語りながら、かつてない大規模な戦争を行ない、そしていまだに戦争を廃絶しえないのだろうか。
近代主義は、個人レベルだけでなく集団レベルでも、エゴイズムを超える原理や制度を見出しえていないということが、一つの(唯一ではないが)大きな理由なのではないだろうか。集団レベルでのエゴイズムを超えうる原理と制度を見出さないかぎり、環境破壊も戦争も、根本的な解決はできない。そういう意味でも、近代主義には未来はないと思う。
宗教でも反宗教でもなく〈霊性〉へ
では、自己絶対視と敵意を生み出す宗教でもなく、エゴイズムとニヒリズムを克服しえない近代主義―反宗教とも異なる、人類の未来を拓きうるような立場はあるだろうか。
ある、それは〈霊性〉の立場である。あるいは霊性と理性の融合された立場、そういう意味でいえば、宗教と近代主義双方の問題点を十分に批判し、しかし普遍妥当な面を正確に取り出して融合した立場である、というのが私の考えである。
〈宗教〉には、たしかに先に述べたような問題点・限界がある。しかし本来宗教の核にあったのは、人間のいのちは、どこまでも人間のいのちでありながら、人間自身が生み出したものではなく、人間を超えた、より大きなものによって生まれたものだ、という感覚だったのではないだろうか。「生きることは生かされて生きることである」「私より大きな何ものかが私を生かしている」という直感、さらに、人間だけでなく、生きているものもそうでないものも、すべてのものがより大きな全体(神、仏、自然、宇宙)に包まれているという根源的な事実への目覚めが、宗教の核にあるものだと思う。
しかし包んでいる何か全体なるものを「神」「仏」「ブラフマン」「アラー」「道」……と呼ぶか、あるいは「自然」または「宇宙」と呼ぶかは、本質的な問題ではない。また、教祖は、それを深く直感した人間なのであり、教義・教団・儀式・修行法といったものは、その直感を他者に伝え共有するための媒介・手段にすぎず、しかもそれらは時代的・文化的に限定されていて絶対ではなく、また絶対でなくてよいものなのではないだろうか。絶対なのはそれを直感し、表現した〈宗教〉ではなく、人間を超えた「より大きな何ものか」そのものである。
言葉の悪い意味での〈宗教〉〔つまり原理主義〕と区別するために、そうした、より大きなものを直感し、すべてのものがみなそれに包まれていることに目覚めるような人間の心の奥底の領域を、私はあえて〈霊性〉と呼んでいる。これは、もちろん誤解さえなければ、たとえば「本当の宗教」とか「宗教の本質」とか呼んでもかまわない。
いのちの原点において、私は、私でないものとふれあい、私でないものに支えられているという事実(かつて滝沢克己がいった言葉を借りれば「インマヌエルの原事実」「人間の原点」)は、近代主義が見落としたことであるが、しかし本来理性と矛盾・対立するものではない。誰でも目を開けさえすれば見える、すべての人に共通の事実なのである。
そして、私のいのちが、どこまでも「私」のいのちでありながら、同時にいわば「私でないものから貸し与えられ、それに支えられている」いのちであるという事実にこそ、ニヒリズムを超える原点がある。つまり、人間のいのちは人間を超えた何かから与えられたものである以上、いのちの意味もある意味ではあらかじめ与えられているといっていいだろう。いのちには、かならず可能性・能力・潜在力が与えられている。個々の人間にとっては、その与えられた意味を発見できるかどうか、つまり与えられた可能性・潜在力を実現できるかどうかだけが問題であって、意味―可能性があるかどうかは問題にならないのだ。
そしてその事実がすべての人にとって共通の事実であるというところに、エゴイズムを超える、根源的な倫理―モラルが成立する原点があると思う。生かされて生きている私が、おなじく生かされて生きている他者に対して、それにふさわしく接するかどうかが、倫理の根源的な基準になるだろう。人類規模の平和も、そこからのみ可能になるだろう。
さらにいえば、同じ宇宙に包まれた宇宙の一員・一部として宇宙の他の一部にどう働きかけるかという視線で見た時、自然は単なる〈資源〉ではなく、自らとつながり、私を支えてくれるもの、ある意味で私の延長、と見えてくるだろう。そのことに気づいた時、私はもはや私を破壊することはできない。環境が私と本質的につながったものであることを深く自覚した上で営まれる経済は、近代の産業主義経済の妥当な面を受け継ぎながらも、決定的に変容したものになるだろう。
おわりに
そのような、〔原理主義的〕宗教の限界と近代主義の限界を超える〈霊性〉の自覚は、現在のところ残念ながら、日本の市民の大多数が共有するものにはなっていない。そういう意味で、既成・新・新新の宗教も近代主義―反宗教も含めて、私たちの文化―精神性はまだきわめて未熟だと思う。しかし、私たちがもはや〔原理主義的〕〈宗教〉をまったく必要としないほど〈霊性〉的に成熟した未来を思い描くことは、決して根拠のない願望ではない、とも思うのである。