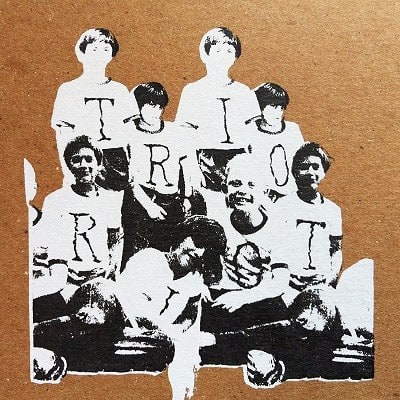齋藤嘉臣『ジャズ・アンバサダーズ 「アメリカ」の音楽外交史』(講談社選書メチエ、2017年)を読む。

かつて、アメリカ発の「ジャズ大使」「ジャズ外交」があった。本書は、それによる相手国でのジャズ受容史であるのと同時に、アメリカ本国においてジャズへの認識がどのように変容していったかを追ったものでもある。
なぜならば、アメリカにおけるジャズとは、少なくとも為政者たちから見れば、当初は一段劣る芸能に過ぎず、自国を代表する芸術とはみなされないからであった。また、共産主義に近いものであり、危険な抵抗の運動であるとも認識されていた。白人が中心に座る国にあって相容れない側面もあった。
事態は変化し続けた。やがて、ジャズは反共の道具、アメリカニズムを発信するためのプロパガンダとして企図されるようになった。そうなればイメージ戦略こそが大事になる。1956年に初めてのジャズ大使に選ばれたのはディジー・ガレスピーであり、人種統合の象徴たることを期待されたわけである。その次はベニー・グッドマンだが、いかにも古く、メンバーとの軋轢も大変なものがあったようだ。デューク・エリントン、デイヴ・ブルーベックらは「高級」でもあり、「反動」のおそれはなく、また音楽は当然素晴らしいものであったため、各地で大評判となった。
しかし、ミュージシャンの側が、政府の期待する役割にやすやすとはまり、一枚岩になったわけではない。チャールス・ミンガスなどは何をしでかすかわからないから忌避された。オーネット・コールマンなどフリージャズも警戒された。ルイ・アームストロングは人種統合の象徴としてうってつけだったが、かれは、アメリカで実現していないことをイメージとして対外発信する欺瞞を指摘し、批判した。
一方の相手国でも、国によって、状況はまるで異なっていた。フランスでは、早くから、ジャズは黒人の音楽であり、自由の文化であり、コスモポリタニズムやモダニズムを体現するものであった。ソ連や東欧では、アメリカニズムの浸透や体制破壊のエネルギーを恐れ、デタントの時代でもその活動は厳重な監視下に置かれた。逆に、反米の象徴となることもあった。アフリカでは、ランディ・ウェストンが、アメリカにおいてよりも熱狂的に受け容れられた。タイではジャズファンのプミポン国王がジャズ大使一行とのセッションを繰り広げた。日本は極めて熱心にジャズを受けとめた。
総じて言うことができるのは、このような過程を通じて、ジャズがもはやアメリカ発祥の文化ではあってもアメリカだけの文化ではなくなったという歴史が形成されてきたことである。それは実に多様で魅力的だ。例えば、中央線ジャズや旧ソ連圏のジャズの愛好家にとってみれば極めて当たり前のことだが、「本場」はあちこちに存在するのである。そしてそれぞれが言葉や顔つきや空気のように異なっている。
こうして本書によって国も時代もまたがって旅をしていくと、ウィントン・マルサリスに象徴されるような「ジャズをアメリカに取り戻そうとする動き」も、相対化して見ることができようというものだ。