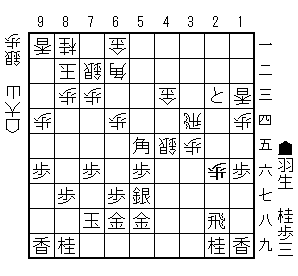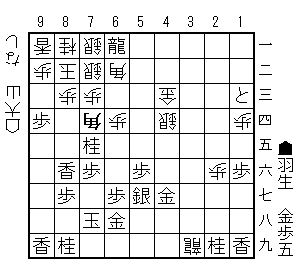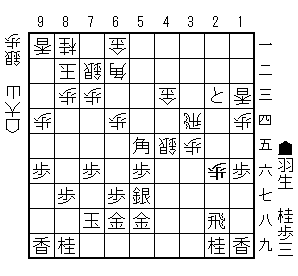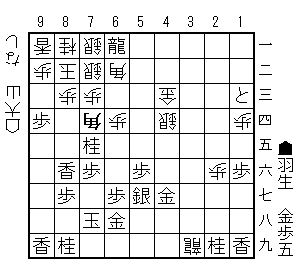今日の棋譜20180902
平成元年1月、羽生善治先生と第2期竜王戦です。羽生先生はまだ5段で初タイトル竜王を取るときですね。

大山先生の四間飛車で羽生先生は鷺ノ宮定跡みたいですが

32飛を見て棒銀にしました。

大山先生が良くある定跡手順にしたのが不思議ですが、実はこの将棋をもとに定跡化されたのかも。

金を上がって受けるのも定跡ですが、大山調という気もします。

この後も一番指された形になりました。(桂を跳ねずに45銀11角成というのもメジャーです。)

28飛には桂を跳ねて

銀桂交換でも飛車先を破れば居飛車十分に見えますが
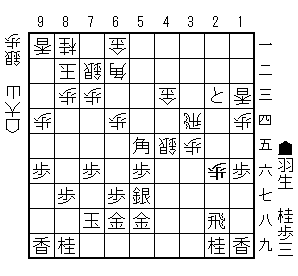
飛車先は止まるので簡単ではないです。

でも端を詰めて後手の歩切れでは、先手よしという気がします。

羽生先生は角取りを放置して香を取りました。

55銀には45の銀を取って

飛車をまわって成り込みます。角と桂香歩の交はやや駒得で、後手玉も堅くない、攻め駒4枚だからはっきり有利でしょう。

63銀というのが不思議な攻め方で、セオリーは小さい駒63香です。53銀と粘られたら面倒だったか。

銀だから大山先生が63同銀と取ったのもわかりますが、8筋が薄いのです。

竜取りにも75桂が利いて

72銀引75桂74角に83桂成。この寄せ方が当時話題になりました。

桂を捨てた後は57銀を寄せに使うのです。

銀は角と交換して

銀を取って銀を捨て(とは言っても取れないのですが)

72銀打に73金で詰んでいます。
定跡を調べたら、この場合は34飛ではなくて中飛車から中央をねらうべきだとありました。この将棋で先手よしがわかったので修正されたのでしょう。
端を詰めて飛車を成り込んだところでは先手有利です。強い若手ならばそのあとの寄せを間違えないでしょうが、羽生先生の寄せの感覚を鑑賞しましょう。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.40 棋譜ファイル ----
開始日時:1989/08/25
手合割:平手
先手:羽生善治5段
後手:大山十五世名人
手数----指手--
1 7六歩(77)
2 3四歩(33)
3 2六歩(27)
4 4四歩(43)
5 4八銀(39)
6 3二銀(31)
7 5六歩(57)
8 4二飛(82)
9 6八玉(59)
10 6二玉(51)
11 7八玉(68)
12 7二玉(62)
13 5八金(49)
14 8二玉(72)
15 3六歩(37)
16 7二銀(71)
17 6八銀(79)
18 4三銀(32)
19 2五歩(26)
20 3三角(22)
21 5七銀(68)
22 5四歩(53)
23 6八金(69)
24 1四歩(13)
25 9六歩(97)
26 9四歩(93)
27 1六歩(17)
28 6四歩(63)
29 3八飛(28)
30 3二飛(42)
31 3七銀(48)
32 5二金(41)
33 2六銀(37)
34 5一角(33)
35 4六歩(47)
36 1三香(11)
37 3五歩(36)
38 6二角(51)
39 3四歩(35)
40 同 銀(43)
41 4五歩(46)
42 4三金(52)
43 4四歩(45)
44 同 金(43)
45 4五歩打
46 4三金(44)
47 3七銀(26)
48 3三桂(21)
49 4六銀(37)
50 3五歩打
51 2八飛(38)
52 4五桂(33)
53 同 銀(46)
54 同 銀(34)
55 2四歩(25)
56 5五歩(54)
57 2三歩成(24)
58 3四飛(32)
59 5五角(88)
60 2六歩打
61 9五歩(96)
62 3六歩(35)
63 9四歩(95)
64 9二歩打
65 4八飛(28)
66 5四銀打
67 1三と(23)
68 5五銀(54)
69 4五飛(48)
70 4四銀(55)
71 2五飛(45)
72 3七歩成(36)
73 2一飛成(25)
74 4七と(37)
75 同 金(58)
76 3九飛成(34)
77 6三銀打
78 同 銀(72)
79 6一龍(21)
80 7一銀打
81 8六香打
82 7二銀(63)
83 7五桂打
84 7四角打
85 8三桂成(75)
86 同 銀(72)
87 6六銀(57)
88 5三銀(44)
89 7五銀(66)
90 7二銀(71)
91 7四銀(75)
92 同 歩(73)
93 8三香成(86)
94 同 銀(72)
95 8四銀打
96 7二銀打
97 7三金打
98 投了
まで97手で先手の勝ち