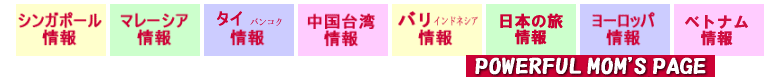
妻「また韓国の本買ってきたのね。そんなに買い込んで、読んでるの?忙しいのに。」
私「少しずつね。」
妻「やっぱり韓国に行くつもり?」
私「そうね。行きたいね。」
妻「何しに?」
私「まず、焼肉かな。本場でしょ?」
妻「何が好きなの。」
私「タン塩かな。」
妻「あら、タン塩は日本のものよ。」
私「タン塩は日本の発明なのか。」
妻「焼肉自体が日本のものなのね。」
私「え!」
そこで、調べてみました。情報は複数にあたって確認です。妻の言っていることを信じないわけではないのですが、念押しをしたいのです。「野村進」著、講談社刊(1996年)、「コリアン世界の旅」に見つけました。
日本の焼肉料理とは何だろうか。純然たる朝鮮料理と思われているが、本当にそうなのか。実際には、テーブルの上で肉を焼いて食べるというやり方が始まったのも、タン塩(清香園の張貞子の発案によるもので、「それまでもタンは焼肉に使っていたんですけど、どこの店もタレにつけて焼いていたんです。でも、ヨーロッパに旅行に行ったとき、レストランでタンをハムみたいに燥製にしたのが出てきたんですよ。それを見て、うちのタンを塩焼きにしたらどうかなあ、と。帰ってきて、塩焼きしたのをお酢と塩とレモンのタレにつける食べ方を考えたんです」)という人気メニューが生まれたのも、朝鮮半島ではなくここ日本の地でのことなのである。付け加えるなら、ユッケ(牛肉のたたき)に卵黄を載せて出したのも、生センマイ(牛の第三胃)を千切りにして酢醤油で食べさせたのも、日本でのことと言われている。韓国の焼肉店でもしタン塩が出てきたら、それは日本から逆輸入されたメニューなのだと思ってまちがいない。
「張貞子 (チャン・ジョンジャ)」 は、1919年にソウルの「張」家に生まれます。1950年、在日韓国大使館の初の政治顧問として駐日していた夫「金修史」のもとに、4人の子供を連れて来日します。1952年、まだ日本に韓国料理店がないころ、親戚の勧めで銀座に「清香園」を開店します。「分量や作り方を文にはできない、料理は自分の舌と身体で覚えるものだ」という信念から86歳になるまで「清香園」のレシピを紹介しなかった張氏も、2005年7月には、「ブックマン社」から「時の香り 清香園の韓国料理」という料理本を出版しています。
その本の記述によると、今日の韓国料理(한국 요리)は、王や両班のための宮廷料理と、庶民の知恵が生んだ郷土料理の融合・発展したものなのだそうです。王朝時代、韓国の料理人は女性だったそうです。現代でも、名高いホテルの料理長は代々女性と決められているなど、韓国料理店の厨房では女性を多く見かけるそうです。張氏は、両班(양반)の家系に生まれ、基本の調味料はすべて家庭で手作りしたものを使っていたそうです。韓国では上流家庭ほど薄味で、上品な仕上がりを好むそうです。
私「じゃ、韓国に焼肉はないの?」
妻「そんなことはないわよ。あるわよ。でも、別物ね。」
韓国で「焼肉」と言えば、普通は「プルコギ(불고기)」を指す。ハングルで「火の肉」を意味するこの料理は、だが、日本の焼肉とは似て非なるものだ。韓国では、真ん中がこんもり盛り上がった鉄鍋に、タレをからませた肉をどさりと載せて焼く。この鍋は誇張するとスペインのソンブレロのような形で、流れ落ちてくる肉汁はソンブレロのつばのところで受け、肉を少しつけたり後でうどんを煮込んだりして食べる。日本の焼肉よりは、ジンギスカンに近い。
妻「プルコギを食べたんだけど、ジンギスカンみたいだったわよ。」
私「ジンギスカンは好きだから、いいね。」
妻「むちゃくちゃ甘いのよ。好みじゃないと思うわよ。」
いま日本にある焼肉のスタイルを作り上げたのは、私は断言してよいと思うが、在日韓国・朝鮮人と帰化者たちなのである。食道園の社長で全国焼肉店経営者協会(現在は、「事業協同組合 全国焼肉協会」)の会長も務める江崎政雄(現在は、「叙々苑」の新井泰道氏)によれば、全国2万軒の焼肉店のおよそ9割が在日か帰化者とその子孫の経営ではないかという。「焼肉文化」というものがあるなら、それはとりもなおさず朝鮮半島から日本に来て住み着いた人々の文化なのである。
焼肉つながりで、「前川恵司」著、「PHP研究所」刊(1997年)、「なぜだ韓国 なるほど韓国」からも引用しておきます(一部省略)。
子どもたちがカルチャーショックを受けたのは、焼き肉屋に入った時のことだ。骨付きカルビ(갈비、galbi、ばら肉のこと)を焼きはじめて、女店員が大きな裁縫ばさみをもってきて、肉をじょきじょき切りはじめた。食べやすい大きさにするためで、どの店でもやるサービスなのだが、そのときに、「食べごろですから切りますよ」とか、「失礼します」と一言、客に声をかけるでもない。
つっかけを引きずりながらやってきて、ぶっちょう面のまま裁縫ばさみを突き出し、焼けた肉を切りだす。いきなり、裁縫ばさみを目の前に突き出され、子どもは反射的に座ったまま後ずさりした。そのショックで食欲をなくし、もう肉に手をつけなかった。
アメリカの大学で勉強している25歳の韓国女性が教えてくれた。「韓国社会は、職業への貴賤感が消えていない社会だから、焼き肉屋の店員というだけで、学校も出してもらうことができない家に育った、という先入観で見られる。汚い仕事ときれいな仕事。頭を使う仕事と力仕事。職業への差別感が強いから、自虐的になってしまうのよ。」
のれんを下げて何代目を誇る気風は、韓国の商人道には薄い。店が繁盛して、金回りが良くなると、店ごと売ってしまうケースが多いのだ。その金で、お抱え運転手をアゴで使うような、もっときれいな「事業」にのり出してこそ、偉くなったといえるのだ。じいさんのころからの小商いを、手堅く続けているなどということは、「うだつの上がらないやつらだ」と見られ、むしろ馬鹿にされてしまう。
極論すれば、誰もが力あるものを至上のものとしている。だから、財閥(재벌)があって商人がいない。巨大なモールのようなショッピングビルやデパートはたくさんある。その他は、露天や屋台、それにアパートの下の店、あとはアーケードも何もない市場(시장)がふつうだ。日本のような華やかな商店街は少ない。
この記述に従うと、料理店の老舗などというのはないのだから、この店に行くとハズレがない、という店はないことになります。最新の情報を手に入れて、中りをつけるしかないようです。そんなエネルギーは割きたくないから、これはわが妻「あみ」に任せることにしましょう。妻なら、ホテルの従業員や市場のおばちゃんに普通に話しかけて、活きのいい情報を手に入れるだろうから。
この店員の愛想の悪さで韓国人を責めることはできなさそうです。中国に関する本でも同じようなことを読んだことがありますし、ドイツに関する本でも読んだことがあります。ことによると、店員の愛想の悪いのが「グローバル・スタンダード」、「世界の常識」で、店員の愛想の良さが「ガラパゴス」、「日本の非常識」なのかも知れません。しかし、どの職業にもその技術の優秀なプロがいて、自信を持って生きており、周囲もまた世間も賞賛するという社会が悪いはずがありません。例えば、みなが社長では社会が動いてはいきませんし、社長になれなかった者が不満を抱いている社会では、社会全体がストレスを感じてしまいます。ひょっとすると、韓国が世界でも上位の自殺率を示すのはそのせいかも知れません。
もう一つ、韓国の作家「韓水山」著、徳間書店刊(1995年)、「隣の日本人」から引用してみます。
食文化の本質がこのように違うなかで、もう一つ明らかに違うのが食堂のありようである。
韓国でいつも羨ましそうに話されるのが、代を継いで商いをしている日本の食堂のことである。「食べ物の商い」に対する認識がかなり改まったとはいうものの、まだ韓国では「水商売」のように見下げて見る傾向がある。
味が評判となって客も絶えずに上々の商いをしていたかと思うと、さっさと転業してしまうのが韓国である。だからといって、代を継ぐ店もないわけではないが、だいたいにおいて食堂は店を開いたら、すぐ閉じるということを繰り返している。
また、どういうわけか韓国の食堂は、誰にでもできる商いになっている。転職した官吏も、会社をつぶした事業家も、やることが見つからなければ始めるのが食堂である。それで韓国の食堂はいつも「祝い鉢」を並べた「新装開店」が多い。
これでは、ガイド本を頼りに美味しい料理を食べさせてくれる店を訪ねることはできそうもありません。取材時と出版時とは時間的にかなりのギャップがありますから、取材者が美味しいと勧める店は私たちが訪れるときにはなくなっているかも知れません。最後の手段、「大衆は過たず」で、客の入りを覗いて判断しましょうか。妻は言っています。「私の鼻に任せなさい。美味しい店は美味しい匂いがするの。私の鼻は嘘をつかないの。」 はい、お任せします。
(この項 健人のパパ)
| Trackback ( 0 )
|
|