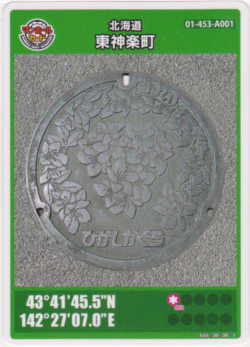留萌市の塩数の子は国内シェアの50%を誇る特産品です。
ニシン漁が盛んなころは大変な賑わいだったと思います。
まぁ、その原料は今はカナダやアラスカ産なのですが。
ということで、マンホールカードのモチーフはまずは数の子です。
マスコットキャラクターの名は「KAZUMO(かずも)」と言うそうで。
それから「日本の夕陽百選」に選ばれた黄金岬から見た夕陽、そしてカモメ。
“地平線を航行する船舶”も描かれているのですが、
地平線を航行するなら留萌に寄港しないのではと思ってしまった。
でもこれは船舶の行き先を照らす灯台をクローズアップしているのですね。
黄金岬からの灯台が、付近を航行する船舶の安全を守っているわけだ。
黄金岬からの夕陽、私はまだ観たことがありません。
その景観はいつか、観てみたいです。
ところで2017年12月26日に発達した低気圧によって海底に沈んだ留萌港西防波堤南灯台。
10月14日に再点灯しました。
留萌の海、世界三大波濤の一つだそうで。
私も留萌で吹雪に遭い死にそうになったことがあります。
厳しい海だなぁ…。