横山拓也『walk in closet』(劇団大阪定期公演、2017年)
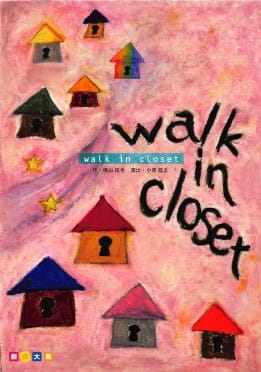 同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。
同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。
冒頭から、記録的な豪雨で河が反乱し、道路が通行止めになってしまい、登場人物たちがみんな主役の政次の家に缶詰状態になって、逃げ場がないという設定が作り出されるのだが、これなんか実に上手い作りである。
登場人物は、政次、母・清美、隣人の椿本、政次がアルバイトをしているカフェの店長の平良と店員の梓のぶ代、さらに父・利弘とかつて政次が告発したことで体操教室を首になり父・利弘が就職などの世話をしてきた小西である。
政次がアルバイトをしているカフェの店長の平良がゲイだという噂があるという話から、政次のクローゼットにゲイのDVDがあったという母・清美の話から、さらに政次を好いている梓が政次に振られたと言ったり、そして平良に小西が政次をゲイの世界に引きずり込むなという発言などなどがあって、梓が勝手に政次はゲイだと口にしてしまう。
そのテンポの良い、大阪弁のやり取りは、小気味よい。一人ひとりの特徴が際立っていて、その特徴的な発言や会話のやり取りの結果、大団円に突っ込んでいく。普通は家族のあいだではこういう問題は触れずにおこうという風になるものだ。それでは芝居が回っていかないので、缶詰状態という設定が作られ、第三者が普通なら言わないでおくところを、口にしてしまう。
自称カウンセラーの椿本は、普通ならスルーすべきところを「その問題をほっておいたらあかんのんとちゃう」とか言って、話の流れを作者の都合のいい方向に導く役目をもっている。
缶ビールを飲んで滑舌が良くなった小西は、政次のせいで人生を狂わされたと思っているのか、政次に直接口出しをしないが、平良を責めて、話をそちらの方向に向けようとする。
政次に振られた梓、この娘もおもしろい。世間の常識的な言葉にツッコミをいれ、高い次元からものを言っているように見えて、じつは政次に振られた腹いせだったり。
平良の演技もいい。ゲイだからといって、やたらとオネエ風の仕草をしないところがいい。しかし、ちょっとしたところにその雰囲気を見せる。26才とはいえ、ゲイということで苦労してきた大人らしく、政次を気遣って、DVDの件を自分のせいだと引き受けたり。
小西は、酒が進むに連れて本性、というよりもこれまで腹の中にためて来たものを出す。
一番戸惑っているのが、母・清美と政次自身だ。政次は台詞にあったように、自分で自分が分からない。大西がその活気のない感じ、ぼんやりしたような表情でそれをよく表していた。
母・清美は、自分の腹を痛めた子にどう接したらいいのか分からない。ただでさえ男の子は20才ともなれば、自分からは完全に離れていくものだ。その上にゲイだと言われたら…。でもなんとか理解しようとして、「好きなようにしたらいい」と言えば、「好きなようにってなんや」と息子から突き放される。そういう心許なさを名取が好演していた。激しい動きや台詞はないが、心の中を繊細に表す演技だった。
新鮮な感じのする芝居だった。芝居っていいなと思う仕上がりだった。
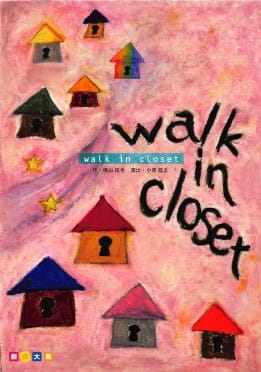 同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。
同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。冒頭から、記録的な豪雨で河が反乱し、道路が通行止めになってしまい、登場人物たちがみんな主役の政次の家に缶詰状態になって、逃げ場がないという設定が作り出されるのだが、これなんか実に上手い作りである。
登場人物は、政次、母・清美、隣人の椿本、政次がアルバイトをしているカフェの店長の平良と店員の梓のぶ代、さらに父・利弘とかつて政次が告発したことで体操教室を首になり父・利弘が就職などの世話をしてきた小西である。
政次がアルバイトをしているカフェの店長の平良がゲイだという噂があるという話から、政次のクローゼットにゲイのDVDがあったという母・清美の話から、さらに政次を好いている梓が政次に振られたと言ったり、そして平良に小西が政次をゲイの世界に引きずり込むなという発言などなどがあって、梓が勝手に政次はゲイだと口にしてしまう。
そのテンポの良い、大阪弁のやり取りは、小気味よい。一人ひとりの特徴が際立っていて、その特徴的な発言や会話のやり取りの結果、大団円に突っ込んでいく。普通は家族のあいだではこういう問題は触れずにおこうという風になるものだ。それでは芝居が回っていかないので、缶詰状態という設定が作られ、第三者が普通なら言わないでおくところを、口にしてしまう。
自称カウンセラーの椿本は、普通ならスルーすべきところを「その問題をほっておいたらあかんのんとちゃう」とか言って、話の流れを作者の都合のいい方向に導く役目をもっている。
缶ビールを飲んで滑舌が良くなった小西は、政次のせいで人生を狂わされたと思っているのか、政次に直接口出しをしないが、平良を責めて、話をそちらの方向に向けようとする。
政次に振られた梓、この娘もおもしろい。世間の常識的な言葉にツッコミをいれ、高い次元からものを言っているように見えて、じつは政次に振られた腹いせだったり。
平良の演技もいい。ゲイだからといって、やたらとオネエ風の仕草をしないところがいい。しかし、ちょっとしたところにその雰囲気を見せる。26才とはいえ、ゲイということで苦労してきた大人らしく、政次を気遣って、DVDの件を自分のせいだと引き受けたり。
小西は、酒が進むに連れて本性、というよりもこれまで腹の中にためて来たものを出す。
一番戸惑っているのが、母・清美と政次自身だ。政次は台詞にあったように、自分で自分が分からない。大西がその活気のない感じ、ぼんやりしたような表情でそれをよく表していた。
母・清美は、自分の腹を痛めた子にどう接したらいいのか分からない。ただでさえ男の子は20才ともなれば、自分からは完全に離れていくものだ。その上にゲイだと言われたら…。でもなんとか理解しようとして、「好きなようにしたらいい」と言えば、「好きなようにってなんや」と息子から突き放される。そういう心許なさを名取が好演していた。激しい動きや台詞はないが、心の中を繊細に表す演技だった。
新鮮な感じのする芝居だった。芝居っていいなと思う仕上がりだった。










 子ども劇場などといいながら、来ているのはジジババばかりの「ジジババ劇場化」している現状に、こういう催し物をすることになったのかどうか、委細は知らない。
子ども劇場などといいながら、来ているのはジジババばかりの「ジジババ劇場化」している現状に、こういう催し物をすることになったのかどうか、委細は知らない。 びわ湖ホールのプロデュースオペラとしてワグナーの『ラインの黄金』を見てきた。「ニーベルングの指環」第四部のうちの序夜になる作品である。
びわ湖ホールのプロデュースオペラとしてワグナーの『ラインの黄金』を見てきた。「ニーベルングの指環」第四部のうちの序夜になる作品である。 まずラインの乙女たちと小人のアルベリヒのやり取りはライン川の水中で行われるという設定になっている。この舞台では、舞台前面に置かれたシルクスクリーンのようなものと舞台奥のスクリーンに映し出された水中の揺らめく中をラインの乙女たちが泳ぎ回る映像と、個々の乙女が歌うときに生身の役者を登場させることで、じつに見事に水中の雰囲気を出していた。私はこれを見た時点で完全にこの演出に感心させられた。
まずラインの乙女たちと小人のアルベリヒのやり取りはライン川の水中で行われるという設定になっている。この舞台では、舞台前面に置かれたシルクスクリーンのようなものと舞台奥のスクリーンに映し出された水中の揺らめく中をラインの乙女たちが泳ぎ回る映像と、個々の乙女が歌うときに生身の役者を登場させることで、じつに見事に水中の雰囲気を出していた。私はこれを見た時点で完全にこの演出に感心させられた。 舞台は1972年、戦後27年で、まもなく本土復帰を迎えようとしている沖縄、ゴザ(今の那覇)。新里あやが営んでいるバー「アヤ」。彼女が戦中に17才で日本兵たちにレイプされて生まれた長男の平和、黒人米兵と結婚して生まれた混血児の洋子、渡嘉敷島から出てきた叔母のヤスとで暮らしている。
舞台は1972年、戦後27年で、まもなく本土復帰を迎えようとしている沖縄、ゴザ(今の那覇)。新里あやが営んでいるバー「アヤ」。彼女が戦中に17才で日本兵たちにレイプされて生まれた長男の平和、黒人米兵と結婚して生まれた混血児の洋子、渡嘉敷島から出てきた叔母のヤスとで暮らしている。 泉ヶ丘にあるビッグ・アイのホールで桂米朝一門会があった。去年も行った。去年は満員御礼だったが、今年はどういうわけかガラガラ。半分も入っていなかったのではないだろうか。どうしてなんだろう。
泉ヶ丘にあるビッグ・アイのホールで桂米朝一門会があった。去年も行った。去年は満員御礼だったが、今年はどういうわけかガラガラ。半分も入っていなかったのではないだろうか。どうしてなんだろう。 シャルル・グノーのオペラ『ファウスト』を観てきた。内容はゲーテの小説で有名なやつだ。老学者のファウストがメフィストフェレスに魂を売って「若さ」を取り戻し、グレートヒェンに恋して妊娠させるが、グレートヒェンはファウストに捨てられ嬰児殺しで投獄されて狂気し、ファウストは最後に悪魔に魂を奪われる寸前で救済されるという話だ。
シャルル・グノーのオペラ『ファウスト』を観てきた。内容はゲーテの小説で有名なやつだ。老学者のファウストがメフィストフェレスに魂を売って「若さ」を取り戻し、グレートヒェンに恋して妊娠させるが、グレートヒェンはファウストに捨てられ嬰児殺しで投獄されて狂気し、ファウストは最後に悪魔に魂を奪われる寸前で救済されるという話だ。 台本の作者は青木豪、演出は兵庫県立ピッコロ劇団の岡田力。劇団大阪の本公演とはいえ、演出を外部から招いている点で、ちょっと異色の作品といえる。当日もらったパンフレットの「ごあいさつ」にも「いつもの劇団大阪公演とは一味違った風合いの世界」と書かれている通り。
台本の作者は青木豪、演出は兵庫県立ピッコロ劇団の岡田力。劇団大阪の本公演とはいえ、演出を外部から招いている点で、ちょっと異色の作品といえる。当日もらったパンフレットの「ごあいさつ」にも「いつもの劇団大阪公演とは一味違った風合いの世界」と書かれている通り。 5年前に第25回の定期公演で『アイーダ』を観てからちょっと久しぶりの伊丹市民オペラだ。今年は上さんと行った。
5年前に第25回の定期公演で『アイーダ』を観てからちょっと久しぶりの伊丹市民オペラだ。今年は上さんと行った。 以前、アンサンブル・シュッツという大阪の宗教音楽を専門にやっている楽団の演奏と歌でこれを聞いたことがあるが、常日頃からバッハのコラールなどを教会で演奏している団体だけあった、じつに切れの良い、素晴らしい演奏だった。
以前、アンサンブル・シュッツという大阪の宗教音楽を専門にやっている楽団の演奏と歌でこれを聞いたことがあるが、常日頃からバッハのコラールなどを教会で演奏している団体だけあった、じつに切れの良い、素晴らしい演奏だった。 桂米朝一門会が堺市の市民寄席であったので上さんと行ってきた。若いころに子連れで一・二度行ったことがあるので、本当に久しぶりだ。堺市民会館が現在建て替え中ということで、泉ヶ丘にあるビッグ・アイでの公演となった。駅のすぐ前で便利。座席も指定席で、急がなくていいから、泉ヶ丘で食事をしてからのんびり行けた。
桂米朝一門会が堺市の市民寄席であったので上さんと行ってきた。若いころに子連れで一・二度行ったことがあるので、本当に久しぶりだ。堺市民会館が現在建て替え中ということで、泉ヶ丘にあるビッグ・アイでの公演となった。駅のすぐ前で便利。座席も指定席で、急がなくていいから、泉ヶ丘で食事をしてからのんびり行けた。