佐藤賢一『褐色の文豪』(文芸春秋、2006年)
 『三銃士』『モンテクリスト伯』『王妃マルゴ』などの小説で有名なアレクサンドル・デュマの伝記的小説である。いちおう、フランス文学に関心をもつものとして、デュマがどんな小説を書いていたか程度のことは知っていたけれども、こうやって小説の形で読むと、シャルル・ノディエとの関わりやあの文豪ビクトル・ユゴーを歯軋りさせた新聞小説での大活躍など有名な人物との関わりや、時代状況が手に取るように分って、じつにためになる。
『三銃士』『モンテクリスト伯』『王妃マルゴ』などの小説で有名なアレクサンドル・デュマの伝記的小説である。いちおう、フランス文学に関心をもつものとして、デュマがどんな小説を書いていたか程度のことは知っていたけれども、こうやって小説の形で読むと、シャルル・ノディエとの関わりやあの文豪ビクトル・ユゴーを歯軋りさせた新聞小説での大活躍など有名な人物との関わりや、時代状況が手に取るように分って、じつにためになる。
興味深く読んだところは二つある。一つは、デュマが作家として活躍を始めて、一躍パリの有名人になった頃に起きた7月革命である。王政復古がなり、ギロチンにかけられたルイ16世の弟であったルイ18世が国王になるが、彼の後を継いだシャルル10世が暴君の名をほしいままにして、矢継ぎ早に彼の支持基盤である大地主に有利な政策を展開していったために7月革命が起きる。そして政治的には自由主義を標榜するオルレアン公ルイ・フィリップが立憲王政を継承することになる。もちろん議会が実施的な政治を行うという意味で立憲王政なのだが、大地主から大ブルジョワに権力が移行しただけの革命とは名ばかりのものであったことは、まぁ一般に歴史の本などで言われていることだ。だがそれをそこに生きたデュマという人物がどのように関わっていったのかということを、生きた人間の物語として提示されると、その相貌もずいぶんと変わって見える。パリのバリケード戦というのは、パリの通りが狭いのですぐできることで有名で、たしかフローベールの『感情教育』の冒頭にも描かれていたのは7月革命の余韻ではなかったかな(記憶違いかもしれない)。それでまた48年には2月革命が起き、クーデタがおきて第二帝政になるときにも同じようなことがおきたため、ナポレオン三世がオスマン将軍に命じて、パリの大改造を行い、簡単にバリケードが気づけないように通りを広くしたという話がある。
二つ目には、新聞小説ということだ。新聞小説といえばバルザックだと思っていたが、たしかに新聞小説が新聞の発行部数を延ばす働きを演じるほどに読者をひきつけるようになったというのはデュマの『三銃士』が最初だったのかもしれない。このなかでも描かれているように、革命前はフランスの識字率はほんとうに低いもので、読者といってもたかが知れているが、19世紀になると学校教育もじょじょに整ってきて、識字率が上がってくる。それにともなって、安価で手に入る新聞で読める小説は読者大衆をひきつけるのに格好のメディアだっただろう。日本でも夏目漱石の小説はほとんど新聞小説で発表されたものだ。新聞好きのフランス人という特徴はこの時代にできたのかもしれない。
新聞小説作家の売れっ子ぶりも書かれているが、それはもう現代の売れっ子漫画家、たとえば手塚治虫の様子を見ているような風に描かれている。もちろん作者の佐藤賢一がそうなのだろうし、現代の売れっ子作家のイメージをそこに投影していることは間違いない。そういう意味でも現代のように文芸が商業ベースにのって、作家をあっという間に時代の寵児にしたり、あっという間に没落させたりというのは、デュマの時代に始まったとみていいだろう。
たしかにユゴーの『レ・ミゼラブル』やバルザックの小説に比べると時代がルイ13世とかルイ14四世とかのように17世紀であってみれば、あまりに古臭い感じがしないでもないから、それが『レ・ミゼラブル』のように今日でもいまだにミュージカルの題材となったりするところと違う。ただ、絶対王政に入る以前のフランス人にはまだ自由闊達なところがあっただろうから、それが『三銃士』のようなはらはらどきどきの活劇的作品を生み出す政治的土壌であったのだろう。
それにしても『三銃士』なんて、少年少女向けのリライトしたものでなくて、そのまま読めるのだろうか? 岩波文庫にありました。
 『三銃士』『モンテクリスト伯』『王妃マルゴ』などの小説で有名なアレクサンドル・デュマの伝記的小説である。いちおう、フランス文学に関心をもつものとして、デュマがどんな小説を書いていたか程度のことは知っていたけれども、こうやって小説の形で読むと、シャルル・ノディエとの関わりやあの文豪ビクトル・ユゴーを歯軋りさせた新聞小説での大活躍など有名な人物との関わりや、時代状況が手に取るように分って、じつにためになる。
『三銃士』『モンテクリスト伯』『王妃マルゴ』などの小説で有名なアレクサンドル・デュマの伝記的小説である。いちおう、フランス文学に関心をもつものとして、デュマがどんな小説を書いていたか程度のことは知っていたけれども、こうやって小説の形で読むと、シャルル・ノディエとの関わりやあの文豪ビクトル・ユゴーを歯軋りさせた新聞小説での大活躍など有名な人物との関わりや、時代状況が手に取るように分って、じつにためになる。興味深く読んだところは二つある。一つは、デュマが作家として活躍を始めて、一躍パリの有名人になった頃に起きた7月革命である。王政復古がなり、ギロチンにかけられたルイ16世の弟であったルイ18世が国王になるが、彼の後を継いだシャルル10世が暴君の名をほしいままにして、矢継ぎ早に彼の支持基盤である大地主に有利な政策を展開していったために7月革命が起きる。そして政治的には自由主義を標榜するオルレアン公ルイ・フィリップが立憲王政を継承することになる。もちろん議会が実施的な政治を行うという意味で立憲王政なのだが、大地主から大ブルジョワに権力が移行しただけの革命とは名ばかりのものであったことは、まぁ一般に歴史の本などで言われていることだ。だがそれをそこに生きたデュマという人物がどのように関わっていったのかということを、生きた人間の物語として提示されると、その相貌もずいぶんと変わって見える。パリのバリケード戦というのは、パリの通りが狭いのですぐできることで有名で、たしかフローベールの『感情教育』の冒頭にも描かれていたのは7月革命の余韻ではなかったかな(記憶違いかもしれない)。それでまた48年には2月革命が起き、クーデタがおきて第二帝政になるときにも同じようなことがおきたため、ナポレオン三世がオスマン将軍に命じて、パリの大改造を行い、簡単にバリケードが気づけないように通りを広くしたという話がある。
二つ目には、新聞小説ということだ。新聞小説といえばバルザックだと思っていたが、たしかに新聞小説が新聞の発行部数を延ばす働きを演じるほどに読者をひきつけるようになったというのはデュマの『三銃士』が最初だったのかもしれない。このなかでも描かれているように、革命前はフランスの識字率はほんとうに低いもので、読者といってもたかが知れているが、19世紀になると学校教育もじょじょに整ってきて、識字率が上がってくる。それにともなって、安価で手に入る新聞で読める小説は読者大衆をひきつけるのに格好のメディアだっただろう。日本でも夏目漱石の小説はほとんど新聞小説で発表されたものだ。新聞好きのフランス人という特徴はこの時代にできたのかもしれない。
新聞小説作家の売れっ子ぶりも書かれているが、それはもう現代の売れっ子漫画家、たとえば手塚治虫の様子を見ているような風に描かれている。もちろん作者の佐藤賢一がそうなのだろうし、現代の売れっ子作家のイメージをそこに投影していることは間違いない。そういう意味でも現代のように文芸が商業ベースにのって、作家をあっという間に時代の寵児にしたり、あっという間に没落させたりというのは、デュマの時代に始まったとみていいだろう。
たしかにユゴーの『レ・ミゼラブル』やバルザックの小説に比べると時代がルイ13世とかルイ14四世とかのように17世紀であってみれば、あまりに古臭い感じがしないでもないから、それが『レ・ミゼラブル』のように今日でもいまだにミュージカルの題材となったりするところと違う。ただ、絶対王政に入る以前のフランス人にはまだ自由闊達なところがあっただろうから、それが『三銃士』のようなはらはらどきどきの活劇的作品を生み出す政治的土壌であったのだろう。
それにしても『三銃士』なんて、少年少女向けのリライトしたものでなくて、そのまま読めるのだろうか? 岩波文庫にありました。










 小学一年生のときに担任だったA先生は持ち上がりで二年生も担任で、その担任が終わる頃、なぜだか一人呼び出されて、一冊の本をプレゼントされた。ユゴーの「ああ無情!」だった。なぜこの先生が私にだけそんな本をプレゼントしてくれたのか、まったく分らない。親がなにかA先生にお返しをしなければならないと思わせるようなことをしたはずもなく、特別に出来がよくて「褒美」にくれたわけでもない。あるいは一人ひとりに個別に渡していたのだろうか?それで自分ひとりがもらったと思っていたのだろうか?そうだとしたらその出費や大変なものになっただろうから、そんなはずもない。まぁどうでもいいことなのだが、いまだに夢だったのかもしれないと思ってしまう事実の出来事だ。
小学一年生のときに担任だったA先生は持ち上がりで二年生も担任で、その担任が終わる頃、なぜだか一人呼び出されて、一冊の本をプレゼントされた。ユゴーの「ああ無情!」だった。なぜこの先生が私にだけそんな本をプレゼントしてくれたのか、まったく分らない。親がなにかA先生にお返しをしなければならないと思わせるようなことをしたはずもなく、特別に出来がよくて「褒美」にくれたわけでもない。あるいは一人ひとりに個別に渡していたのだろうか?それで自分ひとりがもらったと思っていたのだろうか?そうだとしたらその出費や大変なものになっただろうから、そんなはずもない。まぁどうでもいいことなのだが、いまだに夢だったのかもしれないと思ってしまう事実の出来事だ。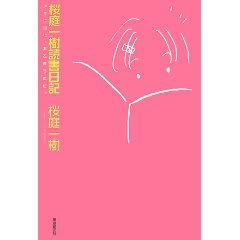 同郷の作家なのに(しかも同じ高校の出身、といっても一回りくらい年齢が違うから当たり前だけど)、存在さえも知らなかっただけに、そんな作家がいるのかと昨年の直木賞をきっかけに知ったときには、多少ともうれしかったのを覚えている。しかも、この読書日記を読むと、最近でもちょこちょこ紅緑村の両親のところに滞在して、あのI書店なんかに出入りして、大量の本を買っているなんて。
同郷の作家なのに(しかも同じ高校の出身、といっても一回りくらい年齢が違うから当たり前だけど)、存在さえも知らなかっただけに、そんな作家がいるのかと昨年の直木賞をきっかけに知ったときには、多少ともうれしかったのを覚えている。しかも、この読書日記を読むと、最近でもちょこちょこ紅緑村の両親のところに滞在して、あのI書店なんかに出入りして、大量の本を買っているなんて。 私も高校生の頃にボート部の連中の影響で「ブンガク」なるものに目覚めたというような話はすでに書いたと思うのだが、それ以来、学校からの帰り道とか休日とかに、いまは寂れてしまった商店街の一角にあるI書店に通うように出入りしては、小説などを買い求めていた。ここで、三島由紀夫の「豊饒の海」とか「奔馬」とか、あるいは「廃市」(これは三島ではなくて、えーっと福永武彦)などを買おうかどうしようかさんざん悩んだ思い出がある。この読書日記を読んでいると高校生とか中学生とかの彼女も同じだったんだね。まぁ金がないからみんな同じようなもんだろうけど。(右の絵は出身高校の校章。二枚の柏葉がロゴスとパトスを表すってことになってます。なかなかしゃれているでしょ。)
私も高校生の頃にボート部の連中の影響で「ブンガク」なるものに目覚めたというような話はすでに書いたと思うのだが、それ以来、学校からの帰り道とか休日とかに、いまは寂れてしまった商店街の一角にあるI書店に通うように出入りしては、小説などを買い求めていた。ここで、三島由紀夫の「豊饒の海」とか「奔馬」とか、あるいは「廃市」(これは三島ではなくて、えーっと福永武彦)などを買おうかどうしようかさんざん悩んだ思い出がある。この読書日記を読んでいると高校生とか中学生とかの彼女も同じだったんだね。まぁ金がないからみんな同じようなもんだろうけど。(右の絵は出身高校の校章。二枚の柏葉がロゴスとパトスを表すってことになってます。なかなかしゃれているでしょ。) 第3回ファンタジーノベル大賞を受賞した作品ということだが、だいたいこの賞の受賞作がそうであるように、どこがファンタジー?と首を傾げざるをえない。まぁ主人公が一つの肉体を共有する双子のバルタザールとメルヒオールで、幽体離脱をするということが、まさにファンタジーなんだろう。
第3回ファンタジーノベル大賞を受賞した作品ということだが、だいたいこの賞の受賞作がそうであるように、どこがファンタジー?と首を傾げざるをえない。まぁ主人公が一つの肉体を共有する双子のバルタザールとメルヒオールで、幽体離脱をするということが、まさにファンタジーなんだろう。 昨年、直木賞を受賞した桜庭一樹の長編小説で、舞台が彼女の出身である鳥取県西部に置かれ、その山の民とかたたらといった神話を題材にした、しかし時代は現代に置かれている、不思議な小説。
昨年、直木賞を受賞した桜庭一樹の長編小説で、舞台が彼女の出身である鳥取県西部に置かれ、その山の民とかたたらといった神話を題材にした、しかし時代は現代に置かれている、不思議な小説。 タイトルの面白さに惹かれて読んでみた。「猿蟹合戦とは何か」と「国語入試問題必勝法」が面白かった。
タイトルの面白さに惹かれて読んでみた。「猿蟹合戦とは何か」と「国語入試問題必勝法」が面白かった。 作者が小説の中で造形する人物が作者ではないことは当然のことだし、ましてや作者の分身とか一部などということも篠田節子くらいになると、ありえない。それを承知の上で、この小説で描かれる主人公の幹郎という人物が私は嫌いだ。はっきり言って、言行不一致、言っている理想と彼の実際にやっている行動がまったく違っている、しかもその違っているということに本人が気づいていないという、典型的な頭でっかち人間、口あたりのいいことを言っているが、現実はそうなっていないことをまったく分っていない、「民主的」(かっこ付きだ)人間といわれるような奴らの典型である。問題は作者がそのことを自覚して書いているのかどうかということもある。私は篠田節子くらいの作家ならそのことをよく分かって書いたのではないかと思うのだが、読みながら、何度もクビをひねった。でも幹郎の妻の由美子に批判的なセリフを言わせていることから考えても、そういうことを狙って書いたのだろう。
作者が小説の中で造形する人物が作者ではないことは当然のことだし、ましてや作者の分身とか一部などということも篠田節子くらいになると、ありえない。それを承知の上で、この小説で描かれる主人公の幹郎という人物が私は嫌いだ。はっきり言って、言行不一致、言っている理想と彼の実際にやっている行動がまったく違っている、しかもその違っているということに本人が気づいていないという、典型的な頭でっかち人間、口あたりのいいことを言っているが、現実はそうなっていないことをまったく分っていない、「民主的」(かっこ付きだ)人間といわれるような奴らの典型である。問題は作者がそのことを自覚して書いているのかどうかということもある。私は篠田節子くらいの作家ならそのことをよく分かって書いたのではないかと思うのだが、読みながら、何度もクビをひねった。でも幹郎の妻の由美子に批判的なセリフを言わせていることから考えても、そういうことを狙って書いたのだろう。 1997年にこの小説で第10回山本周五郎賞を受賞したらしい。そして自作の「女たちのジハード」で直木賞受賞ということだから、ある意味油の乗っていた時期の作品のようだ。私はこのブログを始めた頃に、日本の現代小説といえば、まぁ篠田節子と高村薫くらいしか知らなかった。
1997年にこの小説で第10回山本周五郎賞を受賞したらしい。そして自作の「女たちのジハード」で直木賞受賞ということだから、ある意味油の乗っていた時期の作品のようだ。私はこのブログを始めた頃に、日本の現代小説といえば、まぁ篠田節子と高村薫くらいしか知らなかった。 なんだかんだ言ったって、小説というものは現実を反映しているものだと思う。現実という言い方がまずければ、現実のとらえ方とでもいうものを。そう思えば、この小説も、けっして奇想天外ではなく、現実に足をつけたものの見方を提示しているのがすぐに分かる。だいたい登場人物も出来事も、けっしてありえないことではなく、まさにありそうなことばかりだ。ただこの少女趣味的な、オタク的なイラストが、それを捻じ曲げている、というか別のベクトルを強く押し出しているために、それが見えてこないだけだろう。
なんだかんだ言ったって、小説というものは現実を反映しているものだと思う。現実という言い方がまずければ、現実のとらえ方とでもいうものを。そう思えば、この小説も、けっして奇想天外ではなく、現実に足をつけたものの見方を提示しているのがすぐに分かる。だいたい登場人物も出来事も、けっしてありえないことではなく、まさにありそうなことばかりだ。ただこの少女趣味的な、オタク的なイラストが、それを捻じ曲げている、というか別のベクトルを強く押し出しているために、それが見えてこないだけだろう。 また一つ小説の醍醐味を味わわせてくれる作品に出会った。いろいろ読んでいるとこういう優れものの作品に遭遇するから、捨石はたくさんあっても、自分で探すのはやめられない。人から言われて読んだのでは、なかなかこういう開けてびっくり玉手箱的な喜びは得られないだろう。
また一つ小説の醍醐味を味わわせてくれる作品に出会った。いろいろ読んでいるとこういう優れものの作品に遭遇するから、捨石はたくさんあっても、自分で探すのはやめられない。人から言われて読んだのでは、なかなかこういう開けてびっくり玉手箱的な喜びは得られないだろう。